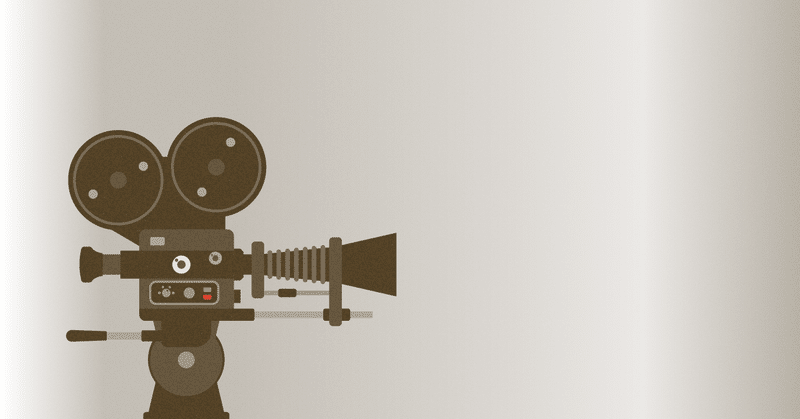
『死霊のはらわた II』:1987、アメリカ
アッシュは恋人のリンダを乗せて車を走らせ、山奥の小屋で一夜を過ごすことにした。持ち主は不在で、2人は勝手に小屋へ入ったのだ。夜も更ける中、アッシュがピアノを演奏、リンダはダンスを踊った。
書斎に入ったアッシュは、机の上のテープレコーダーを発見した。アッシュが再生すると、小屋の住人であるレイモンド・ノウビー教授の音声が録音されていた。古代史の研究者であるレイモンドは、妻のヘンリエッタと娘のアニーを連れて古城へ行った時に「死者の書」を発見したことをテープに吹き込んでいた。
レイモンドは死者の書を小屋に持ち帰り、そこで研究していた。死者の書を翻訳すると、呪文を唱えることで悪霊が森の闇に蘇ることが判明した。アッシュが机に置かれていた死者の書を開いていると、テープレコーダーからレイモンドの唱える呪文が聞こえて来た。
すると森を彷徨っていた悪霊が小屋へ飛び込み、リンダに憑依した。リンダに襲われたアッシュは、ショベルで彼女の首を跳ねた。リンダの遺体を森に埋めたアッシュは、悪霊に憑依される。しかし朝日が昇ると、悪霊は彼の体内から飛び出した。
アッシュは意識を失い、その場に倒れた。やがて目を覚ましたアッシュは、「我々の元へ来い」という悪霊の声を聞く。夜までに逃げようと考えたアッシュは車を走らせるが、来た時に使った橋が崩落していた。
夕日が沈んでいく中、アッシュは急いで小屋へ舞い戻る。悪霊に追われた彼は小屋に飛び込み、地下室に避難した。同じ頃、アニーは死者の書の残り部分を見つけて旅先から戻り、恋人であるエドの出迎えを受けていた。アニーは父に会うため、エドの車で山小屋へ向かうことにした。
悪霊が去ったと考えたアッシュは、地下室から出た。しかしリンダが蘇り、その生首にアッシュは右腕を噛まれてしまう。アッシュは納屋へ駆け込み、生首を万力に固定してチェーンソーで真っ二つに切断した。
しかし小屋に戻ったアッシュは、悪霊に憑依された自分の右腕に襲われる。アッシュはチェーンソーを使い、右手首を切断した。一歩、アニーとエドは橋の崩落地点にやって来た。ジェイクとボビーというカップルに出会ったアニーたちは、報酬と引き換えに山小屋へ行く小道の案内を持ち掛けられ、取り引きを了承した。
アッシュは悪霊が来たと感じ、扉のに向かって発砲する。彼が扉を開けて誰もいないことを確認した直後、ジェイクとエドが飛び込んで彼を捕まえた。2人はアッシュを殴り付け、地下室に閉じ込めた。
テープレコーダーを再生したアニーは、父が悪霊を復活させてしまったこと、母が憑依されたこと、父が母をバラバラに出来ずに地下室へ埋葬したことを知る。地下室のヘンリエッタが蘇り、アッシュに襲い掛かる。アッシュは必死で助けを求め、ジェイクたちが彼を引っ張り上げた。
地下室から這い出そうとしたヘンリエッタはエドを殺害するが、アッシュとジェイクが何とか蓋を閉じた。悪霊となったエドが襲って来たため、アッシュは斧で始末した。
寝室に出現したレイモンドは、死者の書に記されている悪霊を追い払うための呪文を唱えるよう告げた。アッシュの右腕に手を握られたボビーは、絶叫して小屋から飛び出した。彼女は木々から伸びた枝に襲われ、引きずり回された。
アッシュとアニーは、死者の書の呪文を確認しようとする。ジェイクはライフルを2人に向け、一緒にボビーを捜しに行くよう要求した。アッシュが「もう死んでる。この呪文で助かるかもしれないんだ」と言うと、ジェイクは死者の書を奪い取って地下室に放り込んだ。
ジェイクは2人を脅し、小屋から連れ出した。殴り倒されたアッシュは悪霊に憑依され、ジェイクを怪力で投げ飛ばす。小屋に逃げ込んだアニーは、入って来たジェイクを誤って突き刺した。ジェイクはヘンリエッタに襲われ、地下室に引きずり込まれて死亡した…。
監督はサム・ライミ、脚本はサム・ライミ&スコット・スピーゲル、製作はロバート・G・タパート、共同製作はブルース・キャンベル、製作総指揮はアーヴィン・シャピロ&アレックス・デ・ベネデッティー、撮影はピーター・デミング、夜間屋外撮影はユージーン・シルグレイト、編集はケイ・デイヴィス、美術はフィリップ・ダフィン&ランディー・ベネット、特殊メイクアップ・デザイン&創作はマーク・ショーストロム、音楽はジョセフ・ロ・ドゥカ。
出演はブルース・キャンベル、サラ・ベリー、ダン・ヒックス、キャシー・ウェズリー、セオドア・ライミ、デニス・ビクスラー、リチャード・ドメイアー、ジョン・ピークス、ルー・ハンコック他。
―――――――――
「死霊のはらわた」シリーズ第2作。前作に引き続いてサム・ライミが監督と脚本(スコット・スピーゲルと共同)を担当し、ロバート・G・タパートが製作を務めている。
前作から引き続いてのキャストは、アッシュ役のブルース・キャンベルのみ。リンダ役はベッツィー・ベイカーからデニス・ビクスラーに交代。アニーをサラ・ベリー、ジェイクをダン・ヒックス、ボビーをキャシー・ウェズリー、悪霊に憑依されたヘンリエッタをセオドア・ライミ、エドをリチャード・ドメイアー、レイモンドをジョン・ピークス、通常のヘンリエッタをルー・ハンコックが演じている。
前作がヒットしたおかげで予算は大幅にアップしているのだが、どうやら大半はVFXに使われたようで、出演者のランクは上がっていない。
続編ではあるが、同時に1作目のセルフ・リメイクでもある。森の中にある小屋へ来たアッシュが死者の書とテープレコーダーを発見し、リンダが悪霊に憑依され、アッシュが彼女を始末し、悪霊に襲われるという展開は前作と一緒。
で、前作はリンダを始末するのが終盤だったが、今回は序盤で済ませてしまい、それ以降の展開を描こうという作品である。「前作のおさらい」という意味で描写しているのかと思うぐらい、リンダを始末するまでの展開は早い。始まって6分程度で、そこまで辿り着いてしまう。
前作は、ホラー映画でありながら、かなり笑いの要素を強く感じさせる仕上がりになっていた。恐怖演出は色々と盛り込まれているし、グロテスクな残酷描写も多いが、何となく可笑しい雰囲気が漂っていた。「恐怖と笑いは紙一重」という表現があるが、それを具現化したような作品だった。
そして続編である今回は、「ホラーだけどコメディーの匂いがする」という印象が、さらに強くなっている。純然たるホラー映画を見たい人からするとガッカリしたり腹が立ったりするだろうけど、そもそも1作目を見ている人なら、続編でコメディー色が強くなっても「まあ、『死霊のはらわた』の続編だしなあ」と納得できるのではないだろうか。
ただし、明確な形で笑いを取りに行っているとか、露骨に喜劇テイストを持ち込んでいるとか、そういうことではない。ホラー映画をパロディー化しているわけではなくて、基本的には「ホラーとしての演出が行き過ぎた結果として、笑いが生まれている」という形になっている(例外もあるが)。
役者の演技も、ちゃんと悪霊を怖がっているし、ホラー映画としての演技になっている。真剣にやっているけど可笑しさが感じられるという形だ。「真面目にふざける」ってやつだね。
リンダを始末したアッシュが悪霊に襲われたのは深夜であっても朝方じゃなかったはずなのに、すぐに太陽が昇って悪霊が体内から出て行くという不可思議な時間経過。で、朝日が昇ったことで悪霊が退散したはずなのに、小屋から「我々の元へ来い」と悪霊が呼び掛ける。
悪霊は太陽が昇ったら出て来られなくなるのかと思ったら、そういうことは出来るらしい。で、じゃあ小屋に悪霊が潜んでいるのかと思いきや、橋まで行って小屋へ戻るアッシュを追い掛け、逆にアッシュが小屋へ逃げ込んだら去ってしまう。
前作と同じく、猛スピードで空を飛んで来る悪霊は、その悪霊視点によるシェイキーカム(サム・ライミが自作したカメラ)の映像で表現される。ピアノが勝手に演奏されるのは悪霊の仕業のはずだが、アッシュは怖がることも無く、リンダのペンダントを眺めて悲しみに暮れる。
埋葬した場所から腕がニョキッと現れ、ストップモーション・アニメーションの悪霊リンダが踊り始める。今度は小屋に近付いた特殊メイクのリンダがアッシュに襲い掛かる。消えたと思って安堵していたら、リンダの生首が落ちて来て噛み付く。首から下の部分は、チェーンソーを持って襲い掛かる。
アッシュがリンダの生首を始末して小屋に戻ると、椅子が勝手に動くポルターガイスト現象が起きる。鏡を眺めると、そこに写る自分の上半身が飛び出して首を絞めるが、それは幻覚。しかし今度は右腕の欠陥が浮き上がり、アッシュに襲い掛かる。
切断した右腕は、逃亡を図る。壁に向かってライフルを発砲すると、開いた穴から大量の血が噴き出す。壁に飾ってある鹿の首の剥製や電気スタンドや書物などが、アッシュをバカにして笑う。
地下室で特殊メイクのヘンリエッタが復活し、アッシュに襲い掛かる。作り物のヘンリエッタが地下室から顔を出して暴れ、アッシュが蓋を閉じようと踏み付けると、その目玉が飛んでボビーの口にスポッと入る。
悪霊になったエドは宙に浮遊し、ヘンリエッタと共に脅かす。アッシュが斧で何度も殴ると、緑の血がブシャーッと噴き出す。恐ろしい音がして、柱時計の蓋が勝手に開く。寝室でもポルターガイスト現象が発生し、ホログラムのような状態でレイモンドの幽霊が出現する。
アッシュの右腕に襲われて小屋を飛び出したボビーは、木の枝に絡み付かれて引きずり回される。ジェイクに殴り倒されたアッシュは悪霊に憑依され、特殊メイクの状態で襲い掛かる。アニーに誤って突き刺されたジェイクは、地下室から顔を出したヘンリエッタに襲われる。
慌ててアニーが助けようとするが、地下室から大量の血がブシャーッと出てジェイクは引きずり込まれる。地下室から出たヘンリエッタはストップモーション・アニメーションになり、首がニョロッと伸びて襲って来る。小屋の扉に巨大な悪霊が出現し、アッシュを襲う。悪霊にはルールによる制限が無く、何でも有りの状態になっている。その場その場でコロコロと行動パターンが変化し、規則性が無い。
ルールなんて、この映画ではどうでもいいことなのだ。ルール無用にしてあるのは、「特殊視覚効果を色々と見せたい」という目的と、前半に関しては「ブルース・キャンベルの芸を見せたい」という目的が関係している。
前者に関しては、上述の説明でも分かる通り、特殊メイクによる悪霊だけでなくストップモーション・アニメーションも使っていることからも、それが「怖がらせる」というためのモノでないことは明らかだ。ストップモーション・アニメの悪霊なんて、ちっとも怖くないからね。
後者に関しては、まさにブルース・キャンベルのショーケースで、盟友であるサム・ライミは、それを何よりも見せたかったんじゃないかと思うぐらいだ。
このシリーズそのものがブルース・キャンベルの代表作ではあるのだが、1作目よりも2作目の方が彼の存在感や魅力は遥かに強く出ている。何しろ、アニーたちが小屋へ来るまでの時間帯は、ほぼブルース・キャンベルの一人芝居になっているのだ。
「リンダが死んだから一人芝居になるのは当然」と思うかもしれないが、ただの一人芝居ではない。一人芝居だが、重要な相手役がいる。それは自分の右腕だ。
アッシュはリンダの生首に右腕を噛まれ、それを外そうとして苦悶しながら暴れ回る。右腕が悪霊に憑依されて自分を殺そうとする。つまり、ブルース・キャンベルは、「別の意思を持つ自分の右腕が顔を掴み、それを左手で引き離す」とか、「右腕が自分の顔面に皿を叩き付けたり殴って来たりする」とか、そういう一人芝居をやっているのだ。
自分の右腕に襲われてマヌケな姿もさらすアッシュだが、終盤に入り、ペンダントを見て悪霊モードから元の状態に戻ると、地下室にある死者の書を奪還するために戦闘モードへ突入する。チェーンソーを右手首に装着し(ライダーマンのカセットアームみたいなモンだと思えばいい)、ショットガンを背負って地下室に飛び込む。
色々とあって悪霊を退治したアッシュだが、その過程でアニーは命を落とす。さらに、アッシュも次元の悪霊の親玉に続いて裂け目に吸い込まれてしまう。
そうなると、「ああ、みんな死んでしまうバッドエンドってことか」と思うかもしれないが、そうではない。なんと次元の裂け目に吸い込まれたアッシュは、中世にタイムスリップしてしまうのだ。大勢の兵隊に囲まれたアッシュは、翼をもつ悪霊が飛んで来ると、それをショットガン一発で始末する。
それを見ていた兵隊は「天から来た使者だ」と盛り上がるが、アッシュは「ノー!」と苦悩の表情で叫ぶ。最後の最後になって、伏線ゼロの突拍子も無い展開が待ち受けている。「なんじゃ、こりゃ」と思った人のために、シリーズ第3作『キャプテン・スーパーマーケット』が用意されている。
(観賞日:2014年3月25日)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
