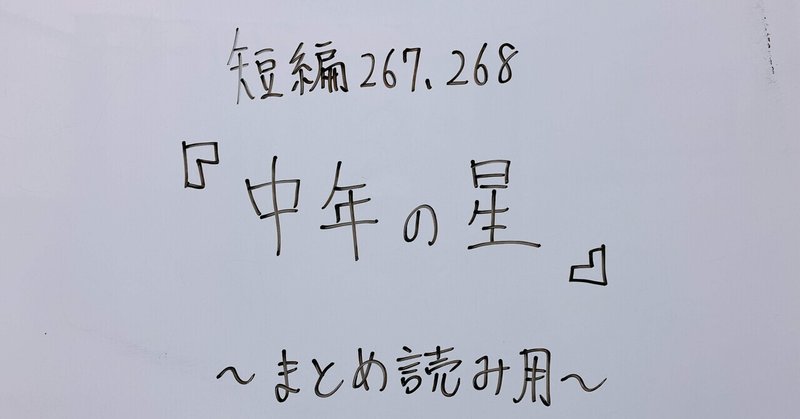
短編267.268『中年の星』(まとめ読み用)
何気なく見た鏡に見知らぬオッさんが映って慌てて飛び退いた。それが自分だと気付くのに数秒を要した。別に酔ってはいない。ただ単純に自分が自分を認識出来なかったのだ。
普段目に見えない”自分”というものはもっと若々しいイメージで構成されているはずだった。その若い姿でコンビニで買い物をし、酒や煙草を嗜み、女性と話していた。それが何だ、中年のオヤジじゃないか。これじゃウィットに富んでいたはずの一言もくだらない駄洒落や救いようのない下ネタに堕ちてしまう。
セルフイメージの危機だった。鏡像段階(@ジャック・ラカン)を経て自我を獲得したものにとってそれは残酷なまでの死亡宣告に違いなかった。ーーーこのままではいけない。ここは重力の星・地球だ。放っておけば、もっと頬は垂れ、隈は深くなり、皺は増える。そうなれば、棺桶まで下を向いて暮らす羽目になるだろう。それは避けねばならない。何せまだ青春を味わい切ってはいないのだから。
ポケットからスマートフォンを取り出し、近所のメンズエステを検索する。齢を重ねた男の初めての挑戦。Googleが一ページ目に表示したそこは、元形成外科医が経営と施術を行うことを謳った半クリニック型のメンズエステだった。ーーー安心と信頼。それは初めての者にとって大いなる安堵感を抱かせるには充分な素材だった。ーーーもう何なら抱かれてもいい、とすら思った。
ホームページ上に記載された簡単なカウンセリングシートに答えを打ち込み、無料体験に申し込んだ。
ーーー私は”中年の星”になる。
そう決意して。
*
駅にほど近い雑居ビルの三階。一見さんに不安を抱かせる為だけに借りたような見事なまでに古いテナント。壁はひび割れ、玄関マットは薄汚れている。私はこのメンズエステのホームページをもう一度、見返した。そして、写真加工の進化に溜め息をついた。
受付は無人。備え付けのベルを鳴らすと、トイレを流す音が聞こえ、毛むくじゃらのデブが如何にも面倒くさそうな様子でこちらに向かって歩いてきた。
「あ…十四時に予約した者ですが」
「知ってますけど」
ーーー知ってますけど?こういう時は『お待ちしてましたー!』とか言うんじゃないのか?グレーゾーンの医療行為とはいえ客商売なら。たとえ、嘘でも。
ウェブ上のトップページで愛嬌ある笑顔を見せていた受付嬢の二人は何処にも居なかった。今更ながら、あれはネット上に転がる無料素材を転用したものだったことに気付いた。ウェブの網の目に絡み取られたような気分になった。時すでに遅し、といったところだが後は蜘蛛に喰われるのを待つしかない身。もはやまな板の上の鯉。
「このカルテに記入して」と渡されたカウンセリングシートは、昨日ネット上にて記入したものと細部に至るまで一文字も違わぬものだった。無意味、その言葉の意味を中年になってようやく本質的に理解した。
致し方なく記入したカウンセリングシートは我が肉体の壊滅的なほどの凋落を端的に示していた。スマートフォンの画面上でデジタルデバイスを介して打ち込むより、自分の手を使ってその綻びを一つ一つピックアップしていく方が遥かに精神的ダメージは大きかった。
ーーー私も知らぬ間に随分と歳をとってしまったみたいだ。
商店街を疾走する私、ランドセルを背負って下校する私、友達と肩を組んで運動会に臨む私。そのどれも深い渓谷に隔てられた向こう側の出来事だった。そう、もはや人生は後戻り出来ない地点まで来てしまっているのだ。締め切られた部屋の中に、一陣の秋風が吹いたような気がした。
私は記入の終わったカウンセリングシート改め【我が肉体の凋落】というエッセイを男に渡した。
「こりゃ酷いね」と男は言った。
医の倫理はどこへ行ったのだろう。ヒポクラテスは滅して久しい。
私は男の後に従って、下手な手書きの字で【施術ルーム】と書かれた札のかかる部屋に入った。
*
ホームページの写真では遥かな奥行きを感じさせた施術ルームは二人入れば息をするのも難儀なほどの狭さだった。私は平均体重をキープしているが片やデブ。酸欠になるのも時間の問題だった。
私は促されるままベッドに仰向けに横たわった。ベッドに掛かるタオルケットは硬くごわつき、一片の空気も含んでいなかった。タオル地の毛並みは潰れ、そして仄かに生温かかった。大方、先程までこの男が昼寝でもしていたのだろう。すえた脂のような臭いがした。
部屋の隅に大掛かりなマシーンがある。この店唯一の金のかかった一品だろう。それはどこか近未来SF小説に出てくるタイムマシンを思わせる造りだった。実際に男がそれを操作し始めると部屋中に轟音が響き渡った。男はこのまま時空の彼方へと消えるんじゃないか、と信じさせるには充分なほどの爆音。
*
施術が始まった。男は仰向けの私の上方に陣取るような形で、腰を下ろした。マシーンから伸びた象の鼻のようなもので頬を吸引していく。今何をやっているのか、の説明もなく始まったため、私の頬は不如意かつ不機嫌に波打ち続けた。
片方の頬が終わると、もう片方の頬へ。そして顎、首へと進んでいった。皮膚は連続的にバイブレーションし、筋肉はそれに耐える為に硬く強ばった。
…顔が近い。男の顔は私の鼻筋の数センチ上に位置している。マスクはしているが、マスク越しにニンニクを含んだ鼻息が絶えず吹き付けてくる。これなら生ゴミに顔を突っ込んでいるのと変わらない。
施術時間は大体、十分程度だった。両頬から顎、首を三周したあたりで終わった。何の満足感もなかった。私は起き上がり、ベッドの縁に座った。男は汗だくだった。あのマシーンをクライアントの頬に当てているだけで、相当なカロリー消費をするものなのだろうか。とてもそうは思えなかった。仮にそうだとするのであれば、施術者とクライアントの役割関係を変えた方が得策だと思う。
手鏡を持たせられ、「どう?」と尋ねられた。ーーーどう?と言われても。相変わらず中年のオッさんがそこには写っていた。
「ちょっと…変化があまり…そうですね」
「頬がリフトアップされてるの、分からない?」断定的な口調だった。
改めて手鏡を使って頬を映すが、そこには赤く腫れた皮膚があるだけだった。
私は手鏡を男に返した。某大手”百円ショップ”の値札が貼ってあった。
「まぁこういうのは回数が必要だからね」と男は言った。妙な自信を以て。
*
レジ前で改めて対面した男は紛うことなきデブだった。ーーーよくこれでメンズエステなんてやっていられるな、と思った。もしかすると、自己肯定感が物凄く高いのかもしれない。それはそれで幸せそうな人生だった。羨ましくはないが。
「次の予約いつにする?」と男は言った。
「今予定分からないので、また連絡します」というありきたりの嘘で答えた。もし仮に死ぬほど退屈でもここにだけは二度と来ないだろう。
「三万八千円ね」と男は言った。
「え?今日のこれ、無料体験じゃないんですか?」私は昨日確かに無料体験のボタンをクリックしたはずだった。
「無料体験の期限は昨日までだね」
財布には二千数百円しか無かった。私はクレジットカードでそれを払った。揉めることでこの場に居続けることになるよりは、そっちの方が遥かに良かった。
*
雑居ビルを出ると同時に、消費生活センターに電話を掛けた。
#メンズエステ #中年 #おじさん #小説 #短編小説 #エッセイ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
