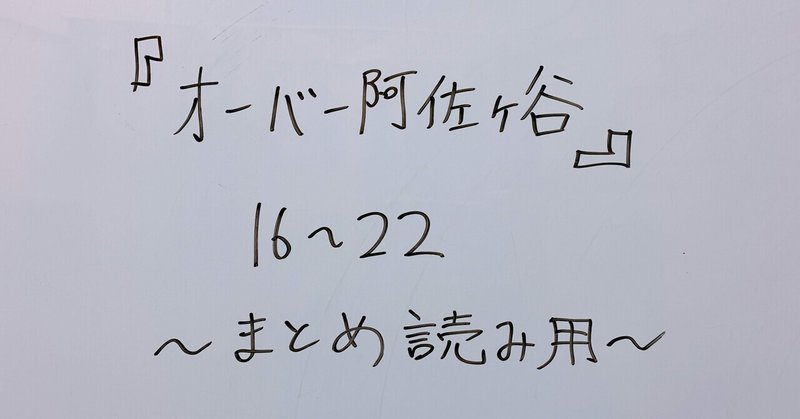
『オーバー阿佐ヶ谷』16〜22(まとめ読み用)
16.
時と頭を交錯する疑問によって、ほとんど眠れぬまま朝を迎えた。短い眠りの間、一度だけ夢を見た。夢の中では私が殺される役回りだった。
【【【”野菜”の配達で辿り着いたマンション。インターホンを押すも誰も出てこない。気配に振り返ると、そこには巨大な怪物が立っていた。全身を覆う黒い毛は満月に照らされて毛先の一本一本まで銀色に輝いている。逃げようにも身体が動かない。振り下ろされた怪物の腕によって割られた額から噴き出す血。顔全体が熱い。私は腕を伸ばす。怪物の顔を覆う毛を掻き分けるとそこには演出家の男の顔があった。】】】
そんなB級ホラームービーのような夢だった。しっかりと寝汗をかいている。しかしまぁ演劇を生業とした男への追悼には相応しい夢のように思えた。今再びのレストインピース。
鎮魂歌代わりにBOO YAA TRIBE『West Koasta Nostra』を流しっぱなしにした。演出家男がコレを聴いたことがあるかは知らない。ただ、私は好きだ。追悼なんてそれで良い。要は気持ち次第だ。Salute.
*
三つ編みのまま寝てしまったので、起きてから一度ほどきシャワーを浴びた。鼻歌は不謹慎なような気がして自主規制した。風呂場の鏡にまだ彫り途中のタトゥーが映る。今はただ金が無く中断しているに過ぎない。断じて、痛みのせいじゃない。断じて。ーーーこれも早々に仕上げなければならない。私の存在自体がアートだ。腕も首も胸元も。そして勿論、人生だって。
濡れた髪を自然乾燥している最中にスマートフォンが鳴った。珍しい。私に掛かってくる電話は大抵が悪い知らせだ。誰それがパクられた、誰それが飛んだ、誰それがーーー云々。バッドニュースにはもううんざりだった。それでも私は電話を取った。【鳴る電話に出ることはそれこそ義務】だと教えられた最後の昭和世代。
「おい。テレビ点いてるか?」レペゼン地元のホーミー。
「よぉ。調子どう?」
「それどころじゃねぇんだって」
リモコンを探してテレビを点けた。「何チャン?」
答えを聞くまでも無く、そこに映されたものに見入った。馴染みの場所、馴染みのあるロゴ、馴染みの顔。そのニュースには『野菜直送便』の胴元の顔が映っていた。
キャスターは言う、”ーーー云々”と。
メイクマネーの方途がまた一つ閉ざされた。ブリる供給源も絶たれた。
*
ーーー警察は劇団関係者を中心に当たっているらしい。昨夜聞いた店主の言葉を辿る。こちらもこちらで演劇関係者に当たってみることにした。もしかしたら怪物について何か知っている奴がいるかもしれない。何のツテもなかったが、確かいつかの日に「観に来いよ」とポケットにねじ込まれたフライヤーがまだ部屋の何処かにあったはずだ。場所を調べて行けばなんとかなるような気はしていた。手練手管は頭の中に入っている。昔読んだ探偵小説が実生活で役に立つ日が来るとは思わなかった。
17.
冬物のパンツのポケットから発見したチラシの皺を伸ばしながら高架下を荻窪方面に歩く。なんというか、センスの感じられない古くさいデザインだった。古さも一周回ればレトロに化けるが、このフライヤーのデザインはただただ古いだけだった。1970年代辺りのチラシをそのまま持ってきたかのように紙の上で時が止まって見えた。見ようによっては「これぞ演劇!」という気もするが、そう見る為にはまず両目にタバスコを撃ち込んでから、度の合わない眼鏡を掛けさせるしかない。
ーーーしかし何故、ラッパーの私がこんな小劇団のチラシを眺める羽目になっているのだろう。まさか劇団のオーディションを受けに行く訳でもあるまいに。
今やっていることなんて、ラッパーというよりは1940年代のパルプフィクションに出てくる探偵そのまんまじゃないか。殺人事件や謎の捜索。小説界の主流から外れたアンダーグラウンド。二十一世紀に今更、そんなことをなぞっているなんて。かの日の私立探偵とラッパー、唯一の違いがあるとすれば、トレンチコートではなく”ペレペレ”のセットアップを着ていることくらいだ。今に繋がるそもそもの発端は何だったか。
その答えは、人類の起源をDNAにまで遡って探すよりは簡単に見つかるものだった。酔っていたとはいえ、大雑把に言えば昨日のことなのだから。
【怪物を探し出して『俺をここから救ってください』と言うことで成功への道は開かれる】
要約すればそういうことだ。そしてそれを私に教えた演出家の男は殺された。このチラシは怪物にまで続くワインディングロードなのかもしれない。そしてその道の先にはウイニングロードが続いている。私はフライヤーのシワを丁寧に伸ばした。
極論、『怪物が何者なのか』、『演出家の男を殺したのは誰なのか』、なんてことはどうだって良い問題だ。前者は学者の仕事であり、後者は警察の管轄だ。怪物の生態系になど興味はないし、演出家の男は別に私のブラザーでもなければ、ホーミーでもないのだから。演出家がどのように殺されようと、怪物を間に挟んだ東西海岸の抗争など起きやしない。しめやかに葬送が執り行われるだけだ。
私はただ怪物を探し出して一、二発殴ってから『さっさと俺を救いやがれマザファカ』と言えばいい。もしその怪物とやらが雌だったなら二、三発ぶち込んでやっても良い。それで結果がより良くなるのなら。
ーーーそうだった。目的はひとつだ。
その為の第一歩としての怪物の居場所探し。だから、今こうして(先ごろ死んだ演出家の)稽古場を訪ねることにしているのだ。あの口の軽い演出家のことだ。きっと劇団員の誰彼構わず怪物の話をしていると踏んでいる。
小劇場演劇には詳しくないが、自前の稽古場を持っている団体というのはあるいは凄いことなのではなかろうか、と思い始めていた道すがら。この私ですら自前のスタジオなんて持っていない。MacBookの中に設えたクラウド上の居場所があるだけだった。
*
青梅街道を横断すれば、目指す建物は目と鼻の先だった。ネズミ捕りの為に、大通りの死角に隠れた白バイ隊員すら愛おしく思えた。
18.
私は既に萎えた気持ちで一棟のビルを見上げていた。この古い雑居ビルの五階に演出家の主催する劇団、その稽古場はあるらしい、がーーー。
この世の中には、人の気持ちを鼓舞するビルと解体させるビル、その二種類が存在する。そこに新築/中古/リノベーションの別はない。築年数に拘らず、アガるものはアガるし、ワックなものは見るだけでもダウナーにさせられる。ビル界のコカインとヘロインみたいなものだ。(コカイン×ヘロイン=スピードボールのようなビルがあるのかは知らない)
その基準から眺める目の前のビル全景は最悪の(質の悪いヘロインの)部類に属するものであり、あえて喩えて言うならば『芸術家が売れないとはどういうことか?』を建物全体で表現しているみたいだった。外見(そとみ)ばかりが衰えて、気だけは若い。そこらへんのライブハウスでよく見るような奴だ。そして人はそれを”#老害”と呼ぶ。
*
外壁のタイルには無数のひびが入り、風雨に曝された挙句、元の色が想像出来ないほどにくすんでいる。きっとビル自身も自分がかつてどんな色彩だったのかなんて忘れてしまっているのだろう。現代はビルも患う認知症。
入り口のガラス扉には蜘蛛の巣状の割れが目立ち(これはこれで見ようによっては前衛アートのようだったが)、四角いノブは積年の指紋で黒ずんでいる。私はそれを靴の踵で押して中に入った。
フロアごとにテナント名が嵌められた案内板を黄白色の裸電球の下で眺める。一〜四階の会社はどれも昭和の時代に付けられたような社名とフォントを持っていた。目指す五階は【演劇集団 暗愚裸座】。とても趣味の良いネーミングだ。それは花咲き誇る庭園で飲む紅茶を連想させる。アールグレイの香り。柔らかな風と蝶が羽ばたく様が目に浮かぶ。ーーーあぁ。勿論、皮肉だぜ?
【演劇集団 暗愚裸座】少なくともオーバーグラウンドは望めそうにもないが、さりとて七十億分の三人くらいは熱狂的信者がいそうな名前だ。
管理人室には誰もいなかった。私にとっては好都合だった。自分の風体の怪しさは充分に自覚している。通報されても厄介だ。「なんか三つ編みをした売人みたいな奴がビルに入ってきたんです」まぁその通りだが、それだけでもパトカーの三〜四台は飛んでくる。一人に対して八人のポリス。生憎、言い訳は用意してない。今日は要件が違う。管理人なんていないに越したことはない。
エレベーターの内部は年代物に相応しく、様々な臭いが染み込み、頭上の電灯ケースの中には虫々の死骸が溜まっていた。五階に上がるまでの間、震度三くらいの揺れが二度あった。多分、このビルのエレベーターの下の地盤だけが弛んでいるのだろう。
五階で扉が開くと、エレベーターホールのすぐ前が稽古場だった。フロアと稽古場は薄いドアに隔てられている。周りを見回すも、どうやらこのフロアには稽古場しかないようだった。
私はドアに横顔を押し当て、聞き耳を立てた。演出家が死んで、稽古どころではないのだろう。はしゃぐ人間達の声が聴こえてくる。まぁどこの集団でも似たようなものなのかもしれない。締め付けているだけの紐帯が緩めば、全ては解けてバラバラになる。家族もバンドも劇団も同じことだ。
私は力任せにドアを開いた。「ヘイ!What’ up!? Doggs! やってるか〜い?」
*
稽古場の全ての動きが止まり、何対もの視線が私に集まる。ひい、ふう、みぃ。稽古場には五人の男女が輪になって座っていた。
19.
出来るだけゆっくり歩んだ。それこそいかにも大物がやって来た、という風に。私は座の中心に立ち、ゆっくりと一周した。そこには若い顔から老け面まで五者五様の顔があった。勿論、誰一人として知る者はいない。それは勿論、向こうも同じだろう。
そこにはただ沈黙だけがあった。換気扇の音だけが室内を支配している。『沈黙』という皿を廻す”DJ 換気扇”はなかなかchillなミュージックがお好きらしい。遠藤周作の描き出した神の沈黙もここまで静かなことは想定してないだろう。
さっきとは逆回りで、また一周した。先程より見知った顔があった。それは数秒前に見た顔だった。向こうも多分、そう思ったことだろう。もしくは「こいつグルグル回ってるけど、一体何してんだ?」ってとこだろう。当然の疑問だ,Bro.。
「何の御用でしょうか」一番年寄りじみた奴が口を開いた。「どこかのフロアと間違えておいでではありませんか?」
「もし何かを間違えているのだとしたら」私は溜め息をついた。「君たちの演出家から怪物の話を聞いてしまったことだろうな」
全員の顔に疑問符が浮かんだ。
「刑事さんか何かですか?」
「いや、俺はラッパー」
全員の頭の上に浮かぶ疑問符が更に大きくなるのが分かった。
「うちの主催とお知り合いの方で?」
「飲み友達、というほどの仲でもないけどな」
皆の顔に少しだけ安堵の色が広がった。しかし、それは年寄り劇団員の次の一言でまた曇ってしまった。
「もし主催に貸したお酒代の取り立てでしたら他をあたって貰えませんか。残念ですが主催はーーー」
「知ってるよ。多分、主催?とやらと最後に言葉を交わしたのは私だ。おそらく犯人を除けば、ということであれば」
「あぁ、なんということでしょう」芝居じみた台詞が年寄りの口から漏れる。涙でも流さんばかりの迫真さで私の手を握った。「わざわざ来て頂いてありがとうございます」
「お礼を言われる筋合いはないぜ、doggs。別の用件で来たんだ」
「香典でも持ってきてくてくれはったんですか?」
中年の域に足を踏み入れ、この先の人生に迷っていそうな女の劇団員が弾む声で言った。
「死者に渡す飲み代があるくらいなら自分で使うさ」私に向けられた強欲な視線を手で制する。「そして別にこの中で犯人探しをしようというんじゃない。安心して話してくれていい」
一人一人を別々に壁際へと連れて行き、話を聞くことにした。背中に突き刺さる他の劇団員の視線に耐えながら。
ーーー要約すれば以下の様になる。
*
劇団員Aの証言。
「怪物?知らないっすねー」
劇団員Bの証言。
「怪物…ですか。ふむ、それは次の芝居の話かなんかでしょうかね?」
劇団員Cの証言
「怪物の話なんか聞いたことなんて無いです。何度かベッドに誘われはしましたけど」
劇団員Dの証言。
「我々にとっては演出家の死も痛ましいが、次の舞台の集客状況の方が痛ましい」
劇団員Eの証言。
「それより主催に貸した三万円、戻ってくるんやろか。香典からでも良いから回収したいわぁ」
*
演出家の醜聞も多少は覚悟の上で尋ねたのだが、逆に良い思い出話など一つも出てこなかった。ーーーあいつ、何なんだ。
20.
私の目論見は大きく外れていた。誰一人として怪物のことなんか知りやしない。それどころかむしろ私が白い目で見られる始末。まぁ分からなくもない。左右に垂らした長い三つ編み、派手派手しい”ペレペレ”の上下セットアップ、二又に編み込んだ顎髭、首元や手の甲にはみ出すタトゥー。まさにラッパーの極北。そんな奴がいきなり稽古場を訪ねてきて「怪物のことを教えてくれよ」なんて、借金取りの方がまだ歓迎されるレベルだろう。
時計の針は正午を指していた。そろそろここを去る潮時だった。劇団員達は各々好き勝手に話をしている。私に興味を無くした犬、みたいに。
「まぁなんか思い出したことがあったら連絡くれよ」
私はポケットに入っていたチラシに連絡先を書いて、年寄りの団員に渡した。
「お、懐かしい」
チラシを囲んで眺めながら、団員達は言った。
*
エレベーターホールで私を下界へと誘う方舟を待っている時、Chickな女(=劇団員C)がドアの向こうから顔を見せた。
「あの…」
大きな目が特徴的だった。多分、演劇界の中では美人の部類に入るんだろう、多分。Tシャツを内側から盛り上げる脂肪組織はこれまで何人の男に揉みしだかれてきたのか分からない程に欲情的だった。私はそれを、アルプスの山並みを眺めるが如く眺め、顕微鏡で未知のウイルスを探す様な専心さで以て観察した。
私の視線で女の胸元が焦げてしまわない内に目を逸らした。
「もしかしたら、ずいぶん前に退団した座長さんが何か知っているかも分からないです。結構な期間在籍していた方で、主催とも長い付き合いだったみたいですし」と女は言った。
「オーケー。そいつの連絡先か居場所分かる?」もう一つ名案を付け加える。「ついでに君の連絡先も教えて貰えない?」明暗は如何に?
「分からないし、教えたくもないですけど、座長さん、主催のお通夜には来るんじゃないかと思います」
「オーケー。君も来るんだろ?通夜。俺、そいつの顔知らないからさ。通夜の席で見かけたら紹介してくれよ」
「OK〜♪」
ーーー急に馴れ馴れしくなりやがった。
(自分の電話番号はお前如きに)教えたくもない、が案外結構心に突き刺さっていた。今宵枕を濡らすことになってしまうかもしれないくらいには。胸元を見過ぎたのが原因かもしれない。ただラッパーなんていう生き様が嫌いなだけかもしれないし、レズビアンなのかもしれない。次はどう断られるのか不安を感じながら尋ねる。「名前は?」
「ワタシですか?それともその」
「君以外に興味はないね」
「まきな、です。小石川真妃奈。あなたは?」
ーーーヴァギナ、みたいな名前だな、と言おうと思ったがこのご時世、コンプラ的にヤバそうなので心の内に留めた。
「まりゅうぎゅう。馬に龍に丑で、馬龍丑。”。”まで込みで馬龍丑。」
「中国の人?」
「いや、レペゼン邪馬台国のGenuine Shitだ」
ドアを閉めようとする若い女に「あ、あと通夜の日取りと場所も教えて」と付け加えた。結局のところ、私は何一つ知らない。
21.
稽古場からの帰り道に”ラーメン二郎 荻窪店”で、茹でた6B鉛筆のような麺を啜った。途中で喉元が強制的に締まり、もうこれ以上の塩分摂取を身体が拒絶していた。ーーーでも、これが食えるうちはまだ大丈夫だ。そう思って残りを胃の中に収めた。
膨れた腹をさすりながら青梅街道を阿佐ヶ谷に向かって歩く。側道では白バイ隊員に向かってヴァンの運転手が怒鳴っていた。「てめぇ、そんなところに隠れてないで、姿晒してた方が交通安全になるだろうが」「では、こちらに拇印お願いします。はい、親指出して」「俺らの税金で食ってる癖に偉そうなんだよ」「これからは気をつけて運転してくださいね〜」みたいな。今日も明日も変わらぬ光景。収奪者は眠らない。人は一日分の稼ぎをカツアゲされる。たかだか数十キロのスピード違反か、停止線を無視したくらいで。いつまで経っても収奪者が収奪される日はやって来ない。マルクスの予言は相変わらず大いに外れ続けている。
白バイ隊員は去り、作業服姿の運転手だけがその場に残っていた。怒りが鎮まらないのだろう、汚れた安全靴でガードレールを盛んに蹴り飛ばしている。私はその光景をレッドブルを飲みながら眺めていた。反戦映画でも観るみたいに。
運転手と目が合った。男はガードレールを跨ぎ超え、私の目の前に立った。背丈は同じくらいだが、盛り上がった僧帽筋がこの男の好戦的な姿勢を援護している。頭に巻いたタオルには建築会社の社名がプリントされていた。
「さっきから何見てんの?」と男は言った。
これは久々に仕掛けられたビーフだった。乗らない手はない。売られたビーフにはフリースタイルで応えることにしている。ラッパーだからだ。
「オカマみてぇに三つ編みなんかしやがって。このチンピラが」と男が言う。それは試合開始のDrop da Beatだった。
「Yo!俺はチンピラッパー。ワッパ掛けるお前の両手。是!が非!でもやらせるぜ強制クラッパー」
みぞおちに鈍い衝撃が走った。同時に横隔膜が収縮し、先程過剰摂取した糖質が喉元をせり上がってくる感覚。
ライムと共に噴射された元・ラーメン二郎は男の顔面を真正面から捉えた。それはゲリラ豪雨で決壊したダムの如き激しさで男を襲った。
男の頭に巻いたタオルに麺が絡み付いている。豚肉の欠片は頬に張り付き、Tシャツはモヤシまみれ。心なしか泡立っているのはレッドブルのせいだろうか。唐突にゲロの嵐に見舞われた男は呆然と立っていた。
「くっせ」と私は言った。もはや韻を踏むどころではなかった。
一日分の給料を違反金で巻き上げられ、免許点数を引かれ、更にゲロを吐きかけられた不運な男をその場に残し、青梅街道を横切った。信号は青だったので、歩行者にとっての当然の権利だ。
道の反対側から眺めた男は相変わらずその場に立ち尽くしていた。
*
私は暴力には頼らない。何故って?ラッパーだからだ。
22.
通夜は今夜だそうだ。何事も鮮度が大切だ。中年で、しかも頭なんかを割られた死体は特に。でも稽古場を訪ねていなければ危うく行きそびれるところだった。これも神の采配の一つなのかもしれない。もしくは、怪物の。
若干、腹が減っていた。昼飯は胃の腑に収まった途端に出て行った。他の男の元へと走る、癇癪持ちのメンヘラ-bitchみたいに。
昼飯は全てリバース
ライムで埋める16verse
ファック da ポリス
形式で魅せるコレ、パリスよりもゴージャス
拭けよ鼻水
…もしかしてそれ、カウパー?
随分と溜まってんだなアマラッパー
リリックが出来上がる頃、家に帰り着いた。
*
台所で煙草を一本吸った。これを食後の一服に数えて良いかは分からなかったが、それなりに美味かった。ニコチン不足だったせいかもしれない。
ーーーさて。
やろうと思って先延ばしにしていたことに着手する。
壁に貼られた『スカーフェイス』のポスターの前に立つ。トニー・モンタナは相変わらずマシンガンを乱射していた。いつだって成り上がりは好戦的だ。私はポスター下部の画鋲を外し、その奥に隠された引き出しを開けた。それは確かにそこにあった。ラップと双璧をなす私のもう一つの武器。幾重にも新聞紙で巻かれたその”道具”を取り出した。
久しぶりのメンテナンスをする。一度、バラしてから各部にグリスを塗り、再び組み上げる。金属管にオイルを挿し、トリガーの調子を確かめる。どこも錆びついてはいなかった。今すぐにでも圧縮された空気を押し出せるし、物凄い音で空間を切り裂くことも出来る。住宅街で発射したら人々は悲鳴を上げて逃げ惑うだろう。
通夜までにはまだまだ時間がある。私は”道具”をハードケースに納め、家を出た。(残念ながらチャカの話じゃないぜ?)
*
妙正寺川の欄干にもたれ、マウスピースを口に当てる。自分の内のメトロノームをBPM73にセットする。私にしか聴こえないカウントに合わせて指を鳴らし、グルーヴを創っていく。バックビートの真っ黒いやつを。深呼吸したあたりで、目の端に白いチャリが映った。
「すいませ〜ん。何してるんですか?」お馴染みの制服に制帽。チャリ松、おそ松よりお粗末。
「見りゃ分かんだろ。これが青姦してる様に見えるか?」
「僕にはトランペットを吹いている様に見えますね」
「残念だな、正確だよ。もし金管とファックしてるように見えるんなら俺が逆に通報してやったのに」
警官の顔にはまだ幼さが残っていた。いつから警察官の多くが歳下になってしまったのだろう。
「ここ、住宅街なので苦情が来る前にどこかへ退散してもらって良いですか?」
「事件を未然に防ぐなんて警官の鏡だな」
取り出したばかりのトランペットを再びハードケースに仕舞い込み、川沿いを歩く。金木犀香るドブ川沿いを。
*
ラップにラッパで二刀流
まるで某メジャーリーガー
でも勿論、ベッドに登らせるHOEは雌限定
ケツを掘らせるつもりはない
*
weedを吸った後のマンチが如く腹が減っていた。結局のところ、最後に食べたのはいつなのか、ラーメン二郎は昼飯に算入して良いのか、答えは出ていなかった。デリバリーを注文することにした。ヘルスの方ではなくチーズの乗った丸いやつを。
Lサイズのピザを独り貪り食った挙句、三十分ほど仮眠を取るつもりで三時間寝た。消化に体力が必要だったのかもしれない。起きた時にはもう陽は翳り、虫の声がし始めていた。
ーーーそろそろ時間だ。
私はタンスを開け、喪服を探した。渋い、それでいて光沢あるベルサーチの喪服を。
#阿佐ヶ谷 #演劇 #小劇場 #小説 #短編小説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
