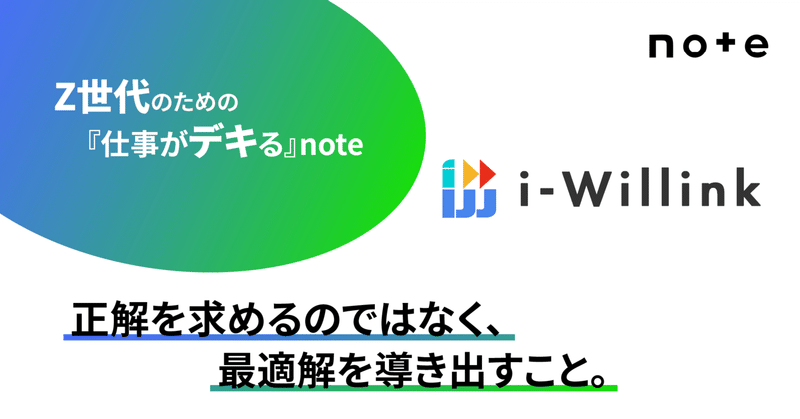
正解を求めるのではなく、最適解を導き出すこと。
こんにちは、白井です。
今回は「最適解を求めること」についてです。
みなさんは、ビジネスシーンで何か課題に直面した際にどのような対応をするでしょうか?
結論から述べると、正解は存在しません。
今の世の中には、様々なビジネスモデルや課題解決のフレームワークがたくさんあります。
しかし、これらは正解を教えてくれるものではありません。
昨今のVUCAと言われる世の中には、唯一解など存在しません。
多様化する社会に合わせた最適なソリューションを導き出す意識と必要となってきます。
解が見出せない時に、何を考えるか。
仕事をする際に、自分の力ではどうすれば良いか分からなくなる場合があります。
まだ若手であるならば、自分の判断で決定することはできませんので、上司に指示を仰ぐことになると思います。
その際、あなたはどのように上司に相談しにいくでしょうか?
「どうすれば良いか?」は、ただの思考停止。
まず三流レベルであり、今すぐやめるべきことをお伝えします。
すぐに「どうすれば良いですか?」と質問することです。
なぜこれがNGなのかというと、完全に考えることを諦めているからです。
何か分からないことがあった時に、何も考えずに正解を教えてもらおうとする意識では、いつまで経っても成長しません。
それどころか、年功序列である日本社会においては、将来的にお金を貪る存在になりかねません。
考えることを諦めてしまったら、AIの方がよっぽど優秀です。
今すぐに、何も考えずに質問をして、解答を貰いに行くことをやめましょう。
自分なりに考えてみる。
まずは間違っていても良いです。
自分なりの解を考えてみることから始めましょう。
当然、上司に聞いた方が早く済むことは間違いありません。
ですが、先に述べた通りで無思考で答えを貰いにいく行為はNGです。
多少時間に余裕があるのであれば、自分なりの解を導き出しましょう。
そうすることで、2つのメリットがあります。
1つは思考力が高まること。
自分なりに解を導き出すのですから当然、思考の練習になります。
だからこそ、あまり時間をかけなくても良いので、自分の解を導き出すことを習慣化しましょう。
もう1つは、自分の上手くいかない方法を指摘してもらえることです。
経験も知識にも大きな差がある上司と比べて、自分の導き出す答えはお粗末なものになるでしょう。
私も、上司が出す解と自分の解を見比べてみて、自分が未熟だったと感じることが多々あります。
だからこそ、自分自身の解を事前に出しておき、自分よりも長けている人の解と比較することで、
・何が足りないのか
・どこがイケてないのか
を知ることができます。
これを繰り返せば、自分自身の思考の幅が広がります。
粗くても浅くても良いです。
正解を出すのではなく、自分自身の最適解を導き出すことを意識していきましょう。
まとめ
今回は「最適解を導き出すこと」についてお伝えしてきました。
今の世の中のビジネスシーンにおいて、正解を導き出すための方程式やフレームワークは存在しません。
だからこそ、自分なりの経験や知識を踏まえて最適解を導き出す努力が必要不可欠です。
すぐに答えを求めようとするクセを改め、常に自ら最適解を考えるよう意識しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!
ぜひ、次回もお楽しみに!
過去の記事はこちら
過去の記事は、以下のマガジンでまとめているので気になった方はぜひご覧ください!
告知
Z世代をつなぐコミュニティ『i-Willink Community』を立ち上げました!
「学び合い高め合うコミュニティ」をモットーに、コミュニティ内の活動や実際の案件を通じて、楽しく学べるコミュニティを目指しています!
今回の記事でお伝えしたような内容を議論したり、実践できる場になっていますので興味のある方はぜひ初月無料期間を利用して体験しにきてください!
メンバーシップを開設しました!
『i-Willink Community』noteメンバーシップを開設しました!
Z世代向けのオンラインコミュニティで、Z世代の仲間同士で「楽しく、成長する。」をモットーに様々なことにチャレンジしています!
過去には、
・本の出版
・子ども向けプログラミングスクールの開催
などなど、メンバーのやりたいを仲間と共に実現していきます!
現在は、SNSアプリ開発を進行中。
何かやりたいことがあるけど、どうすれば良いのかわからない。
そういった方はぜひご参加ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
