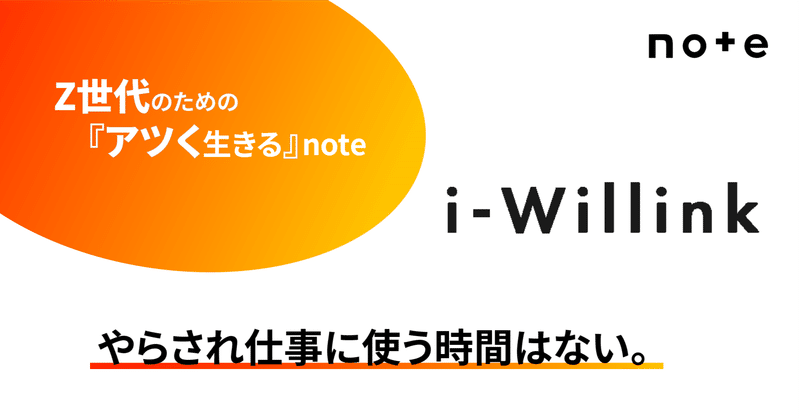
やらされ仕事に使う時間はない。
主体的に物事に取り組む。
この言葉が意味することは何でしょうか?
私たちが今後の働き方を考える上で不可欠なキーワードが、この「主体性」です。
ですが、この主体的というのは、とても抽象的な言葉で、人によって捉え方や粒度が異なります。もちろん、主体性に物事を取り組むというやり方に、正解不正解はありません。
今回は「真の主体性とは何か?」というテーマで、ビジネスシーンのケースを中心に考えていきます。
主体性の粒度。
まずは、主体性という言葉の定義について考えていきたいのですが、改めてご自身で「主体的に働く」ということのレベル感について考えてみてください。ここでは、3つのパターンに分類して、粒度の違いというものを認識いただければと思います。
指示待ち人間
まずは指示待ち人間と呼ばれる人について。この指示待ち人間に入る人たちは、主体性は皆無です。これは言わずもがな。問題なくご理解いただけると思います。
積極的に仕事を取る人
次に考えていくのが、積極的に仕事をとりにいく人についてですが、ここは意見が分かれるところかと思います。
この積極的に仕事を取りに行くことは、一見すると主体的に思えるかもしれませんが、ここに該当する人も主体性があるとは言えないというのが私の答えです。
結局、人からた仕事であることに代わりありません。頼まれ仕事における主体性は「与えられた仕事をどのように効率遂行するか」、「どのように品質を高めるか」という範囲にとどまります。つまり、このレベルでは依頼者の想像の範疇を越えることはできません。
この、積極的に仕事を取る人は主体性ではなく積極性という言葉が正しい表現だと思います。
仕事を生み出す人
本来の主体性とは、自分自身の価値観や目標に基づいて、自分自身で仕事を創り出し、遂行することです。つまり、新たな企画や提案だったり、チームや組織への貢献など、ゼロから自分で生み出した仕事こそが、主体的な仕事であり、主体的な働き方であると考えます。
なぜ主体的な働き方が重要なのか。
なぜ主体的に働くことが重要かということについて話していきます。
シンギュラリティはすでに起きている。
シンギュラリティとは、技術的特異点と言われ、簡単にいうとAIが人類を超えることを指す言葉です。このシンギュラリティは西暦2045年に起こると、一般的には言われていますが、私の見解ではすでに起きていると思っています。というのも、先に述べた指示待ち人間や仕事をもらいにいく人たちは、徐々にAIに代替されていく傾向が見受けられるからです。そういった人たちにとっては、すでにシンギュラリティは起こっていると言っても過言ではありません。
AIの高度な分析能力と処理速度が、ルーチンワークや単純作業を効率良くこなすことを可能にしていて、パワーに関して言えば人間よりも圧倒的に優れています。つまり、指示を出したことによって生み出せる成果に関して言えば、すでに人間に勝ち目はありません。こういった状況から、自ら仕事を生み出す主体性を持つことは、もはや社会人として生きていくための必要条件であると言えるでしょう。
想像の範疇を越えなければ、イノベーションは起こり得ない。
もし私が何が欲しいかと聞いていたとしたら、人々は『もっと速い馬』と答えただろう
アメリカの実業家であり、フォード・モーター・カンパニーの創設者であると同時に、自動車産業のパイオニアでもあるヘンリー・フォードが言ったとされる言葉です。
この言葉が意味するのは、人々が求めていたのは既存のものの改善ではなく、全く新しい価値であり、その新しい価値に至る発想の源泉は、他人から得たものではなく自ら主体的にニーズを探っていったことだということ。これが、主体性から生まれるイノベーションの代表例です。既存の枠組み(移動手段は馬である)にとらわれず、自ら新しい価値を創造することを追求し、車(馬に変わる移動手段)という発明を実現したのです。
人から頼まれたこと=人が欲しがっていることを頼りにしていては、想像の範疇を越えることはできません。それは現時点でのAIも同様です。AIは過去の膨大な情報を元に、最適解を出すことを得意としていますから、全く未知の真新しいものを生み出すのは不可能でしょう。
このように、AIの台頭という時代背景と、イノベーションを起こす(想像を越える成果を出す)という観点から、仕事における主体性の重要性はこれまで以上に高まっています。主体性を持ち、自ら考え、行動することが、新たな価値を創造するスタートラインです。
それは、個人の成長と共に、社会全体の発展にも繋がります。今こそ、主体的に働くことの意味を自分に問いただし、その必要性を今一度考えてみましょう。それこそが、AIに食われてしまうのではなく、AIと共存することにつながるでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
