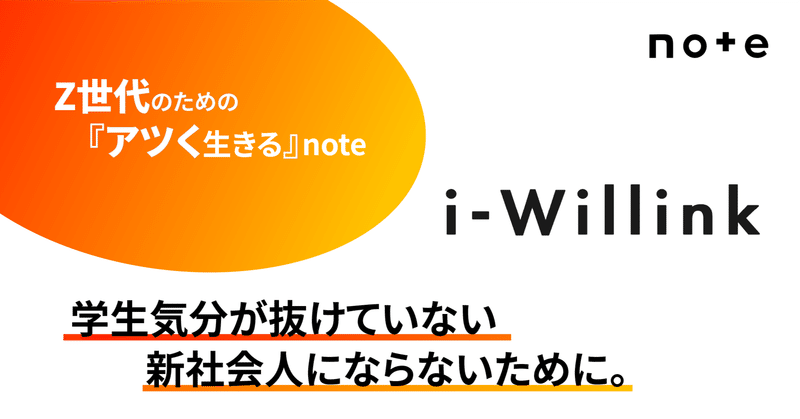
学生気分が抜けていない新社会人にならないために。
こんにちは、白井です。
今回は、2023年度に新社会人になった方々へ、新社会人の良いスタートを切るための心構えをお伝えします。
また、若手のうちから意識しておくべきことでもあるので、今年から社会人2〜3年目の方々も、ぜひ参考にしてみてください。
もうお客さんではない。
まず、学生と社会人の大きな違いは、客ではなく、サービスを提供する側であるということ。
これは、意識すべきというよりも、社会人として当たり前のことです。
が、社会人2, 3年目でも意識できていない人は少なくありません。
学生のうちは、できないことを教わってできるようになるという流れでしたが、社会人はそうはいきません。
仕事で壁にぶつかった時、教えてもらえば良いと思っていたら、一向に成長できません。
壁にぶつかったら自分で試行錯誤しながら解決する。その力を身につけていくことが、学生との大きな違いです。
基本的に、仕事で学ぼうという意識を持たないようにしましょう。
もちろん、仕事で学べることもたくさんありますが、それは自分の成果から生まれる副産物にすぎません。
あるべき姿はその逆。
自分が日々学んだことを仕事でアウトプットするようにしましょう。
この意識を1年目から持てているだけで、持っていない人とはとても大きな差が生まれるでしょう。
自分の頭で考え、判断すること。
学生の頃は、正解に向かって答えを出していくことがほとんどでした。
ですが、社会人はそうではありません。
職種や業種にもよりますが、答えや前例のない課題を解決することが、社会人は往々にしてあります。
大卒の方であれば、卒業研究のようなイメージです。
自分はもちろんのこと、教諭(仕事の場合は上司)ですらも答えが分からないことに取り組んでいく。
社会に出ると、そう言った場面が多くなってきます。
特に、これからの時代は、進化がこれまで以上に激化しています。
ここまでの社会の構造の変化は、これまでに起きていないため、私たちが生きているこの時代こそが、とてつもなく大きな前例のない課題です。
そういった環境で、他人から答えを求めていてばかりいるのでは、周りに置いてかれてしまいます。
その人に判断を委ねるよりも、ChatGPTの方がよっぽど活用できます。
情報が溢れかえっていて、かつ変化が激しい現代社会で、自分の頭で考えて判断しアクションを起こす。
このサイクルを習慣づけられれば、周りの同僚たちに大きな差をつけられることは間違いないでしょう。
今回は、新社会人へ向けて意識しておいて欲しいことをお伝えしました。
新社会人に限らず、若手のうちから意識できていれば、自分を大きく成長させられるようになる心構えでもあります。
ぜひ、これからの長い社会人生活の良いスタートを切っていきましょう!
以下の記事も、ぜひご覧ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
