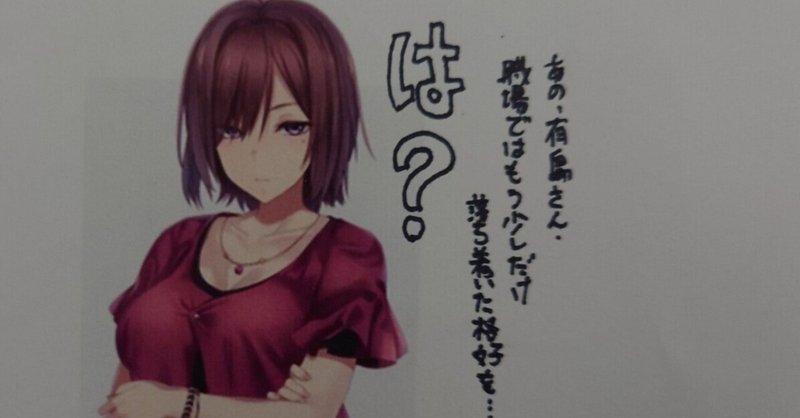
【白昼夢の青写真 case1 二次創作 第9話】
祥子を前にして、無様に怯み、脅え、腰を砕いた。私のこの選択は、私の人生を今日より明日、明日よりあさって、より確実に悪化させるものだった。
アラームが鳴る前に目が覚めた。昨日同様、目が覚めた瞬間に、不快感の塊のようなものが喉につまった。時計を見たら、二度寝をするほどの時間はない。しかし、朝の支度をするには早過ぎる。中途半端な時間だった。
本棚の最上段にある、緑色の背中をしたシェイクスピアの訳本が目に入った。全部で37冊あるはずだ。
「To be, or not to be, that is the question. 」
シェイクスピアの四大悲劇のひとつ、ハムレットにおける有名な一節。
どう日本語に訳すのが最適なのかについては、諸説あり、今にしてなお議論となることもある。一番有名なのはおそらく「生きるべきか死すべきか、それが問題だ。」であろう。私自身は、この緑色の背中の本で翻訳を務めた人の「このままでいいのか、いけないのか。…」という訳が、一番すわりが良いと思っている。祥子とも、そんな話をしたことがあった気がする。遠い昔の話だ。
このままでいいのか、いけないのか。
どんなに自分が悲惨な状況にあれど、それでも、人生は続く。不面目を極めても、醜態を晒し続けても、生きている限りは、明日が、あさってが必ずやってくる。
なら、生きていなければ?自らの死についてわずかでも思いを向けたことで、ふと、波多野秋房のことを思い出した。作家として大成功し、全てを手に入れ、我が世の春を満喫しているであろう最中、あっけなく逝った。死因は心臓発作らしい。
波多野秋房が亡くなったということは、当時大きなニュースになった。私が憧れた道のど真ん中を闊歩し、私の理想を体現し続けたゼミの先輩の死には確かに衝撃を受けたが、心情的には意外なほど淡白だったというか、これ以上に望むところのない、充実した人生だったのだろうな、と漠然と思う程度であった。
生前の波多野秋房は、人生を高らかに謳歌しているように見えた。小説執筆の傍ら、バラエティ番組に出たり、趣味に関する著作を何冊も出していた。仕事に遊びに、毎日が楽しくて楽しくて仕方がなかったことだろう。まさしく完全無欠の成功者。そんな人間が簡単に命を落とし、苦痛にまみれた日々を過ごす私が、こうして恥を刻みながら生き続けている。
何にせよ、幸せな人生であったに違いない。が、仮に悔いがあるとするならば、子供のことくらいだろうか。詳しい話は知らないが、結婚をして、子供をもうけたという話は聞いたことがある。亡くなったときには、まだ小さかったはずだ。波多野秋房は、父親としても完璧だったのだろうか。生き死にの際に思い浮かんだのは、子供の顔、子供への申し訳なさだったりするのだろうか。
不意にアラームが鳴り、本来の起床時間を告げる。波多野秋房を頭の中から振り払い、出勤の準備を始めるため、洗面所に向かう。
仕事に、使命感を持っているわけではない。自分のことを教師とすら思っていない。私は生徒に国語を教える装置として存在することに徹している。身も蓋もない言い方をすると、生計を立てるだけのために、くだらない仕事につまらない姿勢で臨んでいる。ただ、昨日と同様、欠勤しようという発想はなかった。
仕事をするという行為が、どうしようもない自分を人たらしめる、最低限の行為に思えた。同時に、そんな矜持が、いったい何のためになるのかと思った。楽しい人生、明るい未来を求めるには、既に遅い。そういう人生になるような努力もしていない。
このままでいいわけがない。
しかし、今日の私も、祥子から逃げるのだろう。事実、祥子と顔を合わさないよう静かに家を後にし、学校へと向かう。
*
「おっ、有島先生お疲れさん。俺もお疲れ様なんだけどね。今から図書館?その前に喫煙所行かない?俺も吸うから、どうせなら一緒にいこうぜ。」
全ての授業が終わり、図書館に向かおうとするところで、渡辺から声をかけられた。
ああ、とだけ返し、図書館ではなく喫煙所に歩みを進める。
「お前はたばこ持っていないだろ、くらい言ってくれよ。…先生、今日もお疲れな感じだね。何があったの、マジで。」
「別になにもないさ。」
「ならいいんだけど。嘘でも笑ってた方がいいぜ。それより昨日マッチングアプリで、俺のおふくろと同い年のおばさんからいいねが届いててさ…」
そんな話を聞きながら、時に気の抜けた相槌を打ちながら、体育館裏にある3畳ほどのプレハブ小屋に入る。
たばこをテーブルの上に置く。好きに吸ってくれという意思表示だ。互いにたばこを取り、火をつける。カチッという音が2つ鳴った。
「やっぱ先生、元気ないな。どうしたのさ。」
しばらくの沈黙ののち、煙を吐き、軽い深呼吸をして、私は口を開く。
「…お前は、お前の人生、このままでいいと思ってるか?」
渡辺には話さないつもりだった。しかし、魔が差したというか、とんでもないことを言ってしまった。さすがに恥ずかしい。
「げえっ。何??生徒指導みたいなこと言い出して。有島先生、本当に大丈夫?ヤバい宗教とかハマってない?」
「すまん。忘れてくれ。」
本当に忘れてほしい。頭を抱えたくなる。
少し時間を置き、吐き出した煙が換気扇に吸い込まれていく様子を見ながら、いつもより真面目な表情の渡辺が、話を始める。
「…んーまあ。別に、今のままで楽しいよ、俺は。有島先生みたいに賢くもないけど、バカな自分はそれはそれで好きだし。」
どんな自分であれ−もっとも、渡辺が客観的に見て人に劣る存在だとは全く思っていないが−あるがままの自分を肯定できる人間は強い。
「取り返しのつかないことになって、後悔したことはないのか?」
「ないことはないけどさ。でも、そういうのは、死んでからいくらでもすればいいんじゃないの?楽しい時間がもったいないじゃん。」
私には無い考え方だった。恥じて悔いて懺悔をすることで、その代償として何かしら救済に繋がるのではないかと信じる幼稚な私と違い、渡辺は大人だ。大したものだと思う。渡辺はもう一本私のたばこを取り、火をつける。
「子供の頃さ、勉強してるときに書けない漢字があって、答えを見ようとしたら、親にもっと考えろ、って怒られたんだよ。漢字なんて、算数と違って、知ってるか知らないかだろ?考えたってわかんないじゃん。そっから。考えて答えが出るなら考えるけど、考えても仕方がないものは考えない。俺はそうしてるけどね。先生も、それでいいんじゃない?賢すぎるんだよ、先生は。」
私の抱える問題は、考えても答えが出ない、というものではないが、考えていても仕方がないものでもある。
このままでいいのか。
いけないに決まっているが、ではどうしたら良いのかと一人で問い続けても、きっと答えは出ないだろう。
「まあ、先生、変な集まりに顔出して壺とか買うなよ。課金で救われるなら、貧乏人はいつまで経っても地獄だよ。それじゃ俺みたいな貧乏人の救いってどこにあるんだよ、って話だよな。うん。それにしても、今日のたばこはいつもと違う味わいだった。ごちそうさん。」
渡辺と別れ、図書館に寄ることもなく、真っ直ぐ家に帰る。祥子と、向き合おう。そう思えただけで、確かな進歩だと思えた。ずっと踏み出せなかった一歩。惨めでも、情けなくてもいい。昨日よりは前向きな気持ちで家へと帰る自分がいた。
*
あれから2年が経った。
ひとりの女の子が、私の勤める学校に入学した。波多野秋房の一人娘、波多野凛だ。むろん、その頃の私は、彼女がそうだとは知らなかった。
翌年、彼女が2年生になったとき、思いもかけない形で私の人生は大きく動き出した。私は、45歳になっていた。その後の私と凛、私と祥子の話は、また違う場所で語られているとおりだ。
私の作品を読んで「生きてみようと思った。」と言ってくれた凛。そして私は私で、命がけで波多野秋房に挑んだあの日々。波多野秋房が私に、彼の持つペンの魔力を託してくれた気がした。父親として「娘を助けてくれ。」「娘に言葉を届けてやってくれ。」と言ってくれたのかもしれない。彼が生前、唯一成し得なかったことを。
私が確かに一人の女の子に対し物語を届け終えたことで、私の幼い憧れは、作家になることに対する執念は、ついに成仏した。
42歳の誕生日から続いていた本厄が終わった。祥子とのことをなかったことに出来るわけはないが、それでも、捨てる気になりさえすれば、辛く苦しい過去など、そうそう残らないものだ。私の今日は、凛と、凛とのあいだの子供と紡ぐ日常は、きっと、明るい未来へと続いていく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
