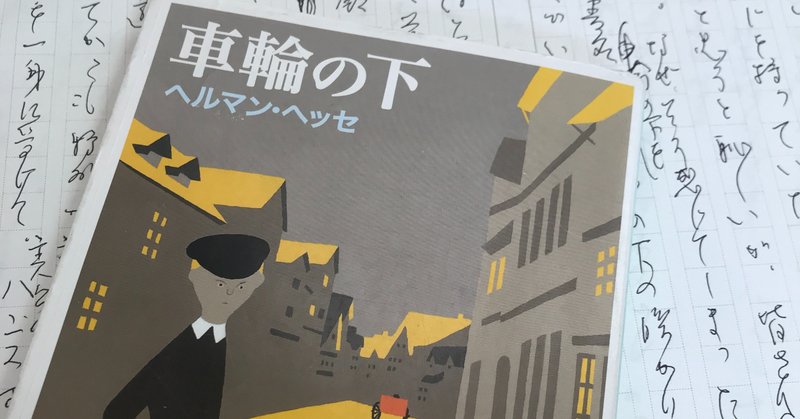
ヘルマン・ヘッセ(著)『車輪の下』を読む。
ヘルマン・ヘッセの『車輪の下』はもうずいぶん長い間、積読の状態になっていた。
『車輪の下』というタイトルから受ける印象はどこか牧歌的だなあと、私は勝手に解釈していた。このような感じを受けているのは私だけなのかもしれないと思うと、恥ずかしいが、皆さんはどうなのだろう。
なぜそう思ってしまうのか。それはこのタイトルの『車輪の下』を幌馬車の下の暗がりと勝手に思い込んでいたからだ。
この本は、そんなほのぼのとした小説ではない。
いや、前半は主人公の少年は、野で遊び、川で魚を釣ったりしている。この自然の描写は美しいし、ヘルマン・ヘッセの自然に向ける眼差しは温かい。
自然の中で遊び、勉強も一生懸命……。牧師や学校の先生の期待を一身に受けて、主人公のハンスはその地域から選ばれてひとり神学校の入学式に臨む。
ハンス少年は神学校の入試を二番の成績で合格することができた。
そうだとわかっていたら……完全に一番になれたのに。
ハンス少年が二番で入学したと報告を受けたときに、思わず出た言葉だ。
神学校に入るとオットー・ハルトなーという少年と友達になる。
その後の展開はネタバレになるので書かないが、どうして自然の中で自由に動き回っていた少年が、勉強も人一倍して二番で入学した少年が、なぜ「車輪の下」に押しつぶされてしまったのか。
作者のヘルマン・ヘッセ自身も幾度となく学校飛び出しているので、この小説は作者の少年期の実体験に基づいているものだ。
車輪の下の「車輪」とは一体何なのか。
この小説は不思議なことに日本だけで人気がある小説だと言う。それだけ日本の子どもたちがUnder Pressureの状態にあるのだろう。
ヘルマン・ヘッセの小説を初めて読んだ。
自然の細やかな描写が美しい。得てして小説はその筋書きを追い、奇抜な展開を好む人が多いのだが、私はヘルマン・ヘッセの自然に対する気配り心配りとその描写力に感心した。自然が少年の心を優しく包んでいる。
そんな自然の中で育ったハンス少年がなぜ?
この小説の最後の場面を読むと、特にそう感じる
ーーー
文字を媒体にしたものはnoteに集中させるため
ブログより移動させた文章です。
↓リンク集↓
https://linktr.ee/hidoor
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
