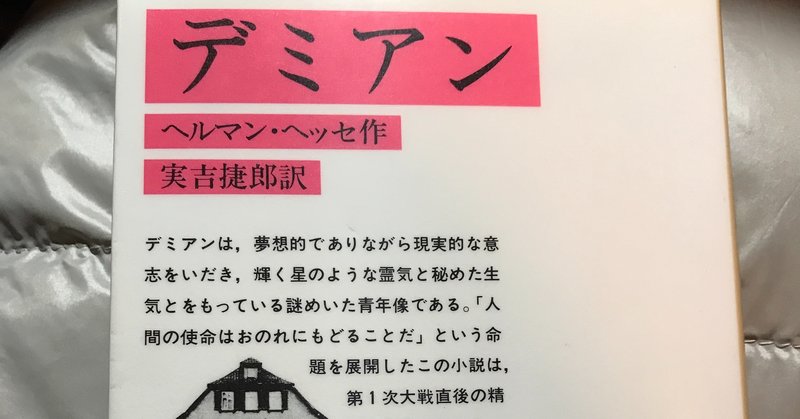
ヘルマン・ヘッセ(著)『デミアン』を読む。
ヘルマン・ヘッセの小説は日本では『車輪の下』が有名ですが、これは日本だけの現象だそうで、世界ではこの『デミアン』を読む人がたくさんいるのです。第一次世界大戦後の若者たちに長く読み継がれている小説です。
ヘルマン・ヘッセは学生時代に自殺を企てるほど悩みます。何に対して悩んだのかは『車輪の下』に詳しく書かれていますが、私自身、学生時代(中学、高校時代)にそんなに深く考えたことがなかったので、ヘッセの悩みそのものさえ、はっきりとつかめないままです。
ただ、この『デミアン』の最初の部分にあるエピソード、それはこの小説の主題を暗示しているのですが、多くの少年たちには共有できるであろうこのエピソードは、よく理解できます。
小さな町のラテン学校に通う、純粋な主人公のジンクリエルが、悪童のクロオマアにおどされる場面です。
悪の道から逃れられない主人公を助けるのがマックス・デミアンという少年です。つまりヘッセはまず悪の世界を見せ、その後、善の世界に入っていきますが、しかしそれは単純な道ではありませんでした。
なぜなら、悪は暗く陰湿なものであり、善はどこまでも明るく、神様の光なのです。ジンクリエルはこの根本的な比較を「果たして本当にそうなのか」と思うようになります。
それはデミアンが、アダムとイブの長男であるカノン(旧約聖書では悪役) は悪人ではない、と発言するからです。つまり、悪人であるクロオマアにいじめられている自分を助けてくれたデミアンは、一方ではカノンを擁護するのです。ジンクリエルの頭がこんがらがるのも当然です。
実はこれには深い意味があります。なぜならこの小説は第一次世界大戦後にあの悲惨な戦争がなぜ起こったのか、ドイツだけが悪いのか、勝ったフランスが絶対的に善だろうか。そうじゃないだろう、と考えたのです。
善とか悪とかの区別なく、それらが溶け合い、昇華していき、高い精神性に向かうべきではないのか。
音楽をぼくはとても愛していますが、それは音楽には、道徳的なところが非常にすくないからだと思います。ほかのものは、みんな道徳的ですよ。そして、ぼくは、そうでないものを、さがしているんです。道徳的なもののために、いつも苦しんでばかりいましたから。
世の中、半分が善で半分が悪なんだよ。それが世の中だし、人間の本来の姿なんだよ。だから、自分自身でよく考えることだ、ということでしょう。
自分で考えたり、自分で自分をさばいたりすることをめんどくさがる人は、だれでも、昔からきまっている禁令に、だまって従ってしまうんだ。
ヘルマン・ヘッセはこの点を強調しながら、この形而上学的小説を書き上げたのだろうと思います。
一体全体、私たちとは何者か。なぜ戦争が起こるのか。それを槍のように突き進む形ではなく、広げる形で、深掘りする形で私たちに提示してくれるのです。そうすることで自分自身の存在している意味をつかむこともできると思います。
『デミアン』は戦争が始まる場面で終わります。
世界がなんと変貌してしまったことか。ぼくは総力をふりしぼって、世にもこのましいえすがたを、よび出そうとしていたのに、今は、運命が突然あらためて、ぞっとするほどおそろしい仮面のなから、ぼくをじっと見ているのである。
ーーー
文字を媒体にしたものはnoteに集中させるため
ブログより移動させた文章です。
↓リンク集↓
https://linktr.ee/hidoor
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
