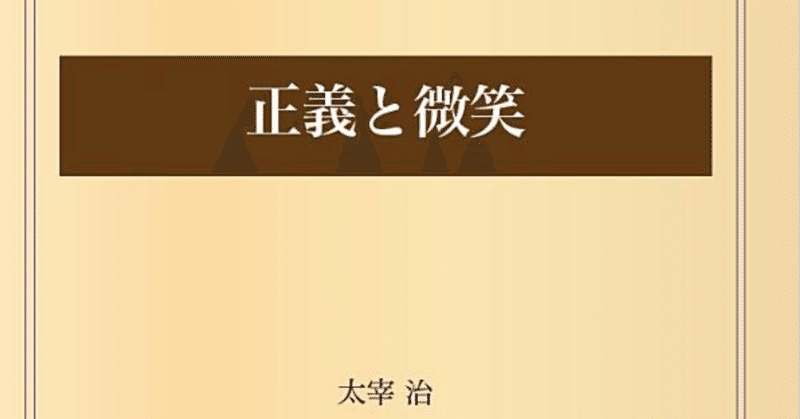
太宰治(著)『正義と微笑』を読む。
今日の昼のことでした。
会社の事務所で、先代の社長の奥さんが、
「今朝、チャンネルを変えたら、途中で教育テレビが映って、めずらしく太宰治をやっていたわ」
と話しかけました。途中で映ってというところが、日頃は教育テレビなんて見ませんよ、って強調したいんだろうけど、意外と熱心に見ているかもと思えるような、ぎごちない言い方でした。
「そうですか、今年は太宰治の没後七十周年ですからね」
と私が言うと
「へえー、そうなの、私の弟が暗い小説が好きでねー。よく太宰を読んでいたのよ」
この「暗い小説の典型は太宰治だ」との考えは一般の常識ですが、太宰の番組が気になったあなたも暗い太宰治の小説が好きなのでは……と思いました。
今回読んだ小説『正義と微笑』は暗い小説ではありません。
さらにここが重要な点ですが、太宰治がこの小説を書いたのは昭和十七年一月から三月にかけてです。太平洋戦争が始まった直後なのです。この時期に書いた小説ですが、読んでいてすこし頬がゆるむくらい楽しい小説なのです。
太宰治は自分が道化の役を演じることで人を喜ばせる術を一生貫きました。
この小説には有名な一文があります。
誰か僕の墓碑に、次のような一句をきざんでくれる人はないか。
「かれは、人を喜ばせるのが、何よりも好きであった!」
僕の、生れた時からの宿命である。
太宰治を読んでいる人はご存知でしょうが、太宰の中期の小説は明るいものが多いです。
特に世の中が一丸となって戦争に突き進むその最中に、その世の中の流れに逆らって、このような明るい小説を書かなければならなかった、太宰の心の哀しみを感じるほどです。
特に戦前、戦中の太宰の小説は、汚い池の水に咲く蓮の花のようではないかと、私には思えるのです。
kindle版は無料で読めます。
ーーー
文字を媒体にしたものはnoteに集中させるため
ブログより移動させた文章です。
↓リンク集↓
https://linktr.ee/hidoor
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
