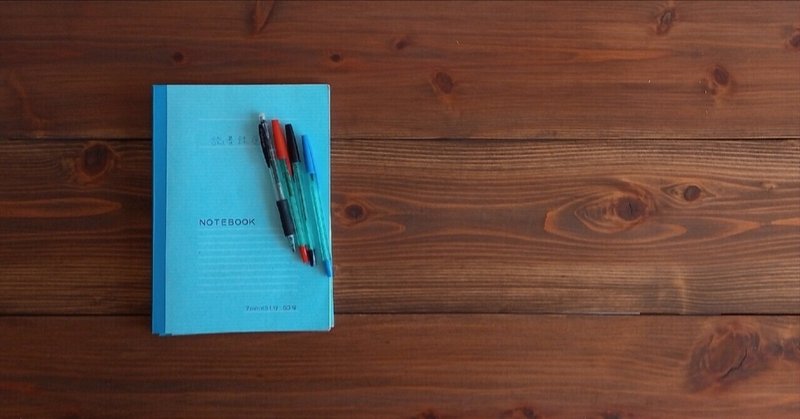
ポンプラボ「にっぽんスズメ散歩」読書感想文
スズメを熱く語るのは避けたい。
「スズメが好き」と言ったものなら失笑される。
それでも、スズメの魅力を話したものなら変人扱いとなる。
感心されたことが1度もないのだった。
そんなことだからか。
スズメの生態は、未だに不明な点が多いという。
おそらく学者の世界でも「スズメの研究をしています」とは言いづらい、もしくは失笑されると思われる。
スズメの歴史は長い。
スズメは人間が穀物を育てる地域に生息している。
そして人家に巣をつくる。
つまりは、村の成立と共にスズメは在る。
人間を警戒しているように見えるスズメだが、多くを人間社会に依存しているのだ。
スズメの恩返し
冬のスズメは、半日食べないと死んでしまう、という。
それを聞いて、古米を鉢受けにいれて、ベランダに置いてみたのが最初だった。
2週間ほどは、1羽も来なかった。
やがて1羽が見つけた。
すると、仲間を連れて毎日来るようになっていく。
朝になると、くちばしでコンコンとガラスを叩いて催促する者もでてくるようになる。
スズメは集団となっていった。
2年後には、50羽ほどが来るようになる。
3合が10分ほどで食べつくされるのだ。
そして突然の逮捕。
「あのスズメたち、食べていけるのかな」と思っているうちに受刑者になってしまった。
そして、ある日。
鉄格子の窓の向こうから「ピヨッ」と聞こえる。
ああ、あのスズメたちが来てくれたんだ、と本気で思った。
朝から泣けてしまう。

*----- 写真 -----*
中野さとる
宮本圭
熊谷勝
井川祥宏
片柳弘史
*-----------------*
スズメ語の解釈
生物のなかで鳥と人間だけが声帯が発達している
スズメ語がわかる、と言おうものなら1発でアウトだ。
ついに頭がおかしくなった人となってしまう。
しかし未決囚のときに、立花隆の「脳を究める」を読んで、鳥類は簡単な言葉を話すのを知った。
それによると、2足で直立するのは、鳥と人間だけ。
直立することにより、気管の空気の通りがよくなって、声帯が発達する。
専門家の研究により、鳥類の鳴き方の中には、短い構文も確認されたという。
やはりあるのだ。
スズメ語が。
スズメ語における「ピヨッ」の正しい発音と解釈
さきほどの「ピヨッ」を訳せば『ここにいるよ』となる。
語尾が下がり気味の「ピヨッ」の場合は『だれ?』となる。
「ピィッ」は仲間同士で多用される。
飛び立ちながらの「ピィッ」は『いくよ!』と言っている。
夕方のスズメのお宿での「ピィッ」だと『どこ?』とか『ここだよ!』と身内を探している。
これが強い「ピィッ」だと『あぶない!』とか『なんかきたぞ!』という警戒語になる。
さらに「ピィィッ」と、語尾が若干伸ばされると『逃げろ!』となる。
スズメ語では「ギィ」が不機嫌を示す説
娑婆のときにネットで調べたときには、誰だか忘れたが、ある生物学者が、スズメが警戒するときは「ギィ」と鳴くとあった。
が、反論したい。
それは誤りである。
その学者は、フィールドワークが足りてない。
スズメが「ギィ」と発するのは、通年で朝イチが多い。
要は『くっそ、ねむいな』とか『ああ、腹すいた』という不機嫌を表す。
あとは、繁殖時期の3月から4月にかけてである。
この時期の日中から「ギィ」を発するのは、観察しているともっぱらメスである。
オスにまとわりつかれて『ちょっとやめてよ!』とか『もう、むこういってよ!』という不機嫌さであった。
この本の感想と特徴
また、スズメを語ってしまった。
読書感想文だった。
この本は、友人から差入された。
自分が、スズメが好きというのを知ってのことだ。
もっとも、そのときの彼も、失笑しただけだったけど。
本書は、スズメ写真集といった内容である。
どの写真も、スズメ好きを自認する者によるベストショットとなっている。
小さな黒目に丸い頭、じゃれあっている様子、毛づくろいをしている仕草、羽ばたくときの躍動感。
冬のふっくらしてる姿、クチバシの端が黄色い子スズメの顔、砂遊びに夢中になってる姿、身を寄せ合ってる様子。
スズメ好きの、スズメ好きによる、スズメ好きのための1冊なのは間違いない。
どの写真も「わかるぅぅ」という感想に尽きる。
この独居の中で、どれほどの癒しになることか。
写真の掲載のあとには10ページほど、撮影者がスズメについて熱く語る。
巻末にも、10ページほどスズメの考察がなされる。
スズメ愛好家でもあり、スズメ研究家でもある田口文男氏によると、スズメの固体は年々と減ってきているらしい。
2000年初頭と比較すると、もしかすると5割は減っているかもしれないと懸念する。
驚きである。
もっと、ふんだんにいると思っていた。
「もし、日本からスズメが姿を消したらと考えるとゾッとする」という氏のコメントには、全く同感である。
都市部のスズメは夏に命を落とす説
スズメ界の大御所である田口氏は、とくに都市部でスズメが減ってきていると指摘する。
これには、深くうなずく。
スズメの食欲は旺盛だ。
都市部で虫などチマチマ食べているよりも、田んぼがある地域で米を食べるのがスズメにとっては幸せなのだ。
あと都市部でスズメが減少している理由のひとつには、自分は推測がある。
夏の猛暑を乗り越えられないスズメが多数いる、とにらんでいる。
というのも、観察をはじめた夏からだ。
ひと夏の間に、道路の隅にジッうずくまっているスズメを見つけることになる。
その数、3羽から5羽。
これは地面に擬態しているので、スズメに関心がない者は、ほぼ全員が気がつかないで通りすぎてしまう。
が、スズメに敏感な自分は、一見して、彼ら彼女らだとわかった。
そしてもう、飛べなくなっているスズメは、間もなく死んでしまうのだ。
夏の猛暑にやられるスズメは、相当数いると推測された。
スズメの寿命は1年なのか?
先ほど、スズメの生態は、未だに不明な点が多いと書いた。
寿命にしても、言われるのはまちまちである。
観察したところ、都内のスズメについては、短くて1年、長くて2年ほどと思われる。
まず、5月の末には、子スズメが姿を見せるようになる。
冬が来るまでの行動は、単独か小集団である。
冬になると群れとなる。
そのときは、クチバシの端が黄色いスズメが半数以上を占めているのが観察された。
クチバシが黒い大人のスズメどこにいったのか?
どこにもいかない。
夏に命を落としている、と考えるのが通常である。
そして翌年の3月頃には、全員が立派な黒いクチバシの大人になって繁殖をする。
で、5月の末に、子スズメが飛ぶようになる。
そして、夏を乗り切ったスズメが、まだ生きることになる。
※ 筆者註 ・・・ スズメ研究は加速しているようです。2015年ころのネットによると、野生のスズメの寿命は最低2年から長くて5年が主流でした。が、いま検索してみると、1年4ヵ月説、1年説も唱えられているのです。私は、当時から1年説を唱えてます。
このほかに私のスズメの観察は、子育ての時期について、聴覚について、テリトリーについて、運動能力について、警戒の基準について、冬の群れについて、擬態について、受刑者との関係、と多々ありますが、すでに読書感想文から大きく逸脱しているので、ここまでにする次第なのです。
