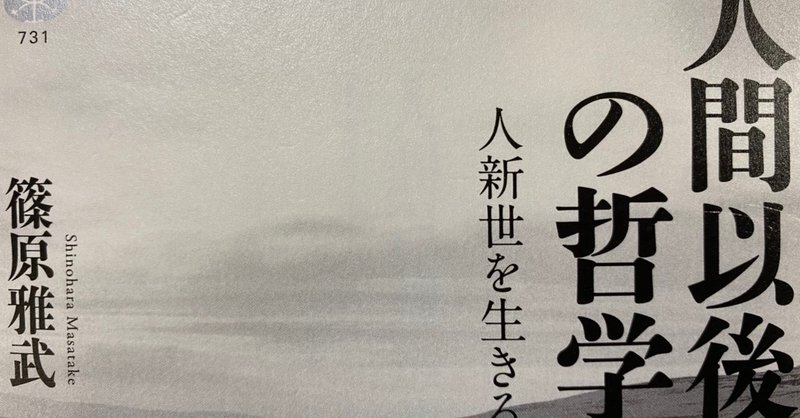
「人間以後」の哲学/篠原雅武
人新世の世において、僕たち人間の生活を危機に陥れようとしているのは、単なる自然ではなく、第2の自然である。
ここで言う「第2の自然」とは、僕ら人間の手によってすっかり状態が変化してしまった人新世の自然環境であり、それ以上に僕ら自身がつくったにもかかわらず僕らによって放棄された、大なり小なりのサイズのさまざまな人工物――マイクロプラスチックや各種化学薬品で汚染された水から人が暮らさなくなった巨大な建物の廃墟や廃棄された原子炉まで――を含んでいる。
それらはいずれも人間のコントロール下から外に出てしまっているという意味で、非人間的な自然である。
もちろん、それはずっと以前から存在しているのだが、それに僕らが関心を傾けざるえなくなっているのは、それらが僕ら人間の生活や生命を脅かす存在としての姿を明瞭にあらわすようになったからだ。
そんな世の中における思考、哲学のあり方を問うのがこの『「人間以後」の哲学』だ。
著者の篠原雅武さんは、こう書いている。
世界の他性、奇妙さは、身の回りのこととして経験される日常的な人間世界に埋没しているかぎり、気づかれることがない。地震や津波や巨大台風といった人間的尺度を超えた事態に飲み込まれ、人間として生きるのが危うくなるとき、私たちは、自分たちの日常意識と相関する身の回りとしての人間世界が、人間世界に尺度を超えた巨大さのなかの一部分でしかないことに気づかされる。
人間がこれまで視野の外に追いやっていた、非人間的な世界。それは人間が存在しようとしまいと存在している世界でもある。
しかし、人新世の世が生まれたように、人間はその非人間的世界にも影響を及ぼしているし、非人間的な世界は人間がどんなにそこから遠ざかろうと僕らに影響を及ぼし、僕らはそのなかで生きざるを得ない。
そのことに僕らが気づいていなかったとしてもだ。
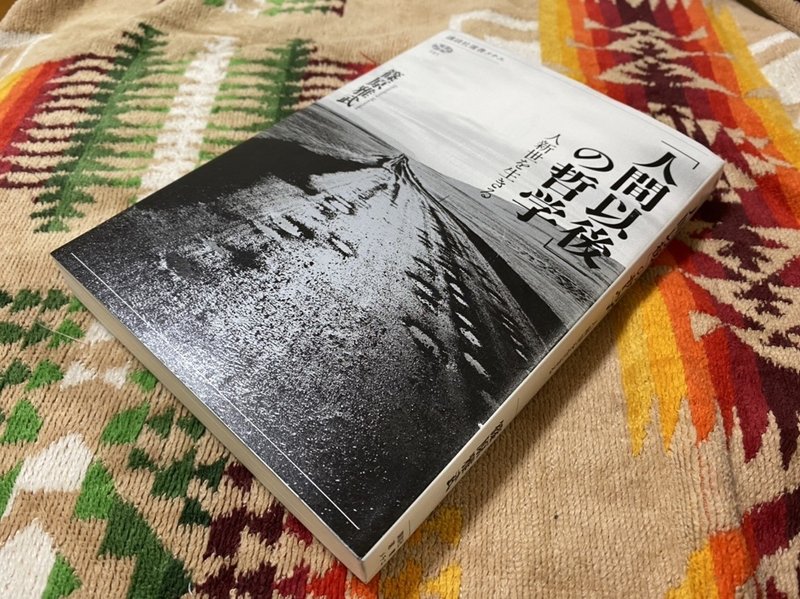
しかし、もう非人間的な世界を無視し続けて生きていくことはできなくなっている。
そんな状況下で、どう哲学するか=思考することができるかが本書で問われていることなのだろう。
人間世界と的な事物の世界地球的事物の世界
この本で篠原さんは「世界についての思想的設定を変更する」ことを目的としている。
安定的に思われる人間の世界が実は脆く、定まらないものであることを思想の前提とするように変更しようというわけである。
人間世界は完全に自律的ではない。それをとりまく地球的事物の世界を人為的に改変する過程で、人間世界そのものが地球的世界に飲み込まれ、その一部になってしまった。人間は、人間世界と地球的世界の2つの世界に同時に住みつくようになった。
人間世界とは別に存在する非人間的な世界に目を向けることは、現在の思想的潮流だといえる。この本で取り上げられている、ティモシー・モートン、グレアム・ハーマン、カンタン・メイヤスーら哲学者の仕事だけでなく、エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロやブリュノ・ラトゥールのような人類学、社会学の領域においてもその兆候は見受けられる。
この本で言及されていないところでも、『ポストヒューマン』のロージ・ブライドッティ、『植物の生の哲学』のエマヌエーレ・コッチャらの展開するものも、人新世の人間世界の危機において、これまでの人間中心主義的な思考に対してオルタナティブな思想のあり方を探ろうとするものだ。
数年続いている気候変動による大規模な被害(日本では主に雨によるものだし、オーストラリアやアメリカにおける大規模な山火事のようなものある)、そして、今回のパンデミックによる社会や経済の危機、あるいは、この本で言及されていない人間の知性に変わろうとするAIの脅威も含めて、人間社会の危機は誰の目にも明らかになっているのだから、それがどの領域でも問われるのは当然である。
それほど危機は誰の身にもリアルなものになっている状況では、この本で指摘される、非人間的な領域から人間社会への危機が迫ってきており、にもかかわらず、それら非人間的な脅威も元を正せば人間の野放図な行いに端を発するものであるという指摘には取り立てて目新しい視点があるわけではない。
しかし、次のようなかたちで世界の脆さを著者が指摘するとき、あまりにも静的で確固たるものとして世界を捉えること自体が、とてつもなく人間的で、人間にとって都合の良い世界観であったということにあらためて気づかされる。
じつは世界は、本当はずっと不確定で脆かったのかもしれない。この現実を、まずは認め、受け入れていくことが求められている。
そのことで、何が見えてくるだろうか。1つには、世界は感覚的なものの領域である、ということだ。そこは人間が概念的に把握するのに先立つところで生じ漂う感覚的なものの領域であり、人間をとりまくものでありながら、事物としての実質はなく、かたちなきかたちとして存在している。
かたちなきかたちとして、実質をもたない事物の世界はある意味では、『時間は存在しない』のカルロ・ロヴェッリのいう「この世界は、ただ1人の指揮官が刻むリズムに従って前進する小隊ではなく、互いに影響を及ぼし合う出来事のネットワークなのだ」だったり、『流れといのち』のエイドリアン・ベジャンの「コンストラクタル法則は生命を、生物界と無生物界の両方の領域で自由に進化する動きと定義している」といった、理論物理学者たちの世界の見方にこそリンクしてくる。
その意味において、ラトゥールが『虚構の「近代」』において暴いた「人間、非人間、なかば抹消された神を同時に生産すること、そうした同時生産を隠蔽しつつ3つを独立したコミュニティとして扱うこと、分離した扱いの産物として、水面下でハイブリッド(異種混交)を増殖し続けること--以上の3つの実践から近代は成り立っている」という近代が前提とした、人間世界と地球的世界の区分が壊れ、人間世界ももはや、かたちなきかたちとしての無数の量子たちの出来事のネットワークでしかなく、生物界と無生物界の両方の領域で自由に進化する動きとしてあるような事物的世界に巻き込まれているのだといえる。
それをどう認識しなおすか?ということが本書での問いだと言えるだろう。
壊れるということをはじまりと捉えて
著者が特に親近感をもって語るのは、ティモシー・モートンだろう。
たとえば、こんな指摘は面白かったし、世界を捉える姿勢としてとても共感できる。
モートンはまず、壊れるということを、始まりとして捉える。始まるとは、何かが新しく起こり、出現することであり、だからそれは何よりまず「不確か」で、不気味で、何が始まったのかよくわからないという不安をともなう。だが、始まりは、始まる前に成り立っていた状況そのものの崩壊であり、だからそのなかにいる者にとって始まりはなにが起きたかわからないというだけでなく、そこにいることがはたして安全かどうかもわからない、もしかしたら、そこにいることがそのまま死への道行きとなる危うい状況なのかもしれない。ゆえに、壊れてしまった状況は、そこにいる者の認知を歪ませ、その内部空間を歪ませる。
壊れてしまう状況で人々の認知は歪み、人間社会の内部空間も歪んでしまう。
いまさまざまなメンタル的な問題や、社会的な衝突が起こっているのもそうした終わりの訪れによる影響だろう。
そして、西洋の歴史をみても、こういう状況が何度か起こっている。
たとえば、しばらく安定期が続いた温暖な中世が終わり、小氷期に入っていく14世紀以降のヨーロッパがまさにそうであった。世界が壊れていくのが忍びよる寒さとともに感じられていたはずである。
そんな終わりのはじまりとともに、歪みから抜けだすための新たな努力を人間は行った。それがルネサンスであり、具体的な成果として、印刷技術や航海技術が生まれ、それが情報の爆発というさらなる変化を起こして人々を苦しめることになる。
そのひとつがヨーロッパ全体を戦争に巻き込んだ宗教改革だろう。世界をどう信仰に耐えうるものにするかということを巡って、古いカトリック的な世界認識と新たなかたちで世界を捉えなおそうとするプロテスタント的なものが対立した。
後者は、フランシス・ベーコンの経験主義的な新たな世界認識の方法の確立をももたらし、結果それがあとでも言及するような17世紀における英国王立協会の科学者、数学者たちによる実験哲学の創出につながり、ラトゥールの指摘する人間社会と自然の切断に根拠を与えるものとなる。
そこからモートンが『自然なきエコロジー』で指摘した「じつは中世においては悪と同義であった自然が、ロマン主義時代には社会的な善の基礎として考えられていた」というロマン主義が小氷期の終わりを前にして生まれるまで、あと一歩だし、そのロマン主義的なものが結局、ずっと隠されていた地球的な事物の世界を見えなくするための人間世界をつくっていたことをこんな風にモートンが指摘していたのを思いだす。
J・R・R・トールキンの3部作『指輪物語』のホビット庄は、世界という球体を、有機的な村として描いている。トールキンは、管理されているが自然なままのようにも見える環境に住み着いている郊外居住者、すなわち「小人」の勝利を語っている。彼らが穴の中にいるとき、グローバルな政治の広大な世界は、地平線の彼方に半ば隠れて、彼らには、喜ばしくも感知し得ないものとなる。(中略)『指輪物語』は、言語、歴史、神話全般だけでなく、周囲をとりまく世界(Umwelt)をも確立している。もしロマン主義が存続していることの証拠があるとしたら、これこそがまさにそうなのである。
中世における温暖期の終わりは、小氷期のはじまりであるとともに、それにともなう人々の歪みを経て、人間世界と事物の世界を、文化と自然という人間の都合のよいよい枠組みに回収して見えなくさせてしまった。
上演状態にある事物
『指輪物語』に残るロマン主義のファンタジーの世界と正反対に位置するのが、アフリカン・アメリカンの思想家フレッド・モーテンが「上演状態にある事物」と呼ぶものだろう。
モーテンは、そこで起きていることを「上演状態にある事物」と表現する。街路で遊ぶ子どもたちが生じさせる生命的なパフォーマンス状況において、事物が上演され、演奏されていく。それとともに、情報過多だが無意味なやりとりが行われている公共圏の形骸性が吹き飛ばされ、裸形となった世界と都市はその物質性において上演状態になる。
篠原さんはこの本のなかで、人間が言葉や記号を用いて捉え、思考する世界の像を公共圏と呼ぶ。それは人間自身がつくりだし、ルール化し、共通財産として扱うきわめて認識的な創作物だ。それはある意味、ホビット庄のように安定して、時間が経っても変化しないものと考えられている。
しかし、そんな静的な状態のホビット庄のような公共圏に相対し、その静けさを打ち破って世間を揺るがすのが、「上演状態にある事物」である。
公共圏の人工的なものの背後に隠されていた事物が世界に舞い戻ってきて、常識的な世界をかき乱す。
ある意味、中世以降廃れていくことになるカーニヴァルが日常世界を逆さまにする――理性的なものが上、身体的・性的なものが下――役割を担い、人間世界に普段隠されていた事物の豊穣さを祝う儀礼であったのと同じだろう。山口昌男さんが『道化の民俗学』で扱った、それこそ、人間と非人間的な領域の交わる世界である。
上演状態にある事物のなかで生きる人たちももた公共圏へのとらわれから自由になり、高尚な哲学の言葉やテクストの存在と相関することのない世界の存在に気づいて、その物質性、情動性、振動性に触れていくところで、共存の形式を模索することになる。モーテンは、これを「地下的な共同性(アンダーコモンズ)」と表現する。
まさに、この地下の共同性を隠したのが、17世紀の半ば以後に起こった近代への変化である。
カーニヴァルが社会から駆逐され、科学が自然を人間文化から切り離し、その後の人新世を用意することになる産業革命へと進みはじめたのが、この小氷期への変化とともに起こったことだったはずである。
僕らが、いま気候変動の人間社会への影響を問いなおす際、このひとつ前の歴史的変化を見ずに済ませることはできないのではないかと思うのだ。
人間世界と事物の世界の分離はいつ起きたのか
だから、そんなこともあって、実は僕自身は篠原さんのいう「思想的設定の変更」ということにいまひとつピンとこなかった部分がある。
いや、篠原さんの書いていることがわからないとか、違うと思うとかではない。
むしろ、よくわかるし、同意なのだ。
ただ、量的にははるかに少なくとも、モートンを読み、ハーマン、メイヤスー、ラトゥール、柄谷行人を読んでいる僕だからそう感じることというのもあるからかもしれないが、篠原さんが「思想的設定の変更」をなそうとされているのが、いや、もうそれについては変更し終わってはいないか(少なくとも、その変更はだいぶ進んでいるのではないか)と思えてしまうというのもある。
しかし、さらに僕はこの本を読みながら、ジョルジュ・バタイユの非―知を思い浮かべるし、エルネスト・グラッシの『形象の力』を思いだす。
バタイユは雑誌『ドキュマン』に寄せた論考「低次唯物論とグノーシス」で「グノーシスはその心理過程において現在の唯物論、つまり存在論を前提とせず、物質が即時存在であることを前提としない唯物論とさして異なるところがなきことが――結局のところ――明らかとなる」と書いているし、グラッシは『形象の力』の冒頭近くでこう書いている。
人間であるぼくは火によって原生林の不気味さを破壊し、人間の場所を作り出すが、それは人間の実現した超越を享け合うゆえに、根源的に神聖な場所となる。これをぼくに許したのは、自然自身であり、ぼくは精神の、知の奇蹟の前に佇んでいるのだ。自然がぼくを欺瞞的に釈放し、ぼくは自然から身を遠ざけ、ぼくは想像もできない距離を闊歩し、歴史がぼくを介して自然を突っ切り始め、ふいにぼくは気がつくのである、目に見えないほどの一本の糸でいかに自然がぼくをつないでいることか。
いずれも、人間世界と事物の世界の関係を問題にしている。しかも、バタイユにしろ、グラッシにしろ、彼らがそう言ったのはずっと前のことで、人間がどんなに否定しようと、人間世界と事物の世界が相互依存関係にあることそのものは、いま「思想的設定の変更」がなくても認識されていたはずである。
ましてや、僕は、ラトゥールが『虚構の「近代」』で取りあげたスティーヴン・シェイピンとサイモン・シャッファーによる『リヴァイアサンと空気ポンプ』も読んだばかりである。
だから、篠原さんが次のように書く、
メイヤスーは、人間の思考が形成する主観的表象には2つの種類のものがあるという。1つが、普遍化可能な、「権利上誰もが実験によって検証可能な」科学的な表象であり、もう1つが、普遍化できず、ゆえに科学の言説の一部となることのできないタイプの表象である。カントが生きた時代の後には前者の普遍化可能な表象が優勢になったが、それにかんしてメイヤスーは「間主観性、すなわち、ある共同体への同意が、孤立した主体による表象と事物それ自体との一致に取って代わり、それが客観性の真正なる基準、さらに言えば、とくに科学的な客観性の基準の地位をもつようになる」と論じていく。
メイヤスー指摘の「共同体への同意が」「科学的な客観性の基準の地位をもつようにな」ったのが、1660年代のボイルをはじめとする英国王立協会の科学者コミュニティによる実験哲学の方法の確立とともに生じたという歴史的背景も知っている。
さらに、そう考えた者たちが神の存在は教会における体験を通じて感じるものではなく、聖書を読むことを通じて理解するものであると変換した者たちでもあったことも、同じプロテスタントたちがシェイクスピア演劇を観るものから同じく読むものに変えたのも同じ17世紀のなかばであったことも知っている。
そこでハムレットの有名なせりふ、「アイ・アム・トゥー・マッチ・イン・ザ・サン」となる。1623年に、決定的な台本ができるまで、シェイクスピアの芝居を活字で読むことはできなかった。『ハムレット』が書かれたのは1601年である。22年間、活字がなかったわけだ。
と高山宏さんは『近代文化史入門』で書いている。
清教徒がロンドン全域の劇場を閉鎖する法律を発したのが1642年である。
事物の世界とまだつながっていたはずの人間世界がそこから切り離され、制御可能な言葉による新しい人間世界として事物の世界から切り離された。
劇場封鎖によって文学といわれるものはほとんど成り立たなくなって、いったん死滅する。さらに文学に一撃を加えたのは、王立協会がコンピュータ言語に相当するものを発明し、普及させようとしたことだ。今までのアンビキュアスな英語は、整理し、「サン」が「息子」だけを意味して、「太陽」は別の表現で表そうとした。
事物の世界が人間社会から締め出され、アンビギュイティが失われた瞬間である。
この17世紀の半ばが、『虚構の「近代」』でラトゥールが「人間と非人間を完全に分離することを善とし、同時にその分離をないものにする」と指摘し、「近代憲法」と呼んだ思考が成立した歴史的時間だ。
そして、そのことをテーマとしているのが本書であるからこそ、そのあたりの歴史的経緯に触れないとラトゥールが『地球に降り立つ』で行っている近しい議論と比べて、いまひとつ主張するところが不鮮明であるようにも感じられた。
もっとある「人間以後」の世界
もうひとつ物足りないなと感じたのは、非人間的なものとして、AI的なものの存在が無視されている点である。これもまた人間が放擲した事物という第2の自然と同様、人工物でありながら人間のコントロール外にあるもので、人間社会を危機に晒す可能性をもつものであるはずである。
たとえば、マックス・テグマークが『LIFE3.0』で描きだすような、今後起こりうる世界観である。
物理的観点から見れば、居住場所や機械や新たな生命形態など、未来の生命が作りたいと思うものはすべて、素粒子をある特定の形で組みあわせたものにすぎない。シロナガスクジラがオキアミを、オキアミがプランクトンを再構成したものであるのと同じように、この太陽系全体も、138億年におよぶ宇宙の進化の中で水素を組み替えたものでしかない。重力が水素を組み替えて恒星を作り、恒星が水素を組み替えてもっと重い原子を作り、その原子が重力によって組み替えられてできた地球の上で、科学的および生物学的なプロセスによって原子がさらに組み替えられることで、生命ができたのだ。
テクノロジーの限界に到達した未来の生命なら、そのような粒子の組み換えをもっと高速かつ効率的におこなうことができる。
といったような未来の生命が人間世界に与える影響がまったく視野に入っていない。
本当はここにいたると、事物とか、生命とかが言葉で概念化して考えてしまうほど単純ではないことに気づけるはずなのだ。
事物とはどういうレベルを考えているのか、人間の目に見える物体なのか、分子や原子は視野に入るのか、さらに量子を事物として捉えられているか、ダークマターは?となるし、生命にしたって僕らと共生する微生物は?となる。
それなら、
過度に先進した諸国の農業バイオテクノロジー部門では、乳牛や羊や養鶏を動物飼料で肥育するという予期せぬカニバリズム的展開がすでに起こっていたのである。後の診断によれば、こうした方策が、牛海綿状脳症(BSE)という致死の病を引き起こす原因であった。俗に「狂牛病」と呼ばれるこの病気は、動物の脳の構造を蝕み、どろどろの状態に変化させる。しかしながら、ここでの狂気は議論の余地なく、人間の側、人間によるバイオテクノロジー産業の側にある。
先進資本主義とそれが有する遺伝子工学技術は、倒錯したポストヒューマンのありかたを生み出している。その革新には人間と動物の相互作用の徹底的な破裂があり、にもかかわらず、すべての生物がグローバル経済という糸車にからめとられている。
といった問題提起で、人間という領域への侵犯を論じる『ポストヒューマン』におけるロージ・ブライドッティの「人間以後」観の方が広く問題のありかを捉えているように思う。
そして、100歳になるガイア理論の提唱者ラヴロックが『ノヴァセン』というアントロポセン=人新世の後の世界を、テグマーク同様に人工知能の世界として描く想像力があることを考えると、やはりちょっと物足りなさを感じてしまう。
歴史の廃墟とともに
こうした点からも、歴史や科学といった領域との絡みがなく、音楽や演劇、アートの領域への言及を通じて「人間以後」が語られるものの、すこし「哲学」という閉じた領域に閉じこもりすぎなのがもったいなく感じたことはある。
それでも、全体を通して共感する部分が多い。
物足りなさを感じるのもその裏返しのようなものだ。
建築家の磯崎新の廃墟論への言及から、ベンヤミンの『ドイツ悲劇の根源』における自然史を廃墟論へと結びつけるところなどは独特な視点で面白かった。
サントナーは、ベンヤミンが『ドイツ悲劇の根源』で論じた「自然史」を、廃墟論として考察する。この考察は、人間生活を、文化や公共圏のような精神的実体とは異なる事物的なものとのかかわりにおいて成り立つものとして捉え、そのうえでベンヤミンを、生きている状態の崩壊と終わりの観点から世界の事物性を考えようとしたものとして読み解いていく。
ベンヤミンの自然史論はもともとアレゴリー論として語られている。そのなかでベンヤミンは「象徴とアレゴリーの関係を鮮明かつ定式的に言い表わす」ことが可能だとし、次のようにその違いを言い表している。
象徴においては、没落の変容とともに、自然の変容して神々しくなった顔貌が、救済の光のなかに一瞬みずからを啓示するのに対して、アレゴリーにおいては、歴史の死相が、硬直した原風景として、見る者の目の前に横たわっているのである。
まさに「歴史の死相が、硬直した原風景として、見る者の前に横たわっている」というあたりが廃墟であり、人間世界の外へと放擲された事物のありようだといえる。この歴史の放擲こそが、近代が行ったことの反転としての「思想的設定の変更」として、いま繰り返されようとしているとしたら、それはどうだろうとも思う。
人間以後の哲学を考えるということは、こうした歴史の廃墟のなかで考えることでもあるのだろう。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
