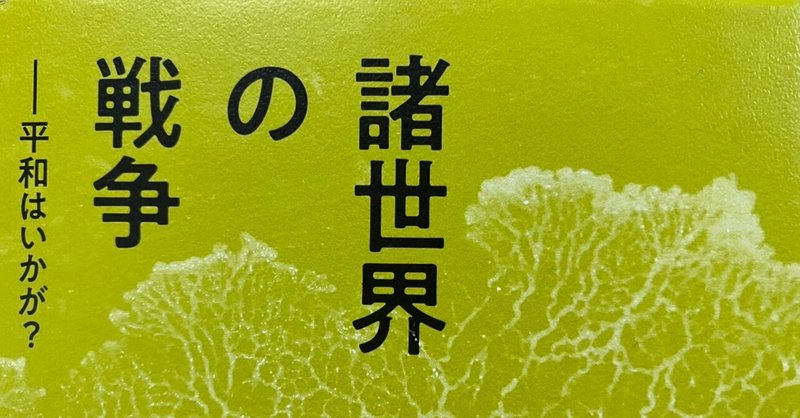
諸世界の戦争――平和はいかが?/ブリュノ・ラトゥール
先に予告。
今回と次の回では、戦争あるいは内戦をめぐる2冊の本を紹介しようと思う。
まず今回紹介するのは、ブリュノ・ラトゥール『諸世界の戦争――平和はいかが?』。
ラトゥールを読むのはひさしぶりだ。
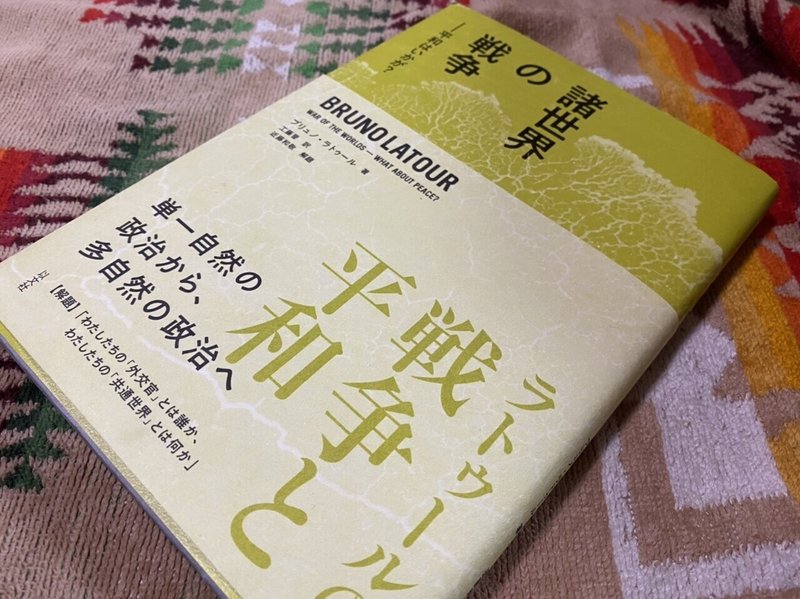
911
日本語版が出たのは昨年10月のことだが、元になっているのは2002年に英訳で出版されたものだ。英訳としたのは、さらにその元になった2000年の講演原稿がフランス語で発表されているためである。
その原稿にラトゥールは、「911」という第1章を付け加えている。そう。講演と出版のあいだの2011年9月11日に起こった出来事への言及を加えた短い章を。
ラトゥールはいう。
「2001年の9月以来、人はあの日と同じ911という緊急コールを呼び続けている」と。
そうだ、そのとおりだ。それはラトゥールがこの本を発表した2002年の時点がそうだっただけでなく、おそらく緊急コールはいまだ一度として止んでいない。
「当然だ、私たちは緊急事態に突入してしまったのだから」というラトゥールの言葉は、いまの僕らにも当てはまり続けていると僕はこの1年あまり、ずっと感じている。
アガンベンの「ホモ・サケル」シリーズを読み続け、ここで紹介し続けているのは、そのためだ。
いまはまぎれもなく「例外状態」である。
現れ出たのは何か?
これまでも何冊かラトゥールの本を読んできたが、僕にとって一番印象に残っているのは『虚構の「近代」―科学人類学は警告する』だ。
その本でラトゥールが展開するのは、自然と文化を分断することでそれぞれの純粋化を推し進めてきた西洋近代が、実はその裏面において両者の混淆を無批判かつ野放図に行われるままにしてきたことへの批判だった。
自然と文化は互いに関与しあわないというふりをしながら近代が進めてきたのは、自然環境を好きなだけ搾取することだし、その結果の気候危機であり、理性や科学の名の下でのグローバリゼーションによる世界中の文化やコミュニティ、生活の破壊がもたらした貧困や差別、経済格差など、さまざまな社会問題である。
この世界はまさに緊急事態真っ只中。
状況は日に日に悪化している。
「非常事態(イマージェンシー)」という語には「現れ出る(イマージェント)」という語が隠されている。この喫緊の事態から何があらわれ、「明るみに出され」ようとしているのか? 戦争のただなかにいることを自覚するとき、私たちは、多くの人々がよりいっそう平和な未来を思い描きあらゆる国民があいまいな近代主義的理想に収れんする、という自己満足から引きずり出されるのかもしれない。
とラトゥールは書く。
そう。これは戦争だ。
近代的な社会システムが理想としたどこまでもつづく経済成長などという夢から「引きずり出されて」、僕らは、いますぐにでも新たな社会システムの構築しなおしをはじめなくてはならない。
そのことは、ひとつ前で紹介したセルジュ・ラトゥーシュの『脱成長』でも明確に示されていたとおりである。
戦争状態が好ましい
9.11の記憶が生々しく残る時期に発表された、この本でラトゥールは、「戦争状態が好ましい」と書く。
巧妙で刺々しいこの小論における私の主張は、結局のところ戦争状態にある方が好ましい、というものである。つまり、戦争など存在しないと想像し、進歩や近代性や発展について際限なく――かくも高尚な目標に到達するために支払う代価を理解せずに――語り続けるよりも、なされるべき外交の仕事について考えることを強いられる方が好ましいのである。
「近代は一度もはじまったことがない」とさえ言ったりする、ラトゥールらしい言い回しだ。
近代西洋が歴史のなかでさまざまな戦争を起こし関わってきながら、それが戦争行為であるというよりも、自然(あるいは科学、あるいは理性)という絶対的な調停者の名の下に行われる警察行動であるかのようなふりをしてきた近代主義者の姿勢をラトゥールは否定する。
その考えはアガンベンの本でも言及されていた2つの世界大戦期に「例外状態」という概念を発見した法学者カール・シュミットの考えを参照したものでもある。
争いを監視する調停者から与えられる権限が有効であるとき、人は戦争ではなくただ警察活動をおこなっているのだ、とシュミットは言う。「自然の要求」に従って働くように遣わされた近代主義者たちは、ただ世界の治安を維持していたのであり、自分たちはかつて誰とも戦争をしたことはないと胸を張って言うことができたのである。
ラトゥールは、こうした近代主義者が9.11に対する報復をこれまた警察行動のように扱おうとする態度に対して、それなら「戦争状態にある方が好ましい」ということで「非常事態」にあることをひた隠しにし続けようとする近代主義の残滓のような態度にNOというのだ。
戦争状態にあることをちゃんと認めたうえで、敵国との外交交渉を進めるなかで、バラバラの状態をあらたにまとめ直すことの重要性を解くのだ。
まさにここでラトゥールが求めている外交の仕事とは、彼が提唱するアクターネットワーク理論における作業――「私が提案したのは、「自然をめぐる政治」を1つの共通世界の漸進的な組み上げで置き換えることである」――と同じことなのだ。
置き去りにされた生きる意味
ラトゥールが指摘する現在の危機は、こんなところに起因する。
近代化する西洋は「自然中心主義」あるいは「理性中心主義」であったと言えるだろうが、これほど非自民族中心主義である政治的編成は他にはなかった。それゆえに近代化する西洋は、生まれついた民族集団にかかわらず誰に対しても、驚くべき寛容さで、自分と同じように普遍的になるチャンスを与えた。科学的客観性、技術的効率性、経済的収益性の仲立ちによって、誰もが、祖先を持たぬ土地、しきたりのない民族集団、国境なき国に加わることができた。それは、批判と理性的議論の強力な働きによって統一する自然にアクセスできる理性の国であった。
だがその結果、生きることの意味は置き去りにされた。
絶対的な客観性をもった自然(科学)、あるいは理性という幻想のもとに、西洋近代は、すべてを飲み込んで真っさらな状態をつくってしまうかのようなグローバリゼーションを推し進めてきた。西洋はおそるべき寛容さで、多様な文化を認めてきたふりをしてきたが、実際は新自由主義的な規模による暴力が多様な文化の根っこを弱体化させ、「その結果、生きることの意味は置き去りにされた」。
その生きる意味を、この戦時下において、緊急事態のなかで、あらゆる敵との交渉のなかで組み直す作業をはじめなくてはいけないというのが、この2020年から2021年にかけて起きている出来事を知らなかったラトゥールが提示しているのものであり、その発展が後に書かれた『地球に降り立つ――新気候体制を生き抜くための政治』で示されているとも言える。
ふたたび構成する
ラトゥールは、その本のなかで、緊急事態下にある僕らは「では何をすれば良いのか」という問いに対して、「第一に、これまでとは違う記述を作り出すことだ」と言っている。本書でいうところの「外交の仕事」がまさにそれである。
地球が私たちのために用意してくれたものをすべて調査し目録を作る。それが「人間」であるなら1人ずつ、それが「モノ」であるなら1つの存在ごとに、1センチ1センチ測って詳細に記録を残す。記録を作らずして政治行動に訴えることなど、どうしてできようか。(中略)見えなくなった居住場所を記述し直そう。そういう提案をしない政治はすべからく信頼できない。記述の段階を省いて前に進むことなどできない。〔記述抜きの〕予定表だけの提案はどんな政治的虚言よりも恥知らずなものだ。
「記録を作らずして政治行動に訴えることなど、どうしてできようか」。
まさにこれが戦争状態であることを認めたうえで、これまで近代主義者がその存在を無視してきた近代の外にある敵たち(人に限らず、さまざまなモノたちも含めて)との政治的交渉を進める際に不可欠なものなのだろう。
まず必要なのはいまが戦争中であること、緊急事態下にあることを認めることなのだろう。
西洋は、近代化に努めたその歴史とはうらはらに、平和に到達するためには戦争が存在することを認めなければならない。すなわち西洋には敵が存在したという事実を引き受け、世界の多様性を真摯に考え、単なる寛容を拒絶し、地域的なものとグローバルなものの両方の構成をふたたび試みなければならない。
そして、自然主義者であることをあらためて、構成をふたたび試みる構成主義者となって、多様な敵たちとの交渉を進めていくべきなのだろう。
それが近代が置き去りにしてきた「生きる意味」をふたたび構成しなおし手にするための唯一の道なのだろう。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
