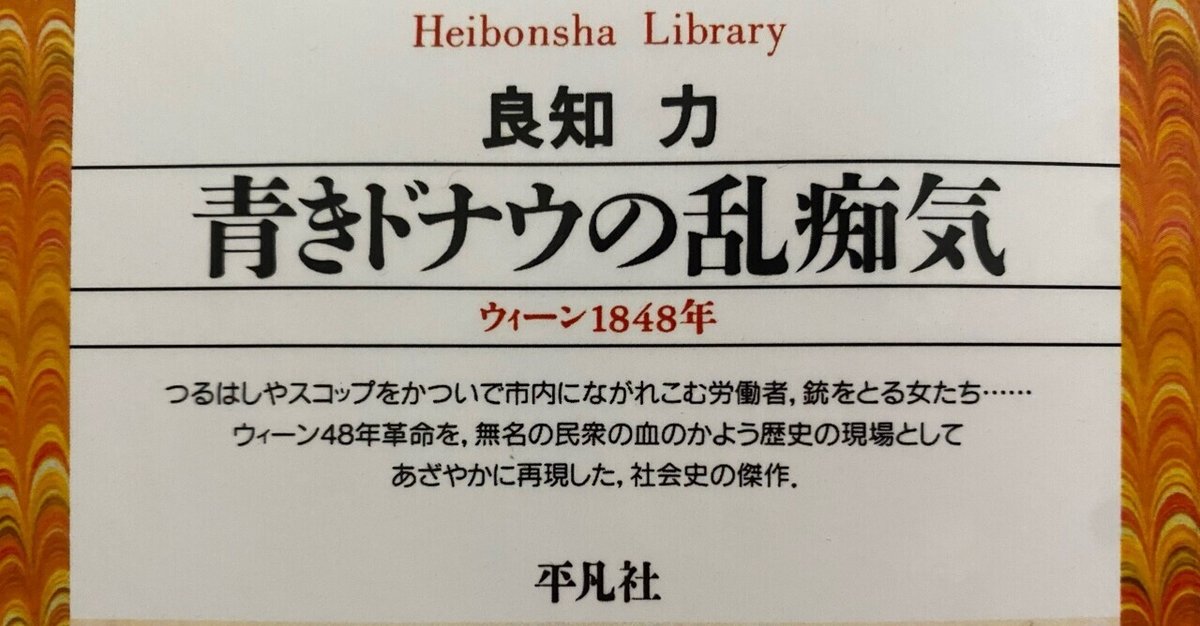
青きドナウの乱痴気 ウィーン1848年/良知力
この本を読んでみて、革命というものの印象が変わった。
革命というと、大義的なものに導かれて社会変革を促そうとする創造的な面をもった市民の行動のようなものを想像していたが、そういうものではないのかもしれない。自分たちが今日明日を生きるため、生き続けるために、ほんとに最低限ものすら手にすることのできない人々が切羽詰まって行動にいたる、激情的で事後の明確なヴィジョンももたない反抗なのではないか。
19世紀半ばのウィーンでの革命の様子を綴った良知力さんの『青きドナウの乱痴気 ウィーン1848年』を読んで、そう思った。
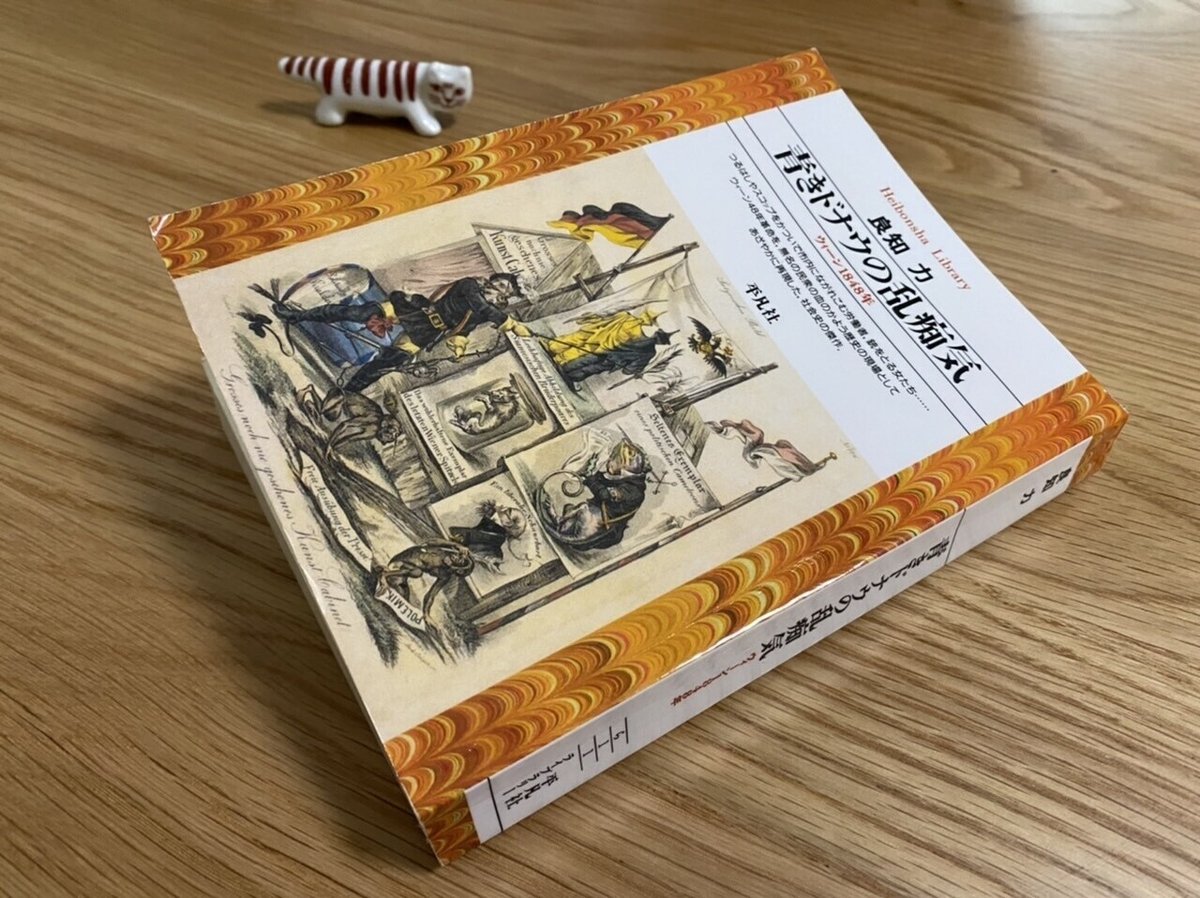
下層の民衆たちによる革命
いまもさまざまな環境課題、社会課題を前に、僕自身、変革ということを考えない日はないのだけれど、そんな風に頭で考えて変化をデザインしようとする姿勢と、この本で描かれた19世紀の革命に参加した人びとの姿勢とはまるで違うのだということは認めざるを得ない。日々を生きる術を徹底的に欠いていた下層の民衆たちによる行動は、なんらかの具体的な明日の姿を夢見て起こしたものというより、とにかくもはやいまのままでは耐えられなかった状況での唯一の選択肢のようなものだったのだから。
もはや行動に出るしかないという強力なオブセッションに駆られた民衆たちによる19世紀の革命と似たような状況が、いま現在、止まることなく開き続ける経済格差のなか同じように日々を暮らすことに困窮する層の人たちから生まれてきてもおかしくないとも感じられた。それは僕がイメージしていた積極的な選択としての変革とはまるで別物なのだが、はるかにこの19世紀の革命に似た下層からの行動のほうが現実的に起こり得るのではないかとも思うのだ。
1848年という年はヨーロッパで革命の連鎖が起こった年である。それはその前の世紀に起こったブルジョワ革命とはまた異なる性質のものだったのだと思う。19世紀の革命の主役たちが求めたのは、自由や博愛や平等のような抽象的な理想ではなく、リアルに明日を生きるための糧やそれを得るための方策だった。
1月にイタリアでシチリア革命が起き、2月にはフランス2月革命が、そして3月3日にハンガリー革命、そして、同じ3月の13日にウィーン3月革命へと革命の連鎖が続いた。1814-1815年のウィーン会議をへて確立していた従来の君主制に立脚する列強を中心として自由主義・国民主義運動を抑圧することで保たれていたヨーロッパの秩序=ウィーン体制が、一気に崩れ去ることになる事態を動かしたのはまぎれもなく、産業革命以降に深刻化しつつ複雑に絡みあう経済的な格差を生み出していた社会のなかで貧困にあえぐ下層の民衆たちだった。彼らは何か具体的な変化を求めて行動を起こしたというより、とにかくもうこれ以上、いまの状況のまま生きることができないほど困窮していたのだった。
下層の民衆の悲惨な状況
最下層に位置するのは、チェコやスロバキアなどからやってきた外国人たちだったという。
彼らは仕事も住む場所もなく、ドナウ運河に横穴のように口をあけた下水道のなかに寒さを凌ぐために潜り込んでいたりもしたそうだ。
著者はその様子を描いた当時の人の描写を引用している。
寒さのきびしい冬でしたが、ある日私は所用のためある警察を訪れました。なかへ入ると、控えの部屋にたったいま一網打尽となったばかりの「穴暮らしの住民」が20人ほどかたまっていました。そのきたなくて臭いこと、なにしろ垢だの汚物だのがかさぶたのように体にへばりついていて、ボロボロのシャツとリンネルの下ばきを身につけているだけなのですから。どこもかしこと肌がむき出しになり、寒さ凌ぎに足にぼろ布をまきつけ、帽子をかぶっている者など1人としていませんでした。
読んでるだけで、彼らの寒さが伝わってきて居た堪れなくなる。プラハからウィーンまでくる汽車に乗るための三等の切符一枚買うのに2ヶ月分の賃金が必要になるのをなんとか工面してたどり着いた結果、寝る場所もなく、こんな状況に追いやられてしまうのだ。
もちろん、仕事にありつけ、ぼろ家ながら住む場所を確保できた者もいた。彼らはプロレタリアと呼ばれ、ウィーンの街を取り囲む壁の外で暮らした。
便所もない、水もない疫病の温床のような不衛生な住居に多くの人数が一緒くたに詰め込まれて暮らしていた。女も子どもも家族総出で工場などで働いていたが、あまりの給料の安さに日々の暮らしを続けることもできない有様だった。
仕事を求めてきたのに仕事にありつけず
1830年代、40年代には、ウィーンだけでなく、ロンドンでもパリでもベルリンでも、ヨーロッパの大都市の人口は急激に膨れ上がって、仕事や住む場所にありつけない人が大量に発生するが、その原因は上に書いたような地方や他国からの流入人口だった。
工業のみならず農業なども含めて、社会の産業化が進むと同時に、地方の農村である程度の自給自足的な暮らしを営むことができていた人々も、土地を失い、仕事を失い、地方の暮らしを捨て、工場などで働くために都市に移住しなくてはならなくなる。しかし、都市にはもともと住んでいた市民やその土地の農民たちもいるし、都市に移り住んでくる人も年々増加する一方なので、流民たちは仕事にもありつくのがむずかしいし、お金がないから住む場所にも困る。いまのヨーロッパなどでの移民たちの問題とも通じるところだ。とうぜん、犯罪増加の原因ともなる。
地方から都会に出てきて職を求める人々が工場の仕事にも見つからなくて、ようやくありつける仕事のひとつは道路掃除だったという。箒とスコップをかついで、泥やあふれ出る汚水、馬車馬が落とす馬糞やその他もろもろの汚物を、早朝から昼ごろまで掃除して歩く。もちろんもらえるお金は安く、家賃すら払えない。

オーナーたちも困窮して
一方で、そんな貧しい流民たちが年々増えていく都市自体の経済もまた徐々に苦しくなっていく。
地方から仕入れる必要のある食材をはじめとする資材も年々高騰し、パンや肉の値段も上げざるを得ない。しかし、店のオーナーたちにしてみれば、利益率は減る一方なのに家賃は上がるし、従業員たちも増やさざるを得ない。それで仕方なく商品の値段を上げるのだが、貧しい人々は同じ値段で買えるパンや肉の量が減ることに文句を言う。
文句を言うだけではおさまらず、プロレタリアたちは、シャリバリと呼ばれた夜中に店のまわりで指笛を鳴らしたり、桶やフライパンを打ち鳴らして抗議する行動をはじめ、しまいには店を壊す暴力にまで発展した。

こうしてウィーンの街は大きく4つの層に分けられることなる。
王宮に暮らす皇帝や宮廷人たち、そして政治家や警察からなる層が1つ。パン屋や肉屋を含むさまざまな店や工場などのオーナーを中心とした市民層が2つめ。次に、もともとウィーンで暮らしていた労働者層が3つめで、残りが他国からの来たプロレタリアだ。
もちろん、この順で収入は少なく生活は厳しくなる。
社会を分断する2つの壁
この4つの社会的な層が当時のウィーンの地図には、はっきりと可視化されている。
ウィーンはちょうどドーナツのように二重の壁に取り巻かれていた。

真ん中に王宮をもつ市内区は、「中世以来の都市、市内区で、ショッテン、ヴィンマー、シュトゥーベン、ケルントナーの4区に分かれていた」という。その「市内区の周囲を市壁が取り巻く」。
その「市壁の外は空堀」となっていて、「市壁には12の門が設けられて」いたという。「市門を出ると空堀に架けられた橋を渡ることになる」。

その堀の外に、「グラシとかグラシスとかいわれる緑地帯」があった。これは「1529年と1683年の二度にわたってトルコ軍に包囲された教訓に学んで、市壁から600歩以内のところは建物造営禁止となった」ためにできたものだ。「市民の生活感覚ではこのグラシまでが市内だった」そうだ。つまり、この門の内側の市内区に住んでいたのが、皇帝を含む政治を司る人たちと、経済を司ったウィーンの市民たちであった。
市壁の外の世界を市民は「門の外」「門の向う」と呼び、そこにいくばくかの蔑みの色合いを含ませた。
市外区とそのさらに外側
市民たちがウィーンの外と認識していた「グラシの外は市外区である」。
市外区は「34の行政区に分れ、主として小市民やら職人やらが暮す商工業の街だった」。つまり、3つめの層の人たちが中心の街ではある。けれど「金持の市民や貴族もいないわけではなく、ラントシュトラーセにはメッテルニヒの、マリアヒルフ通りにはエスターハージの屋敷もあった」そうだ。メッテルニヒは30年間にわたるウィーン体制を象徴してきたオーストリアの宰相である。彼は3月に起こった革命で辞任に追いやられ、ウィーンから脱出することになる。

市内区と市外区を隔てた「12の市門からはボヘミア、西ドイツ、ハンガリー、イタリア、クロアティアなど各地へ向けて街道が放射状に走」っていて、「いずれも市外区を抜けなければならない」。
そして、「市外区が終わったところで街道は大木戸にぶつかる」。このリーニエ(英語でいえばライン)と呼ばれた、市街区とさらにその外を隔てた壁と門は「ウィーンに出入りする旅人を取り調べ、消費税を取り立てる」ために機能した。まさに、このリーニエの外の非ウィーンと認識されていた地域にプロレタリアートは暮らしていたのである。
社会的・経済的な格差が革命の原因
まさに王宮、市内区と市壁とグラシ、市外区とリーニエ、そしてリーニエの外という4つのエリア分けがそのまま社会的な格差を可視化して、それぞれの人々の暮らしの質を大きく異なるものにしていたのであり、この格差による不満が爆発したのが1848年の革命なのだ。
だから、市民が絶対王政を引いた王侯貴族から自分たちの権利を勝ち取ろうとした18世紀の啓蒙の時代の革命と、このウィーンに代表される19世紀の革命とはまったくの別物だろう。実際、この革命では市内区に住む市民と市外区に住む労働者たちが争ったり、のちにはこの2者がいっしょになった国民軍が、プロレタリアと学生たちが手を組んだ外国人たちの層と争ったりする。

さらにそこに正式な軍隊が絡んだりして、互いにその争いによって何か明確なものを勝ち取ろうとして争うというより、社会的な身分の違いからたがいの利益が背反する相手とのあいだで自身の利益を守ろうとしたり、自身のもたない利益をもつものから奪おうとしたりという、まさに生きていくための経済的価値をとりあえず得たり守ったりするために戦ったのだ。
19世紀の革命のこうした構図をみると、現代の国内レベルでも、グローバルレベルでも存在する社会的・経済的な格差がさまざまな衝突の原因となっていることもまた違った深刻さを漂わせるように思う。持つ者は自身の経済的な資産や権利を守るためにナショナリズムに走ったり保守的な姿勢を強めたりする一方で、持たざる者は自分たちの今日明日の暮らしの困窮をなんとかすこしでも改善したい思いから持つ者たちを敵視する。
この本で描かれた1848年のウィーンの革命と同じ構図はいま僕たちの目の前にあると感じた。
それなりの分量あるが、読みやすく軽快な文章でさらっと楽しんで読めた。
この記事が参加している募集
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
