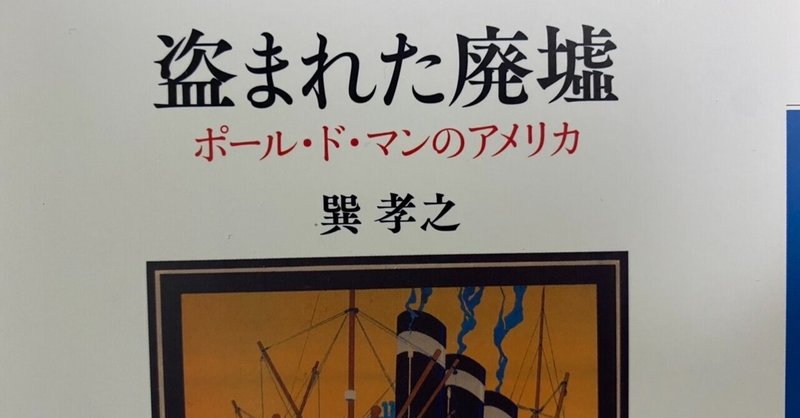
盗まれた廃墟 ポール・ド・マンのアメリカ/巽孝之
アメリカの文化史には縁がない。
ヨーロッパの文化史は中世後半くらいから20世紀くらいまで、それなりに独学で学んできて知ってることもそれなりはあるが、それと比べれば歴史の浅いほうのアメリカについては、興味そのものももてなかったので、ほとんど知らない。
そうではあったんだけど、最近読んだ高山宏さんの巽孝之さんの対談集『マニエリスム談義 驚異の大陸をめぐる超英米文学史』で、17世紀なかば、イギリス国教会からの分離を求めて、アメリカに渡ったピューリタンたちがピルグリム・ファーザーズで、それ以降同じWASP(ホワイト・アングロサクソン・プロテスタント)中心の国として歩むことになる「イギリスとアメリカはほんとうにパラレル」であり、両国の文化史は「まさしくトランスアトランティック」にシンクロしているというのを知って俄然興味がでた。
特に、第二次世界大戦後にヨーロッパからアメリカに亡命してきた脱構築派の思想家・批評家ポール・ド・マンをめぐる話に興味が惹かれて、ド・マンの『ロマン主義のレトリック』と、この巽孝之さんの『盗まれた廃墟 ポール・ド・マンのアメリカ』を買ってみた。そして手始めに巽さんの本から読んでみたわけだ。

修辞学を復活させる
さて、巽さんは本書の主人公ポール・ド・マンを「20世紀後半に活躍した不世出の学者批評家(スカラー・クリティック)」と紹介している。
それと同時に「学者批評家としてのド・マンはなおざりにされていた」といい、日本では脱構築派の哲学者、思想家といった観点で語られがちであるド・マンを次のような視点で見直そうと試みたのが本書である。
「ソーカル事件」では文化研究が自然科学を隠喩として濫用してきた点が批判されたが、ド・マンが喝破したのは、そもそも比喩の濫用、転じては濫喩が自然化してしまった脱修辞学的効果こそがわれわれの生きる現実だということだった。そして何より、脱構築がその一翼を担ったポストモダニズムは、ド・マンに従えば必ずしも先端的ではなく古典三教科の修辞学を復活させ文献学の伝統へ回帰しようとする点でまぎれもなく人文学の復興を促すものだった。
ここでいう「ソーカル事件」とは、ニューヨーク大学の物理学教授アラン・ソーカルが、1996年(ド・マンはすでに亡くなっている)にカルチュラル・スタディーズの牙城たる学術誌〈ソーシャル・テクスト〉に「境界を侵犯すること――量子重力の変型解釈学へ向けて」という問題論文を送り、それがそのまま受理、掲載されたことに端を発する。
事件というのは、掲載後、ソーカル自身が別の学術誌〈リンガ・フランカ〉に、「暴露――物理学者は文化研究をこう試した」で、自分が投稿した「境界を侵犯すること――量子重力の変型解釈学へ向けて」はまったく根も葉もないデタラメ論文で、科学と文学の学際研究どころか、ポストモダンの思想家たちが「難解な新造語だらけの専門用語をふりまわしつつ科学をポスト構造主義的、転じては社会構築主義的に解釈し、科学という隠喩を乱用するばかりであるのを告発するパロディ論文だった」と種明かししたからだ。
レボリューションはもともと天文学用語
ところが、ソーカルが訳知り顔で指摘した科学的な用語の文化的な使用といった事柄は、なにも20世紀後半に新しく起こりはじめた事柄などではまったくない。
たとえば、ひとつの例は、ド・マン同様に、ヨーロッパからアメリカへと亡命してきた哲学者のハンナ・アーレントが『革命について』の次のような例をみればわかる。
「革命」(revolution)という言葉は、もともと天文学上の用語であり、コペルニクスのいう天体の回転(De revolutionibus orbium coeleptium)によって自然科学で重要性を増していた。この言葉の正確なラテン語の意味は、このような科学上の用語法のなかに表現されており、天体の周期的で合法則的な回転運動を意味していた。この運動は、人間の力を超えており、したがって抵抗できないものであることが知られていたので、もちろん、新しさとか暴力をその特徴としたものではなかった。
『マニエリスム談義 驚異の大陸をめぐる超英米文学史』でも、"fact"とか"real"という英単語が最初に登場したのはそれぞれ1632年と1601年であって、せいぜい350-400年程度前のことでしかないことが指摘される。
ファクトの元になったラテン語のファクトゥスは「つくられたもの」という意味であったのが、この17世紀のはじめに何故か「科学的な一定の動かぬ事実」みたいな意味になったということも指摘されていたとおり、科学の側が乱用する例も事欠かないのだ。
「比喩の濫用、転じては濫喩が自然化してしまった脱修辞学的効果こそがわれわれの生きる現実」だというド・マンの指摘そのとおりだ。
事実というつくりものを超えて
それに、ブルーノ・ラトゥールが『虚構の「近代」』で指摘しているとおりで、自然―科学と、人工―文化的なものを相互に独立したものとしてみる発想そのものが「近代」の誤謬でしかない。
ラトゥールがこんな風に、自然科学者ボイルと政治思想家ホッブズの対立のなかに読み解く、出来事そのものがのちにレボリューションを天文学から政治的な用語へと移し替え、ソーカルがトンチンカンな指摘を我が物顔ですることになる背景を用意している。まさに"fact"とか"real"が英単語として登場した直後の17世紀半ばの出来事である。
ボイルの時代以来、私たちの文化の根幹を構成するものが常時、人類学者の目をすり抜けてきている。私たちの住処であるコミュニティを支えているのが、実験室で作られた対象を軸として結ばれる社会的絆であることに彼らは気づいていない。実践が思想に、あるいはコントロール下で紡ぎ出されるドクサが反直証論法に、そして科学者の承認が万人の同意に取って代わったことも見過ごされている。事実は人間が作り出すものとはいえ、人間の手作り品ではない…。事実には因果律はないが説明は可能である…――事実の超自然的起源が、こうして実験室内で高らかに宣言される。そうした私的空間が随所に増えていくにつれ、ホッブスが蘇らせようとした秩序は無力化していくことになる。
実験室でつくられた「事実」が僕たちの社会の絆を支える根底であるかのような誤解がこのときつくられる。
そのマジックにおよそ350年ぶりくらいにようやく綻びが生じてきたのがポスト・トゥルースの現在なのだが、それは真実の危機ではなく、真実なるものがそもそも修辞学的なものでしかないということが元通り、僕らの手に入ろうとしているということなのだ。
そして、そんな風に、350年にもわたって僕らにありもしない絆に生命を吹き込んでしまう力が、修辞学、あるいは言葉にはあることを明らかにしたのがド・マンをはじめとする脱構築派の思想家たちであったことを巽さんは指摘している。
アメリカ新批評が文学作品のうちにユダヤ=キリスト教的な神のロゴスを見出そうとした点でプロテスタンティズムの聖書解釈学に近接することは頻繁に指摘されてきたけれども、いっぽうフランス系アメリカから生まれた脱構築批評は、聖書ならぬたんなるモノとしてのテクストが神でもロゴスでもないたんなるメカニズムとしての言語の力によってなぜか生命を帯びてしまうこと、しかも独り歩きし始めてしまうことをめぐる理論であったと断定しても過言ではない。
非道なタスクのサラリーマン的陳腐化
ところで、この本を読んで、あらためて僕が関心をもったのが、全体主義を可能にする人間のサラリーマン的性質だ。
本書では、ユダヤ人大量虐殺の実行を担ったアイヒマンを、アーレントが分析する『エルサレムのアイヒマン: 悪の陳腐さについての報告』について言及されるのだけど(この本も読みたくなった)、ここで考えさせられるのは、大量虐殺を可能にしたのが、狂信的で残酷非道な性格によるものでも、強制的な指示によるものでもなく、むしろ機械的で、従順に与えられたタスクをこなす自分自身の判断を喪失したサラリーマン的な精神によるものだということである。
アーレントやティモシー・クドーを持ち出さずとも、そもそも「陳腐」"banality"という単語の成り立ちそのものに、強制された労働が一般化し陳腐化していくプロセスが凝縮されているのである。すなわち、アイヒマンが行なったユダヤ人大虐殺が悪の陳腐化を露呈したというよりも、あらゆる強制的な労働には陳腐という倫理観は転化する契機が――構築主義的にいうなら当初は特異な言説でしかなかったものがいつしか自然化していく契機が――語源的に孕まれており、それこそはアイヒマンが嬉々として機械的労働とともに合法的な悪を積み重ねていった経緯にほかならない。
引用中にあるティモシー・クドーという人物は、2015年に巽さんがニューヨーク・タイムズの紙面で見つけた「いかに殺人を学んだか」というインタビューに答える元海軍大佐だ。そこで彼は「戦争の狂気のさなかにあって、わたしは殺人すら陳腐になりうることを目の当たりにした」と言っていたのだという。
つまり、1940年代に起きた事柄は、2000年代になっても変わらず繰り返されているのであり、殺人や大量殺戮といった大それたことが可能になるのは、「悪の陳腐化」という転化が起こるからであるということだ。
そして、それが僕らにとっても無縁ではないと思うのは、殺人といった事柄だけではなく、「あらゆる強制的な労働には陳腐という倫理観は転化する契機」があるというからで、なるほど、なぜ官僚的なサラリーマンたちが「ブルシット・ジョブ」の罠にいとも容易く陥ってしまうのかもあらためて理解できる。
非人間が人間化する
しかも、ここで注目すべきは、陳腐化の契機が「語源的に孕まれて」いると指摘されていることだ。
どういうことだろう?
ここでも修辞学的な視点が役に立つ。
ここで「陳腐」の概念として採用されている英語(banality)とは、もともと「禁止する、放逐する」を意味する動詞(ban)から強制的(compulsory)な感覚を担いつつ、結果的に一般的(common)という意味合いを帯びるように至った概念である。「強制的」なものが「一般的」なものになりうるという論理の道筋は掴みにくいかもしれないが、歴史的にたぐりなおせば、この語源は中世フランス語で封建社会における市民一般に共通して課された賦役、すなわち労働義務を指す。したがって、みんなが強制的に労働しなければならないというところから一般的という意が生じ、転じては陳腐なもの、ありふれたものという侮蔑的なニュアンスを帯びるに至っている。ここで肝心なのは、当初は強制的に命令された結果だったものが、あまりにも一般化してしまったので陳腐なものという語義をも帯びるに至ったことだ。
『中動態の世界 意志と責任の考古学』のなかで國分功一郎は、いまは使われなくなった動詞の態「中動態」を論じながら、能動態と受動態のする/されるのなかにある意志や責任の議論とは異なる思考や価値観が成立していたはずの能動態と中動態が対立軸としてあった古代ギリシアの社会を想像して、「言語は思考ではなくて思考の可能性を規定する」と書いていた(ちなみに國分さんも意志との関係のなかでアーレントのアイヒマン論を紹介している)。
まさに今回紹介しているこの本で巽さんが言っていること、さらにド・マンが修辞学の復権を目指したのも、言葉の変化が人間の思考や行動を規定するものだからなとだといえる。それはおそらく日本における言霊の思想ともそう遠くはない。
名論文「メタファーの認識論」(1978年)において、ジョン・ロックの『人間知性論』を読むド・マンは「言語の乱用は、もちろんそれ自体が濫喩という文彩として命名されている」と宣言し、ロックの「混合様相」理論を援用してこう述べる。「いかに無害に見える濫喩のうちにも怪物的なるものがひそむ。たとえば人が机の脚(レッグス)や山の面(フェイス)を口にするとき、濫喩はすでに非人間を人間化する活喩へと転じており、世界には亡霊たちや怪物たちが潜在していることが徐々に明らかになっていく」。
修辞学的なもののうちで、非人間が人間化するとき、ソーカルが訳知り顔で指摘したような乱用などはいまさら何を言わんかという程度でしかなく、そもそもこの修辞学的な基礎を忘却して、非人間と人間、自然と文化を不自然に引き離した結果が、悪の陳腐化をより引き起こしやすくなった要因ですらある。
こうしたスピークアウト=言葉の力、言霊を軽んじたところに、いま現在の多くの環境・社会課題の原因を見ることが必要ではないか?
その意味では、いまポール・ド・マンの読みなおす必要があるのだろう。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
