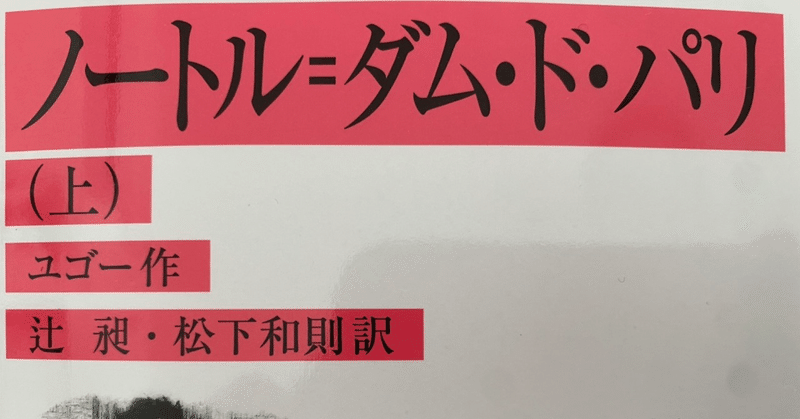
ノートル=ダム・ド・パリ/ヴィクトル・ユゴー
I miss you paris.
そんな思いを感じながら、ついに読んだ。
ヴィクトル・ユゴーの『ノートル=ダム・ド・パリ』。
上下巻あわせて1000ページ強の大作を年末年始またいで。年明けバタバタしていて紹介するのが遅くなったけれど、ほんとに読んでよかったと思えたパリという都市や建築に対する愛情と人びとの心からそれが失われていくことへの失望に満ちた中世の都市を舞台にした叙事詩。
それがユゴーの『ノートル=ダム・ド・パリ』だ。
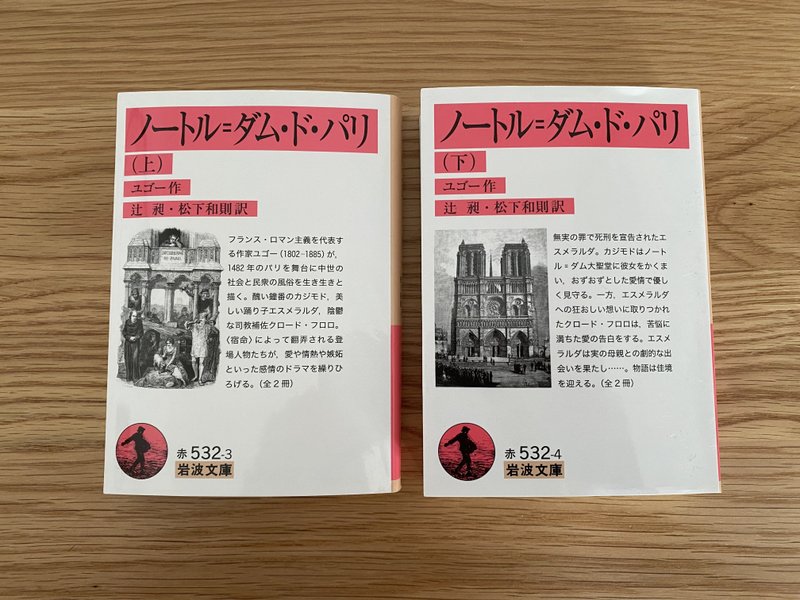
近代小説の二元論的世界
ユゴーのこの作品を読んで感じたのは、小説に主人公がいるなんていうのは、きわめて近代的な見方なんだということだ。
僕らはもはやそれを当たり前のものであるかのように感じているが、それは近代以降の小説という形式のなかのことでしかない。それ以前の文学形式においても当然、登場人物はいるのだけれど、彼らは物語の流れのなかで自分たちの意思とは無関係に大きな流れのなかで翻弄される存在でしかない。
それが近代以降の小説になると、人間それぞれが内面をもっていて、いろんな状況に悩み、喜び、怒り、打ちのめされる、心の動きが中心に描かれるようになる。そのとき、まわりの環境は人間の力でどうにかされるべきものだったり、逆に、幸福を手に入れようと励む人間の苦労など無関係なように振る舞う横暴で不条理な存在として人間と敵対するものであるかのように描かれたりする。これまで大きな流れのなかで一体化していた人間を含む環境が、人間とそれ以外のものという二元論的な関係となる。
結局のところ、近代以降の自然を含めたそうした環境の描かれ方は、あくまで前面に描かれる人間を中心として、環境の側は制御や改変、攻略や占拠の対象であるかのように描かれる。
それらはまるで舞台の書割り、いまの映画でグリーンバックを背景に演技する俳優たちの背後に後からクロマキー合成されるCG映像のように、人間とは二元論的に切り分けられてしまっている。
主人公ら人間以外の環境は背景に押しやられ、帝国主義のもとでの植民地のごとく、これから征服される対象であるか、すでに征服済みのものであるかのように、登場人物たちの心のなかの世界より優先度が低いものとして扱われがちだ。あくまで優先順位が高いのは現実世界である人間の外にある環境ではなく、幸せになりたいという人間の思いであるということをなんの疑いもなく前提としているのが近代小説の世界である。
クロマキー合成ではない都市環境で
ところが、このユゴーの作品はそうではない。
この作品では、パリという都市、ノートル=ダム大聖堂という建築物が、登場人物と同じレベルのキャラクターとして扱われる。

1482年のパリという都市で起こる出来事において、醜い鐘番のカジモド、美しいジプシーの踊り子エスメラルダ、あらゆる知を制したノートル=ダムの司教補佐クロード・フロロといった登場人物と、ノートル=ダム大聖堂や泥棒や物乞いの巣窟で「奇跡御殿」と呼ばれる区画、現在パリ市庁舎オテル・ド・ヴィルが建つグレーヴ広場も、ユゴーによって歌われる一大叙事詩には必要な要素として等しい扱いだ。そこに人間と物、人間と自然といった二元論はない。それらは等しく叙事詩的な変化のなかで相互に絡み合う要素である。
ノートル=ダム大聖堂が人々によって傷つけられるのと、フロロやエスメラルダが不幸に巻き込まれていくのも何の変わりもなく、叙事詩的な出来事の変化の一部として描かれるのだ。
それは古代ローマの詩人オウィディウスが『変身物語』で描いた数々の神々の変身、神々による人間の変身という変化と同じで、人間の心がすべての出来事において優先させるということなどなく、あらゆる変化が植物が育ち、動物が生まれ死に、雨が降ったり風が吹いたり、国が興り衰退したりするのと同じように、互いに影響を受け与えるエコシステムのなかにあるものとして描かれるのだ。
叙事詩のなかでは、あとからクロマキー合成で追加される背景的な環境などはない。
パリを俯瞰する視点
だからと言っていいだろう。ユゴーはこの小説の一部に決して短くはない。当時のパリの街を俯瞰してみせる章を割いている。第3編の「パリ鳥瞰」と題された章だ。その前の章は「ノートル=ダム」と題して「パリのノートル=ダム大聖堂は、疑いもなく、今日でもなお、荘厳で崇高な建造物である」と評したその建造物について語っているのだから、この作品でユゴーがパリとその街を代表する美しい建造物であるノートル=ダムを、登場人物であるカジモドやエルメラルダやフロロ司教補佐と同等以上に扱っていることは疑いはない(パリやノートル=ダムに丸々裂かれた章はあっても、カジモドやエスメラルダなどに割かれた章はないのだから)。
「私はこれまで、パリのノートル=ダム大聖堂の昔の素晴らしい姿を、みなさんにお伝えしようと努めてきた」と書き、今はもう失われたが15世紀にはまだ大聖堂が備えていた「美しい眺めの数々」を話したがまだ「肝心なことがまだ1つ残っている」といい、「昔この大聖堂の塔の頂から見おろした当時のパリの眺め」について「パリ鳥瞰」の章を語りはじめるのだ。
そう、ユゴーはノートル=ダムの頂という高い位置からの俯瞰でパリを見る。しかし、それはこの章に限ったことというより、この作品全体に共通する視点だといえる。近代小説が登場人物の内面を描くために顔の表情がわかるバストアップの視野で見ることが多いのに対し、ユゴーのこの作品は、ノートル=ダムの頂からのようなすごく高い位置からの視野がすべてではないにしろ、個々の人物をバストアップで捉える視野よりも、もっと引いて、人びとの姿を群像として捉えることの方が多い。大きな「叙事」のなかで人間だけを特別視して描くことはない。
変わるパリ
ユゴーは15世紀のパリの姿を想像する。ユゴーがこの作品を描いたときから350年前のパリ。それはルイ11世の時代のパリであり、ユゴーの時代のパリよりも3分の2くらいの大きさだった。
ユゴーはその街のはじまりである「中の島=シテ」からそれを語りはじめ、そこから徐々にパリが拡大していく様子を語る。
はじめはシテ島を囲むセーヌ川そのものが堀として機能し、生まれ変わる右岸と左岸にかかる橋の先に、それぞれグラン=シャトレとプチ=シャトレが城門であり城砦として設けられていたものが、島のなかだけでは窮屈になると外へと溢れ出し、ユゴーの時代、すでに「今ではボーデ門とかボードワイエ門――「ポルタ・バガウダ(盗賊門)」――とかの言い伝えがあちこちに残っているだけ」の古い城壁が築かれる。この古き城壁のなかもすぐに窮屈になり、フィリップ=オーギュストの城壁と呼ばれる12世紀につくられ、いまもマレ地区などにその痕跡が残る城壁が新たにつくられるが、そのエリア内でパリがおさまっていたのも1世紀と半分くらいのあいだで、1367年には城外に広がってしまった町や村のためにシャルル5世は新たに城壁を築かなくてはならなくなる。そして、ユゴーがこの作品の「パリの鳥瞰」で描くのは、このシャルル5世の城壁もまたそれまでの城壁と同じ運命をたどりはじめ、家々が壁の外に広がりはじめたパリの姿である。
シテを描いたあと、ユゴーはパリの左岸と右岸を順に描く。どちらかと言うと真面目な機能=社会が集約された左岸と、市民たちの街という印象を与える右岸。それはいまと変わらぬパリの性格といえる。
しかし、ユゴーはパリがその頃変わってしまったことを知っている。フランス革命ではノートル=ダムを含む多くの建造物が破壊された。もちろん変化=破壊は、人びとの暴力的な振る舞いによって起こるだけではない。古い建造物を新たに建て替えたり、街路を変更する際にも古くからあった街は失われる。
当時のパリは、ただ美しい都市というだけではなかった。パリは、まじりもののない都市であり、中世の建築術と歴史の産物であり、石でできた年代記だった。それはロマネスク層とゴチック層という2つの層だけからできているまちであった。

現在は中世美術館として使用される
ユゴーがこう評したパリは、その後50年ほど経ってルネサンスの時代がはじまると変化しはじめる。
簡素ではあるが変化に富んだこのパリという統一体に、ルネサンス時代のさまざまな気まぐれや方式という、目もくらむばかりに豪華な建築法、つまりローマ式半円アーチ、ギリシア式列柱、ゴチック式扁円アーチという混乱した形式や、優雅で空想的な彫刻や、アラベスク模様や、アカンサス飾りに対する特別な好みや、ルターと時代を同じくする異端的な建築法、こうしたものが付け加えられたのである。その結果、まちは、目にも心にも調和を欠いて映るようになったが、おそらくいっそう美しくなったのである。
どうやらここまでの変化はユゴーもお気に召していたようである。しかし「この華麗な時代はほんのわずかしかつづかなかった」といい、次のようにルネサンスの精神の不公平さを糾弾する。
建設するだけでは足りず、破壊もやりたがったのだ。羽をのばす場所が必要だったということも事実だが。だから、ゴチックふうのパリは完成されたかと思うと破壊されてしまったのだ。サン=ジャック=ド=ラ=ブーリュリ教会ができあがるかできあがらないうちに、古いルーヴル宮のとりこわしがはじまるというしまつだった。
ユゴーははその後、もっと大きな変化を知ることになる。1853年、ナポレオン3世のもと、県知事となったオスマンによるパリ大改造である。古い街路の拡張をはかるため、通りに面した建物の多くが壊されることになる。
こうして、パリの建築の歴史的な意味は、日一日と消え去っていく。
これがあれを滅ぼすだろう
こうした点からみると、この作品において有名なフロロ司教補佐のセリフで、後にマクルーハンも着目した「これがあれを滅ぼすだろう。書物が建物を滅ぼすだろう」という言葉をユゴーが書き記した意味も見えてくる。
ユゴー自身、こう書いている。
事実、世界のはじまりからキリスト紀元の15世紀の末までは、建築は人類の持っていた偉大な書物の役目をつとめてきた。能力や知能のさまざまな発展段階にあった人間の主な思想表現の手段となってきた。
と。
建築、それは15世紀までは石に書かれた書物だったのだ。テクストによってというよりも、建築そのものに刻まれた彫刻、ステンドグラス、タピスリーや絵画が建物そのものと一体となって、人間の知恵や思想を表現していた。

さらに、ユゴーは書く。
社会のあらゆる物質力とあらゆる知力が、建築という一つの点に集中してしまったのだ。そこで、神に捧げる教会を建てるのだという口実のもとに、芸術はすさまじい勢いで発展したのである。
当時、詩的才能をもって生まれた者は、誰もかれも建築家になった。そのころの民衆のなかに散らばっていた天才は、まるで青銅の盾を頭の上に「亀甲型に連ねられた」みたいに、すっかり封建制のもとに抑えつけられていて、建築の分野にはけ口を見いだすよりほかに仕方がなかった。そこで民衆の『イリアス』は大聖堂という形をとるようになったのである。
この状態が15世紀後半のグーテンベルクによる印刷術の発明によって変わる。まさに「これがあれを滅ぼす」時代のはじまりだ。
この作品の冒頭のシーンでこんな会話が交わされる。
大学に出入りする書籍商アンドリア・ミュニエ親方が、国王御着用毛皮類製造人ジル・ルコルニュ親方の耳元に口を近づけてしゃべるシーンだ。
「いやはや、あなた、世も終わりですな。学生どものあんならんちき騒ぎは、生まれてこのかた見たこともありませんよ。近ごろのろくでもない発明とやらが、何もかもだいなしにしまうんですよ。大砲だの、セルパンチーヌ砲だの、臼砲だの、とりわけドイツからはやりだしたあのやっかいな印刷術だの。もう写本もいらん、本もいらん!てわけです。印刷術は本屋殺しですよ。いやいや世も終わりですなあ」
「ビロード地もいい物ができるようになりましたからねえ、そのへんのところはよくわかりますよ」と、毛皮屋は答える。
ルネサンス時代の建築が、多様になるとともに、それ以前のゴシック建築をいともたやすく破壊してしまったのも、それが唯一の知や思想のアーカイブのためのメディアでなくなったということも大きいのだろう。
建築がほかの芸術なみの芸術としてしかとり扱わなくなったとき以来、つまり総合芸術、最高芸術、専制君主的芸術として認められなくなったとき以来、建築は他のいろいろな技術を手もとに引きとめておく力をもうもたなくなってしまった。そこで他の芸術は自由の身になり、建築家のくびきをふりはらって、それぞれ気に入った道を歩きはじめた。芸術はみな、こうして建築と手を切ったことから利益を得た。孤独はあらゆるものを育てる。教会彫刻は彫像術に、宗教画は絵画に、典文は音楽に進化した。

元あったノートル=ダムからは切り離されて
彫刻が、絵画が、音楽が、建築という統一体から離れて自由になる。そのとき、全体を見渡す俯瞰的な視点は失われ、個々をバラバラにみるバストアップ的な視点が可能になる。建築物は、街は、そのとき、個々の人の背景に追いやられて、クロマキーでいつでも取り替え可能なものの地位に追いやられてしまう。
ユゴーがこの叙事詩的な作品で描き出しているのは、そうしてルネサンス以降失われていくことになる、街や建築物のもっていた意味だろう。特にそれはパリや、ノートル=ダムという具体的な存在への愛として描かれている。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
