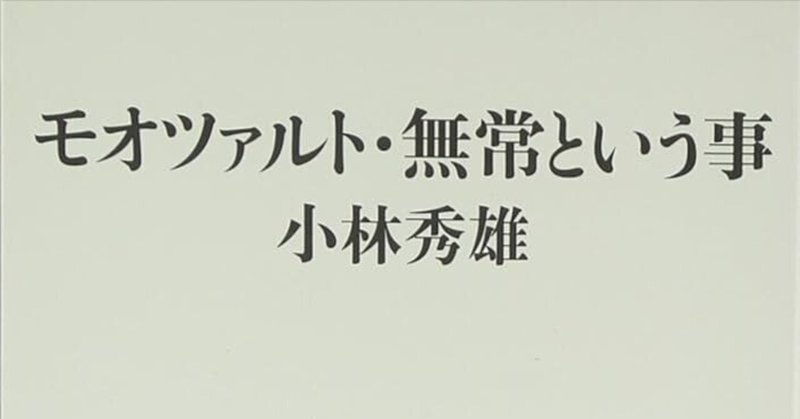
ものを五感であじわう〜小林秀雄「骨董」を読む〜
小林秀雄というひとの文章は、こころを直接に刺激してくるものだ。古くさいようでいて、現代を生きるわれわれの五感を刺激するような芳醇さが、どうもそこにはある。なかでもぼくのこころを捉えたのが、「骨董」なる短文である。そこでは、なんとも言えぬ薫りを纏ったことばが織りなされる。
骨董という文字には一種の魔力があって、人を捕える。骨董と聞いて、いやな顔をする人だって同じ事だ。相手に魔力があればこそだ。骨董という言葉が発散する、何とも知れぬ臭気が堪らないのである。
この文章の「あじわい」に、ハッとさせられた。率直に言って、これほどまでにことばを感覚的に味わうという経験を、これまでなし得なかったように思われたからだ。骨董という文字の「魔力」。「臭気」。どういうわけだかわからないが、確かにそれは存在するように思えてならない。「骨董」ということばに触れるたびに、魔力がぼくの触覚を刺激し、臭気が鼻を通り抜けていくのだ。
街を歩いている時、これが骨董屋だな、と直観される店にいくつも出くわした。胡散臭さを醸し出しているわけではない。だが、みずから掲げることなくとも、確かにそれは魔力を放つ。骨董屋とは、そういう存在なのだろう。
「骨董はいじるものである、美術は鑑賞するものである」(同上、220頁)。小林は「古美術」ということばとの対比をまじえながら、こう述べる。確かに「骨董いじり」とはいうが、「古美術いじり」とは言わない。かれにいわせれば、「古美術」と呼んでしまうのは、「臭いものに蓋」なのだ。このことは、さらなる含蓄を持っているように思われてならない。
現代では、大量生産の規格品が溢れかえっている。多くの生活用品は画一化され、そこに存在するオシャレは、言ってしまえば均質化された牢獄にすぎない。生活の中に骨董がつけいる隙はほとんど失われ、「古美術」として美術館や博物館のガラスケースにどんどん押し込められていく。まるで、それが放つ臭気を覆うように。
思えば、現代のものたちは、個性を失っている。均質に製造され、多くのものは廉価でも手にはいる。それらはたいてい、短いスパンでお役御免だ。こうして、われわれは「消費」を繰り返す。
どうやら、いわゆる産業革命の前夜から、こうしたライフスタイルは変わっていないようだ。いや、むしろそれが加速度的に進展してきた、と言ってよい。オランダの経済史家ヤン・ド・フリースは、当時の西欧の人々の精神変化を「勤勉革命」と名づける。単純化のきらいもあるが、彼の説明を簡単に要約してみる(ヤン・ド・フリース『勤勉革命』)。
17世紀ヨーロッパでは、工業技術の発展に伴い、それまで宮廷貴族の専売特許であった華やかな衣服や陶磁器、家具や調度品の大量生産が可能となった。また、タバコやパンなどの消費財も、中流階級の手の届く品に変貌していく。それはつまるところ、「廉価な贅沢」の誕生であった。きらびやかな衣食住を、手軽に獲得できる。ここに、人々は消費への欲望を増大させる。一方、生産工程にもより多くの労力を要するようになる。こうしてひとびとはみずからを労働へと駆り立て、産業革命への道程を準備した…。
かれの説明の中でなるほど、と思わされたのは、このとき大量生産が可能となった廉価な陶器の類は、「こわれやすさ」を内包していたという点だ。大量生産される皿は、決して耐久性に優れたものではない。むしろそれは、「こわれやすい」からこそ意味があるのだ。こわれやすいからこそ、ひとびとは廉価な製品を、なん度もなん度も購入する。
こうしたライフスタイルは、多分に漏れず日本にも舶来した。そのことに危機感を覚えた人物のひとりとして、柳宗悦の名を挙げることには、おそらく多くのひとが納得を覚えるのではなかろうか。
都市化・工業化が進む中で、柳は「民藝運動」を開始した。昭和戦前期のことである。大量生産が世を覆い尽くしていく時代にあって、かれは、民間人によって普段もちいられている、質素な「民藝」のうつくしさを守るべく立ち上がったのだ。
そんな柳は、1948年に『手仕事の日本』を出版する。「機械仕事」との対比をまじえ、「手仕事」の尊さを主張したのだ。いうなればそれは、機械製造が本格化する時代になされた、「たましいの叫び」である。
機械に依らなければ出来ない品物があると共に、機械では生れないものが数々あるわけであります。凡てを機械に任せてしまうと、第一に国民的な特色あるものが乏しくなってきます。機械は世界のもの共通にしてしまう傾きがあります。それに残念なことに、機械はとかく利得のために用いられるので、出来る品物が粗末になりがちであります。それに人間が機械に使われてしまうためか、働く人からとかく悦びを奪ってしまいます。こういうことが禍いして、機械製品には良いものが少なくなってきました。これらの欠点を補うためには、どうしても手仕事が守られねばなりません。
柳の文言には、機械製造の普及によって失われゆくものが端的に示されている。製品は均質化され、利潤追求が目的となり、粗末になりがちである。それに、作り手の「悦び」までもが奪われる。まさに、現代社会の生産過程における、核心的問題を提示しているのではなかろうか。
機械製造によって均質的に作られた製品には、こころが感ぜられない。これこそが、柳が言わんとしたことの核心だと、ぼくは感じる。柳は、ものに宿るこころを何よりも重視していたし、だからこそ、こころがこもる手仕事に価値を見出したのだ。
そもそも手が機械と異る点は、それがいつも直接心に繋がれていることであります。機械には心がありません。これが手仕事に不思議な働きを起させる所以だと思います。てはただ動くのではなく、いつも奥に心が控えていて、これがものを創らせたり、働きに悦びを与えたり、また道徳を守らせたりするのであります。そうしてこれこそは品物に美しい性質を与える原因であると思われます。それ故手仕事は一面に心の仕事だと申してもよいのでありましょう。手より更に神秘な機械があるでありましょうか。
かれがいうように、手よりも「神秘な機械」はない。大量生産で均質な同型に作られた器と、職人がろくろでまわした陶器を比べれば、その差は一目瞭然だ。かたや見事なまでに同質性を維持しているが、そこに「あじわい」はどうも感じがたい。一方の手作業には、こころが感じられる。いわばその細部に神が宿り、ものは個性を持つ。
「骨董いじり」が持つ魅力というのは、まさにこのことにあるのではなかろうか。手仕事に宿るこころは、手にとることによって、使用することによってこそ、はっきりと感じられる。古美術のように鑑賞するだけでは、その魅力には到達し得ない。骨董が放つ「臭気」とは、いわば骨董から滲み出るこころのことを指すのだろう。いじることによってこそ、そのこころに到達できるのだ。
手仕事に宿ったこころは、鑑賞するだけでは飽き足らない。手に取り、臭気を感じとり、こころの声を聞く。そしてその味わいを嗜む。五感を研ぎ澄ましてこそ、ものの良さに触れることができるのだ。
現代では、骨董いじりはおろか、手仕事も相当程度に失われつつある。ものはこころを失い、魔力と臭気を発することができなくなっている。一概に骨董いじりの高尚さを称揚するつもりもないが、ものの魔力に美を感じとる姿勢は、失われつつある。
僕は骨董いじりを弁護しているのではない。それは女道楽を弁護するくらい愚かなことだ。しかし、僕はこんな風に考える――美を生活の友とする尋常な趣味生活がほとんど不可能になって了った現代、人々が全く観念的な美の享受の世界に追い込まれるのは致し方ない傾向だとしても、この世界を楽しむのが、女道楽より何か高級な意味あることだと思い上っているのは滑稽である。また、この滑稽を少くとも美の享受の道を通じて痛感するためには、骨董いじりと言う一種の魔道により、美と実際に交際してみる喜怒哀楽によるほかはないとは悲しむべき状態である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
