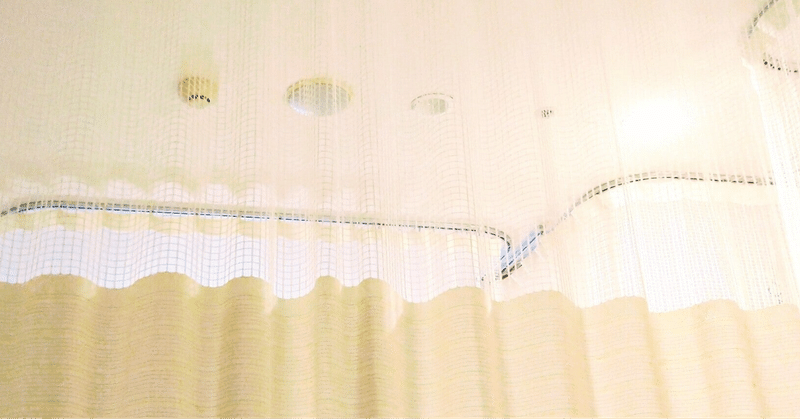
【小説】病室
「もう別にいいのに、お見舞いなんて」
千歳さんが、ベッドの横に吊るしてあるリモコンを操作し、ゆっくりと大きな音を立てて起き上がる。
「いえいえ。私も好きで来てるので。ご迷惑だったらアレですけど」
「全然迷惑じゃないんだけどね。千佳子ちゃんの負担になってないかなって」
「それは全然」
私は、花瓶に入った干涸びた花たちを取り出し、さっき駅前の花屋さんで買ってきた橙色のガーベラと入れ替えながら、この花達について考える。
花にとって、美しさのピークを迎えたその時——人間で言うと、人によって違うけど大体20代とか?——に刈られ、知らない誰かの悲しみ・喜びに寄り添いつつただ枯れるのを待つだけ。
そういうの、寂しいよなと思いつつ、羨ましさも感じる。この花達は、ただ存在するだけで養分をもらうことができるし、その存在にお金が払われる。それに比べて私は、働かなければお金を得ることはできないし、食にもありつけない。
「今日何かあったの?」
「ああ」と、私は一年ぶりに来た真っ黒いスーツを触りながら応える。「一周忌だったんです。父の」
「そう……。もう1年も経つんだね」
千歳さんは少し顔を曇らせてから、「改めてご冥福をお祈り申し上げます」と頭を下げた。
こういう言葉がさっと出てくるところが大人だよなと感心し、肌艶も良く白髪ひとつもないから忘れがちだけれど、私と千歳さんの間に親子ほどの歳が離れていることを改めて思い出す。
「いえ、ありがとうございます」
私はといえば、『ご冥福』の意味さえも良くわかっていないので、なんとなくの返事と深々と頭を下げることで誤魔化した。
千歳さんと私は、親戚でもなければ友達でもない。
今から1年半ほど前に、この病室で出会っただけの関係だ。
その頃の私は、社会人も3年目になりなんとなく仕事にも慣れてきていて、そろそろ一人暮らしでも始めようかなと計画していた。いつものように、仕事中のお昼休みにスマートフォンで物件探しをしていると母からの着信があり、電話に出てみると、耳が痛くなるような大声が耳に飛び込んだ。
「お父さんが、お父さんが倒れちゃって。今から病院行くんだけど、千佳子も来れる?お願い、来てくれない?」
会社を早退し、病院に駆けつけ、病室で横になっている父の代わりに私と母が医師から話を聞いたところ、精密検査の結果膵臓がんが発覚し、肝臓や肺に転移をしているとのことだ。
「手術はできないんですか?お願いです、お願いします」と泣き崩れながら医師に懇願する母を横目に、「あー、しばらくは一人暮らしはできないかもなー」と、不謹慎にもそんなことばかりを考えていた。
医師からの話を聞き終え憔悴しきった母は、父のいる病室に寄ることもなく、「帰ろう。……あ、運転お願いしてもいい?」と言って車の鍵を渡すので、驚きその鍵を凝視してしまった。
私が免許をとって間もない頃に母が大事にしてるミニクーパーを凹ませて帰ってきてからというもの、頑なに自分の車を私に運転させることはなかったのだが、それほど疲れ切っていたのだろう。
それから数日後、ノー残業デーである水曜日の業務後に父の病室にお見舞いに行った。
お花でも持って行った方がいいんだろうなと思いお花屋さんに行ったが、父が好きな花はおろか父が花を好きだったかどうかさえわからず、結局は私の知っている父の唯一の好物であるシュークリームをコンビニで買うことにした。
受付で案内された病室へ向かうと、病室内には6つほどベッドが並んでおり、その一番奥に父が横になっている。
「お父さん、調子どう?シュークリーム買ってきたよ」
私は努めて明るい声を出し、父にシュークリームを差し出した。
父は、シュークリームと私の顔を交互に見て、不思議そうな顔をしている。
そんな父の顔をまじまじと見て、「ああ、歳を取ったんだな」としみじみと感じた。髪は薄くなり、おでこには幾重にもしわが重なっている。そして、口をぽかんと開け目をしょぼしょぼとしている様は、昔見たアニメに登場するおじいちゃんそのものだった。
「どちら様ですか?」
父が間の抜けた声でそう言う。
私は理解が追いつかず「え?」と聞き返すと、また父は「どちら様ですか?」と繰り返す。
思わず手に持っていたシュークリームを地面に落としてしまい、「こういう時って、本当にドラマみたいにモノを落としちゃうんだな」と冷静に考えながらも、父の発した言葉やその意味については、何も考えることができなかった。
「人違いじゃありませんか?」
父は本当に不思議そうな目で私を見つめてくるので、どう返答しようか答えが出ないでいると、「千佳子ちゃん」とどこからか女性の声が聞こえた。
振り返ると、ベッドに腰掛けた女性おり、「千佳子ちゃん、こっち。場所間違えてるよ」と私に声をかけている。それが、千歳さんだった。
私が訳もわからず千歳さんの方へふらふらと歩き出すと、父は「ああ、なるほど」と納得したような声を出し、ベッドを覆い隠すようにカーテンを閉めた。
千歳さんのベッドの横まで行くと、千歳さんは「ごめんね、迷惑じゃなかった?」と心配するような目つきを向ける。
「えっと……」と私が状況を飲み込めていないでいると、絵本でも読み上げるように、私に優しく語りかけた。
「あのね、ちょっと会話が聞こえて。私も、夫が亡くなる前に認知症とかになってね。だから、少しだけだけど気持ちはわかるから。すぐには受け入れられないよね」
「あ……」と、千歳さんが私を助けてくれたことに今更ながら気づいた。
「昔からあるでしょ、女の子が男の人に声かけられて、困ってる時に『その子俺の彼女だけどなんか用?』みたいに助けるやつ。あれやってみたかったんだよねー。まあちょっと……というかだいぶシチュエーションも違うけど、それ、してみました」
千歳さんは戯けたような表情で私にウインクをする。
私は一礼し、「あの……本当に、ありがとうございました。……あれ以上、父と……お父さんと、喋ってたら、きっと……」と喋ったところで意図せず涙がこぼれ落ちてしまい、「すいません」と謝りながら服の裾で涙を拭った。
すると千歳さんは私を引き寄せ、ぎゅっと抱きしめた。「好きなだけ泣いていいんだよ」と優しく声をかけた千歳さんは、「やりたかった少女漫画のシチュエーション、全部できたかも」と戯けて笑った。
それから半年が経った頃、遂に私の事を一度も思い出す事なく、父は他界した。
それでも私は父がいた頃と変わらず、月に一度はこの病室にお見舞いに通っている。
「千佳子ちゃん、仕事は順調?」
「順調……とは言い難いですね。チームリーダーとか任されるようになっちゃって」
「へー、チームリーダー。優秀な証拠だね」
「いやいや、そんな事ないですよ。面倒な役割を押し付けられてるだけで」
そんな、たわいのない会話を10分ほどして帰るのだが、看護師さんや他の患者さん達からは、私たちの関係はどう見えているのだろう。そして実のところ、私たちの関係は何と形容されるのだろう。
毎週会っては会話をし、家族や友人にさえ話せない事も千歳さんには打ち明けることができる。しかし、私は千歳さんの病名さえ知らないし、千歳さんは私の名前さえ知らない。
そして、「千佳子ちゃん」と最初に千歳さんが呼びかけてから、私はいつも千佳子ちゃんと呼ばれているのだが、なぜ「千佳子ちゃん」と呼びかけたのか、その理由も私は知らない。
