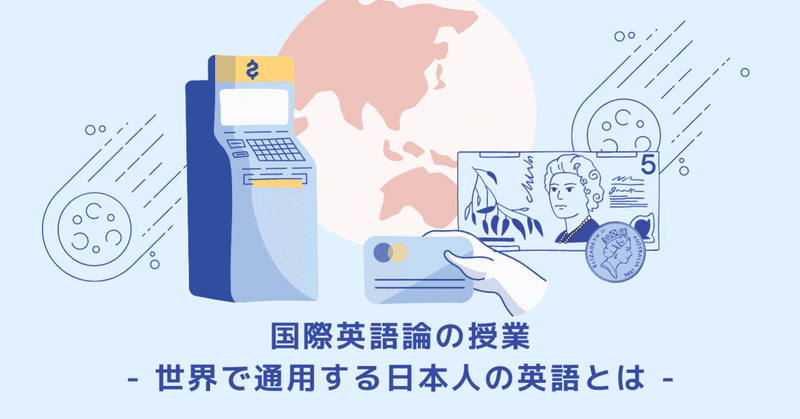
国際英語論の授業(高校1年生)その2
本記事は下の記事の続きになります。
高校1年生が様々な英語変種の会話例を聞いた後に,「日本英語」があるとしたらどのような会話例になるかを考え,録画・録音した授業。その完成品をクラス全体で共有した上で,それぞれのグループや個々の学習者がどのようなことを意識したのかを少し掘ってみた。
高校生の考える,日本英語の発話
まずやはり注目が集まりがちだったのが「発音」である。
「カタカナ英語」というキーワードが複数の班から聞かれた。
ある班では"Nice to meet you."を「ナイストー・ミート・ユー」といった発音で読む生徒がおり,それには「やり過ぎだろ」「馬鹿にしてる」といった声も聞かれた。
他の班の多くは「不自然じゃない程度のカタカナ英語」で話したとのことだった。
発話の面でこのクラスの言葉への鋭さが発揮されたのはこの後である。ある班は「わざと『えーっと』とか,余計な言葉を入れた」らしい。つまり意図的にフィラーを入れたのである。
"Let me see"や"Well"のような英語のフィラーではなく,日本語の「えーっと」を入れたのは,シンガポール英語の文末に"ma"などの非英語語彙が入っていたことを受けての選択だ。
日本語母語話者が人と口頭でコミュニケーションをする際に多言語母語話者に比べてフィラーが多いのかどうかは定かではない。研究はあるのかもしれないが,私も生徒たちも知らない。
しかし,「日本英語」と聞いてフィラーの量に注目が集まったことは彼らが普段の自らの日本語・英語でのコミュニケーションを深く振り返ったからこそだろう。それが日本語での会話における関係性の調整等のためのフィラーの多さに由来する発想なのか,英語で会話する際の英語力不足から来るフィラーの増加に由来する発想なのかは分からない。授業中にそこまで考察が及ばず,生徒たちに問いかけなかったのは私の力不足だ。
高校生の考える,日本英語の文法
録画・録音をするにあたってアメリカ英語の自己紹介の動画の台本を生徒に渡し,「日本英語専用に台本をマイナーチェンジしてもOK」と伝えたところ,多くの班が台本の英語に変化を加えてきた。
キーワードは,英語に関する「知識」と「意識」だ。
例えばある班は「SVを含んだちゃんとした文にする」ことを意識した。相手を食事に誘う際の最後に"Maybe next week?"というセリフが元々のアメリカ英語版では発せられているのだが,これを"Shall we go to dinner next week?"としたのである。これは個人的には意外だった。規範的な英文法からの逸脱を許すことで英語非母語話者にとって「やさしい」英語にするという傾向を勝手に予測していたが,その逆というか,全ての文に主語と動詞を存在させるという(規範的な)学校文法への「寄せ」が見られた。高校生は学校や塾でのみ英語を習い,「全ての文はSVを含む」という「知識」とそこから来る「英語を発話するときにはSVを必ず含むようにする」という強い「意識」が定着している。そんな彼らにとってはネイティブの日常会話で生まれるような伝統文法から逸脱した発話は英語という言語の体系性を乱すものとして認識される。「日本人は『正しい』英文法を使うはずだ」という認識からの台本の改変だ。
似たような意見で「教科書でよく見る英語」というのもあったが,これはどちらかというと「日本人の英語への意識」というよりは単純に「日本人の英語に関する知識」の問題として考えたらしい。
アメリカ英語版の"a couple of"を"some"に変えたり,名前を名乗る際にも"I'm"ではなく"My name is"を使ったりという具合である。後者については若干彼らの中での「教科書の英語」のイメージがデフォルメされている気もしないではないが。
また,これと似た例で,「単語を簡単にした」という班もあった。
この日本人の英語に対する「意識」や「知識」の問題を反映したもう一つの例は「短縮系の不使用」である。
複数の班が"We'd"や"We've"を"We would", "We have"にあえて直した。理由は「最初何のことか分からなかったし,多分わざわざ短縮系を使わないと思う」とのことだ。
「最初何のことか分からなかった」というのは英語の知識の面で彼らにあまり馴染んでいないということを表す。
そして「わざわざ短縮系を使わないと思う」という発想はかなり興味深い。「わざわざ全部の音をちゃんと言わなくても伝わるよね」というところから「短縮系」というのは生まれていると思うのだが,日本語を母語とする彼らにとっては本来含まれている単語を音の上でのみ省略するという(認知的)行為は煩わしさを増すのだ。
"don't"ぐらい繰り返し習って定着した表現ならまだしも,"We'd"や"We've"は彼らにとってはあえて使おうとはしない,奇抜な表現なのかもしれない。
高校生の考える,日本英語のコミュニケーションストラテジー
ある班は「やたらと"Sorry"を言うようにした」とのことだ。
理由は「日本人の大人はやたら『ごめん』とか『すいません』とか言う」からだそうだ。
僕自身は多分比較的横柄な態度を取る傾向にあるので,自分ごととしてはあまりピンと来ないのだが,確かに多くの人が会話中,特に会話の切り出しと終わり頃にやたらと「すみません」「ごめんね」を言うイメージはある。
母親の電話を聞いていると切る前の20秒ぐらいはもう「はーい,すみませーん。はーい,ごめんねごめんね,はーい。じゃ,すみませーん,はーい,失礼しまーす。すみませーん」みたいな感じだ。確かに隙あらば謝っている。
「どんだけ悪いことしたんや」とツッコみたくなるが,別に何か悪いことをしたから謝っているわけではない。
相手との適切な距離感や上下関係を会話の中で常に微調整する機能を果たしていると考えられる。(完全に専門外なので,見当違いなら訂正いただけると嬉しい)
日本語母語話者のコミュニケーションの特徴を,「謝罪の言葉を使って相手との距離感・上下関係の調整を行う」と捉え,会話の随所に"Sorry"を入れ込んだ。欲を言えば,どういったタイミングでどういったトーンの"Sorry"が入るかはもっと考察を深めてもらいたいところではあったが,非常に鋭い分析であると思う。
そして,My Englishへ
上で「カタカナ英語」的な発音について触れたが,発音について興味深い選択をした班があった。彼らは「僕ら日本人なので,自分が喋る英語が『日本英語』だと思って,普段の自分のままの英語の発音にした」という。
つまり,「日本英語」という言葉を聞いて想像する何かしらの特徴を持った英語を意図的に発音するという行為を選択しなかったのだ。
加えて彼らに「君らの今の英語の発音が日本人の標準ってこと?」と聞いてみると,「というよりは,どうせみんな違うし自分たちの話す英語でいい」というような趣旨の答えを返してきた。
もしかしたら彼らは考えることが煩わしくて「別に俺ら日本人なんだから俺らの発音でよくね?」と投げやりにその選択をした可能性もある。
しかし少なくとも,「どうせみんな違うし自分たちの話す英語でいい」という発想はまさにMy Englishの考え方そのものではないだろうか。
授業の最終盤にその班の生徒たちの言葉をもう一度引いて,「日本英語」や「シンガポール英語」などとまとめるとはどういうことで,それに対してMy Englishの考え方はどういう立場を取るのかを説明した。
(その中身は以前の記事,または参考文献へ)
そしてチャイムが鳴るスレスレの時間ではあったが,最終的に伝えたかったことを伝えた。
最終的に目指したいのは,みんなが外国語コミュニケーションに対して今より積極的になれること。それが「真鍋さんはああいう感じだったけど,俺はもっとアメリカンな英語の発音を目指して頑張ろう」でも「あれぐらいの発音でもいいんだ。それなら俺でもいけるかも」でも構わない。一人一人が現時点で話す,そして将来話せるようになることを目指す英語に対してポジティブな気持ちを持ってくれればそれでいい。
そしてそれよりもっと大切な核としては,他の人のどんな英語も馬鹿にしたり蔑んだりは決してしない大人になってもらいたい。
話を聞いてもらえるだけの人,とは?
日本語を母語とするノーベル賞受賞者やメジャーリーガーの英語を聞かせるというような指導に対して,「そういうのは,話を聞いてもらえるだけの人達だから,生徒にあれでいいんだと思わせない方がいい」という声もある。私も大学生時代にはそんなことを思っていた。
どこで聞いた話とはあえて書かないが,海外で一流のビジネスマンとして活躍してきた人たち曰く,「日本人の英語の発音は海外のビジネスでは通用しない。馬鹿にされて,相手にされない」らしい。
それは現時点で事実なのかもしれない。
目の前にいる生徒達を今すぐ世界で活躍するビジネスパーソンに育てなければならないのであれば私も発音には徹底的に拘るだろう。
しかし,学校教育の目的は経済界のための人材育成でもなければ,現状の社会への適応でもない。
むしろ,国際英語論の立場に立てば,問題とされるのは「発音の悪いやつの話は聞く価値がない」とする英語使用者の文化の方だろう。国際英語論は(仮に非英語母語話者のための考え方であったとしても),非母語話者にしか働きかけないというものではない。むしろ母語話者の方にこそ,正確には母語話者か非母語話者かの区別とは無関係に,英語コミュニケーションのあり方を問うものだ。
教育とは現状の社会のあり方とは一定の距離を保ちながら,より良い社会のあり方を模索・実現していく営みである。
もちろん今高校1年生の生徒達が二十歳そこそこの時点で海外でビジネスパーソンとしてバリバリやりたければそれに向けて発音のトレーニングをすることは望ましいかもしれない。私の授業で伝えたメッセージは決してそれを妨げるものではない。
むしろ重要なのは,海外でビジネスをする上でも様々な英語の変種に対して何ら差別的な態度・評価を示すことなくコミュニケーションを取るようになってほしいということである。
そうすれば,世界は今よりほんの少しだけ良くなる。
そして,これは世界に出る者に限らない。英語使用者は我々の身近なところにどれだけでもいる。日本にいれば片言の日本語を使う人々にも沢山出会う。
そのような人々とのコミュニケーションに対しても,私の基本的な考え方は同じである。
ある人の言語(そしてそれを形成するその人の背景)が差別の理由になどなってはならない。
言語を用いて他の生物種とは比にならないほどの発展(と破壊)を生み出してきた人間だからこそ,言語に対する姿勢について思慮的であり過ぎることはない。
参考文献
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
