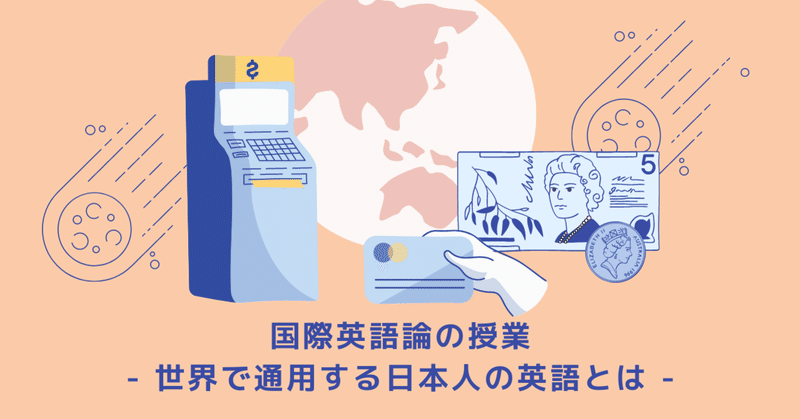
国際英語論の授業(高校1年生)
先日ノーベル物理学賞を受賞した真鍋淑郎氏のプリンストン大学での会見を観て,「これはちょっといい教材になるかも」ということで高校1年生相手に「国際英語論」を扱ってみることに。
流れとしては,(1)「アメリカ英語」「イギリス英語」以外の英語変種の存在とその特徴を(ざっくりとでも)掴んだ上で,(2)それぞれの変種を英語として認める態度を持ち,(3)「日本英語」というものがあるとしたらどんなものかを考え,(4)最終的には,一人一人が置かれた文化・環境,培ってきた言語学習の結果として現時点で使う英語,つまり「My English」に自信を持ちながら今後の英語学習や英語使用に前向きに取り組む姿勢を持つことがゴールだ。
このあと紹介する諸活動は私のオリジナルであるが,理論のベースは主に『「国際英語論」で変わる日本の英語教育』(塩澤ほか, 2016)の第3章,塩澤の「国際英語論に基づく英語教育実践」を参考にしている。
塩澤は国際英語論に基づく英語教育実践の大きな目標を以下の5つに集約している。
1. 英語の多様性や世界共通語としての英語の特徴を認識する
2. 多様な英語に対して非評価的で寛容な態度を育む
3. 国際的コミュニケーションストラテジーを身につける
4. 国際共通語としての"My English"(「自分の英語」)を肯定する
5. 多様な英語を喋る人たちとコミュニケーションをとる喜びを知る
(p. 56)
本実践はこの内1~4を射程に入れたものである。5も本当なら近隣の大学への留学生などを呼ぶなどして今すぐにでも実施したいところであるが,生憎のご時世でまだ留学生は入国できていないそう。オンラインでの国際交流も徐々に活発になってきているため,そちらでもチャンスはありそうだ。
多様な英語に関する知識と寛容な態度の寛容
まずは上記目標の1と2について,ここで用いたのは「東京外国語大学言語モジュール」。
このサイトで「英語」を選ぶとアメリカ,イギリス,オーストラリア,カナダ,ニュージーランド,シンガポール,アイルランド,インド,フィリピン,マレーシアの10種類の英語での会話を視聴することが出来る。
時間をたっぷり取れるのであれば,例えばそれぞれの生徒を10種類の英語のうちどれか1つの担当にして,各変種の特徴を分析して報告するなどという活動もありかもしれない。
今回は高校生の英語表現の授業の中である意味ゲリラ的に用意した単元ということもあり,そこまでの時間は取りづらいため,ここでは「自己紹介」の会話例をいくつか聴いて「色々な種類の英語があるんだなぁ」ということをざっくり知るにとどめる。
(後から聞くと家でひたすら色んな英語を聞いたという生徒も若干名いた。そういう興味を刺激できただけでも十分だろう。)
その「知る」過程でどうしてもアジア系の英語を中心に生徒から「笑い」が起こる。これに「人の英語を笑うな!」と一喝することは簡単だが,「人の英語を笑うと怒られるから笑っちゃいけない」という考えを持つことは避けたい。と言ってもあまり気の利いた言い方も思いつかず「今笑った人,自分もアメリカ人に笑われるしれないよ」と意地悪っぽく言うことしかできず…。ただ,少し真面目なトーンに切り替えて,インドなどの国は好きで英語を使い始めたわけではなく,イギリス植民地時代に押し付けられたものであること(仲, 2020, p. 29)を教えると,少し神妙な顔つきになる。
本当の意味で世界の英語変種に非評価的で寛容になるためには自分たちの英語に目を向ける必要がある。というわけで生徒たちには「日本英語」なるものを考えてもらう。
上の「東京外国語大学 言語モジュール」の英語の会話例に「日本英語」という項目を作るとしたら「自己紹介」の会話はどのようなものになるかをグループで考え,(アメリカ英語版の台本を「日本人の話す英語らしさ」という観点から自由に改変し,)会話を録画・録音する。
生徒たちはやはりまずは「カタカナ英語」をベースに考える。
生徒たちの録音した音声を聴いてみると,予想通り一つ一つの音がカタカナっぽいだけでなく,文全体としても強勢があまり置かれていないものがほとんどである。(授業として全体で聴くのは次回に持ち越したが,録画・録音し終わったグループのものをその場で聴かせてもらった)
やはり「日本人の英語」というとカタカナ発音で平板なイントネーションというイメージがあるのだろう。興味深いのは,そのような発音は多くの生徒の本来の発音からは程遠いものであるということだ。
日本人である彼らが考える日本人らしい英語は,全く彼ららしくはないのである。
試しにある生徒に「普段そんな話し方してなくない?」と訊いてみると,「確かに。でも日本人の平均みたいな感じで考えると,こんな感じかな」とのこと。彼にとって「日本英語」は「日本人の平均」というイメージらしい。
「平均」というワードは自分はあまり意識していなかったが,そこから離れた色々な英語を日本人が話すことは自然であるという認識に基づいた言葉とも言える。
国際的コミュニケーションストラテジーを身につける
正直に言うと,数時間の一単元で「国際的コミュニケーションストラテジーを身につける」ことは不可能だ。
しかし,「世界で通じるためにはこういう工夫はあった方がいいんだろうな」とか「こういう感じでもちゃんと伝わるのかも」というイメージを掴んでおくことは後のコミュニケーションストラテジー(を含む英語運用能力)の習得に繋がるだろう。
ここでようやく例の動画の出番である。
真鍋氏の英語はいわゆる「カタカナ英語」と呼ばれるであろう発音である。rとlはどちらも「ラリルレロ」で発音し(一番手っ取り早く聞くなら18:00あたりの"broken English"というフレーズで分かる),sとthもあまり区別されている感じはしない(例えば18:44辺りの"thank"は文脈がなければ"sank"に聞こえそうだ)。"easy"という単語の/zi/の音も「ジー」という感じだ(20:41辺り)。
それでも,会見場では「気候変動を理解することは現代の政治を理解することに比べれば難しくない」という受け答えで笑いも起きるほどにしっかりと通じている。
ただ,私たちが素朴に想像する「カタカナ英語」とは少々違う点もある。私が注目したいのは"mysterious"(20:50辺り)という単語の発音だ。カタカナであれば「ミステリアス」となるところ,真鍋氏は「ミステアリアス」という感じで発音してる。
このことが示唆するのは,仮に一つ一つの音がカタカナで発音されてもそれなりに通じるとしても,日本でも広まっているカタカナ語が英語として理解されるためには日本で広まっている発音ではなく,元の英語に近い発音を保たなければならないという可能性だ。
そしてこれは発音の問題からは離れたストラテジーになるが,真鍋氏は質問者や司会の方を頻りに確認しながら話をしていることがこの動画ではよく分かる。ここでは自分の英語がきちんと伝わっているか都度確認したいという真鍋氏の意思が働いている可能性はないだろうか。
真鍋氏の行為がその意図によるものであるとすれば高校生にとって非常に重要な教えとなり得る。母語同士でさえ言語コミュニケーションは会話者間に誤解を生むことが日常茶飯事である。況してや外国語でのコミュニケーションとなればより意識的に相手の理解を確かめようとする態度は重要なものとなるだろう。
"My English"を肯定する
真鍋氏は確かに「日本語母語話者っぽい英語」を話しているかもしれない。しかしそれは真鍋氏が「日本人の英語はこうだ!」というものを見せる(聞かせる)ためにやっていることではないはずだ。それ以外にもニュース等でアスリートやアーティストをはじめとした様々な日本人の英語を聞く機会は沢山あるが,大谷翔平も錦織圭も宇多田ヒカルもみんなまるで違う英語を話す。ちなみに英語の授業で僕が見せがちなのは,出川哲朗よりも元メジャーリーガーの川崎宗則だ。(日本語学習者の例にはなるが,最近だとガンバ大阪のパトリックもすごく良い。動画にまとめたJリーグ公式も天晴れだ。)
結局のところはそれぞれの人がそれぞれの文脈の中で身につけてきたその人自身の英語(My English)でしかない。シンガポール英語,インド英語などの英語変種もあるコミュニティの中で一人一人違う英語を話している多くの話者の英語を恣意的に体系化したものである。(仲, 2020, pp. 106-7)
体系化すること自体は簡単なことではなく,そのための研究をしてきた人たちには最大限に敬意を表すべきだし,実際そういった積み重ねがあったからこそこの授業で使った言語モジュールも利用可能だったわけだ。
しかし教室にいる一人一人の英語学習者にとっては「日本人の話す日本英語はこういうのだよ」と示すことは,「ネイティブはこう話す。これを真似しよう」ということと何も変わらない。国際英語論を授業で取り上げる意味すら失われてしまいかねない。
改めて,この単元のゴールは「日本人の平均」としての「日本英語」の規範を見出すことではない。
最終的に目指したいのは生徒が外国語コミュニケーションに対して今より積極的になれることである。それが「真鍋さんはああいう感じだったけど,俺はもっとアメリカンな英語の発音を目指して頑張ろう」でも「あれぐらいの発音でもいいんだ。それなら俺でもいけるかも」でも構わないと思う。一人一人が現時点で話す,そして将来話せるようになることを目指す英語に対してポジティブな気持ちを持ってくれればそれでいい。
そしてそれよりもっと大切な核としては,他の人のどんな英語も馬鹿にしたり蔑んだりは決してしない大人になってもらいたい。
My Englishを認める姿勢はYour EnglishもHis/Her Englishも同じように認めることに繋がるはずだ。
というわけで,次回の授業では生徒たちが録画・録音した会話を実際にみんなで聞き,「普段の英語と話し方違う人は,どういう意図でどういう英語を話そうとしたの?」と問うてみたり,逆に普段通り話した生徒に対してもその意図を聞いみたりしようと思う。
録画・録音を聴き合う前に,すでに一つ興味深いのは,いくつかの班で結構ダイナミックな台本の改変があったことだ。これについても次回の授業でその意図を聞いみてようと思う。グループワークを覗いてみた限りでは,We'veやWe'dなどの短縮形をWe have, We wouldに直しているといった様子が見られたり,「この人1人でずっと喋ってるから,こっちの人が相槌入れよう」などという話し声が聞こえた。
「日本英語」といったときに発音ばかりに目を向けるのではなく,文法や語彙の表現,さらにはコミュニケーションスタイルにまで目を向けたその生徒たちの言語観,ことば・コミュニケーションへの鋭い洞察には頭が下がる。
実際に生徒たちと一緒に音声を聞いてディスカッションし,My Englishという考え方を提示する後半戦については下の記事をお読みください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
