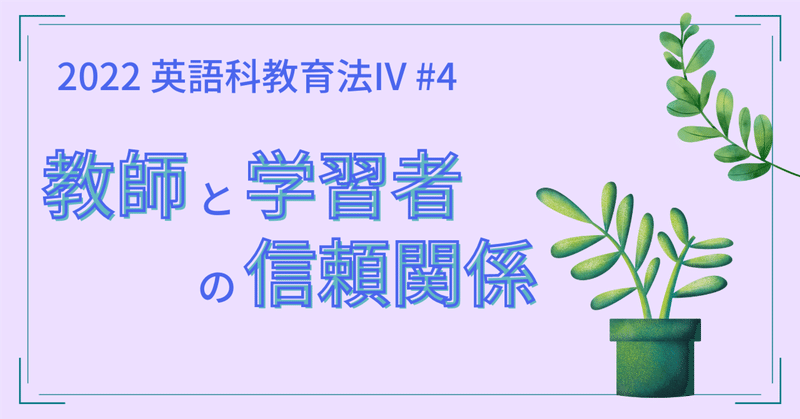
教師と学習者の信頼関係
英語科教育法IV『外国語学習者エンゲージメント』の第3章前半。
「教師と学習者の信頼関係(ラポール)」の理論的根拠を検討した。
原則1「近づきやすさ」
教師はいつでも近づきやすい存在であることが必要であり、そのために(適切なレベルでの)自己開示が重要であるという筆者らの主張にどの学生も概ね同意しながらも「適切なレベル」を巡っては意見が分かれた。
プライベートな話までしてくれる先生をより信頼する傾向の強い学生が多数派ではあった(過剰だと思わないぐらいに、という程度問題にまた陥る)が、プライベートなことは別に教えてくれなくても、それが信頼関係や近づきやすさに関わることはないという学生もいた。
私個人としては指導技術や知識そのものよりも、(そういう力を身につけた過程も含めて)教師の人柄が信頼できるか否かに大きく関わるタイプだったので、自分が育てる教師達にも可能な限りでの自己開示をできるようになってほしいと思っているし、私自身も教師教育者として可能な限りの自己開示をするようにしているという(ほとんど無意識的にやっていることもある)部分を言語化することができた。
また、近づきやすい・親しみやすい先生と、ナメられる先生の違いは何か、どうしたらナメられることなく親しみやすい先生としていられるか、という(おそらく若手教師や教育実習生あるあるな)疑問について、多くの学生が「叱るべきときはきちんと叱ることが大事」とした。
私からはそれに付け加えて、「教師の教科専門性」(あるいはPCK)をナメられないことの要因に挙げた。学齢にもよる気もするが、どれだけ親しみやすく優しく歳の近い先生だとしても、教科に関する専門的な知識に富んでいて授業もわかりやすければ多くの生徒が正当なリスペクトの気持ちを向けるだろう。
これは分かりやすい授業が大好きだった川村少年の思想にやや偏った意見とも言えるかもしれないが…。
原則3「学習者の個性を尊重する」
ここでは①ここの学習者の固有の特徴に注目することと、②全ての学習者に学びを保証することの2点が重要と挙げられていたが、この②について「全ての学習者がそれぞれに見合った異なる方法で同じ目標を達成できるように授業をデザインすること」とされており、どの学生もそこに違和感を抱いていた。
一人ひとりに合わせた方法をとることの物理的限界もさることながら、全ての学習者が同じ目標を達成するということも現実的には思えなかった。Task Based Language Teaching的な発想で、同一の課題の解決・達成を目指すという捉え方をすればやや現実的にはなるが、学習内容の習得となるとなかなか厳しいだろうというのが学生の共通見解であった。
一方で「もし物理的に可能であれば、一人ひとりに最適の方法で勉強させたい」ということも共通見解だった。つまり、いわゆる「(方法論的に)個別最適化された教育」の発想には肯定的らしいことが分かった。
私の教育観をどこまで前面に出すかは迷いどころだが、私としては(仮に物理的・教員の能力的に可能だとしても)完全な個別最適化には賛成しない。
それは将来の社会の成員を育てるという教育の役割を考えたとき、どういう社会にしたいかという価値観の問題になる。
「あなたは一人でこの問題を解けるから、一人でやってていいよ」「あなたはあの子とペアを組むと一番上手く行くよ」「あなたはこの問題をやる必要はないよ」そんな風に大人からあるいはAIから指示されて、自分の能力を高めるために最適な道だけを進んできた人間が何万人、何十万人と大人になって社会に出たとき、社会はどのような姿になるだろう。
SF作家ではないからこれ以上のことはあまり想像できないが、あまり生きやすそうな世界とは思えない。
教育に関わる以上、「自分だったらどうしてほしいか」という考え方から時に脱却できる思考の余白を持ち、ある教育行為が教室全員、学年全員、教師をしている間に出会う全ての子どもたちに(副作用的なものも含めて)どのような影響を与えるかを視野に入れて教育方法の是非を問う姿勢が求められる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
