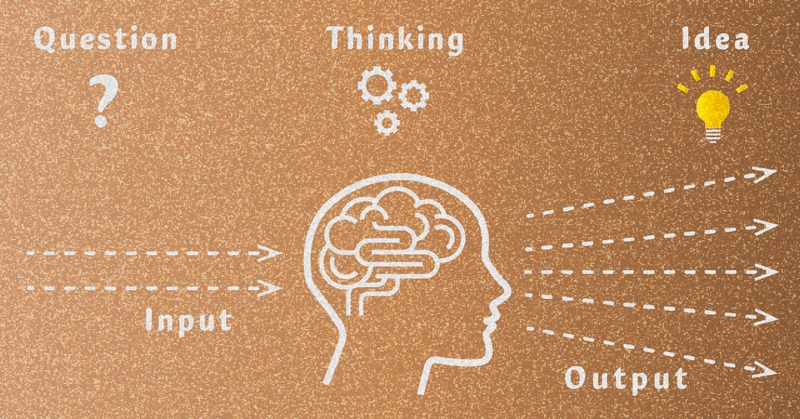
ラヴェッソンの『習慣論』をChatGPT(GPT4)に再度要約してもらってみた
Ⅰ
習慣とは、一般的かつ恒常的な存在の仕方であり、ある存在者の状態を示すものです。獲得された習慣は、変化の結果として生じますが、本著の主題は、その変化に関連して得られた習慣です。習慣は原因となる変化を超えて存続し、習慣である限り、可能的変化のために存在します。これにより、習慣は状態だけでなく、素質や能力ともなります。
変化は、時間の中で実現されますが、習慣を生むのは単なる変化ではなく、時間の中で実現される変化です。変化が長く続くほど、習慣はより強力になります。習慣は、変化の連続や反復によって生まれる素質です。
ただし、すべての変化が習慣を生むわけではありません。物体が場所を変えても、習慣が形成されるわけではありません。習慣が成立するためには、単なる可変性だけでは足りず、変化しない持続性が必要です。習慣は、内部で変化を生みながら自らは変化しないものの、内的な素質・潜在力・能力における変化を前提としています。
(Ⅰ)
存在の普遍的法則や根本的特質は、自らの存在の仕方を維持しようとする傾向です。存在が私たちに現れる条件は、空間と時間です。空間は安定性や恒常性の顕著で基本的な形式であり、時間は変化の普遍的条件です。したがって、最も一般的で単純な変化は空間自体に関する変化、すなわち運動です。運動する延長体は存在の最も基本的な形式であり、物体の一般的特質を構成します。
すべての存在者は、存在を固執する傾向があり、その運動を固執します。運動を固持するこの傾向が惰性です。惰性は恒久の素質に変じることができる限定された力ではなく、無際限に変動し、質量の無限の中に無限に広がる力です。しかし、習慣が実在的な存在者を構成するためには、実在的統一が必要です。
自然の第一の領域全体では、合一する要素が異なる方法で結合します。機械的合一、物理的合一、化学的合一として分類されます。これらの場合では、持続的な変化や恒常的な潜勢が存在せず、習慣を生み出すことはできません。
同質的全体は、その構成要素がどのように多様であっても、相互に相似的な部分に分けられます。不可分者に出会うことはありません。化学は原子を求めて得られません。同質性は個性や真の統一、真の存在者と相容れません。同質的総合の中には、分散する力の下で無限に分割できる多様な存在しかありません。そこでは、潜在的力が宿る習慣が実現され保存されるような限定された実体や個性的な活力は存在しません。したがって、無機界を形成するこの直接性と同質性の国では、習慣は存在できません。
(Ⅱ)
自然界において、変化が統合される過程が単純な結合から複雑な過程へと進化し、時間と空間の中で連続的で異質的なものとなります。この異質的な統合は有機組織であり、継続性を持つ統一は生命です。そして、継続性と異質性が個性を生み出します。生命は個性とともに始まり、独立した一つの世界を形成します。無機物は外部からの影響を受け、一般的な法則に従います。一方、生物は変化の中で独自の運命や本質を持ちます。この意味で、無機界は宿命の国、有機界は自然の国と考えられます。
生命は変化の連鎖や反復によって、存在者の質を変え、自然を変容させます。生命は無機的存在に優越していますが、無機的存在を条件として前提としています。有機組織は無機的世界から質料を持ち、それに形を与えます。生命は外部からの影響を受けつつも、自己の能力で変化を克服し、進化します。
生物は外部から受ける変化の連続と反復が破壊的でない限り、それから受ける影響は次第に減少し、自己発生的な変化が増加します。感受性が減少し、自発性が増加することが習慣の一般的法則です。習慣は自然を前提とし、自然の進化の方向に力を付与します。
有機組織が無機的存在からわずかに隔てられている限り、生命の原因が多様で分散され、生命の変化が少ない限り、存在者は必然性からほとんど解放されず、習慣が存在者に浸透することが困難です。植物的生命においては、習慣がほとんど発生しないが、変化が長期間続くと、永続的な痕跡が生じます。たとえ野生の植物でも、栽培によって変化することができます。
(Ⅲ)
植物は生命の高い形態ではあるが、それ以上に動物的生命が存在します。生命の段階が上がることは、より多様な変形、複雑な組織、高い異質性を意味します。動物的生命は、様々な要素を摂取し、適切な器官で処理し、運動が必要となります。また、動物的生命は外部から印象を受け取り、自ら適切な運動を決定する能力が必要です。
生命の段階が上がるにつれて、存在の関係が空間と時間で多様性が増し、限定されていくことがわかります。それぞれの存在は、物体、鉱物、植物的生命、動物的生命という4つの一般的特質を持っています。
物体は時間に関係なく存在し、植物的生命は連続的な持続がありますが、動物的生命は非連続の時間を含みます。動物的生命において自発性が現れるのは、機能の間欠性にあります。運動が一度止まった後、何の外的原因もなく再び始まることから、自ら運動を始める力があることがわかります。
動物的生命の初期段階から、変化の持続が二重の影響を及ぼし、明確に現れます。一方で受容性の低下が進み、他方で周期性が現れ、自発性が高まります。これらの現象は、動物的生命に固有の性質であり、習慣の形成に関連しています。
(Ⅳ)
生命が進化するにつれて、存在者は全体として空間を移動し、場所を変えるようになります。この段階では、受容性と自発性の対比がより強く示され、生命の世界では、外界の作用と生命自身の反作用が徐々に差異を生じ、独立して現れます。植物的生命では両者は似通っており密接につながっていますが、動物的生命では分離・区別され、空間的な活動が増えます。動物が全体として移動すると、受容性と自発性の対立は新たな特質を持ち、外的対象は新たな器官に印象を与えるようになります。これにより、習慣の二重の法則がより顕著に現れます。
印象は繰り返されることで弱まり、受容性の低下は超有機的な原因によるところが多くなると考えられます。一方で、運動は印象に対して独立し、有機体の物質的変化から遠ざかります。この過程で、受けた作用と反作用の間の関係を独立して統制する中心が必要となり、それは認識や評価、予見、決定する裁判官であり、精神と呼ばれる原理です。このようにして、自然の中に認識の領域や予見の領域が現れ、自由の微光が出現すると考えられます。
この段階ではまだ不明瞭で不確実な徴候ですが、生命は最後の一歩を踏み出します。運動力は、運動器官とともに最後の完成の段階に達し、かつて機械的世界から出てきた存在者が、最も自由な活動性を持つ形式で現れます。そして、その存在者は我々自身であり、意識が始まり、知性と意志が輝き出るのです。意識においては、はたらくものと見るものが同一であり、はたらきと見ることが合一しているため、意識の中でのみ、習慣の原理を理解し、生成を洞察することができるとされています。
Ⅱ
(Ⅰ)
意識は知識を包含し、知識は知性を包含する。知性は多様性の知性的統一であり、その統一を達成するために判断が必要で、それが悟性である。多様性は量の質料であり、統一は量の形式である。悟性は数の形式や連続量を把握でき、共存的な連続量は延長である。しかし、空間の無限の中には統一は存在せず、私たちは自分自身から統一を見つけ出し、外部に適用する。私たちが多様性を表象するのは、延長の中の区分の多数性であり、全体性を表象するためには部分を加えて一つにする必要がある。この加算は継起的であり、時間を含む。
時間においてはすべてが過ぎ去り、何も留まらない。連続性は悟性によって共存性の条件下で把握される。そして、運動は運動範囲や速度によって様々な量を持ち、その実在性の度は強度である。運動は抵抗に対する力の過剰から生じ、力と抵抗の比は努力の意識の中にある。
私たちが意志的活動の形式の下で人格性を表現するのは、努力の意識においてであり、努力は能動と受動の二つの要素を含む。能動は認識の客観と主観の区別の条件であり、受動は判明な認識と意識と両立しない。意識の範囲全体において、知覚と感覚はそれぞれ能動と受動と同じように方向相反し、反比例する。これは必然的な法則である。
努力は能動と受動、知覚と感覚が均衡を保つ場所であり、触覚において実現されます。触覚は受動の極から能動の極へ広がり、両極端の中間段階を包含します。触覚の器官が意志的運動から外れると、感覚が支配します。感覚は器官を快または苦の形式で支配し、主観は自己と感覚をほとんど区別しません。しかし、触覚の器官が意志に従うと、知覚が支配します。感覚は消え、すべてが知性と知識の対象となります。
一方で、抵抗が消えると、能動の原理を反省させるものがなくなります。純粋な受動では、主観は自己を他と区別せず、純粋な能動では、主観は自らを認識しなくなります。人格性は極端な主観性と客観性のどちらでも消滅し、触覚の中間領域で反省とともに最も明確な意識が見出されます。
感覚能力は触覚の発展に沿って同じ法則に従います。味覚や嗅覚は受動態で運動を含まず、聴覚や視覚は運動を含む機能を持ちます。聴覚は音を明確な知覚の対象とし、視覚は色彩を運動とともに現れる延長の形式で捉えます。知覚は感覚が衰えるにつれて力を増し、意識と知識は能動とともに発展します。しかし、絶対的能動性と絶対的受動性の極では、意識は存在しえず、知識は非人格性に没入します。
(Ⅱ)
意識の中にあるすべてのものは、運動という一般的条件の下に存在し、運動は時間の中で起こるため、意識の条件や存在も時間の中にあると言えます。時間は意識の第一の法則であり、その必然的な形式です。そのため、意識の中にあるすべてのものは、持続して変化するものであり、その変化は持続する主体において起こります。
感覚と能動性(運動においての能動性)は意識の領域全体において、互いに反方向に働き、反比例する関係にあります。感覚は長く続けたり繰り返したりすることで衰え、最終的には消えてしまいますが、運動は長く続けたり繰り返したりすることで次第に容易で速く確実になります。知覚も運動に結びついているため、同様に徐々に明瞭で確実で敏捷になります。
運動の意識の中には感受性の要素が存在し、それは努力です。努力は運動の連続や反復によって減少します。一方で、感覚の中には運動性や知覚が関与しており、連続や反復によって破壊されず、むしろ発展し完全になる要素があります。
能動性は感覚に働きかけることで、それを明確な知覚の対象に変え、感覚の中の認識や判断の要素を発展させます。その結果、快感を求めるだけの感覚は鈍くなりますが、知識を求める人の感覚は鋭く敏感になります。
感覚と共に、それに伴う快感や苦痛も徐々に弱くなります。しかし、能動性には快感が結びついており、持続することでその快感が増すのです。運動においても、努力が消えることで疲労や苦痛が消えます。
能動性はすべての場面で、持続によって受動性を弱め、能動性を高めます。この二つの相反する力の中には共通の特徴があり、それが他のすべてを説明するものです。感覚が長く続いたり繰り返されたりするにつれて、感覚が消えるにつれて、それは徐々に欲求に変わります。感覚を制限するために必要だった繰り返し与えられていた印象が、もはや与えられなくなると、不安や不快感が生じ、これが感受性の中に達成できない欲望があることを徐々に明らかにします。
このように、意識の中での変化と持続に関連する要素は、感覚や能動性の相互作用によって説明されます。能動性は持続することで感覚を変化させ、鈍くなる感覚を鋭く敏感にすることができます。また、能動性は感覚の中の認識や判断の要素を発展させ、人が知識を求めるようになります。全体として、持続は受動性を弱め、能動性を高める効果があり、この二つの相反する力の中に共通の特徴が存在し、他のすべてを説明するものとなります。
運動において、努力が消え、能動が自由かつ迅速になるにつれ、能動は傾向や傾性になり、意志の指図を待たずに行動するようになります。連続や反復により、感受性と能動性に一種の曖昧な能動性が生まれ、能動性では意志に、感受性では外的対象の印象に先んずるようになります。
受動の条件は、主体の現実の状態と、主体を導く原因の状態との間に存在する反対性です。感受性が同じ印象を繰り返し受けると、その印象に導かれた同じ状態を固執し、感覚は徐々に弱まります。繰り返される感覚は感受性を鈍らせ、眠りを引き起こします。
感受性の漸進的減衰は、内的能動性の漸進的発展によって説明されます。運動には受動が含まれ、能動は運動の原因にあり、受動は主体の中に存在します。運動が繰り返されることで、徐々に隠れた能動性が生じます。
感覚が消えることで感覚能力の中に欲望が生まれますが、これは真の能動性ではありません。能動性も受動性も同じくらい影響を受ける盲目的な傾向です。反復は感受性を弱め、能動性を強めるが、同じ原因によって行われる。その原因は、無反省な自発性が有機的組織の受動性に徐々に進入し定着することです。
感覚が徐々に減衰し、運動が容易になることは、おそらく器官の物質的構成に起こる変化によって説明されるでしょう。しかし、感覚の減衰や努力の低下に合致する傾向は説明できない。注意や意志や知性の発展によって説明することもできない。物理的理論も合理主義的理論も、この場合、誤りです。習慣の法則は、受動的で能動的であり、機械的宿命と反省的自由のどちらとも異なる自発性の発展によってしか説明されません。
(Ⅲ)
運動は意志と反省の範囲を離れるが、知性からは離れない。運動は外的衝撃の結果ではなく、意志に代わる傾性の結果であり、知性を含んでいる。習慣の発展により、傾性が意志に取って代わり、行動に近づく。運動の持続は潜勢力から傾向、そして行動へと変化し、目的と傾性が合一する。反省や意志の中で、運動の目的は理想であり、運動と傾向が合一することで実現される。習慣は実体的観念となり、直接的知性で主観と客観が合一し、存在と思惟が合一する実在的直観となる。
習慣が形成される過程で、人格性の領域を脱し、意志の中枢器官の範囲から運動の直接の器官へと移る。傾性と観念は器官の形式や存在そのものとなる。しかし、これは微小な段階を経て起こり、習慣的行動が中断されると緊張を失い、意志の領域に戻ることがある。意識は連続的な上昇と低下を通じて感じ、意志とともに消失・再生する。
習慣によって意志の支配を受ける運動は、知性の範囲を去らず、機械的な支配には陥らない。運動は知性的活動から離れず、同じ力が人格性を保ちながら、多様化し、傾向や動作、観念となる。習慣の必然性は外的強制的必然性ではなく、傾向と欲望の必然性であり、恩寵の法則である。目的原因が動力原因を支配し併合し、終わりと始め、事実と法則が必然性の中に合一する。
習慣と本能の違いは、習慣が行動の反復によって生まれる傾向であり、本能は生まれながらの傾向である点です。本能は習慣よりも無意識であり、抵抗できないほど強力ですが、習慣は本能に近づく努力を続けます。この違いは程度の差であり、無限に縮められると考えられます。
習慣は意志と自然の間に位置し、努力が能動と受動の間にあるように、習慣も動的で絶えず変化する境界です。習慣は自然と意志との間の関係を無限収束系列によって近づく方法として見られます。
習慣は意識を伴いつつ自然の奥底に入り込みます。これは獲得された自然であり、第一の自然を理解するための方法です。習慣は意志的運動を本能的運動に変える役割があります。
習慣が身につくことで、努力の意識は消えていきます。運動が自然になると、運動力の最初の行使が本能的に行われるようになります。しかし、努力と抵抗の循環から脱することは難しいです。
意志は客観の観念を前提とし、客観の観念も主観の観念を前提とします。努力には必然的に努力なき傾向が先立ち、運動の意志的部分の意識と意志の低下は運動全体の諸状態を表現します。
習慣の最後の段階は自然そのものに相当し、自然は欲望の自発性における実在性と観念性の直接的な合一です。習慣の発展に伴い、運動は多様な傾向と器官の中に分散し、人格性の中心的統一の下で力と知性が広がります。
運動的活動は意志から本能に至る能力を包含し、低次の能力は要約された形で含まれる。機能は運動から栄養、成長に至るまで様々であり、機械性は生命の力動性に譲る。習慣の力は混合的機能や植物的生命にも影響し、筋肉や関節を敏活にし、栄養供給を増加させる。習慣は衛生学、診断学、治療において重要な要素である。
習慣は有機組織の基本的な機能に影響し、観念と実在を同一化する秘儀を照らし出す。また、変態的寄生的運命や親から子への生命の相伝の神秘も明かされる。運動的活動は低次の形式を縮図の形で包含し、全世界の生命の発展を要約する。習慣は意識の内的生命の発展において自然の諸力の発展を描く。空間形式と継時的形式の区別は制限を含み、絶体的連続性は証明できない。しかし、習慣の実在的連続性は自然の観念的連続性の証明となる。
習慣の発展は人間の意識を意志から本能へと導き、人格から非人格へ分散させる。生命の機能や形式の原理は一つの力、一つの知性である。しかし、空間と運動、反省と記憶の条件が消えると、最も不随意な機能は本能に化された昔の習慣となる。習慣は意志的運動を本能に変え、意志と意識の低下は反省的悟性と意志の条件の消滅に起因する。これは生命機能の段階的系列においても同様である。
最も完全な有機組織は習慣の極点で実現される。習慣は生命の多様性や植物、結晶体の中にも思考や能動性が存在することを示す。存在の全系列は同一の原理に基づく力の連続的系列であり、これらは生命形式の階層で包み込まれ、習慣の進行において逆の方向に展開する。下限は必然性であり、自然の自発性の中の宿命である。上限は悟性の自由であり、習慣は反対者を接近させ、内面的本質と必然的結合を明らかにする。
(Ⅳ)
能動と受動は意志や知性にも関連し、習慣の力は精神や心情に影響を与える。習慣の法則や原理は一般性を持つ。精神が自己意識に到達すると、独自の生命や目的を持つ世界が開かれる。感情は善悪の感覚的表示であり、連続や反復は感情を弱めるが、道徳的活動性を強める。善を行う人の心情は、習慣が受動的感動を破壊することで成長する。愛は力を増し、情熱を絶えず新たに開く。精神の活動では、習慣が活動の意志を不随意な傾性に変え、徳が形成される。教育は善に向かう実行を促す。
精神の内部でも習慣の発展により活動が限界に達し、自然の非人格性が再び見出される。道徳的世界は自由であり、目的や行動は自由によって指導される。しかし、善に推し進めるものは意志や抽象的悟性ではなく、愛である。意志は行動の形式を作り、愛が行動の実体を作る。自然は欲望の中に含まれ、欲望は善に含まれる。これにより、「自然は先行する恩寵である」という言葉が確証される。自然は内なる神であり、隠された神である。
(Ⅴ)
最後に、純粋悟性や抽象理性の領域でも、習慣の法則と自然的自発性が見られる。悟性は感受性や受動性とは逆の方向で発展するが、受動性が全くないわけではない。悟性は運動の想像を含み、注意や意志が影響を受ける。連続や反復は、受動性と能動性に対して相反する影響を及ぼす。
長く続く知覚や表象は次第に消えるが、悟性や想像力を働かせることで綜合が容易になる。習慣の法則と原理が観念の連合を説明する。自然的自発性は知性の統一と個性を無限の多様性の中に散らす。
習慣により意志や運動も還元され、明確な意志や限定された運動についても、判明な思惟の条件と源泉を成す。反省的思惟は、不明な直観を前提にしている。意志が限界をとらえ形式を定めるのは、無意志的自発性の流れにおいてである。自然の必然性は縦糸であり、自由が横糸を通す。それは動く縦糸で、欲望や愛などの必然性である。
(Ⅵ)
要約すると、悟性と意志は限界と終わりに関係し、運動は間隔を測り、連続性は無限に分割可能である。この知性と意志は、無限に進むとは言えない。直接的知性と意志は、中間領域を包含し、観念が具体的思考と欲望、愛の形で現れる。自然は連続性と実在の充実を作り、意志は目的に向かい、技術は限界を支配する。知識は悟性の業で、自然が経験で事物の実体性を与える。自然と反省的自由の間には無限の段階があり、習慣はそれを降りて反対と運動の領域に存在する。習慣の歴史は自由と自然的自発性の相互作用を示す。習慣とその原理は、存在の基本法則と一般的形式に基づく。
解説
(Ⅰ)
ビランは、習慣論を提唱し、人間の精神が感受性と自発性、受動と能動の両面から力学的に構成されていると考えました。習慣は、感受性を弱める一方で、自発性を高める作用があると説明しました。しかし、ビランは習慣の原理を統一的に捉えることはできませんでした。ラヴェッソンは、習慣を統一的に把握し、アリストテレス・ライプニッツの存在論の地平に立ち、習慣を独特な潜勢と考えました。習慣は存在理解の方法となり、意識から自然への媒介者となるとされました。習慣の理解は唯物論や合理主義からはできず、アリストテレス主義が必要とされました。ラヴェッソンは、ライプニッツのモナドの内面的発展を基に、モナド相互の予定調和を具象的に捉える立場を取りました。後続の新唯心論の思想家には、ラシュリエ、エミル・ブートルー、ベルグソンがいます。
(Ⅱ)
本書の冒頭で示される習慣の定義はアリストテレスに由来し、「習慣とは一般的且つ恒常的な存在の仕方である」とされています。また、習慣は変化の結果として得られるものであり、この書は「エトスはあたかも自然の如し」という言葉をモットーとしています。習慣は恒常化と変化が組み合わさったもので、変化の反復や連続によって生じるとされています。
無機物には習慣は存在せず、生命の世界で習慣が成立します。そこで個性が現れ、内と外が分かれ、自発性と受容性の対立が生じることで、習慣の二重作用が明確になります。生命の第一段階は植物的生命で、習慣の作用はまだ小さいですが、植物を栽培して野性を矯正することができます。第二の段階は動物的生命で、植物的生命が基盤となり、感覚・運動機能が成立します。動物的生命では習慣の影響が顕著で、受容的感覚が次第に弱まり、印象に応じた運動が増大することで習慣が作用と反作用の隔たりを大きくする。そして、相反する両方向を統一する中心が現れ、それが精神であり、意識的生命が成立するのです。
(Ⅲ)
意識の分析では、知性の機能は多様性の統一であり、空間の諸部分を時間的に統合することです。綜合は自我の運動によって起こり、運動は方向の意志を予想するため、知性の合には意志が含まれています。運動の質性は力であり、力が抵抗に打って実現するものと解されます。この力と抵抗との比の意識こそ努力であり、意識の人格的意志的な面です。ラヴェッソンはカントの認識論を意志的方向に推進し、メーヌ・ド・ビランの「努力」に導きました。
意識は能動と受動の均衡の場所であり、意識のすべての段階で能動と受動が絡み合っています。これが意識の法則です。触覚を始めとする感覚は、受動的な面と能動的な面があり、両者のバランスが意識を構成します。味覚・嗅覚・聴覚・視覚の四つの感覚能力も、このバランスによって成り立っています。
習慣の影響は、能動を強め受動を弱める働きがあります。習慣の根底にある原理は、「一種の不明瞭な能動性」であり、観念が存在に化した実体的観念と言えます。習慣は、能動を強める反省的意志を自動化し、受動化する一方で、隠れた自発性・能動性を育てます。習慣の根底には、「同時に受動的で能動的な自発性」があると言えるでしょう。
(Ⅳ)
習慣は第二の自然であり、第一の自然の秘密を理解する鍵です。まず、人間の生命全体を統一的に理解できます。意志は行動の形式と終局点を意識しますが、力の発動や身体の動かし方は理解できません。しかし、習慣を通じて観念と実現の合一が見られます。これにより、自然における観念と存在の合一が理解でき、力の発動や本能も習慣を通じて近づくことができます。また、病気の原因や生命の継承の秘密も自然の働きとして理解されます。人間の生命は一つの精神によって浸透されていると言えます。
第二に、外界の空間的形式で並存する諸々の生命段階も、意識内の習慣の時間的発展から類推できます。動物、植物、さらに結晶の中にも思考の光が分散していくことが認識できます。また、「自然の連続性」も習慣の実在的連続性に基づいて証明されるべきです。
このように、「存在の全系列は同一の原理から成る連続的系列であり、これら諸力が生命形式の階層においては互いに包み込まれていき、習慣の進行においては逆の方向に展開される」。下限は必然性、自然であり、上限は自由である
(Ⅴ)
最後に、意志と知性における習慣を考えます。意志の受動性は感情であり、能動性は善悪を追求する道徳的活動です。習慣は受動的な感情を弱め、仁愛の活動を強めます。愛は自己を示すことによって力を増し、活動は傾性に変わり、習俗や道徳を形成します。これらの習慣の根底は自然であり、自然が恩寵と一体であることを示しています。
知性においても、悟性や想像が綜合の活動を繰り返すことで、活動はより迅速かつ正確になります。同時に、これらの活動は自動的になり、「観念の連合」を形成します。習慣が観念の連合を説明し、その逆ではありません。
反省的な意志や知性の根底には、習慣が示すような直接的な意志や知性が存在します。前者は目的や限界に関係し、手段と中間の連関を理解できません。後者がそれを実現し、反省的能力の基盤と源泉となります。
この書は有名な比喩で終わります。存在の様々な段階は、自然から自由へと螺旋状に形成されており、「習慣はこの螺旋を再び降りて、その生と起源を我々に教える」のです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
