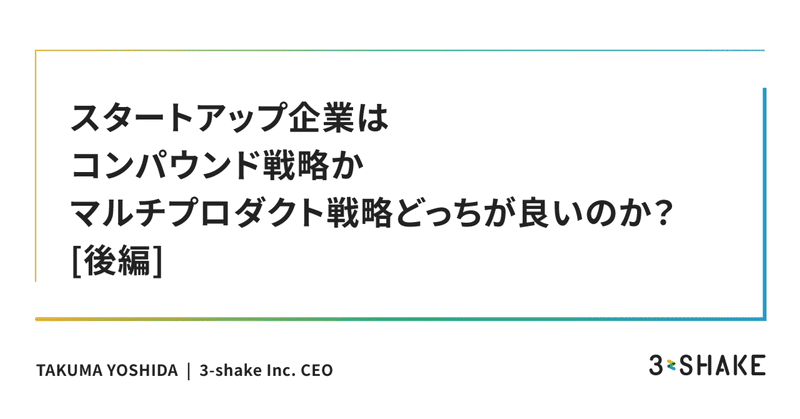
スタートアップ企業はコンパウンド戦略かマルチプロダクト戦略どっちが良いのか?[後編]
はじめに
スリーシェイクの吉田です。
前回はコンパウンド戦略とマルチプロダクト戦略の概要について解説しました。
後編では、スリーシェイクがマルチプロダクト戦略を選択した理由と推進する上でのポイントを解説します
スリーシェイクはなぜマルチプロダクト戦略なのか?
そもそもシングルプロダクト戦略ではだめなのか?
前提としてシングルプロダクト戦略は経営戦略として秀逸だと思います。1つのプロダクトに集中することは、ヒト・モノ・カネが限られたスタートアップにおいてとても有効な戦略です。叶えていきたいVision/Missionに対して1プロダクトで解決できるのであれば、まずはこの戦略を検討するのがベターでしょう。
一方で、スリーシェイクのVisionは「インフラの世界でイノベーションを起こし、社会になくてはならない存在になっていく」、Missionは「労苦〈Toil〉を無くすサービスを適正な価格で提供し続ける」というゴールを掲げています。インフラというレイヤーや労苦(手作業であり、長期的な価値を持たない業務)をなくしていくには、ワンソリューションで解決していくことは厳しいです。
そういう意味で、DevOps/クラウド導入支援からスタートしたスリーシェイクですが、創業時からシングルプロダクト戦略を採用する予定はありませんでした。
インフラレイヤーでのコンパウンド戦略はめちゃくちゃ難しい
マルチプロダクトを選択した理由の一つに、インフラレイヤーならではの事情があります。
インフラのレイヤーでは、例えばSnowflakeやDatabricksといった名だたるグローバルプロダクトがいます。どのプロダクトを見ても、投資してからユーザー数が拡大するまで、10年、20年といった長い年月がかかっているのが実態です。
話は逸れますが、最近だとCI/CDツールのHarnessは個人的に結構注目しています。
2017年創業で$427M資金調達(シリーズD)して、GitOpsに始まり、セキュリティ診断や開発プロセス管理などDevOpsにまつわる総合的なソリューションを一気に取り揃えようとしています。(Sreakeの一部プロジェクトで使っており、プロダクトの作り込みを見た感じ流石だなと思いました)このレベルを目指すと10年かかって、1000億円ぐらい投資が必要かと思われます。
日本において、インフラレイヤーの投資回収リスクやマーケット拡大を判断できる方(例: ベンチャーキャピタルや金融機関)は殆どいらっしゃらないです。これは良い悪いではなく、事実として向き合う必要がありました。
その中で同時多発的にプロダクトを出すコンパウンド戦略は、集める資金も莫大になり、創業当時は選択できませんでした。
マルチプロダクト戦略をやる上でのポイント
プロダクトに明確な課題設定とやりきれる想いがあるのか
それぞれサービスの内容は異なりますが、共通して守っているポイントが2つあります。
①自分自身の経験がある領域であること
②限られたエンジニアリングリソースが世の中で最大化されるためのサービスあること
Securifyも、Reckonerも、Relanceも、すべてSREの事業をやりながら、そこで実際出てきたお客様の困りごとから派生して生まれたサービスです。
またどの事業も、「エンジニアの世界がもっと変わってほしい」という想いで立ち上げています。スキルアップしろとか生成AIで自動化しようとか、そういうことじゃない。今あるリソースや今ある皆さんのスキルセットでも、ものすごく社会を変えるパワーはあると思っていて。そのための仕掛けをしていくのが、私たちが目指している、提供している価値になっています。
このように自分自身の目で見た、手で触れた、五感で感じた明確な課題設定と、その課題を解決した先に叶えたい世界観に対してのモチベーションがマルチプロダクト戦略では大事かなと思います。
PL/BSのバランスがとれているか
新規事業が収益化する見通しを立てることは非常に難しいことです。ほぼ博打といっていいでしょう。主力プロダクトが収益化したあとに、どのタイミングでどれぐらい新規事業に投資するかは、どこで撤退ラインを設けるか、マルチプロダクトを進める上で悩むポイントです。
その点で、まずは主力プロダクトの収益で給与と間接費(バックオフィスや固定費)を賄える段階までは、マルチプロダクトを進めるのはリスクが大きいと考えます。仮に新規事業を完全撤退しても、キャッシュポジションを高く維持でき、次の挑戦がしやすくなるからです。
次にどれだけキャッシュポジションが高くとも、減損処理から起因する債務超過は気にするべき部分かなと思います。いざ事業撤退する際に、長年ソフトウェア開発などで積み上げた資産の減損処理で債務超過になるとその後の主力プロダクトの運営に大きく影響がでてしまうからです。
このあたりのリスクに対してのバランスを見ながら、複数事業を立ち上げていくと良いのかなと思います。一方で、立ち上げた事業に見通しがあれば、上記リスクを含んだ上で突き進んでいくのも良いと思います。
おわりに
「私たちは本当にインフラレイヤーをシンプルにしているか」という問いに対しては、まだまだ実現できていないと私は思っています。
より参入障壁が高いプロダクトやサービスに長い時間をかけてコミットして、エンジニアリングのトイル(労苦)が無くなるようなサービスを提供し続けていきたいと考えています。
スリーシェイクのこれからにご興味をお持ちいただいた方、想いに共感してくださった方がいましたら、私やスリーシェイクのメンバーにお気軽にお声がけください!
