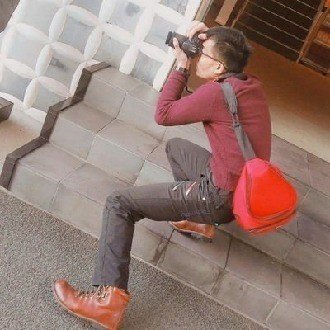地域創生・地域ブランディング界隈のニュースや事例分析の他、マーケティングやデザインなど地域活性化やまちづくりに役立つnoteをまとめております。
- 運営しているクリエイター
2018年4月の記事一覧

#2 うなぎの寝床という、九州ちくごのものづくりを発信するローカル拠点型アンテナショップを立ち上げた理由と背景、そして、地域のものづくりにおける役割とは?
うなぎの寝床は、九州ちくごのものづくりを伝えるアンテナショップとしてスタートしました。行政ではなく完全民間による運営です。アンテナショップというと、東京に地方の行政が出展するという形態が主流ですが、僕らは作り手がたくさんいる地域に、その地域の物がみれる場所をつくるというローカル拠点型アンテナショップを2012年7月にオープンしました。それは、あまりにも地域で、地域のものづくりが知られていなかったり、素晴らしい資源や人がいるのに、伝わっていなかったりする現実がそこにあったか