
アンラーン💣リラーン📚ためらわん♫run82…⭐事実に埋没することなく、俯瞰して比べられることが素敵なお話の源泉発見につながる⭐️
(これまでの虚栄を解きほぐす「unlearn」のため、頭の中を刷新する「relearn」を躊躇なく進めるための記録)
【記事累積:2055本目、連続投稿:988日目】
<探究対象…コラム、俯瞰、客観、比較、分析、ブレヒト>
毎週実施している特別授業の3回目は「ラオス」でした。ラオスはシンガポールの6年間住んでいた状態に比べると2年間だけなので、あまりネタがないかなと思っていましたが、いざスライド作成をしてみると、知らせたいことだらけで1コマ50分の授業内に収まらないくらいのスライド数になってしまいました。
しかし次の授業もあるので泣く泣くスライドを割愛し、特に知ってほしいことを優先してお話したのでした。実は第1回シンガポール、第2回インド、第3回ラオスを実施してみて、スライドのボリュームが意外にも少なかったのは、一番長く住んでいたシンガポールだったのです。
これはシンガポールが初回でどんな方向性で授業展開するか手探りだったということも関係しているかもしれません。しかし、そのことを抜きにしてもラオスのボリュームが圧倒的でした。
確かにラオスに住んでいた期間は2年間ではあるものの、第1期(2019年度)の1年間と第2期(2023年度)の1年間という形で、住んだそれぞれの期間の途中に3年間という時間の隔たりがあることが影響している気がします。
シンガポールは第1期として4年間住んだ後、1年間の沖縄暮らしを挟んですぐに第2期の2年間の生活がスタートしたため、6年間はほとんど連続したものだったのです。これに対してラオスは3年間の隔たりの中で、第2期の生活というものが、第1期の生活と並べるようにしながら俯瞰というか客観的というか、とにかくそんな位置づけになっていた気がするのです。
それによって単なる連続する事実としての海外生活ではなく、比較したり分析したりするみたいな意識で捉えることができていたのだと思います。
「観察するには比較することを学ばねばならぬ。比較するには観察しておかねばならぬ。観察によって知識はつくられる。だが観察するには知識がいる。」
これはドイツの詩人であるベルトルト・ブレヒトの言葉とされています。
私が第3回でラオスを扱ったとき、たくさんの知らせたい情報をスライドにすることができたのは、それが単なる事実ではなく或る捉え方によって論点化できるものが蓄積されていたからだと思います。それはブレヒトの言葉でいう「観察によってつくられる知識」なのかもしれません。しかし彼は同時に観察には知識が必要といっているので、やみくもに観察すればよいわけではなく、何らかの意図・狙いをもって観察する必要があると思います。そして、その何らかの意図・狙いがブレヒトの言葉でいう「観察に必要な知識」だと思います。
ただその何らかの意図・狙いはどのように獲得できたのかというと、私の場合、ラオス第1期の経験によるところが大きいと思います。つまりラオス第1期の経験が、観察に必要な知識としての意図・狙いにつながり、それに基づいて、ラオス第1期と第2期を「比較」することで、「単に事実を眺めるようなレベルの観察」で終わることなく、「分析的に考えられるレベルの観察」となり、そこで得られたものが「観察によってつくられる論点を含んだ知識」だったと感じています。
ただ長く住んでいれば良いわけでなく、そこでの生活とどのように繋がり、どのように向き合い、どのように見つめるかが大切だと改めて思いました。
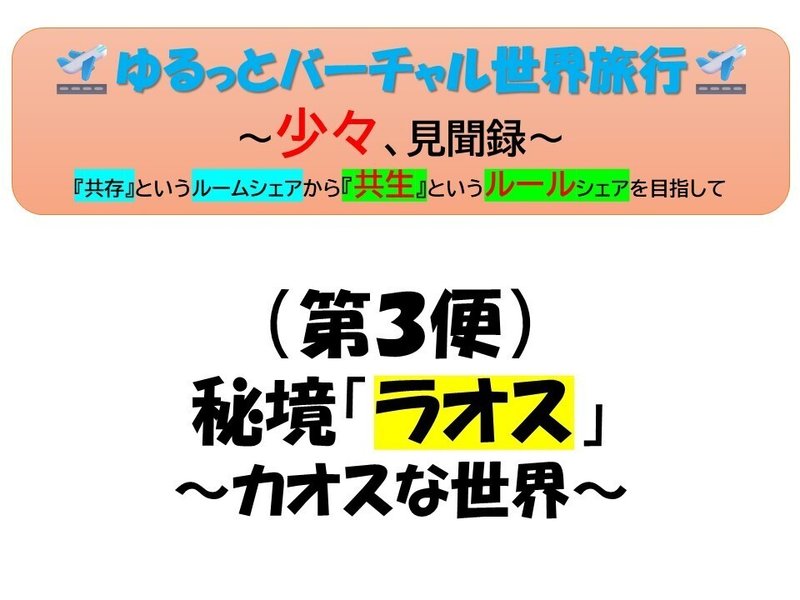


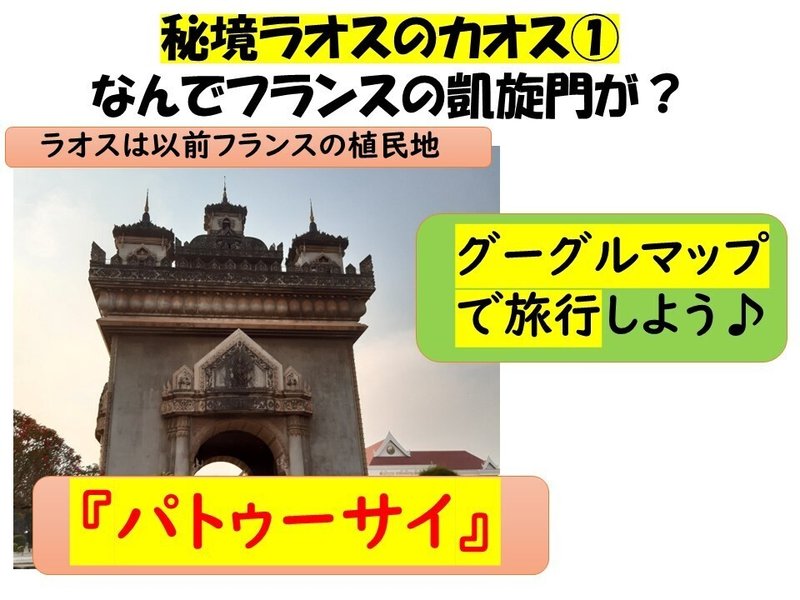


















この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
