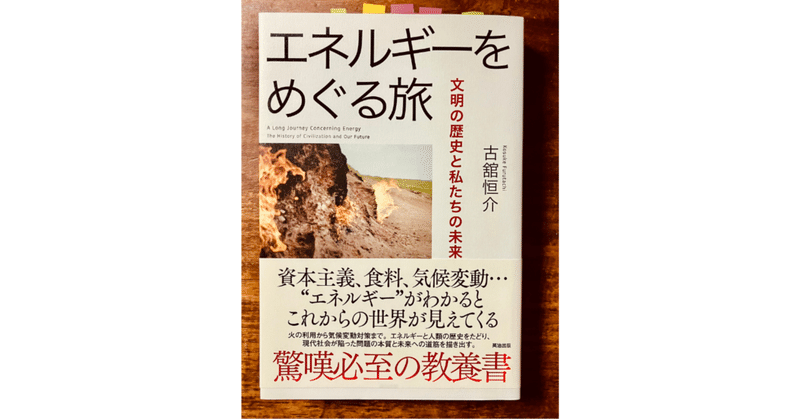
読書アウトプット#6「エネルギーをめぐる旅」(古舘恒介)
まえがき
みなさん、こんにちは!
最近、この読者アウトプットを書くのが驚くほど早くなりました。その秘密は「Claude」という生成AI。このClaudeが素晴らしいのは、Chat-gptよりも入力できる文字数が多く、精度も高い点。あくまで私の肌感ですが。おかげで、アウトプットのスピードが爆速になりました!
でも、この読者アウトプットを振り返る時間を確保するのは、なかなか大変なんです。そんな中、私はある方法を試してみようと思っているんです!
それは、Claudeに書いてもらった文章を音声合成サービスで音声に変換することなんです。こうすれば、家事をしながらや移動中に、耳から知識を入れることができるんじゃないかなと。まだ実践していないんですが、これからチャレンジしてみるつもりです。
うまくいけば、このやり方をnoteにまとめますので、お楽しみに。
紹介したい本
きっかけ
荒木博之さんのフックカフェで絶賛され、エネルギーを軸に歴史を振り返る視点に興味を持ったことが購入のきっかけでした。
学びのポイント3つ
散逸構造が織りなす生命と経済の秩序
地球上の生命と資本主義経済は、太陽エネルギーで維持される散逸構造である。生命は太陽エネルギーを利用して秩序を維持し、資本主義経済は経済成長を続けることで構造を維持している。散逸構造の視点から、エネルギー問題を通して生命と経済の本質を理解する視点を提供する時間短縮が導く文明の発展と課題
人類は火の獲得で発達した脳により時間の概念を生み出し、時間を早回しにすることで文明を発展させてきた。しかし、肥大化した脳と身体のバランスが現代社会の課題となっている。時間短縮の視点から、エネルギー問題を通して人類の進化と文明の発展、そしてその課題を抽出する人類とイネ科植物の共進化
人類によって選ばれたイネ科の穀物は、人類との共生の中で進化を遂げた。人類が競争相手を取り除くことで、イネ科植物は背丈を伸ばすことに使っていたエネルギーを、種子を増やすことに振り向けるようになった。これは、人類から安定的な生育環境を得る代わりに、種子の増産で人類に恩返しをするという、相利共生の関係が築かれたことを意味する。この進化の結果、イネ科植物は人類の主要な食料となり、人類の発展を支えてきた
感想
『エネルギーをめぐる旅』は、ここ数年で私が一番最も学びになった本です。エネルギーという視点から人類の歴史を見るというユニークな構成が、秀逸なんです。太陽エネルギーから始まって、生命の進化、文明の発展、経済のしくみなどが、散逸構造っていう考え方でうまくつながっているんですよ。絶妙なバランスで人類は存在しているんです。ありがたい。
特に印象に残ったのは、人間が火を手に入れたことで発達した脳で時間の概念を生み出し、時間を短くすることで文明を発展させてきたっていう指摘。時間短縮はこれからも続くでしょうけど、それは人間の際限ない欲求だから。それを抑えるには脳に直接アプローチしないといけないのかも。でも一方で、でかくなりすぎた脳と体のバランスが今の社会の問題になってるって話も興味深かったです。時間をゆっくりさせるためにヨガに取り組むのは理にかなった行動ですね。
あと、この本を読んでいくうちに、改めて太陽ってスゴイなって実感しました。地球上の生命も文明も経済活動も、ぜーんぶ太陽エネルギーに支えられてるんですよね。私たちは、この恩恵に感謝しながら、地球に優しい方法でエネルギーを使っていかないという気持ちになりました。
さらにこの本の著者がサラリーマンという点にビックリ。知りたいという気持ちと探究心があれば、こんなに凄い書籍を出版できるんだって勇気づけられました。
この本は、エネルギー問題を生命、文明、経済、社会の色んな面から捉え、全体的に理解するのにぜひ読んでほしい一冊です。私たちが向き合うエネルギーの課題について、歴史的な流れから考えるためのヒントがいっぱい詰まってます。
マジでオススメです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
