
2倍以上の組織拡大に耐え得るために......!リーダー・マネージャー育成プロジェクト、プルス・ウルトラ計画の内容を大公開!
今回は、社内でのスキルアップ勉強会である、プルス・ウルトラ計画(略してPU計画)について紹介します!
PLEXでは、週次の1on1を必ず実行しており、社内でのナレッジシェア・フィードバック体制の構築にはかなり力を入れております。さらに、この3ヶ月、業務時間外にプルス・ウルトラ計画という勉強会を行っておりました。
では、プルス・ウルトラ計画とは何か。ざっくり言うと、「リーダー、マネージャー候補の育成」というのが勉強会の目的です!
この記事では、そもそもどういう背景でこの勉強会を行っていたのか、何を行っていたのか、結果どうだったのか、ということをご紹介していきます。
何を行っていたのか、という点は、実際のコンテンツまでかなり詳しく説明するので、読んでいただいた方のインプットとしても活きれば幸いです。
現状の倍以上の組織拡大にあたって、リーダー/マネージャー層の創出が急務だった
まず、プルス・ウルトラ計画の背景をお話します。
PLEXの事業と組織拡大目標
PLEXにおいては、人材紹介事業がメイン事業であり、求職者様と企業様のマッチングをする"キャリアパートナー"(一般的に、キャリアアドバイザーやキャリアコンサルタント、CA/RAと呼ばれる職種)が組織の主体となっております。

キャリアパートナーは、現在10数人の組織規模なのですが、今期(2021年4月~2022年3月)で、人数を倍以上にするというアグレッシブな計画を掲げています。
社内からのリーダー/マネージャーの創出を目指した
そして、人数が増えれば、コミュニケーションのハブとなる、リーダーやマネージャー層が必要になってきます。
ところが、過去様々な組織検証(誰にどういった役割を担ってもらうか)を行っていましたが、明らかに今後必要なリーダー・マネージャー数に対して、担えるメンバーが不足しているという認識をしておりました。
ではリーダー・マネージャー層を制限要因として組織拡大目標を立て直すかというと、そんなことはありません。
組織を拡大すればその分売上・利益が増えることは見えていたので、なんとかリーダー・マネージャーを創出し、拡大に耐えうる組織を作りたいと考えました。
そして、内部から育成するか、外部から採用するか、が選択肢となりますが、社内からの信頼を得やすいという意味では、すでにある程度の業務経験のある既存メンバーから何とか育成したい、という思いがありました。
また、既存メンバーも、自らの役割を拡張して、マネジメントにチャレンジしてみたい、事業を作っていきたい、という意欲的なメンバーが複数いました。
個人的には、既存の能力はどうであれ、その人の成長幅・ポテンシャルを決めるのは、その人が何を目指しているか、というところに尽きると思っています。ですので、意欲的なメンバーがおり、事業的にも育成が必要なのであれば、しっかり時間をとって、あるべきとのギャップを埋めるための活動を行っていくべきと結論付けました。それがプルス・ウルトラ計画なのです!

リーダーを任せられるか?という質問にみながYESと答えられる状態を目指す
上記の背景から始まったため、プルス・ウルトラ計画では、参加メンバーがリーダーになれる状態を目指すことにしました。
もちろん細かい要件はあるのですが、最終的には、プルス・ウルトラ計画終了時に、
"事業責任者や、現マネージャーに「◯◯さんにリーダーを任せられるか?」という質問をしたときに、「Yes」という答えが返ってくること"
を目標にしました。
というのも、必要な要件はある程度言語化できるのですが、やはり抽象的にはなってしまうため、「他社からの評価」という結果を求めることにしたのです。「仕事に関する9つの嘘」(サンマーク出版, 2020)にも、抽象的な能力の評価は難しいが、他社からの評価はファクトである、といった趣旨のことが書いてあります。
とはいえ、事業部としてリーダーの要件は言語化してあり、下記が要件となっております。
- 成果:高い売上を出しているか(具体的基準はありますがここでは伏せます)
- 言語化:コミュニケーションのハブとして、複雑な状況を整理し、わかりやすく伝えることができるか
- 信頼:「この人のもとで働きたい」と思ってもらえるような信頼、「この人に任せれば安心だ」という信頼を社内で得られているか
- 戦略理解:会社、事業、ファンクションの上位戦略を理解し、メンバーに伝えられるか
- スタンス:組織・会社への貢献意識があるか、高い熱量を持って仕事をしているか
この能力の中で、下記を満たすものを勉強会の射程としました。
1. メンバーに現状足りていない
2. 各人課題が共通しており勉強会の形でキャッチアップできる
3. 通常の業務の一環では、キャッチアップしにくい

つまり、リーダーになるにあたって必要なことすべてではなく、一部、各人に共通して課題となっているところをキャッチアップしよう、といのがプルス・ウルトラ計画の射程になりました。
では、具体的にそれは何なのか。
今回の要件でいうと、下記3つになります。
- 言語化
- 戦略理解
- スタンス
逆に言えば、成果は通常の業務改善で取り組めることであったり、信頼は個々人の問題であったりするため、直接的な対象にしなかったのです。
上記3つが「通常の業務の一環では、キャッチアップしにくい」という条件を満たす理由について補足すると、日々の業務では、コミュニケーション力(営業力)や時間配分、量をこなすキャパシティが大事になってくるため、いわゆる論理的思考や言語化を行わなくても、問題なく業務遂行できるからです。
プルス・ウルトラ計画では、少しいい方を変えて、下記の3つのキャッチアップを目指しました。
- 問題解決力
- ドキュメントコミュニケーション力
- スタンス・マインドセット
そして、リーダー/マネージャーへの意欲があり、上記スキルが課題になっていそう4人のメンバーに声をかけ、プルス・ウルトラ計画が始動しました。
声をかける段階では、本人のコミットメントを大事にしたかったため、趣旨の説明と、「通常業務にプラスしてインテンシブに行うため、かなり大変な期間になると思う。一度話を聞いた上で持ち帰って、自分の時間配分としてやりきれるか考えてほしい。」と伝えました。結果4人とも、勉強会に参加することになりました。
ちなみに、「なんでプルス・ウルトラ計画って名前なの?もしかして......」とずっと疑問に思いながら読んでいた方もいらっしゃるかと思いますが、「僕のヒーローアカデミア」の主人公が通う学校の標語から取りました。「さらに向こうへ」という意味で、キャリアパートナー業務で成果を出すために直接的に必要な能力から、さらにプラスして、リーダー・マネージャーになるために必要な能力をキャッチアップしよう、という意味合いが込められています。
(ちなみに命名当時に、ヒロアカ読んでいて、ノリでつけました。)

画像出典: https://twitter.com/heroaca_anime/status/971690417002487808
インプットとアウトプットの両軸を回していく
改めて整理すると、プルス・ウルトラ計画の概要は下記になります。
- 目的:リーダーになるにあたって必要な能力のキャッチアップ
- 期間:3ヶ月
- 参加人数:4人
- 内容:本によるインプットで基本を学び、実際に業務に活かすことで、考え方を身体に染み込ませる
問題解決力、ドキュメントコミュニケーション力、スタンス/マインドセットをキャッチアップしていくにあたって、基本方針は下記としました。
1. インプット|本を読んで内容を理解し、実際の業務に学んだことを活かすにはどうするかを考える
2. アウトプット|実際に自分が考えている個人施策やチーム施策に、学んだ内容を活かし、設計・実行まで行う
その方針のもと、基本的には毎週水曜の20:00~21:30に集まり、勉強会を行っていきました。
インプットパート
問題解決やドキュメントコミュニケーションという点では、素晴らしい本が多数存在するため、先人の知恵をお借りし、まず本を読んでその内容をものにしよう、というのがインプットパートの趣旨です。
下記のようなスケジュールで、本を読んでいきました。


サラリーマン・サバイバル、成長マインドセットだけ少し毛色が違い、スタンス/マインドセットのインプットを目的としておりますが、それ以外は問題解決、ドキュメント・コミュニケーションのインプットを目的としています。
コンテンツとしては、事前課題として、本を読んだ上で下記をまとめてきてもらい、それを踏まえて理解の確認、業務に活かせそうなことの議論を行いました。
- 本の主張
- 感想
- 業務に活かせそうなこと
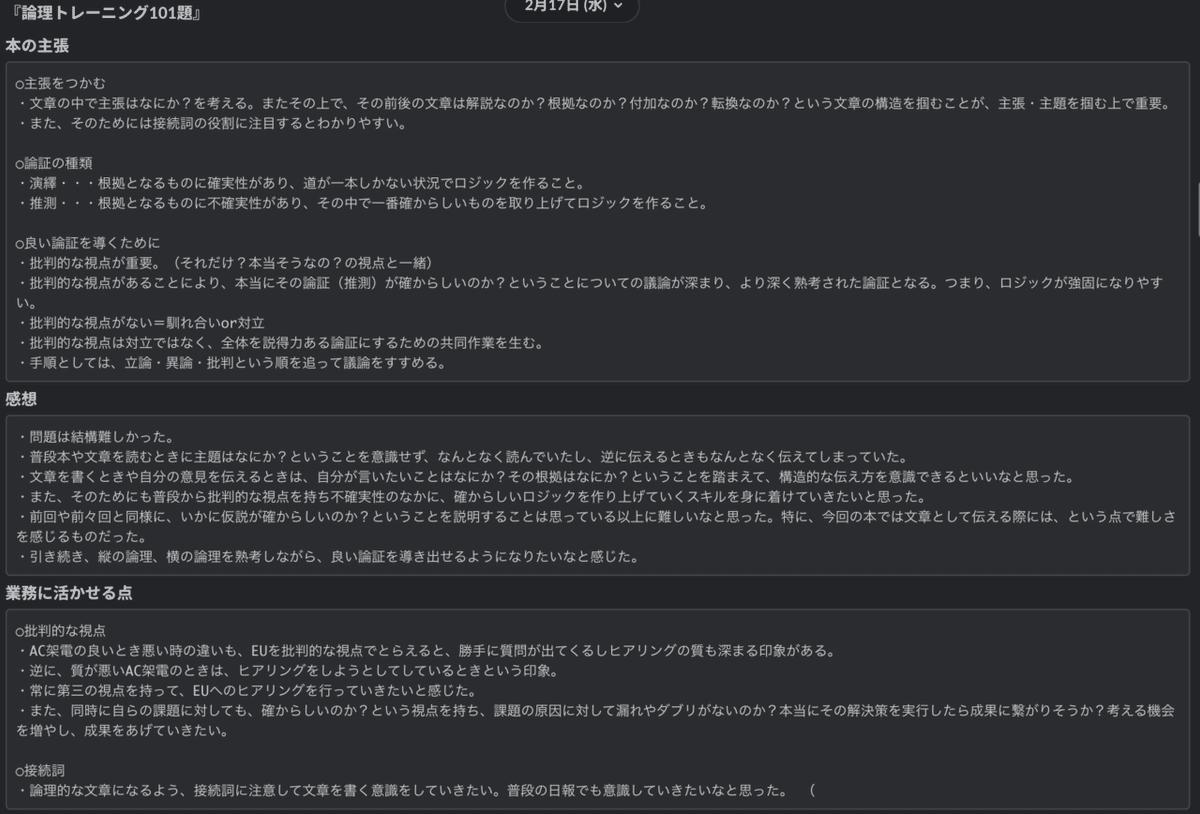
↑実際に、事前課題としてまとめてもらったもの
週に1冊のペースで、課題を出していたので、ペース的には割と大変だったと思います。
コミットが低い人がいては周りにも悪影響があるので、課題3回間に合わなければ、参加を辞めてもらうことにしていましたが、結果的に全員しっかりこなしていました。
では、なぜその本を選定したのかということと、その内容を紹介していきます!
『原因を推論する』

画像出典:https://www.amazon.co.jp/
PLEXでは、「検証する」ことを大事にしています。PLEXの由来も、Play & Experiment であり、不確実な環境だからこそ、楽しみながら検証して、得たインプットをもとに課題を解決していく、といった考えが浸透しています。
では、「検証する」とはどういうことか、何がどうなれば「検証できた」と言えるのか、といったことについて理解してもらうために、この本を題材にしました。
この本は、ひとことでいえば、「因果関係があるとはどういうことか」を解説しています。政治学者が書いた本であり、具体例も政治学のケースが多いですが、検証する、実験する、因果関係を推論する、といったことについて汎用的に書かれています。
AがBの原因であり、因果関係がある、とは、下記の3つの条件を満たすこと、と紹介しています。
1. 時間的先行:AがBより先に起こっていること
2. 相関関係:AとBが同時に動いていること
3. 他要因の統制:Bに影響を及ぼしそうなA以外の要因がすべて統制されていること(同じであること)
1と2は当たり前ですが、3は少々わかりにくいかもしれません。
たとえば、「小学3年生の子どもが毎日、木の棒を触っていたら、身長が1年で10cm伸びた」といわれたときに、「木の棒を触ったから身長が伸びた」と思う人はいないはずです。これは明らかに木の棒を触る、ということ以外の別の要因(食事、単に時間が過ぎたこと)が影響しています。つまり、木の棒を触る以外にも、結果に影響を与える他の要因も変化していた、ということで、因果関係の条件の3が満たされていないのです。
結果に影響を及ぼしそうな他の要因はないか、という視点は抜けがちなので、とても重要です。
それ以外にも、統計的有意性、サンプル数が少ない事例研究においての因果関係の推定方法等、ビジネスにも活きる話が紹介されています。
ビジネスにおいては、曖昧な中でも意思決定をしていかなくてはならないので、厳密な因果関係を検証することはできないし、ファクトが揃うのを待てない場面もありますが、それでも厳密に考えればどうなのかを理解しておき、できるだけ厳密であろうとする態度は大事だと思っています。
チームの施策を考える上でも、客観性がメンバーの納得につながるので、少し内容は難しいですが、まず最初に読んでもらいました。
勉強会では、実際に人材紹介業務においてある検証をしたいときに何がわかればいいのか、何に気をつけるべきか、各人具体例を出しながら議論しました。

勉強会の風景
『ロジカル・プレゼンテーション』

画像出典:https://www.amazon.co.jp/
有名な本なので簡単な紹介にとどめます。
主に、論理的であるとはどういうことか、どう伝えればいいか、といったことについて書かれています。
話を聞いたときに相手が感じる疑問は「本当にそうなの?」「それだけなの?」の2種類しかなく、その疑問を抱かせないように、縦の論理と横の論理を展開するのが大事、と紹介されています。
いわゆる論理的思考の基本が書かれており、施策を考えたり、上位戦略を咀嚼したり、考えをチーム/マネージャーに伝えたりするときに活きる基本動作として、読んでもらいました。
また、勉強会で話題になったフレーズとして、「考える労力をこちらで受け持つ」というのがありました。相手に判断を委ねず、相談するにしても、自ら考え抜いて相談することですが、あまり意識できていないメンバーが多く、はっとさせられたそうです。
実際にslackで、「相談」というキーワードで調べてみると、状況整理、今後の対応の仮説が全くなく、単に「相談したいです」とだけチャットしている履歴が数多見つかりました。自分なりに整理して、オプションの提示にとどまらず、こうしようと思っている、というところまで考えよう、というフィードバックをしました。
『論理トレーニング101題』

画像出典:https://www.amazon.co.jp/
タイトルの通り、問題形式になっている本で、「空欄に当てはまる接続詞はなにか」や、「この文章を構造化して図にせよ」といった問題が101題掲載されています。
接続詞の問題は、簡単そうに見えて意外と難しく、みな苦戦したようでした。
メールや社内ドキュメントの作成、またその読解において、文章同士のつながりを意識し、構造化して捉える、という訓練として読んでもらいました。
勉強会では、トラブル案件の対応など、重めなメールの履歴を見ながら、構造化やもっとよくできるポイントを議論しました。
『サラリーマン・サバイバル』

画像出典:https://www.amazon.co.jp/
大前研一氏が「知的ホワイトカラー」として仕事に望むスタンスを説いた本です。
論理的思考などの技術的なところから離れて、マインドセット・スタンスをアップデートするために題材にしました。「今日の仕事は明日に残さない」「知りたいと思ったことは調べ、経験したいと思ったことは経験し、行ってみたいと思ったところには行かなければならない」「面白い仕事、面白くない仕事というのは存在しない。面白い仕事のやり方、面白くなり仕事のやり方があるだけ」「解決案を常に懐に温めておく」「ノーエクスキューズを徹底する」「知的に怠惰でない人は、とことん考えているので、明確に欲しい情報がある」等、多くの金言があり、各々自分のスタンスを見直しました。
特に、「今日の仕事は明日に残さない」の話で、大前研一氏はその日やるべき仕事が終わるまでは絶対に家に帰らなかったというエピソードは深く刺さったようでした。あるメンバーは、「長い職業人生において、毎日やるべきことを終えて帰るか、このくらいでいいやと明日に残すかでは、長期的に大きな差が生まれると思った」と話していました。
また、ダスキンの社長は社長になるずっと前から、大前研一氏のところに相談にきて、まるで社長かのような視座で議論していた、というエピソードも印象的でした。よく、「二個上の役職の視点で考える」といいますが、役割にとらわれず高い視座を持つことの重要性を改めて伝えました。
『成長マインドセット』

画像出典:https://www.amazon.co.jp/
元ガリバーの取締役で若手経営者の支援などをされている方が書かれた本です。
こちらも、マインドセット・スタンス面でのインプットのために選定しました。
物語調で書かれた本で、「成長とはなにか?」という問いかけから始まります。そして、成長とは、「できなかったことができるようになること」といった技術面での成長ではなく、「自分のアイスバーグを大きくすること」だと説かれています。アイスバーグとは下記の図です。

目に見える成果に一喜一憂せず、成果を生み出す能力や、能力を形作る日々の習慣を良くしていくことが成長ということです。
そして、アイスバーグを大きくするために、とにかく自責100%で考えてみたり、自分の中にある"子どもな感情"に向き合ってみたり、自分の目指す方向を理解した上で業務に紐付けたりしていこう、という主張がされています。
とかくわかりやすいものに目が向きがちですが、能力や日々の習慣にもしっかり目を向けようという趣旨で選定しました。最初に書いたように、このプルス・ウルトラ計画も、論理的思考力、言語化力といった抽象的な能力や、マインドセット・スタンスといった日々の習慣をスコープとしていました。
『イシューから始めよ』

画像出典:https://www.amazon.co.jp/
こちらも有名な本で、実際にメンバーも一度は読んだことのある本だったので、内容は簡単な紹介にとどめます。
まず解くべき課題をしっかり見極めろ、間違った課題をいくら上手く問いてもバリューはない、ということが書かれています。

出典:『イシューからはじめよ』(英治出版, 2010)
主張は明快ですが、実践するのはかなり難しいと思っています。とはいえ、リーダー・マネージャーになるにあたってはかなり重要度の高い考え方でもあります。
というのも、役職が上がる、ということは、「扱う変数が増える」ということを意味しています。新人は、たとえばまず架電数を追う、というように業務範囲も、その中で改善すべき変数も固定されていることがほとんどです。これはある意味、「解くべき課題を上司が設定してくれている」ということです。そして、自分の責任範囲が増えてくれば、「解いたほうが良い課題」が増えてきますが、その中で「解くべき課題は何か」を考えてフォーカスする力が求められます。行動量は多いほうが良いし、行動の質は高いほうが良いし、チームの心理的安全性は高いほうがいいし、メンバーのモチベーションは高いほうが良いのは当たり前です。その中で、今解くべき課題はなにか、を考えることは複数のメンバーを持ちマネジメントする立場にあたっては必須の能力と思います。
勉強会では、面白い議論も出ました。「解くべき課題を見極めるのは難しいので、やると決めたことをしっかりやりきるのが大事では」という議論です。これもある意味正しいと思います。自分なりになにか仮説を持ってアクションをして、結果のフィードバックを得る、という経験が少なければ、解くべき課題を見極めるのはなかなか難しいです。また、そもそも情報が少ない環境において、明確に課題が浮かび上がってくることも多くはありません。だからこそ、一定は考え抜いた上で、あとはとにかくスピード早く徹底して実行する、そのインプットから新たな課題設定をする、ということも大事だ、という議論をしました。
『考える技術・書く技術』

画像出典:https://www.amazon.co.jp/
論理的に考えが整理されているとは、ピラミッドストラクチャーが成立していることだ、と書かれた本です。前述したロジカル・プレゼンテーションの、論理的思考、整理という点についてより詳しく説明した本です。「読み手にとって最も分かりやすいのは、まず主たる大きな考えを受け取り、その後にその大きな考えを構成する小さな考えを受け取るという並べ方」と書いてあり、いわゆる結論ファーストで喋れ、という話が丁寧に説明されています。
勉強会では、実際に業務に関係のある主張(提案数を伸ばすべき、など)をピラミッドストラクチャーで構成するとどうなるか、など議論しました。
また、構造化の練習として、日々のslackのチャット、日報でもできるだけ構造化を意識しようという話をしました。
ちょうどその頃、slackにおいてインデント機能が実装されていたこともあり、日々書く日報でインデントを使いながら構造化の練習をしていき、お互いにフィードバックすることにしました。副次的効果として、一部の人が構造化された文章を書いていれば、周りの人もまねするようになるので、体感として会社全体のチャットコミュニケーションがスムーズになった印象を受けています。
アウトプットパート
まずアウトプットパートに入る準備として、スプレッドシートでの分析の講習を行いました。
スプレッドシートの講習をここでやったのには意図があり、分析自体は手段に過ぎず、明確な問い、リサーチプランがあってこそ意味を成すため、インプットパートの後に行いました。
もともと日々の営業活動の計数管理はかなり緻密にしており、ダッシュボード等整っているのですが、施策を考えるにあたってダッシュボードでは見えない数字を見たいときに、自分で分析ができるようにするのが目的でした。
その上で、アウトプットパートでは、個人施策の検討、振り返りを行いました。日々の業務活動で、部署マネージャーと各メンバーで個人施策を検討し、実行しています。その個人施策において、インプットパートで学んだ考えを活かしながら、実際に課題解決をする精度をあげていくトレーニングを行いました。
具体的には、下記を考え、お互い突っ込み合ってブラッシュアップしていきました。
- 課題(定性・定量)
- 本当にそれは課題なのか(他のところが課題ではないのか)
- 施策
- なぜその施策を選んだのか
- 指標
- 期間
- 施策がうまくいかないリスク
実際に自分の課題で考えると、なかなかインプットパートで学んだことを活かせないもどかしさや、逆に理解が深まった部分もあったようです。
ブラッシュアップした上で施策を実行することで、短期で満足のいく成果を出したメンバーもおり、「検証」という点において、一段レベルアップしたと感じています。
また、お互いの課題についてフィードバックしあう中で、実際にメンバーから相談を受けた時どう整理し、どう話し合っていけば良いのか、という点においても学びを得られました。

勉強会の風景
3ヶ月やり抜き、一人はリーダーに
当初予定していた3ヶ月の期間、業務時間外の活動だったためかなり大変だった思いますが、しっかりやり抜き、無事終了しました。
では結果を振り返ってみるとどうだったのでしょうか。
リーダーという点では、4人中1人がプルス・ウルトラ計画中にリーダーになりました。ただ、もちろんプルス・ウルトラ計画の寄与は一部に過ぎません。
そして、実際にいまリーダーになっているかどうかはおいておき、「任せられる人材か?」という質問においては、残念ながらまだ参加者4人中1人だと思っています。
しかし、もともとプルス・ウルトラ計画がスコープとしていた、リーダー要件のうちの言語化、戦略理解、スタンスといったところはだいぶ進歩したと考えています。十分高い能力になったとは言えないですが、基本的な考え方、立ち返るべき軸はできたので、日々の思考習慣で今後も更に良くなっていくと思っています。
また、プルス・ウルトラ計画がスコープ外としていた、成果、信頼といった要件において、個々人取り組むべき課題がまだあるため、その点が「リーダーになるにあたってまだ届いていないところです。その個々人の課題についても、今後の宿題として、しっかり自己認識し、勉強会を終了しました。
最後に個々人に感想を書いてもらいましたが、抜粋して掲載します!
客観的にリーダーになるという目標達成はまだかなっていないのは正直悔しい気持ちがある。
しかし、目標と現状の差分がしっかりわかるようにはなったので良かった。
それは上記のような問題解決能力や論理的思考力がついたから理解も明確になったと思うし、今後も活かしていきたいと思った。
理論だけじゃなくて具体(キャリアパートナー業務なら、プレックスなら)で考える時間があったのでより腹落ちして知識を得られた
元々リーダーになるという目的で始めたPU計画だったので、達成できなかったことに対しては悔しい気持ちがあった。
ただ想像していたよりも求められることと現状の差分が明確になり、まだリーダーになれていないことへの納得感はあった。
明確に差分が理解できたことで何に取り組むべきかが具体的になり、少しずつ業務への取り組み方に変化が生まれたと思う。
また、複数人でやることに大きな意味があると改めて思った。
みんなでやるからこそ、単純に迷惑をかけられないと思って取り組むことができた。
ロジカルシンキングは元々苦手意識があり、前職でもプレックスでも避けていた。しかし、リーダーとして他の人の成果をあげるための「言語化」には必要な能力だと気づかせてもらい、取り組むことができた。まだ能力としては他の人よりも低いと感じることが多々あるが、課題意識をもって、継続的に取り組んでいきたい。
長くなってしまいましたが、ここまで読んでくださった方は本当にありがとうございます。
個人的にも今回の勉強会は、議論による学びもあったし、向上心を持った人と課題解決の取り組みをしていくやりがいがありました。
スタートアップで働く大きな魅力、最大の福利厚生は、一緒に働く人だと思います。
そして個人的には、向上心を持った人たちと働いていきたいです。高い目標を掲げ、自分が足りていないことを自覚し、そのギャップを埋めていくために頑張る行為ほど尊いものはないと思っています。それがリーダを目指すということであれ、個人として高い成果を出すということであれ、うまく会議を回せるようになるということであれ、粒度感は何あれ前に向いている事自体が素敵だと感じます。そういった人たちと働くのはとても楽しいですし、会社としても成長機会を提供できるようにこういった勉強会等の取り組みは積極的に行っていきたいと思っています。
積極採用中ですので、向上心を持った方のご連絡お待ちしてます!!
運営サイト: プレックスジョブ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
