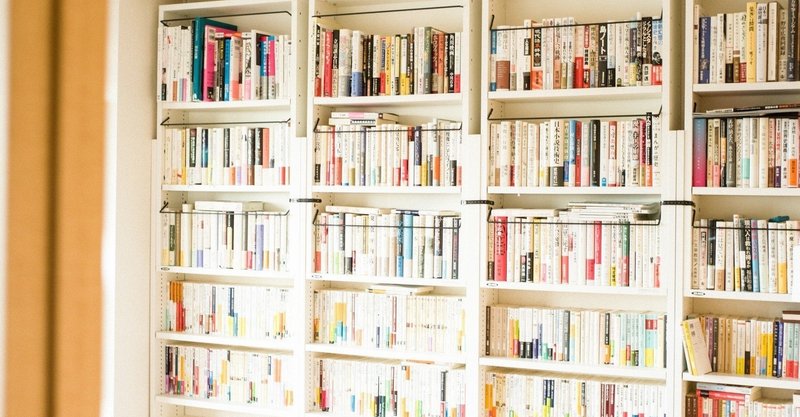
自#177|若い頃には、背伸びして、難しい文章を読むことも、必要(自由note)
朝日新聞の日曜版に、新書のはじまりについて書いてありました。講談社、文藝春秋、新潮社、光文社など、各社から新書は発刊されていますが、我々および、自分たちより上の世代にとって、新書とはつまり岩波新書のことです。岩波新書の始まりは、戦前に発刊された赤版(最初の赤版)ですが、戦後の民主主義時代の我々が、慣れ親しんだ岩波新書は、青版です。
町の本屋さんは、次々に消滅しています。私は、武蔵野市に住んでいて、最寄り駅は中央線の武蔵境駅です。武蔵境に来る前は、井の頭公園の近くで、長い間、暮らしていました。武蔵境に引っ越して来て15、6年が、経過しました。この15、6年の間に、武蔵境北口にあった三つの本屋は、すべて潰れました。私が以前、勤めていたJ高校の最寄り駅は、京王線の仙川駅でした。私がJ高校に赴任した11年前には、駅ビルにあった啓文堂さんを含めて、三店舗、本屋がありました。11年間に、商店街にあった音楽系が充実していた本屋は閉店し、商店街を抜けた交差点の角にあった本屋は、スペースを3分の1くらいに縮小し、残りの3分の2は、セブンイレブンの店舗として、貸し出しました。
今、私は、板橋区のK高校に勤めています。JR埼京線の板橋駅が、最寄り駅です。板橋駅は、池袋からわずか一駅で、都心部と言ってもいいぐらいの街だと思いますが、私が通っている通学路には、本屋は一店舗もありません。夏休みに、月刊雑誌(文藝春秋)を買おうと思って、お昼休みに中仙道を歩きました。所々、シャッターは降りていますが、商店街は、延々と続いていました。25分くらい歩いたんですが、本屋は、やはり一店舗もありませんでした。
今、これを書いていて、なかせんどうの「せん」が「山」なのか「仙」なのか、確認するために辞書を引きました。どっちでも良さそうですが、「仙」の方が、旧五街道っぽい感じはします。中仙道を、どこまで歩いたのか、昭文社の首都圏地図を開いて確認しました。環七の少し手前まで、距離にして2キロくらい歩いています。岩波書店のはじまりの記事を読んで、若い頃読んだ青本の書名、著者名を、正確に把握しておこうと、古本屋で買って来た古い青本の最後の書名リストのページを開いてみました。書名は、だいたい覚えていますし、著者名も、そうそう忘れてはいません。が、著者名を正確に漢字で書けるかどうかは、微妙です。書名リストを見ながら書いた方が、確実です。speedが要求されるSNSの世界では、たとえば、前首相の苗字が、安部でも阿倍でも安陪でも、流れの中で、前首相だと判れば、no problemなのかもしれませんが、我々、年寄りは、そういう風には、あっさり割り切れません。ところで、正確な用語の漢字も、地図も、書名・著者名も、すべてスマホがあれば検索できます。電子辞書が登場した時、あの小さなガゼットの中に、英和中辞典、広辞苑、字源などの辞書の内容が、すべてコンパクトに収納されていると知って、驚きました。今、スリムな小さなスマホがあれば、知識に関しては、すべて事足りてしまいます。スマホの中に、データーをストックする必要は、まったくなくて、どこかのサーバーに保存してあるデーターに、スマホでアクセスすればいいんです。正直、これはやはり、驚異的な知の革命だなと思ってしまいます。博覧強記のただ記憶しているだけの膨大な頭の中の知識は、インターネット時代には、さくっと無用になってしまいました。外国語をわざわざ学習しなくても、日常会話でしたら、困らない程度に翻訳してくれる翻訳機は、ヨドバシにだって売っています。
本を読まなくても、調べれば判ると云う安直な結論が、たやすく引き出されてしまいそうな気がします。本は、そういうものじゃないからと、正論を吐こうとしても、今や大学生の半数以上が、年間の読書量=0冊と云う時代ですから、多勢に無勢だろうとも思います。私は、高校時代、1年間に平均して180冊くらい本を読んでいました。最初に入った学校を途中で中退したので、4ヶ月間くらいはバーテン見習いの時期がありましたが、4年間で、4×180=720冊。実際は、もっと多くて、1000冊には届きませんが、800冊は超えています。高3の受験時代ですら、毎日、二時間は読んでいました。ゲームばかりやっている高校生が、結構いますが、私だって本ばかり読んでいました。ゲームオタク、ゲーム廃人の方に、どうこう言える資格はありません。
もう、今はほとんど読みませんが、岩波文庫、岩波新書は、かなり読みました。岩波文庫は基本、外国の翻訳小説ですし、岩波新書は、欧米の自由な思想を、日本に導入しようと始めた新たなスタイルの本です。今のような、ダイエットのため、モテるため、人間関係に悩まないため、みたいな実用書が登場するとは、岩波の青本を読んでいた頃は、夢想にだにしませんでした。
岩波新書は、吉野源三郎さんが考案します。そうあのマンガにもなった、「君たちはどう生きるか」をお書きになった吉野さんです。岩波文庫は、ドイツのレクラムがルーツです。岩波新書のルーツは、英国のペリカンブックスです。吉野さんは、丸善の洋書部で、創刊されたばかりのペリカンブックスを見て、感銘を受けます。値段も手頃、判型はスマートでハンディ。文章量も、読み切るのにほど良いくらい。テーマは、哲学・歴史・考古学(英国人は考古学が好きですから)・自然科学など、diversityに富んでいます。吉野さんは、当時の知の巨人であった、哲学者の三木清さんに相談し、協力を得て、タイトル、著者の顔ぶれ、装丁などについて議論し、工夫に工夫を重ねます。前年に、盧溝橋事件が起こり、大日本帝国のmajorityは、偏狭な国粋主義、狂信的な軍国主義・権威主義に、とりつかれています。欧米の自由なエートスを、本の中に潜ませた岩波新書は、時流のトレンドとは相容れない書籍だったので、絶対に売れない、リスクが高すぎると、社内でも反対意見が多かったそうです。最後は、書店主の岩波茂雄さんの「やろう」と云う鶴のひと声で、Go サインが出ます。いざ、出版してみると、予想に反して、創刊された20種類の岩波新書は、すべて売り切れたそうです。いつの時代にも、良心的なminorityは、存在していると云うことです。
吉野さんは、戦後、雑誌「世界」を創刊し、初代編集長になります。「世界」の格調高い教養主義の枠組みを拵えた、最大の功労者です。私は、学生時代、学部の図書館で、左は「現代の目」から右は「正論」まで、総合雑誌の興味のある記事だけは、だいたい目を通していました。学生時代、本はあまり読んでませんが、雑誌は読みました。「世界」は、学部の大学生にとっては難しく(大学院の修士課程レベルの雑誌だったと思います)、たいして解らないのに、無理して読んでいました。が、若い頃には、背伸びして、難しい文章を読むことも、必要だと思います(もっとも、若い人に、我々の世代の教養主義を押しつけるつもりはありませんが)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
