
「敵は家康」読了者限定読書会レポート (3)
さらに前回の続き。
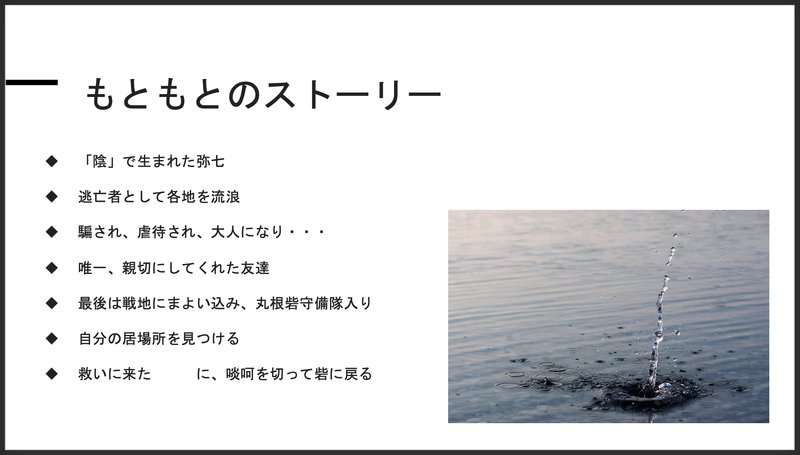
本作、書き始めようと考えたときの構想(?)は、現在の形とは全く違っておりました。
まず、長編ではなく、中編。もちろん私に長編執筆の経験が皆無で、まったく自信がなかった、いや、書き上げられる可能性などないと思い込んでいたことから自然に導き出される結論です。
ストーリーも、当初はきわめてシンプルなもの。中世の被差別部落に生まれ、己が何者であるかも知らずに育った少年が、あるきっかけで部落を出て、追手を逃れて外の世界を彷徨い、やがて戦場へと足を踏み入れ、そこに自分の居場所を見つける、という筋です。
ネタバレになるため詳しくは書けませんが、結末も、現在のものとは全く違っておりました。実際の戦闘シーンまでは描かず、砦を訪ねてきたとある登場人物に、主人公が堂々と啖呵を切って死地に戻っていく、ここで終了する予定でした。
つまり。
中世日本の名もなき貧しき少年の、自己の発見と、そして死へと至る旅路を、ほぼ彼の足取りだけを追って描いていくものだったのです。
ところが・・・
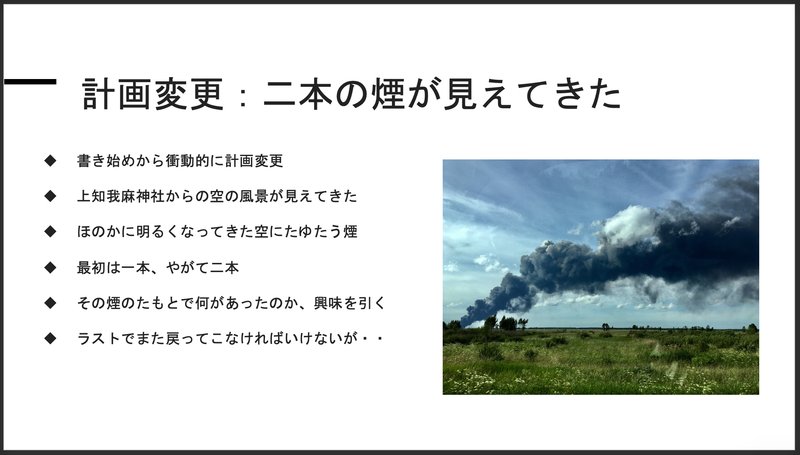
(煙はイメージです)
のっけから、計画変更(笑
前記のファミリーレストラン、COCO'Sの席に座り、書き出しの一言を、あーでもない、こーでもない、と考えているとき、ふと、有名資料「信長公記」にも書かれている、全く関係のない別のシーンが頭に浮かんできたのです。
そのシーンとは、熱田神宮境内にある境内社、上知我麻神社(かみちかまじんじゃ)から見た、南の空の映像です(脳内に、映像が見えました)。「信長公記」によると、まさにこの位置から、織田信長が、陥落したふたつの砦から立ち上る、二本の煙を見たそうです。
視界いちめんに広がる、まだ明け切らぬ空。そこに立ち上る煙。映画などのオープニングには持ってこいの詩的なシーンに思えます。なので、ここから物語を始めようと、その場で咄嗟に決断しました。まともな執筆経験もないのに、よくもまあ図々しくもそんな決断をしたものだと我ながら呆れますが、しかし、こうした自分の経験や実力などを顧慮せぬ蛮勇、というか心の声に従うと、なんとかなることが多いです(笑)
もちろん、ここから物語を始めると、またラストもここに戻ってこないといけません。当初のアイデアでは、桶狭間の合戦とストーリーをつなげる考えは無かったのですが、この脳内映像の出現により、有名合戦の前日譚・秘話としての性格がつけ加わることになりました。
まあ、要は場当たりです(汗
また・・・ひとつ告白しておきます。実は、上知我麻神社の方角から南を見ると、鷲津砦・丸根砦は、ほぼ重なって見えていたはずです。つまり、両砦から立ち上る煙は、ほとんど重なって見えていたと思われるのですが、後でこの地理的なファクトに気づいたとき(←遅い)、どうも画にならないので、脳内で一切、無視を決め込むことにしました。このあたり、校閲の厳しい出版社だと、かなり厳しく言われてしまっていたかもしれません。
不慣れな新人作家の創意を摘まず、まずはおおらかに書かせていただいた版元のアルファポリス社には感謝しております。

さて、ここで、ご質問の多かった冒頭、「陰」(ほと)について。
読者の皆様の中には、この名称を、本当に日本の中世で使われていた地名、ないし特定の地域・地勢につけられた俗称だと感じた方もおられたようです。どのような根拠で、どのような出典で採用したのか、数名の方に問われたのですが。
・・・すいません、全くの捏造でございます(←またかよ)。
実は、この言葉(?)を私が目にしたのは、記憶によると1982年か83年のこと。当時高校生だった私は、ワンゲル(ワンダーフォーゲル)部に所属しており、「山と渓谷」という月刊誌を愛読しておりました。
「山と渓谷」誌は、「ヤマケイ」として現在でも存続しておりますが、当時はまだアウトドアやソロキャンプ、あるいは「山ガール」といった言葉がカジュアルになる、ずっとずっと前の話。「山と渓谷」も、上のイメージに掲げたような、かなり地味な体裁の雑誌でした。紙質もあまり良くなく、特に誌面半ばのページは、触るとバリバリと音がしてシワが寄ってしまうような、安価な紙が使われていたと記憶しています。
その、まさに紙質最悪のページの中央部分、誠に見ずらい一角に小さなコラム欄があり、そこに、南アルプス深南部の沢筋に引きこもる仙人のような登山者がおり、彼に対する取材記事が載っておりました。そして、「陰」とは、彼の口から発せられた言葉であったと記憶しております。既に現物が手元になく、細部の記憶は曖昧ですが、おそらくかなり現代に近い時期、地方、あるいは登山者の会話の中で使われていた俗称だったようです。
しかし、このなんてことのないコラムが、その後40年間、ずっと私の頭の中に残っており、ある意味で非常に中世ぽくもある、また人間の肉体性を物語に盛り込むのに好適な語感でもあったため、大いに史実(?)を捏造し、この言葉を使ったという訳です。歴史小説に、史的な誠実さを求めるタイプの読者様に対しては、誠に申し訳のないことです。
(もっとも私は、こうした捏造というか歪曲は、創作の許容範囲だと思い、その後も何度か同じようなことをやらかしております。ここはいろいろと議論のあるところだと思いますので、あまり声高に主張はせず、まずはいったん経緯のご説明のみ)
長くなりました。また改めて書かせていただきます!
(レポートは次回でいったん打ち止めとし、その後はみなさまからいただいたご指摘やご意見などについて書きます)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
