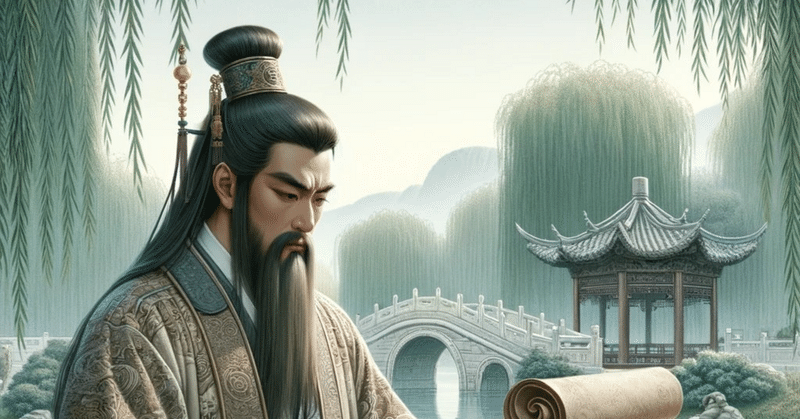
【時事抄】 歴史は繰り返さないが、韻を踏む
ロシアのウクライナ侵攻は2年が経過し、今はロシア軍の優勢が伝えられています。侵攻開始直後の2022年、米国をはじめとする西側諸国は「前例のない」大規模且つ厳しい経済・金融制裁をロシアに課してきました。
・半導体などの戦略物資のロシアへの輸出停止
・ロシア産資源の輸入停止
・ロシアの個人・企業・銀行の資産凍結
・ロシア一部銀行の国際決済網からの排除
資源高に支えられているとはいえ、これほど大規模な経済制裁を課されたロシア経済は、しかし破綻する様子もなく、期待された効果が出ていません。中国が経済軍事の両面でロシアを手助けをしているらしく、米国の苛立ちは頂点に達しています。まさに「孫子の兵法」が生まれた古代中国の戦国時代さながらの国際情勢です。
外交安保分野を専門とする日本経済新聞の名コラムニスト、秋田浩之氏の最新記事を見てみます。
<要約>
ロシア・プーチン大統領が16日に訪中し、習近平・中国国家主席と会談した。世界に及ぼす影響はかつてなく大きく、西側陣営と中露枢軸、両陣営の対立を決定づけた。
◆怒るバイデン政権
分断の最大の火種はロシアのウクライナ侵攻だ。中国は工作機械やドローン、衛星画像といった軍民両用品をロシアに提供し続け、米国は中国も”共犯”とみなす。プーチン氏の訪中は中ロの戦時協力を深める。
ウクライナ軍の劣勢のなか、ロシアを間接的に支える中国に対し、バイデン政権の怒りはかつてなく強い。ウクライナの敗北を食い止めるべく、米政権は4月以降、NATO各国にも対中圧力を強めるよう求めてきた。独仏両首脳は軍民両用品の対ロ輸出を止めるよう習氏に迫るも、習氏は輸出管理の厳格化を述べるの留まった。
従来、経済・安保で対立してきた西側陣営と中ロ陣営だが、ウクライナ問題は影響がはるかに大きく、米中の確執を、異次元の領域に引き込むだろう。
◆対立の3段階
これまで米中は3段階を経て対立を深めてきた。第1段階はオバマ政権の2期目途中(10年代後半)から、トランプ政権3年目(20年1月)まで。争点は、中国によるサイバースパイ、国家主導のハイテク産業育成、周辺海域での軍備拡張だった。
コロナ感染で対立は第2段階を迎える。米国人100万人超の命がコロナ禍で奪われた。感染爆発を招いた中国共産党の体質に米国が憤り、「政治体制」の争いに発展した。
そして、対立は第3段階を迎えている。米国はウクライナへ侵攻するロシアを「現秩序の破壊者」とみなし、これを敗北させたい。中国は米国主導の現秩序こそ壊すべき対象と考えていて、ロシアへ軍事支援する。争点がハイテクなど個別問題から、両者相入れることない世界秩序観に変わってきた。
◆米中とも強硬論に傾く
11月の米大統領選挙を控え、米国内はで対中論議が険しさを増す。相互不信の連鎖は、例えばトランプ陣営の高官たちが公にした論文にも現れる。米中競争は、管理から、米国の勝利を目指せと目標の変更を訴えた。
中国は対米強硬に進む。焚き付けているのはプーチン氏だ。「米国は中国共産党体制を転覆させるつもりだ。いまの香港を見れば明らかだ」。西側の中国専門家によれば、香港で反中デモが吹き荒れた当時、プーチン氏は幾度となく習氏にこう説いたという。今回の訪中でも米国の陰謀を説き続けただろう。
米中対立の深化は、日本を含む米同盟国にも新たな対応を迫る。サプライチェーンの再構築や安保協力体制の強化などと共に、米国と密に政策をすり合わせる必要がある。一方、意図せぬ紛争が生じぬよう、危機管理の努力もより必要になる。もし米中冷戦が戦争に転じれば、皆が敗者になりかねない。
(原文2103文字→1131文字)
ロシアのウクライナ侵攻の発端を紐とけば、2019年にウクライナ大統領に就任した、元俳優・コメディアンという異例の経歴の持ち主、ゼレンスキー氏の登場でした。就任直後に70%を超えた支持率でしたが、直後から低下し続け、起死回生を図ったのでしょうか、NATO(北大西洋条約機構)加盟に向けて西側諸国の支持取付けに動き出します。ロシアは猛反発します。米国主導の西側軍事同盟NATOの加盟国が、ロシアの隣接国となるのですから。

ロシアのウクライナ侵攻は国際法に違反した明白な侵略行為であって、その行いは決して正当化できるものではありません。ウクライナは多大な犠牲を払いながらも、徹底抗戦を繰り広げている。この前提を踏まえつつも、もしゼレンスキー氏がNATO加盟に動き出さなければ、と歴史の「If」を思わずにはいられません。ウクライナがNATO加盟への意欲をもつ限り、ロシアはウクライナから手を引くわけにはいかないというのが現実でしょう。
内政の失敗は一内閣が倒れれば足りるが、外交の失敗は一国を亡ぼす
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
