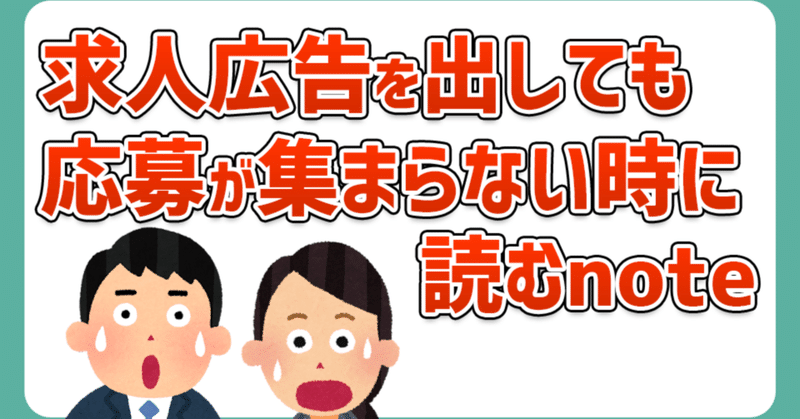
求人広告を出しても応募が集まらない時に読むnote
この記事の読者:
求人広告を出稿している企業の経営者・採用担当者など
この記事を読むメリット:
応募が集まらない求人広告の理由と対処法が分かる
挨拶
こんにちは、採用コピーライターのオヤマダです。
みなさん、最近いかがお過ごしでしょうか。僕は企業の採用担当者の方から「ちょっと採用の相談に乗ってほしい」と言われ、お客様先にお伺いすることが増えています。
そこで感じるのは、求人広告を出稿している多くの企業様が、応募は集まっているけど有効応募は集まっておらず、当然採用に結び付く結果になっておらず、広告出稿にお金を使いすぎて採用についてどうすればいいか頭を抱えている、ということです。
応募が集まらない原因も分かっていないことが多いと感じられているため、今回は「求人広告を出しても応募が集まらないのは、こういうことが原因で、こういう対策を考えていくべきなんだよ」という内容のnoteを書いてみたいと思います。
求人広告に応募が集まらない理由

求人広告を出しても応募が集まらない理由は、上記の「求人広告が見られていない可能性」か、「求人広告は見られてはいるけど応募する理由が見つからない状態になっている可能性」、どちらかと推測されます。
それでは、求人広告が求職者に見られていない可能性について、考えていきましょう。
求人広告が見られていない可能性

なぜ、求人広告が見られていないのか。その可能性として、上記(A)~(D)が考えられます。
(A)と(B)は似ているのですが、ちょっと意味が異なります。(A)はそもそもいない人を求人広告のターゲットにしている可能性の示唆であり、(B)は出稿媒体とターゲットが出あわない可能性を指しています。ターゲットがいなければターゲットからの応募が来るはずがないですし、ターゲットが見ない場所に広告を出してても応募は来ない、ということです。
(C)は、出稿媒体に掲載されている求人広告が多く、その中の1つとして埋もれてしまっていてターゲットに見られていない可能性です。ネット求人広告に掲載している場合、プランによっては掲載順位が下のほうになってしまうため、これは結構あるある話です。
(D)は(C)と似ているのですが、同時期に掲載されている求人広告が多いため、パッと見ただけではメリットを感じられず、スルーされてしまっているパターンです。この可能性が一番深刻であり、【応募する理由がない】にも片足突っ込んでいる話とも言えます。
応募する理由がない可能性
求人広告を出しても応募が集まらない理由の2つ目は、「求職者にとってその求人広告に応募する理由がない」です。
注意点ですが、ここからの話は求人が一般的な給与と休日と福利厚生があることが大前提となります。給与が極端に低い、休日が全然ない、福利厚生がない求人は応募が集まらないのは当たり前なので、そのような場合は先にやるべきことをやってください。
で、話が戻りますが、一般的な給与と休日と福利厚生がある求人はどんな仕事でも応募が来ます。それでも応募が来ないというのは、コミュニケーションが成立しておらず、「どんな会社のどんな仕事かよく分からないから応募しない」と求職者に思われています。

理由として、上記の(A)~(D)が考えられます。
(A)について。応募が来ない多くの企業がこれをやっています。求職者は基本的に世の中にどんな産業や仕事が存在するのかを知りません。なぜなら、学校で教わらないからです。テレビでも放送しません。そのため、ほとんどの企業の求人広告に書かれている仕事は、求職者にとってよく分からないモノと考えたほうがいいです。
世の中にどんな産業や仕事が存在するのかを知らない人たちに、どんな仕事なのかイメージが湧くように伝えられていないと応募は集まりません。応募があったとしても仕事理解が薄い(と企業側が判断する)人からの応募しか来ないと思います。
「仕事理解が薄い応募者しか応募してこない」というのは、企業側の伝え方に問題がある場合が多いのです。
(B)について。これは(A)と同じく、求職者は世の中にどんな産業や仕事が存在するのかを知らないわけで、その人にどんな事業を行なっているかを分かりやすく説明できていないと、求職者にとって募集企業は「何かやっている会社」以上にはなれません。
とはいえ、企業ホームページの事業内容に書かれていることを、世の中にどんな産業や仕事が存在するのかを知らない求職者に分かりやすく伝えるのは結構難しい話です。①経営者はどんな未来を実現したいと考えているのか、②そのために何をやっているのか、③その手段として募集職種はどんな役割を果たすのか、といった流れで説明すると。ストーリーになって分かりやすいと思います。
(C)について。求職者は世の中にどんな産業や仕事が存在するのかを知らないのと同時に、自分がどんな仕事に向いているのかも分かりません。なぜなら学校で教わってきていないからです。しかし逆に考えれば、求職者が募集職種に向いている理由を伝えられれば、それは求職者にとって応募する理由になるということなんですよ。
これを実現するためには、募集職種に必要な採用要件をきちんと整理して、スキル・経験だけでなく志向性も、よくある求める人物像のテンプレートではなく、占いに書かれているような「あっ、自分にはこういうところがある!」と気づかせるような書きかたで伝えられると、強いです。
(D)について。これは、入社後に得られる恩恵、入社すると得られる未来を伝えられれば、それが応募の決定打になります。仕事探しって部屋探しに似ているんですよ。部屋自体のスペックも大切ですが、多くの人はその部屋で始まる新生活をイメージして決めるじゃないですか。就職も同じで、明るい未来を見せられるかどうかで、応募数って変わるんですよ。
これはマーケティング用語でベネフィットというのですが、この設定方法や考えかたはそれだけで記事1回分くらいのテキスト量になるので今回は省略させていただきますね。
動画案内
今回お話しした内容よりもう少しくわしい解説を加えたものを動画にしています。興味がある方はこちらも見てみてください。
さいごに
YouTubeではこんな感じの動画を随時アップしています。採用したいけれども採用活動が上手くいっていない企業様へのアドバイスになる動画が他にもあります。興味がある方はチャンネル登録していただけると励みになって嬉しいです!
それでは、別の記事でまたお会いしましょう!
今日があなたにとって実りの多い一日でありますように!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
