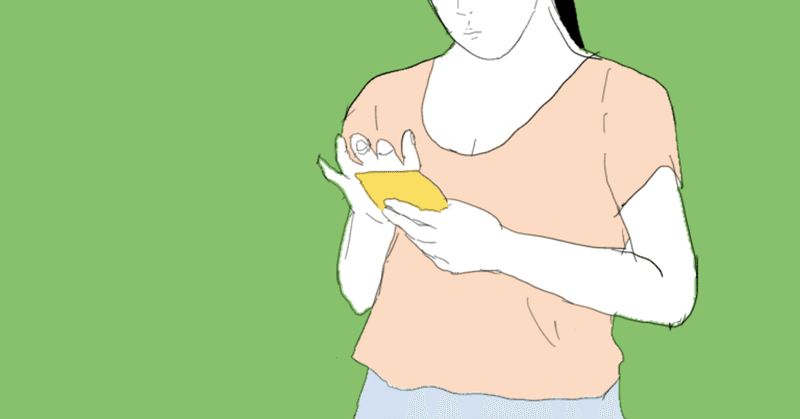
『私の知らない夫』(短編小説)
「ねえ・・・」
「・・・」
「ねえ? ねえってば! 」
「ん? 」
「もうっ、さっきから呼んでるのに、ぜんぜん聞こえてない」
「ああ、悪い悪い」
「毎日スマホばっかり見てるじゃない・・・」
ここのところずっと、夫の様子がおかしい。暇さえあれば、スマホをのぞき、指で何かの文字を打ち込んでいる。急にテンションがあがったり、攻撃的になったり、時には涙もろくなったりする。
「ちょっと最近おかしいよ」
「なんで? 」
「食事の時も、子どもの面倒を見ている時も、ずっとスマホを触り続けてるじゃん」
「仕事のメールとかしてるんだよ 」
「嘘」
「ほんとだって。会社宛のメールをスマホに転送・・・」
「いい加減にしてっ! 」
夫が何に夢中になっているのか、私は知っている。だから、仕事のメールという言い訳が嘘なのもわかっていた。
以前、夫がトイレに立った時、ソファの上にスマホが置きっぱなしのことがあった。いつもなら、肌身離さずスマホを持っているのに、その時だけは忘れていったから、チャンスとばかりに画面を覗き込んだ。
スマホの画面には、「mote」という文字と「一ノ瀬ハヤ」というアカウント名がはっきり見えた。ネットで調べてみると、「mote」は最近流行っているSNSらしい。そして「一ノ瀬ハヤ」の「ハヤ」は夫の名前であるハヤトからとったアカウント名なのだと理解した。
「ちょっと友達と会ってくる」
先週末はそんなふうに言い残してどこかへと出かけていった。誰と会うかは言っていなかったが、深夜にスマホ片手にニヤニヤしながら帰ってきたのを覚えている。moteのフォロワーの誰かと会っていたに違いない。
夫婦であっても、お互いにプライベートはある。それはわきまえているつもりだ。それでも、私が存在していないかのように起きている時間はずっとmoteに夢中で、私に見せないような表情でスマホを操作する夫の姿が憎たらしかった。 SNSをやるのは構わない。でも、私にも限界がある。家族を忘れている夫のことが許せなかった。
あのmoteに夢中な日々をぶっ壊してやりたい。私は確かにそう思った。
数週間後。夫はますますSNSにのめりこみ、私とはほとんど口をきかなくなった。話しかけてもそっけない返事をするだけ。何をしている時もスマホに夢中で、家族のことなんて全く興味がないみたいだった。
ある考えが、私の頭をよぎった。
そうだ。私自身がmoteで匿名アカウントを登録して、夫のフォロワーになって、懐に侵入してやろう。
見てろよ。この作戦で、地獄に突き落としてやる。夫の苦虫を食いつぶしたような顔を想像すると武者震いした。
ある日の夜、夫はスマホ片手に鼻歌を歌いながらご機嫌な顔で帰宅した。
「あら、おかえりなさい。何かいいことでもあったの? 」
「え・・・、あっ、特に何も」
「鼻歌が聞こえたから・・・」
「・・・別にいいだろ。ほら、その・・・商談がうまくいっただけだ」
「へえ、そうなんだ」
・・・この単純なバカ男め。お前がニヤニヤしている理由なんてお見通しなんだよ。全部、知ってるんだよ。だって、私が仕掛けているんだから。
アカウント名は「綾瀬夏香」。ネットで適当に拾ってきた猫顔のアイドルっぽい女の画像をアイコンに設定。プロフィールには「元アイドルの20代女子。好きな映画はアメリ。moteで書いて書いて書きまくるぞぉ!」とそれらしく書いた。
初心者ユーザーっぽい口調で、夫(一ノ瀬ハヤ)の記事に好き好きコメントをする。夫は毎日更新を頑張っているようなので、こちらも毎日欠かさずコメントを書き込む。
すてきな記事でした。一ノ瀬ハヤさんの書く文章に惚れています。読んでいると元気になれるんです。まだmoteを始めたばかりの初心者ですが、よろしくお願いします(*^_^*)
とか、
今日も、すごく良い記事でしたね。なんだか感動しちゃいました。わたし、SNSの超初心者なんです。またいろいろ教えてくださいね。一ノ瀬ハヤさんみたいになりたい☆
とか
ああ・・・素敵、うっとりする。ハヤさんのmoteを読むのが私の日課になっています。ずっと、その文章に、その言葉に抱かれていたい・・・
とかね。
計画通り、私の匿名アカウントと一ノ瀬ハヤは急接近した。どんどん親密な雰囲気になっていく。私がコメントを書き忘れた日なんかは、寂しくなったのか、こちらの過去のアリバイ記事に「どうしたの?」なんてコメントしにくる。アホだ。
一ヶ月ほど経った頃、なんとなく一ノ瀬ハヤという世界観がわかってきた。それは夫とは別の人格のようだった。
「みんなが幸せだと、僕もね、幸せな気分でいっぱいになるの☆」や「僕はきっと僕。あなたがあなたであるように。ねえ、一緒に愛について語ろうよ」といった安っぽい言葉を、毎日投稿している。プロフィールには、“愛に恋する吟遊詩人”と書いてあって、ケッとなった。
毎日更新だけでなく、月に一回オフ会のようなイベントを主催しているようだ。moteで仲の良い相互フォロワーと飲みに行ったりするらしい。
そして予想していた通り、一ノ瀬ハヤは私の匿名アカウントにイベントの招待メールを送ってきた。「綾瀬夏香さん、ぜひ一度会いましょう。いろいろお話しましょう(@^^@)」というコメントを添えて。顔文字なんて使っているの見たことがないぞ、この野郎。
「では、10日の18時30分に、代官山のモンターレで。今のところ10人くらい来る予定です。あと、もしよかったら2人だけで2次会とかどうでしょう。moteについていっぱい語りませんか」
*
イベント当日になった。子供を実家の母にあずけて、かつて着たことがないような派手めの洋服を身にまとい、私らしくない男受けしそうな髪型にして家を出た。夫は、仕事を終えたら職場からそのまま会場に向かうはずだ。
会場のイタリアンレストランに到着すると、既に5人くらいが席についていた。私に気が付いたアラサーくらいの女が「あ、一ノ瀬ハヤさん主催の会の方ですか」と聞いてきたので、静かに頷いた。
「どうも、綾瀬夏香です」
「あっ、夏香さんだったんですね。わかりませんでした。はじめまして。私、ダックスハント純です。いつも、イイネ押してくれてありがとうございます」
「ああー。私のあの写真、画像加工アプリのやつで・・・」
アイコンの写真との違いは適当にごまかした。夫の周辺のアカウントもリサーチ対象としてフォローしているので、この会に来るメンバーもだいたい目星がついていた。しかし、ネットでしか話したことがない人と実際に会うのは変な感覚だ。
「ハヤさん、残業があって少し遅れるんだって」
「じゃ、みんなで先に始めますか」
「そうですね」
残業で遅れるらしい。夫の一ノ瀬ハヤがいないまま、会はスタートした。グラスに白ワインが注がれる。ぞくぞくと料理が出てくる。私は、まだかまだかと夫の到着を待ちつつ、綾瀬夏香を演じ続けた。
1時間ほど経った頃、社会人一年目の宮崎君がスマホを見ながら言った。
「ハヤさん。今日来れないんだって。急な仕事が重なっちゃったみたい」
「ええー、ハヤさんめずらしい。いつもなら真っ先に来るのに」
「まあ今回は仕方ないね。また来月だね」
その時、自分のスマホに2件のお知らせが来ていることに気づいた。1件は妻である私宛に「今日は仕事で遅くなる。ごはんはいらない」だった。もう1件は、綾瀬夏香宛に「夏香さん、1次会行けなくてごめんなさい。超楽しみにしてたのに。でも、2次会には間に合いそうだから2人でゆっくり会いましょう(*^_^*)」だった。ふふ、好都合だ。
代官山のイタリアンの会の解散後、私は、2次会の待ち合わせ場所である渋谷に向かった。ぽつぽつと雨が降っている。東横線の車窓に雨水で歪んだ再開発の街が流れていく。この世界は絶えず変化している、そう思った。
奥渋にあるグローバルカフェという洒落た店に到着する。席は予約してあるらしい。深いブルーのテーブルクロスが敷かれたテーブルに案内され、私は店のエントランスを背にして座り、一ノ瀬ハヤを待った。雨音が強くなっていく。「最初にどんな言葉をかけてやろうか」。私はそんなことばかり考えていた。
しばらくすると、エントランスの方から男の声がした。
「すみません、一ノ瀬ハヤで予約していたんですが・・・」
「お連れの方が先に席につかれております」
はあはあと息をきらしている。この雨の中、走ってきたのだろう。革靴の足音が少しずつテーブルに近づいてくる。雨で肩と鞄を濡らしたスーツの夫が目の前に現れる。
「こんにちは」
私の顔を見た夫は、特に驚きもせず取り乱す様子もなく、向かいのチェアに腰をかけた。
「いやあ、すごい雨だったね」
「・・・」
・・・こんなはずじゃない。言葉が出てこない。なぜそんなに堂々としていられるんだ。目の前にいるのはお前の妻だ。ドッキリをしかけられて驚きのあまり床に倒れ込むようなバカな夫の姿を想像していたのに。
私はうつむき加減のまま、しばらく沈黙していた。夫が沈黙を破ってゆっくりと話し出した。
「俺ね、夏香さんとやりとりする中でね、思い出したんだ。出会ったあの頃のこと」
「・・・」
「すぐに気づいたよ。夏香さんの中の人が誰かってことに」
「え・・・」
「ごめんね。本当にごめんね。今日こうやってお前にあやまるために、わざと騙されているフリしてたんだよ」
「・・・嘘。絶対嘘よ。そんなわけない」
「わかってたから、2人だけの2次会に誘ったんだよ」
「そんな見え透いた言い訳・・・」
その時だった。ドリンクを運んできたウェイターがつまづいて派手に転んだ。トレーとグラスが宙に舞い、スパークリングワインがあたりに飛び散った。
突然、店内のBGMがダンシングクイーンに変わった。派手に転んだウェイターはぐるりと一回転して立ち上がり、音楽に合わせて、華麗なステップとともに両手をリズミカルに動かし出した。
すると、それにつられるように、隣りのテーブルに座っていた小太りのおじさんがキレッキレの動きで体を躍動させ始めた。さらにその隣りのテーブルの品の良い老夫婦も席を立ち上がり、幸せいっぱいの笑顔で、音楽に体を合わせ始めた。
「えっ、なにこれ」
しまいには、カフェに居合わせる人たち全員が、音楽に合わせてノリノリのダンスをし始めた。踊る全員が、細やかな動きまでぴったりとシンクロさせている。みんな満面の笑顔で踊りながらも、その視線は私に注がれていた。
呆気にとられる私の手を、夫がつかんだ。
「一緒に踊ってくれませんか」
夫に引っ張られるがままに、私は見よう見まねでダンスした。なんだろう、この初めての感覚。体中からあふれ出すアドレナリン。You can dance !! You can jive !! ああ、生きてるって美しい。愛って美しい。
ダンシングクイーンの曲が終わるのと同時に、夫は跪き、いつの間にか用意していた色とりどりの花束を私に差し出した。同時に、夫のスーツの内ポケットから小さな箱のプレゼントが出てきた。
「誕生日おめでとう」
カフェに響く拍手の嵐。震える背中。無意識にあふれ出す涙。私はそのままその場でうずくまってしまった。
moteの侵入作戦なんて完全にどこかに消え失せてしまった。フラッシュモブなんてずるい。ずるいよ。ベタでちょっと古いけど。
「約束する。これからは家族をもっと大切にする。もうスマホは見ないよ」
「・・・」
「moteもやめる」
「・・・ねえ、一つだけお願いがあるの」
「なに? 」
「一ノ瀬ハヤさん。あなたはあなたのままでいてください。綾瀬夏香のことも引き続きよろしくお願いします」
(了)
読んでもらえるだけで幸せ。スキしてくれたらもっと幸せ。
