
留学中の事件の数々 その1
文字数: 12,138字
まえがき
急に留学時代のことを思い出してちょこまかとしたことを書いてみたくなった。「ワクワク ホームステイこぼれ話」と題してシリーズの形で4本の記事を書いてきた。最後の「4 ワークショップ」を執筆中だが、その間ずっと留学の記事を書いてみたくなっていた。もっとも「ワクワク ヒューストン 悲しきウノ 葬儀等飛び入り参加」と題して留学時代の冬休みの勉強とは異なる諸相をしたためてきた。留学については「留学ってきつい 楽しい」と題して2本書いた。「その1」は最初の短期留学時代のミシガン大学でのことが主体だ。「その2」は1年間のインディアナ州立大学での留学体験だ。今回の記事はそれに載せていない部分を書いてみた。勉強以外の諸相といえば楽しそうだ。楽しいこともあればしんどい記憶もある。それを紹介できればと思っている。乞ご期待だ。
1.弱者の味方
留学先の大学寮の4階に、台湾出身の留学生Kがいた。Kは大学4年生であった。
ISUでは、学生が各学期で取得を目指しても良い単位数の上限が決められている。大学生がどれだけだったか覚えていないが、私が学ぶ大学院では最高12単位である。科目数で考えると、一般的には最高が4教科ということになる。
私は最初の学期(秋)は3教科、次の春は4教科、あと夏の3つの短期コースのうち2つが上限の教科数という厳しい綱渡りであった。しかもあと1つの短期コースでは、口頭試問が待ち構えていた。
この台湾からの留学生Kは、大学生にとっての上限の教科数を取っていた。
大学では、大学院と違って、日本の中学や高校のように豆テストを頻繁に行う。予習しているかどうかをチェックするのである。つまりこの豆テストというのが予習テストなのだ。
私が大学で授業をするようになった時に、この予習テストを毎時間行った。準備が大変だったが、学生は必死に予習してきたので授業をすることがとても楽だった。学生も予習した人は楽だったはずだ。
中間考査、期末考査は大学院でもほとんどあったが、それ以外にも大きなテストをする教授もいる。どの教授も、学生は自分の教科しか受講していないと誤解しているらしい。最初の時間にその学期の授業プランをプリントにして渡してくれる教授も多い。少なくとも、試験と宿題はどの教授も前もって報せてくれる。
台湾人Kは寮でよく倒れた。彼が倒れる時は、必ず2つ、3つのテストが重なったり、続けざまにあったりする。予習もしないといけないから、それは大騒ぎだ。
私には彼の気持ちが痛いほどよく分かった。だが、助けてあげることはできない。食事をしながら話を聞いてあげることぐらいだ。同じ苦しさを同時に体験している者だけが、それをしてあげることが出来る。自分の方が落ち込んでいても、頑張れよと言って励ます。励ましているうちに、自分にも元気が出てくるから不思議だ。そんなKを、ルームメイトも周囲の者も労わる。
私が結婚したのは23歳になったばかりの時だ。大学卒業の1週間前の結婚式だ。だからお金はなかった。結婚披露宴も新婚旅行も行っていない。こんな話を大学ですると、学生からブーイングだった。女子大学だからだ。そこで、実は21周年記念に旧婚旅行にアメリカ18日間の旅に連れて行った、と話すと、急に彼らの目が輝いた。それなら許してやる、というのだ。別に彼らに許してもらわなければいけない理由はない。
その妻が、旅行中何度か口にした言葉がある。
「アメリカでは、人間が保護されてるね」
こんな 表現を私は聞いたことがない。どういう意味なのかを聞き損なってしまった。そしていつの間にか、私も同じ感覚を持つようになっていた。
私がいた寮には、一人の目の見えない女性がいた。白い杖を持っていたから分かった。彼女が一人ぼっちで歩いているのを、私は見たことがない。常に1人か2人が彼女と一緒に歩いている。いつも同じ人と一緒というわけでもない。彼女は、白い杖を巧みに操って、安全に歩く。一緒にいる人たちが手を貸すというわけでもない。キャンパスで、何人かがグループで歩いているといった、よく見かける光景だ。白い杖を持っていなければ、ごく普通のグループだ。いや、白い杖があってもごく自然だ。
どう自然なのかと問われたら、私には分からないとしか答えようがない。
同じ寮に入っているからなのか。同じ大学で学んでいるからなのか。同じキャンパスを歩いているからなのか。同じエレベーターでよく一緒になるからなのか。とにかく当たり前の毎日なのだ。
もう一人女性がいた。私は当時の身長が170センチだから、あと10センチ背が伸びればと思ったのは、馬鹿げたことだっただろうか。混雑したエレベーターの中で、私は前が見えない。正確には、見えている。私と向かい合わせで立っている黒人の胸が、そこにはある。彼は、プロバスケットボールチームから声がかかっている。ドラフトで指名され、卒業を待つばかりだ。彼の連れもバスケット部員だ。まるで林立する摩天楼の中にポツンと残された古びた家屋だ。私が2階建てなら、彼女は平屋だ。いや、私でさえも彼女の前では摩天楼の仲間入りが出来そうである。
彼女は大学院生だが、何を専攻しているのかは知らない。知っていることは、彼女が極めて背が低く、ギラムホールの一員であることくらいだ。彼女にとって、アメリカは住み心地の悪い国だろう。しかし彼女はいつも笑顔だ。誰とでも話す。彼女から声をかけるし、皆も彼女に声をかける。
彼女は9階の住人らしい。寮のフロントの横に、全室の郵便受けがあって、彼女の郵便受けが一番上にあることから分かる。私は6階の住人だから、、彼女のよりも少し下の方に郵便受けがある。
私は手紙が来ているかどうかを背伸びして確認する。留学中の私には、この動作は習慣性となった。寮の出入りをするたびに取る動作だのである。留学生でなくとも家族と別れての寮生活だ。彼らにとっても習慣性動作となっている。私は時々、寮の学生全員がこのフロントの前に集まって、この習慣性動作を一斉にしたらさぞ面白かろうと思ったりした。勉強にも自信がつき、不安が自分を襲うことが少なくなった頃のことである。
かの女性も私たちと同じだ。しかしいくら背伸びをしても、飛び上がっても、私の郵便受けすら覗けない。
彼女がフロント付近に姿を見せる。郵便受けはエレベーターの前にある。そこには絶えずエレベーターを待つ学生がいる。彼女が背伸びをしている。エレベーターの前からごく自然に、1人、2人とやって来て代わりに覗いてやる。手紙が入っていると、キーを受け取って取り出して渡す。自然な一連の動作だ。例のバスケット部員も、頼まれなくとも勝手に覗いて、入っているかどうかを伝える。パーティーフロアの暴れん坊も、通りすがりに覗いてやっている。
注:パーティーフロア ⇒ ギラムホールで毎週末にパーティーをやるフロアが6階だ。私の部屋も6階にあって、毎週うるさくてたまらなかった。トイレに行くにもドアを開けるとすぐそこに人がぎっしりだ。そして一斉にこちらをみるのだ。その目は酔いにトロンとしている。あまりの腹立たしさに相手をキッと睨みつけたこともあったほどだ。
2.トマトのオバチャン
図書館を入ると、すぐ右手にエレベーターがある。「やあ」と知り合いが声をかけてきた。私はその時、エレベーターの前で呆然と立ち尽くしていた。夜9時10分頃のことであった。6時過ぎから9時まで、私は「20世紀ドラマ」の授業を受けてきた直後だった。
この授業の教授は、まるで機関銃のようにしゃべった。3時間ぶっ続けだ。秋の学期の最初の水曜日。ディスカッションもよくするのだが、その日は一方的に言葉を撃つ。私の身体は上から下まで穴だらけだ。わずか10人足らずのクラスだから、なおさら身にこたえる。
ノートが全くと言っていいほど取れない。贔屓目に見ても、20~30%といったところだ。木曜日の書誌学でさえ、初日からほぼ100%ノートが取れていた。
妻へ書いた手紙を引用してみよう。
(注:3時間ドラマ=3時間ぶっ続けの授業))
『9月16日 23:00 そちら9/17 13:00
3時間ドラマ、今週は先週よりももっとひどくて全くノートが取れませんでした。でも、この3時間ドラマの級友?の60才をこえたオバチャンが、先週のノートをとてもわかりやすく(頼みもしないのに)タイプしてきてくれたのです。庭で採れたトマトはもらうし、ノートといいとても親切で何かしてあげようと張り切っています・・・。』
『10月14日 23:00
・・・そして夜は例によってノートも取れない3時間ドラマ。今日はさらに分からずお手上げ。トマトをまたもらったのが収穫ぐらいなものです。
来週このオバチャン来ないようなので、これは困ったと思って、別の人に借りてコピーし、今帰ってきましたが、これが又さっぱり読めないのでがっくり。暗号解きに頑張らねば・・・』
私の親友を、私はトマトのオバチャンと呼んだ。水曜日の「20世紀ドラマ」のクラスメイトとして出会ったのである。学期が始まって、第2周目のことだった。彼女は、びっしりタイプを打ち込んだ2枚の紙と、大きなトマトを数個私にくれた。遠い国から来て大変だから、と言うのである。アメリカにいると、そういう目で見てくれる人は少ない。英語が喋れて当たり前、という考え方がごく一般的である。
(「留学ってきつい、楽しい その2」で「トマトのオバチャン」という同じ大見出しで別角度から扱っています)
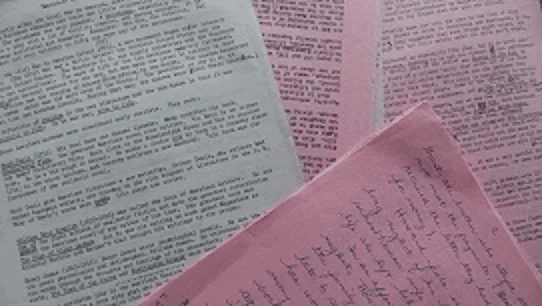
多いときは10枚、時には両面

ありがとうございました
彼女の持ってきてくれたトマトは美味しかった。大きかった。真っ赤だった。
彼女は自分は作家だと言っていた。授業では、自分の意見をとうとうと喋りまくり、教授の考えと食い違うとむきになることもあった。2人のやり取りは、いつもその日のポイントがぼんやりとしか入っていない私の頭には、整理の助けとなった。私もディスカッションの仲間入りをしたいと思うが、教師もオバチャンも機関銃。私の入る余地はない。
しかし、楽しいやり取りだ。授業が味付けられて行く。3時間ぶっ続け撃ちまくられるから、ノートを取るのが大変だ。最初の1時間はまだいい。気力集中力とも十分だ。それを過ぎると鈍化する一方だ。味わう余裕などない。
オバチャンがしゃべりだす。10人ほどのクラスが身を乗り出す。教授は、彼女の意見に対して説明を加えながら、賛成したり反対したりする。他の学生も加わる。もうこうなると討論会だ。私は取り残される。でも頭の中では何とかついて行く。予習の時にさっぱり理解できなかった部分が、だんだんと浮き彫りにされてくる。私が子供の頃流行ったあぶり出しのようだ。
ミカンの汁を筆につけて、はがきに「賀正」と書く。友人からそんな年賀状を受け取った。居間の中央に置かれた火鉢の上で、そのハガキを火に焙る。期待の眼だ。父や母、兄、姉、妹、皆の目がそのハガキに注がれる。少しずつ、少しずつ、文字や絵が姿を現す。充足感。家族の団欒。冬の中の暖かさ。心にしみわたる楽しさ。うまく焙りだせた誇り。
授業が終わると、疲労感がどっしりと重くのしかかる。暗くなった道を、寮に向かって歩く。オバチャンは必ず声をかけてくれる。「この人は授業中は黙っていて、何を考えているのかさっぱり分からないけど、授業が終わると結構おかしいことを言って面白いのよ」彼女はそう言って、私のことをクラスメイト達に話してくれる。おかげで、他の人たちとも、少しずつ話をすることが出来るようになった。
11月に入ると、トマトのオバチャンは、アメリカらしいアメリカを紹介するから、時間を作るようにと言ってくれた。アメリカの典型的な感謝祭のディナーへの招待だった。
こうして11月28日に、私はランディと交代したルームメイトと一緒に、ケスター家へ行った。車で迎えてくれたケスター夫人は、私たちを乗せて上機嫌だった。
車は大学町を離れる。町を離れると、田舎の真只中だ。前後左右に畑が広がる。典型的なアメリカの風景だ。畑に埋もれるようにして走っていると、永遠にそこから抜け出すことが出来ないかのように感じる。どこを見ても、一軒の家も見当たらない。4、50分も走っただろうか。車はスピードを落として右折する。その角の所に、鳥の巣箱のような郵便受けが4,5本、殺風景に立っている。「ここが私の家の郵便受けよ。ここまで取りに来るのが面倒でね」
車はそこから更に5分ほど走る。向こうに一軒の家がポツンと建っている。2階屋だ。
家の前には、色とりどりの花が咲いている。家の裏手に回ると、そこには枯れてしまったトマトが疲れたようにうなだれている。あそこからもぎ取っていたのか、ご苦労さん。どんなに励まされたことか。
もう夕方。外の空気は冷たい。中に入ると、いきなり広いリビングルームだ。暖炉が燃えている。アメリカの家に暖炉はつきものだ。
ここの家の暖炉は、マイナス20度、30度の極寒からこの老夫婦を守る。大抵の暖炉は、客が来た時だけ燃やす飾りだ。その命の守護神の前で話をする。ご主人もよく話す。夕食までの1時間、彼の話を聞く。歴史の博士号を持っているだけに、年号がやたらと入る。ピンと来ない。いちいち和暦に直して聞こうとする。もう次の話が始まっている。夕食前にクタクタになる。
ダイニングルームからの香りに誘われて、手伝いに行く。七面鳥が裸で火に当たっている。もうだいぶ出来上がっている。そしてポテト。あまりよく覚えていないが、開拓時代のテレビ劇でよく見かける伝統的なアメリカの御馳走だ。
彼女は、自分の生活に誇りを持っている。果てしなく広がる畑。見渡す限り老夫婦の畑だ。私がニューヨークに行った、ロサンジェルスに行った、と手紙を書くと、必ず、奥さんを自分の家に連れてきなさい、と書いてくる。
この手紙のやり取りは帰国した後も長く続いた。例の3時間ドラマのタイプしてくれたノートを思い出す。紙も同じなら、びっしりと詰めて打ち込んだタイプも同じだ。上記に出した写真は1988年頃に手紙と一緒に送ってくれたものだ。本棚の中から、私を見ていてくれる。
3.試 験
トマトのオバチャン出現
リリリン、リリリン。
トマトのオバチャンからだ。彼女からの電話は短くて30分、長いと1時間を超える。
明日は試験だ。不安だ。特に、その前3週間分の「劇」(ドラマの授業)のうち、最後の3つがさっぱり分からない。ディスカッションで分かったことは、クラスメイト達にも分からないということだ。そこで、図書館でいろいろ調べてみたが収穫はなかった。オバチャンは心配して電話してきたのだった。
『・・・で、今日の3時間半のうち最初の1時間は殆んど何も書けず、ただ茫然として問題を睨んでいました。その間の苦しいことと言ったらありませんでした。
勿論何も書かないで出すわけにもいかないし、そこで1時間くらい経ってから、何か書かなくてはとえっちらおっちら書き始めて残りの2時間半で何とか答えみたいなのを書いてきました』(日付不明 水曜日の夜の第1回試験を受けて)
マイちゃんとブルーブック
『11/13 12:30 (日本11/14 2:30)
今マイちゃんの試験の後、昼食を食べて帰ってきました。ぐったり疲れてしまいました。
(注:マイちゃん=月・水・金10:00~10:50 「ネオクラシシズム」の教授)
この前と比べて実に素晴らしい問題ばかりでした。難しかったという意味です。16ページのテスト用ノート(通称、ブルーブック)にびっしり書いて書いて書き続けました。今日は20分ほど余分に時間をくれたので少々助かりました。でも、自分の持っている100%出せてないのではと思ったりしますが、今更考えてもしようがありません・・・』

『12月26日 22:00 (日本 12・17 12:00)
暫くの間お休み許されたし。ついに今、全ての試験を終了してこの長かった秋の学期が終わりました。3つの試験ともとてもじゃないけど難しかったです。そして心理的にもかなりのプレッシャーの10日間でした。そちらから来る手紙は、「これが着くころは試験も終わってほっとしていることでしょう」みたいなことばかり書いてあったので、イライラしてかなり腹を立てていました。遠いからしょうがないけど。
先週の木曜日(11日)の夜1つ終わりましたが、どう考えても50~60点どまりなので、もしかしたらこの教科は不合格かも知れません。この教科だけは試験が一度きりなので多分ダメでしょう。とにかく歯が立ちませんでした。2時間半かかってわかる部分は書いたけど、ほとんど降参という感じで出してきました。そして本日、マイチャンが1時~3時までと水曜日の分が6時~9時半までというわけです。
マイちゃんのは今まで4回の試験のうち最も難しくて勉強していなかったところから出ましたが、とにかく2時間休まず書き続けました。おかげで手は痛くなるは、肩はこるはで夜の試験が心配でした。ブルーノート24頁殆んどびっしり書きまくってきました。要するに頭に入れたことを全部吐き出してきたというわけです』
小川のせせらぎ
アメリカの学生は、問題用紙をもらうとすぐに書き出す。もらうのと書き始めるのと、ほとんど同時の動作である。私の知る限り、例外はあまりない。
大学では教科ごとに番号が付いている。100番代は主として初級で1年生が、400番代は上級だから主として4年生が選択する教科だ。500番代以上が大学院生というわけだ。この400番代と500番代は同じクラスで行われることが多い。500番代を取る院生には宿題が多くなるか、重い宿題が余分に課せられる。
アメリカでの初めての試験のことだった。それはマイちゃんのクラスの試験だった。マイちゃんのクラスは私にとっては500番代だ。学生数も多く、400番代の学生を合わせると40人ほどだ。その学生たちが、問題を手にすると一斉に書き出した。私はみんなすごいと思った。私は書き出すどころか、問題の意味を正しくとらえようと必死だった。教室中から鉛筆やペンを走らせるさらさらという音が、小川のせせらぎのように聞こえてくる。
ようやく私もペンを手にする。そして書き始める。隣の大学生は、音からして、もう既に3~4ページ目を書いていそうだ。ブルーブックは予めブックストアで購入しておくのだ。
すべてが論文形式だから大変だ。でもマイちゃんは親切だ。各問題の最後に、15分だの、30分だのと書いてある。それ位の時間だと、全問に目が通せますよという目安を示してくれている。初めての試験だから大いに助かった。
マイちゃんは学生の名前を覚える天才だ。そもそも天才的なのだ。イギリスのドクター・ジョンソン学会のアメリカでの会長などをこなす人材なのだ。
彼は答案や宿題を返してくれる時、必ずその人物の席へ行って、机上にきちんと置いてくれる。それだけではない。クラスに持って来る時には、席順に整理されているのである。
クラスの席は決まっているわけではない。教室に早く来た者が4列あるうちの最前列に座ろうとする。自分は一生懸命頑張っているのだと、アピールするためだ。アメリカでは、自分の努力の姿勢を表に出すことは、殊の外重要だ。だから、私は教授たちのオフィスに足繫く通ったのである。
教授は私たち学生より先に来ている。教室が使用中の場合は、私たちより先に廊下で待機している。だから、私たちも早めに教室へ行く。遅刻をするものはほとんどいない。それこそ印象が悪い。で、日が重なるにつれて、自分の好きな席が固定してくるというわけだ。わざと1つずらして座ってみたことがある。勿論、余裕が出来てからだ。みな、一瞬キョロキョロして、仕方なく1つずつずれて座った。
返却された答案を隠すものは1人もいない。この国では、自分は自分、人は人なのだ。右隣の女性はB.「私、Bだったわ」にっこり笑う目はブルーだ。美しい色。不思議な色。優しい色。左隣はC+。なあんだ。つい日本人の感覚でそんな風に思ってしまう。問題用紙をもらった途端に書き始めたこの2人は、いったい何を書いたのだろうなどといらぬお節介だ。これこそ島国根性だ。傲慢だ。
4.火 事
妻からの手紙
「11/19(月) pm 5:15
昨日(日)の午前1時半頃「火事だ!」といいう声でビックリして飛び起き外を見たら、煙が出てくさかったので、てっきりUさんのところかと思って心臓はドキドキ、足はガクガクで、○○(息子の名前)を起こしても起きないので蹴っ飛ばしてやっと目がさめ、△△(娘の名前)はたたき起こし、パジャマのままで外に出ました。
みんあ階段をおりたりかねをならしたりで大騒ぎでしたが、よく見たらA棟のSさんの所でした。寒さが厳しいのと、恐ろしさでふるえましたよ。風も引いていたので家に入って成り行きを見てました。
△△はMさんのご主人やCちゃんと一緒になって階段を走って降りて行くので、必死で止めましたが、○○はA棟と判ったらさっさと布団に入って、又、コトンと寝てしまいました。Sさんの所は全焼です。4階のベランダは真っ黒、3階は水びたしで、家具屋畳のカス等たくさん運び出していましたよ。ほんとにこわいです。ストーブが原因らしいです・・・」
11月18日に私のところに届いた妻からの手紙である。
私は奇妙な、不思議な、わけの分からない気持ちでこれを読んだ。ふと見た遠くの景色が、ずーっと昔みたことがあるような気がしてくる、あの類だ。数日前に、私は極めつけの失敗をしていた。
大学寮の退避訓練
大学寮では、何度か退避訓練があった。何の予告もない。だから初めての時は慌てた。訓練と分かっていても、みな真面目に逃げる。勿論、エレベーターは使わない。日頃通る者の少ない階段が、あっという間に人で溢れる。シャワーを浴びている最中だったのだろう、バスタオルを腰に巻いただけの者までいる。
私は最初、練習だろうと思って勉強を続けていた。廊下がだんだん賑やかになる。まるで週末だ。パーティーの賑やかさは、動きの少ないものだ。しかし、この騒ぎは移動性だ。
そこで窓から下を見下ろす。学生がかなり下に降りている。不安になり、大事なものを身につけて廊下に出る。階段は部屋の真ん前だ。重い扉を開けると、上からどんどん人が降りてくる。真剣に階段を降り正面玄関を出る。その階段を降りると、広い駐車場だ。みんな寮の方を見て、真剣な目つきだ。9月25日の午後3時頃のことだった。

一晩でこの積雪はちょくちょく出現
聞くところによると、女子寮では、この退避訓練が夜中の2時頃にあったそうだ。殆んどみんな寝入っていたから、大変だったようだ。先に目が覚めた者が、寝ている者を起こして回ったり、「火事よ!」と叫んで回ったり・・・。寝ぼけ眼で訳も分からず、皆につられて階段を降りた者もいたらしい。
何しろ真夜中のことだから、みんな夜着のままだったそうだ。ガウンでも身につけていればよいが、そうでなければ、9月末の夜中の空気は寒かったはずだ。手紙を読んでみると、大学のブックストアで買ったジャンパーを、私は10月6日にはもう着ていたほどだ。
これらの退避訓練は、どうやら寮委員会の企画らしい。全部で3回あったが、3回とも秋の学期に実施された。これはアメリカでは、新学期に当たることと無関係ではなかったと思う。
なるから夏にかけては、トーネイドー(竜巻)警報訓練もあった。これは外に出るのではなくて、部屋から廊下に逃げるのである。トーネイドーの恐ろしさを私は知らない。寮の人たちに聞くと、火事より怖いということだ。
日本でも近年、アメリカの巨大トーネイドーのニュース映像や日本での竜巻のニュースも耳にする。
相当前のことだが、当時私が定期購入していた雑誌がある。ナショナルジオグラフィックというアメリカの月刊誌だ。今記念として家の棚に残しているのは下記の画像のものだけだ。あとは全て引っ越し等で処分してしまった。後悔している。
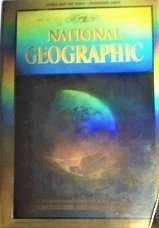
光の宛て具合でキラキラ光る特別仕立て
この月刊誌のいずれかにトーネイドーの写真が掲載されていた。トーネイドーが通過した場所だけ、家が木っ端みじんになっていた。そして、その両脇は何の被害も受けていないのだ。まるで、トーネイドーが作った林道のようだ。
5.火事にまつわる大恥事件
さて、私の失敗は、今思い出しても背筋に汗が出そうなほどのものだった。
11月13日の午後7時半頃、奇しくもその日は金曜日だった。金曜日が私の洗濯日と決めていた。その日はルームメイトも一緒だ。地下に洗濯場がある。洗濯機と乾燥機が5,6台ずつ置いてある。もっとたくさんあったかもしれない。その日は運悪くそのいずれも使用中だった。そこで2人は隣のサンディソンホールへ行くことにした。両手に荷物を持っていた。Tシャツと短パンだったので、外に出るには寒すぎた。自分の寮で洗うつもりだったために軽装だったのである。洗濯を早くすませて、99セント映画に行きたかったので、私は近道をしようと思い立った。
どうしてあんな馬鹿げた愚かなことをしてしまったのか、今でも分からない。やはり、連続する宿題の締め切りとテスト、そして予習とでいささか疲れていたのだろう。判断力が著しく低下していたのだろう。早くすませたいと一途になっていたのかもしれない。
ギラムホールの地下から、うんざりして階段を上る。地下と1階との中間地点に、ドアがある。そこを出ると地上部になる。階段を上りながら目をあげると、そのドアが目に入る。荷物を持ったままの不自由な手で、ドアに手をかける。そのドアが、簡単に開く。
リリリリリリリリリリリリリリリリン
体中から汗がどっと噴き出す。ベルの音が耳に焼き付く。何事だ? 何が起きたのか? 一瞬何のことか分からない。リリリリリリリン。ベルの音がけたたましい。寮全体が騒然としてくる。階段を駆け下りる足音。我に返る。
そうだ。このドアは非常口だった。赤い文字が目に飛び込んでくる。慌てて洗濯物を抱えたまま、フロントへ走る。そこはもう嵐に巻き込まれている。どこから火事が起きたのかと、騒いでいる。何人もの人が、大声で何か言い合っている。どこだ、どこだ、という叫び声だ。逃げ出したくなる。胸が締め付けられるような気持ちだ。とんでもないことになったものだ。
リリリリリリリリン。その間も、けたたましい。フロントを覗き込む。みんな、うるさいといった風だ。お前のことなんか構ってられないという顔つきだ。落ち着いたら相手になってやる、と言わんばかりだ。
聞いてくれ、非常口を開けたんだ。ついうっかりしてたんだ。悪かった。思わず開けてしまったんだ。・・・・冗談じゃないぜ。おい、エレベーターで上の階の者に、間違いだと言ってきてくれ。それから君は、階段だ。寮長はてきぱきと指示する。二度とこんなことをしてくれるなよ。ようやく彼は私の方に顔を向ける。エレベーターに駆け込む者の顔にも、階段へ走る者の顔にも、フロント付近にいる者たちの顔にも、「非難」の2文字。
「アイム テリブリ ソーリー」
「OK。二度と非常口を開けるなよ」
自分よりも10才以上も若い寮長が許してくれる。
階段を使って部屋に戻る者。エレベーターを待つ者。みんなうんざりしているフロントに平静が戻る。私は我に返った。洗濯物を持って、裏のドアからサンディソンホールの地下へと歩く。
ドアを出た途端に、緊張が緩む。ドアのところまでは、まるで13階段だ。一歩一歩重い足取りだ。針の筵だ。走りたいのに我慢して歩く。サンディソンの地下には誰もいない。シーンとした中で、ついさっきのことを思い出して、またゾッとする。
洗濯物を入れてから、クウォーター(25セント貨)を2枚入れる。水が入る音。じっとその音に耳を傾ける。その騒音に勇気づけられて、漸くしゃべりだす。「びっくりしたなぁ」「大恥だ」そう言って大笑いする。安堵感、解放感。
洗濯には小一時間かかる。その間、さっきのことを何度も話した。話しては笑った。機械の音が大きいので、話す声も大きい。乾燥機が止まると、再び静寂が戻った。2人の話も一緒にストップした。
洗濯物をたたんで、階段を上がる。寮の階段は人を暗くする。外の賑やかさと反比例する静けさだ。昼間でも薄暗い。人に会わないで済むという利点もある。
サンディソンホールを出ると、外はもう薄暗く、寒い。気温も、日によっては零度Cに近くなる。Tシャツ、短パンの者にとって、この寒さは厳しい。走ればほんの30秒のギラムホールが遠い。足取りが重いからだ。部屋に戻るには、フロントの前を通らなければならない。寮に入ったらすぐ速足だ。エレベーターなどとんでもない。それで、階段を選ぶ。静かな暗い階段は、まさに救いの神だ。6階に上がってドアを開ければ、目の前に604号室のドアがある。部屋に入ると、また開放感。結局、その日は99セント映画を断念したのだった。私は勉強を始めた。勉強は全てを忘れさせてくれた。
6.またもや火災報知器が・・・
「留学中の事件の数々 その2」につづく・・・。
完
(ここで一応、この記事は完結ということにする。そして「留学中の事件の数々」は「その1」と「その2」にする。これからは、続編として「留学中の事件の数々 その2」を執筆していくことになる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
