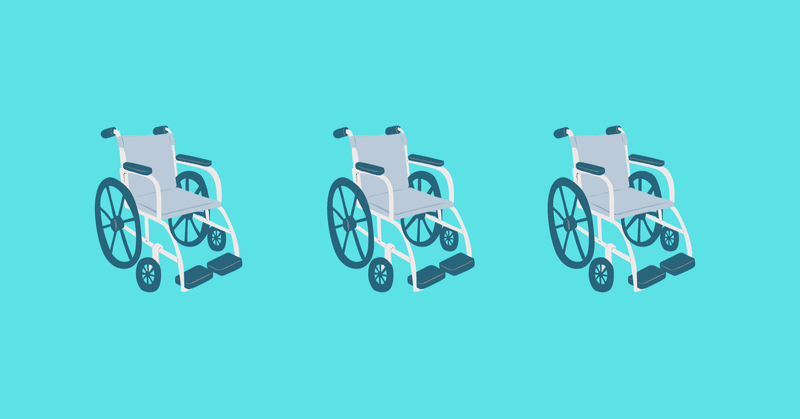
介護業界の最新事情「IoTデバイスを活用した尊厳ある介護を目指すトリプル・ダブリュー・ジャパン」
※本記事は月間企業診断2021年6月号への拙稿を基に出版社に許可を得て掲載しております。
※※つい最近がっちりマンデーにも出てましたね!
1.介護業界の市場動向
厚生労働省が公表している介護保険事業状況報告では、65歳以上の第一号被保険者数が2000年4月末2,165万人から2020年4月末3,557万人と1.6倍に増加している。また、要介護(要支援)認定者は、2000年4月末218万人から2020年4月末669万人まで3.1倍まで拡大している。*1
介護保険制度が2000年に創設されてから20年以上経過し、現在高齢者の介護になくてはならない制度として定着している。今後、さらなる高齢化にともない介護サービスを必要とする人はますます増えていくため、介護サービス市場は拡大が続く見通しである。
そもそも介護保険制度とは、高齢化の進展にともなう要介護者の増加や介護期間の長期化に社会全体で対応するためにスタート。40歳以上の国民が納めた保険料と国や地方自治体の税金を5割ずつの割合で財源として確保し、介護サービスを提供するという制度になっている。40歳以上の人は全て加入義務があり、この財源を活用することで利用者は1割程度の金額を負担するだけでさまざまな介護サービスを利用することができる。
65歳以上は「第一号被保険者」となり、要介護(要支援)認定を受けると介護給付を受けることができる。また、40歳〜64歳までは「第二号被保険者」となり、末期がんや関節リウマチ、初老期における認知症など特定疾病に該当した場合に、要介護認定を受ければ介護給付を受けられる仕組みとなっている。
介護需要が増大する一方、これらは社会保障費の増加につながり、国や地方自治体の財政を圧迫している。この20年ほどの間に、介護保険給付費・地域支援事業費は2000年3.2兆円から2017年9.8兆円まで大幅に増加。*2今後も高齢化にともない社会保障費は上昇し続ける見込みであり、国としてもその増え続ける負担に耐えられる余地は少ない。そのため、3年ごとに介護報酬の改訂が行われているが、事業者に支払われる介護報酬単価の大幅な増加は今後も見込みにくい。
すでに近年、介護報酬単価は抑制される傾向にあり、社会福祉法人は全体の3割程度、通所介護(デイサービス)・訪問介護事業者は全体の4割程度まで赤字法人となっている。*3
また、人手不足も顕著だ。低賃金・重労働のイメージが強く、2020年12月の介護サービスの職業における有効求人倍率は3.99倍と産業全体の1.03倍程度に比べて非常に高くなっている。*4団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となる2025年には、介護人材が30万人以上不足すると見込まれている。*5
介護事業所は施設ごとに介護職員や看護職員などの人員配置基準が定められており、それを下回った場合には介護報酬の減額等のペナルティを受けることになる。人手不足がまさに企業の死活問題となってしまうのだ。それを避けるため人材派遣会社へ頼り、業務委託費が増加し経営が圧迫されるケースもある。
2.IoTによる排尿予知システム
こうした介護業界の課題にICTやIoTを活用し業務の効率化を行うことにより、生産性の向上や従業員の負担の軽減を目指す動きが増えている。世界に先駆けて排尿を予知するウェアラブルIoTデバイス「DFree」を開発したトリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社もその1社だ。*6代表取締役中西敦士氏は、排泄にまつわる課題をハードウェアで解決するため、日本国内で大人用オムツが子供用オムツの売上を逆転し、少子高齢化が大きな社会問題化としてクローズアップされた時期でもある2015年に起業。現在は介護施設などの法人向けと個人向けに販売している。
「DFree」の仕組みとしては、センサーを下腹部に装着し超音波で膀胱の変化を捉え、溜まった尿を検知する。そこでどれくらいの量が溜まっているのか1~10段階の数値で評価し、Bluetoothでスマートフォンやタブレットにデータを送信。そして個人ごとの設定に合わせて、排尿のタイミングを通知する仕組みとなっている。
数値化により、10段階のうち9を表示しているのに「全然トイレに行きたいと思わない」という人もいれば、まだ3しか表示されていないのに「我慢できない」という人もいることがわかるようになる。それにより、ぎりぎりでお漏らししてしまう人には早めにトイレに行くことを促せ、あまり溜まってないのに頻繁にトイレに行く人には、もう少し溜めてみようとトレーニングすることができる。
同社調査では、「DFree」導入によりトイレ排尿率23.7%増加、失禁回数46.8%減少、排泄関連業務22.5%減少といった大きな効果が現れている。*7これは、介護される側にとっては、トイレでの排泄回数を増やしたい、また頻尿や尿漏れを少なくしたいという悩みを解消していることを意味する。特に排泄トラブルがあるとつらい思いをすることがあり、それが日常的になると自尊心すら失うことになりかねない重大な問題であるため、これらの悩みを解消することは介護される側にとって大きな価値を生み出す。
また、介護する側にとっても、排泄関連業務の減少というメリットがある。トイレのタイミングを適切に把握することができるため、オムツの取り替えが減ること、トイレへの介助回数の削減など介護負担の軽減につながる。現場からは「今まで1〜2時間おきにトイレに誘導するケアを行なっていたが、利用者さんのタイミングで排泄ケアをできるようになり画期的」との声も上がる。人手不足に悩む介護業界にとって、「DFree」は有効な業務効率化の一つの手段となっている。
また、2018年の介護報酬改訂により排泄支援加算が創設された。これにより、排泄状態が改善する支援を行なった事業者が基本介護報酬とは別に加算額を取得できるようになった。現状ではまだこの加算に対する体制を整えられないことや、金額が低いことを理由に加算算定しない企業も多い。しかし、2021年の介護報酬改訂ではこの制度が強化されたため、これから加算算定企業は増えていく見込みであり、同社にとっては追い風となるだろう。
3.徹底した利用者目線から尊厳ある介護の実現
これまで説明してきたように、今後の介護業界は少子高齢化が進む中で人材不足になり、介護報酬も上がりづらい状況が続く。こうした状況の中、業務の効率化により生産性を向上させることが事業者にとって必須であり、そのための手段としてICTやIoTの導入が重要である。
ただし、こうした新しい機器は経営層にとってはコストに対する効果が見えにくいことから導入を断念するケースや、現場従業員からはタブレットなどの機器に不慣れであることから反発されるケースもある。そのため、普及に向けた重要な鍵は、ただ機器を導入するのではなく、サポート体制を整備し、導入後にシステムを利用できる人材の育成もあわせて進めることだ。
また、介護する側の業務の効率化につながるのと同時に、徹底的に利用者目線から商品・サービスを磨くことも大切である。同社では「バイタルテクノロジーで”Live your life”を実現する」というビジョンのもと、尊厳を保ち続ける社会に寄与することを掲げ、事業を展開している。オムツ以外の選択肢を増やし、トイレに悩むことなく元気に外出することができるのだ。この姿勢により、今まで一律に排泄ケアしていた状況から、個々の人に合わせて排泄ケアを行うことができるようになり始めている。
長寿社会となるこれからの高齢者向けビジネスでは、「健康で長生きできる」、「最後まで自分らしく生きることができる」という人間の本質的価値観に応えられる企業が今まで以上に支持されていく。当社の目指す尊厳ある介護は、まさにこうした価値観に基づいており、今後ますます必要とされるだろう。
これまで介護事業所は、サービス利用者をケアマネージャー(介護支援専門員)からの紹介を中心に獲得してきた。そのためケアマネージャーとの関係を構築することが稼働率向上のためには大切であった。もちろん今後も重要ではあり続けるが、今後はネットで自ら情報を検索して介護事業所を選ぶケースも増えるだろう。その際に徹底した利用者目線のサービスを提供している企業が選ばれるようになるはずだ。同社が提供する仕組みは、介護する側にもされる側にも大きな価値を生み出している。同社のようなサービスが介護業界をどのように変化させていくのか、今後の動向に注目していきたい。
*1厚生労働省 介護保険事業状況報告月報
*2厚生労働省「介護分野をめぐる状況について」
*3独立行政法人福祉医療機構 経営分析参考指標
*4厚生労働省 一般職業紹介状況
*5厚生労働省 「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計について」
*6https://www-biz.co/
*7https://dfree.biz/professional/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
