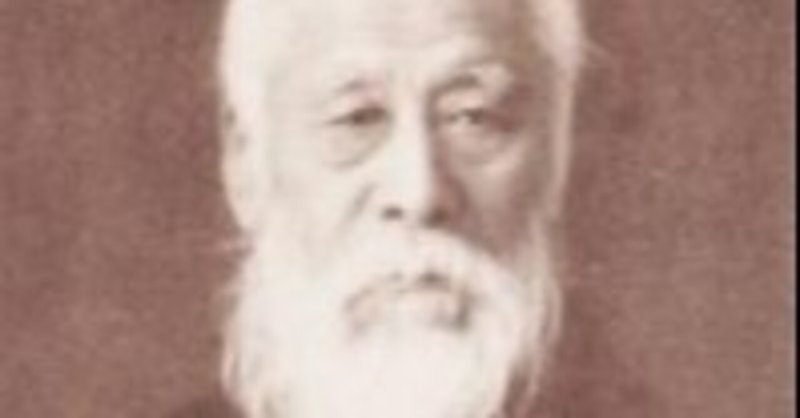
正直は最良の商略。ノリタケ創業者の森村市左衛門がキリスト教徒になった理由
日本には、宗教の理念をもって経営にあたり、事業に成功した実業家は少なくありません。東京大学名誉教授で経済史学者の土屋喬雄(つちやたかお)(1896~1988)は「渋沢栄一は孔孟(孔子と孟子)の教えを、森村市左衛門はキリストの精神を、伊藤忠兵衛は釈迦の心をそれぞれ事業経営のよりどころとした」と語っています。
渋沢栄一と儒教の関係性について紹介した第1回に引き続き、今回は日本陶器の創業者・森村市左衛門(もりむらいちざえもん)とキリスト教の関係性についてご紹介します。
ノリタケの創業者・森村市左衛門とは
森村市左衛門(1839~1919)は日本陶器(現・ノリタケカンパニーリミテド)の創業者です。ビジネスだけではなく教育にも力を入れ、学校・森村学園そして教育や学術を支援する森村豊明会の創業者でもあります。森村は社会事業にあたって渋沢栄一と行動を共にすることが多く、2人は「明治大正期のメセナ(文化支援)の両雄」と評されます。
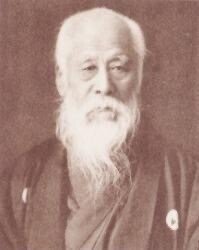
森村市左衛門(1839~1919)
森村は1839(天保10)年、江戸の商家に生まれました。後に貿易商を設立していますが、そのきっかけは福沢諭吉との出会いでした。
当時、福沢は遣米使節の一員として咸臨丸(かんりんまる)で帰国して間もない時で、江戸で蘭学塾(現・慶應義塾)を開いていました。森村は福沢から、今後外国との貿易が盛んになるとの説明を受けました。そこで森村は貿易商開設を目指し、必要な語学や実務を学ぶため福沢の指導を仰ぎ、さらに弟・豊を福沢の塾に入れました。豊の卒業後、1876(明治9)年に兄弟で貿易商・森村組を創業しました。
設立当初は、「森村組には主人もなし雇人もなし」という方針でした。ただし会社が拡大するとこの方針では不都合が生じるため、職制や規則が制定されています。
森村は事業を通して、ヨーロッパの陶磁器を知りました。そこで、日本でも美しい洋食器を作りたいと考え、日本陶器を創業しました。ここでは社員のため夜学校が併設されていました。
同社は後に、事業ごとに分社しました。そうして設立されたのが、東洋陶器(現・TOTO)、日本碍子(現・日本ガイシ)、大倉陶園などです。
花を咲かせるより人を育てる
森村はビジネスに成功したのですが、教育にも力を入れていました。実業界での経験から、人材育成の重要性を知ったからです。
そこで教育や学術などを支えることを目的として、1901(明治34)年に森村豊明会を設立しました(会の名称は、森村市左衛門の弟・豊と長男・明六に因んでいます)。この会は、さまざまな学校に多額の寄付をしてきました。その第一号が、日本女子大学附属豊明(ほうめい)小学校・幼稚園です(この名前は森村豊明会に由来します)。
ここが最初だったのは、当時は「女性に学問は不要」という考えがある中、森村は「女子の教育を疎(おろそ)かにする国は繁栄しない。文明国になるには女子教育が欠かせない」という信念を持っていたからです。これにとどまらず、森村は渋沢栄一や大隈重信と共に、女子教育推進のための講演会をさまざまな地域で開いています。
さらに、森村は福沢諭吉とも共同で学術への支援を行っており、北里柴三郎の伝染病研究所(現・北里研究所)設立の資金を提供しています。
森村は他の学校を支援するだけでなく、自身でも学校を設立しました。そのきっかけは、森村邸を訪れた甲賀ふじ(日本女子大学附属豊明幼稚園主任)が、花を愛ながら述べた言葉「美しい花を咲かせるのもいいですが、生きた人間を作ったほうがどれほど楽しいかわかりません」でした。
そこで森村は「花を咲かせるより生きた人間を育てる」との決意のもと、1910(明治43)年、高輪(東京都港区)の私邸に私立南高輪尋常小学校・幼稚園を開きました。これは後に森村学園と改称し、中学校と高校を設置しています。設立以来高輪にありましたが、1978(昭和53)年に長津田(ながつた)(横浜市緑区)に移転し、現在に至ります。なお、創立者・森村市左衛門は開校後にキリスト教徒になっていますが、この学校に特定の宗教はありません。
森村学園の校訓は、「正直・親切・勤勉」です。この校訓は、森村市左衛門の経営の理念に通じるものがあります。

横浜市緑区にある森村学園
正直は最良の商略
森村市左衛門は「正直は最良の商略」と主張しています。そして、「自分を修養していくには宗教の助けを借りなければならない」と考えていました。そこで、まずは仏教を学びました。やがて森村は、真言宗の僧・渡辺雲照(わたなべうんしょう)に教えを受けるようになりました。渡辺は戒律を重んじ、森村はその徳に感化されたと語っています。
ところが1909(明治42)年に渡辺が亡くなります。その後、森村はキリスト教に関心を示すようになり、独学しました。そして1913(大正2)年、キリスト教徒になりました。ただし、キリスト教徒になったとは言ってもどこの教会にも属さず、洗礼を受けるつもりはないと述べています(実際には亡くなる2年前に洗礼を受けていますが、その相手はどの教会にも属さない、聖職者ではない人物です)。
森村がキリスト教徒になったきっかけは、ヨーロッパへ渡った時の経験です。滞在中、学校へ十分に通っていたとは思えないような人が、礼儀正しく、大金や貴重品を預けても間違いやごまかしがないことに感銘を受けました。このような、「本分をつくす」という態度は、学校ではなくキリスト教の信仰によって養われたと、森村は考えたのです。
さて、森村が制定した「我社の精神」は6項目あります。1909(明治42)年に制定され、1919(大正8)年に改訂されました。改訂版の各項目からそれぞれ一部を抜き出しますと、次のようになります。
「海外貿易は、四海兄弟、万国平和、共同、幸福、人道のため」
「国民の発達するを目的とす」
「約束を違えざる事」
「虚言、慢心、怒、驕、怠を慎む事」
「和合協力する功果、金銭などの及ぶ所にあらず」
「神の道を信じ万事を経営する自覚を確信すべし」
私見ですが、森村が訴えたかったのは前の5項目であって、その精神を養うのにふさわしいと判断したのがキリスト教だったということなのでしょう。
森村もまた、ビジネスは利益を上げればそれでよいというものではなく、人々ひいては世界の平和と発展に貢献するべきものでした。教育や学術の支援に力を入れていたのは、そのためでしょう。
【参考文献】
森村豊明会編『儲けんと思わば天に貸せ』(社会思想社)
砂川幸雄著『森村市左衛門 無欲の生涯』(草思社)
『森村学園の100年』(森村学園)
(文/編集委員・多田 修)
第1回 「渋沢栄一の成功の裏には、儒教の存在があった? ビジネスと宗教の関係性」はこちらからどうぞ
※本記事は『築地本願寺新報』9月号に掲載された記事を転載したものです。本誌やバックナンバーをご覧になりたい方はこちらからどうぞ。
