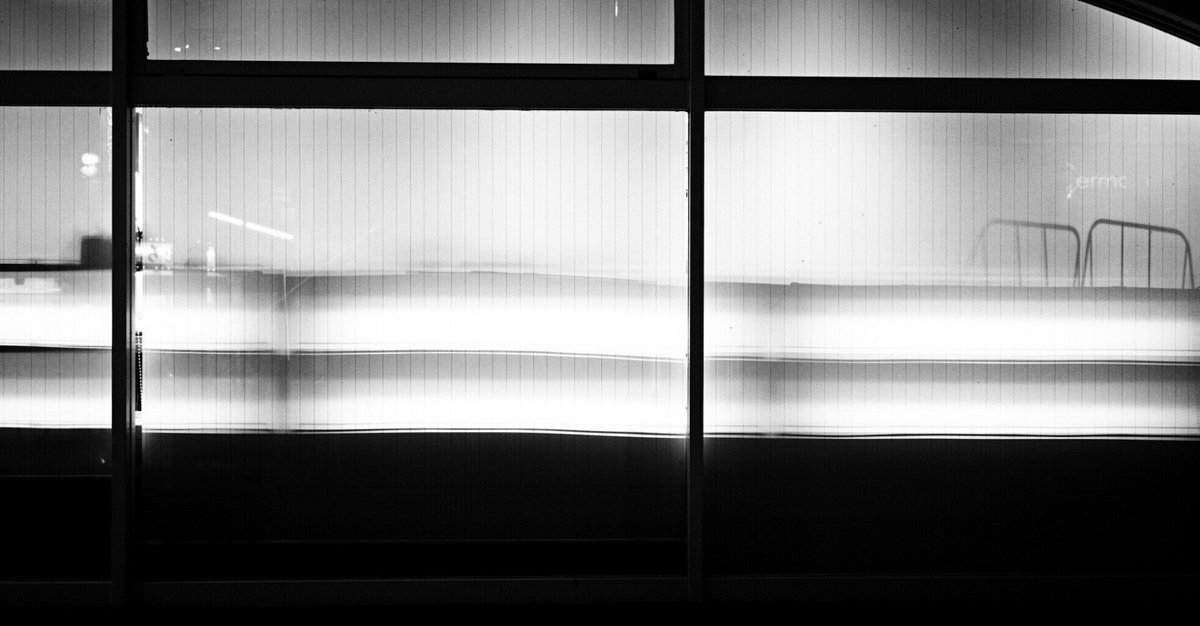
社会学って何ですか? 第8回『社会学史』⑧ ―社会学のアメリカへの移動/パーソンズ(前半)
今回からは、第一次世界大戦以降の社会学の潮流(『社会学史』ではⅢ章に対応。)を扱う。まずは、『社会学史』でこの章のはじめに解説されている、この時代の社会学の前提についてまとめる。
◆ヨーロッパからアメリカへ
前回記事の最後でも述べたが、この時代の社会学でまずおさえておくべきことは、その中心がヨーロッパからアメリカへと移ったことだ。主な原因は、ナチスの迫害から逃れるため、フランクフルト学派(今後の回で紹介、ホルクハイマーやアドルノなど)など、ユダヤ人の学者がアメリカへと亡命したこと、また政治・経済・文化的な覇権の移動、だ。
アメリカは、三つの時期に分かれてやってきた移民から構成される。詳しくアメリカ史を調べていただければと思うが、アメリカの社会学はこのうちの第二波の研究から始まった。その初の成果が『ヨーロッパとアメリカにおけるポーランド農民』(『ポーランド農民』)だ。アメリカ人社会学者トマスと共著者でポーランド人のナズニエスツキが、ポーランド現地農民と移民の実態を調査した書籍だ。
『ポーランド農民』は、膨大な一次資料を収集して研究するという新しい実証研究の方法の確立、および「トマスの定理」というアイデアの2点に意義がある。「トマスの定理」は、状況が現実となるのは、人がある状況を現実として定義したからだ、とする。
アメリカの初期の社会学者の多くはシカゴ大学(※シカゴは、第二波移民を代表する都市だった。)から登場し、シカゴ学派と呼ばれた。トマスや、ジンメルを出発点とする都市社会学において著名なパーク(「人間生態学」)とバージェス(「同心円モデル」)、そしてパーソンズがその一員だ。
と、前置きが長くなったが、これで社会学の中心がアメリカへ移り、そこでどういった研究がスタートしたのか、押さえられただろう。個人的には、『社会学史』の読者を置いていかない感じが好きだ。ここから、この時期の社会学者の代表であるパーソンズについてまとめていく。
◆パーソンズ

・パーソンズのアイデアの中心は、人間の主体性を重視する「主意主義的行為理論」だ。
・まず、パーソンズは功利主義を否定していた。功利主義は、個人主義、合理性、経験主義、そして目的のランダムネスを特徴とする。そして、功利主義は、目的はランダムで、個人の選好により、価値合理性を持ち合わせない。これでは、「ホッブズ問題」、つまり自然状態を解消できない、とされた。
・『社会的行為の構造』は、功利主義の代表であるアルフレッド・マーシャル、パレート最適の提唱者でありながらも人間の非論理的行為(「残基」)にも着目したヴィルフレド・パレート、デュルケームを取り上げ、彼らを「実証主義」とした。そして、それに対するヴェーバーを「理念主義」とした。パーソンズはヴェーバーの、人間の行為における理念や価値といった側面への言及を評価した。パーソンズの理論は、広いベースで人間の行為を捉え、動機や感情だけでなく社会的に共有された価値・規範・役割を重視し、行為の受動性・能動性の両面を視界に収めていた。
・パーソンズは、「行為の準拠枠(action frame of reference)」を提唱した。『社会システム』で、パーソンズは行為者は客体への関心、「指向」を持つが、これは欲求の充足を期待する「動機指向」と文化的な価値の実現を期待する「価値指向」に分類される。さらに、2つの指向それぞれに対して「認知的」「カセクシス的」「評価的」アスペクトを持つ、とした。パーソンズは、共通の価値が行為者の学習(「社会化」)を通じ欲求の一部となる=「内面化」し、その価値が社会システムの中で正統性とサンクション(報酬と制裁)を付与される=「制度化」する、ことで、社会秩序が形成される、と結論付けた。
新しい用語が増えてきたので今回はこの辺で。次回はこの「内面化」の根拠について「構造―機能理論」を通してまとめ、それに対する批判もみていく。
参考文献:
大澤真幸 (2019) 『社会学史』 講談社
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
