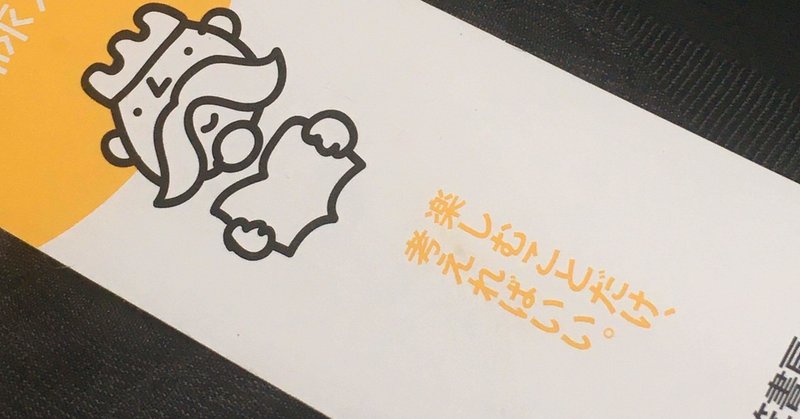
「本嫌い」だと思ってた
母は勉強大好き、本大好き。
時代もあって「女だから」と学校に行かせてもらえず、結婚後に学校へ行くほど勉強が好きだった。
二人姉妹の姉は、本の虫。
本が好きすぎて、お金が入れば本を買い、時間があれば週に10冊も読み、仕事も出版社に入るほどである。
そんな母と姉を持つ私は、
幼少期より「あなたは本が嫌いだから」と言われてきた。
「本を読むの嫌いだもんね」
「まだ読めてないの?苦手なら読まなくていいよ」
その言葉を信じて、何十年もわたしは「本嫌い」「活字嫌い」を演じてきた。
数年前。
私は「毒親」という言葉に出会い、そこから「スキーマ療法」を少しずつ学び始めた。
そして、親や周りに与えられた自身のイメージが、本当にそうだったのか?疑問を持ち始めたのである。
本当に私は「本嫌い」だったのだろうか?
幼少期。
姉は初めての子ども&両祖父母にとって初孫で、沢山の新しい本や玩具が与えられた。
私は2番目なので、全て姉の「お古」であった。
姉の物は私のものではない。
だから「私のための何か」でなくてはいけなかったが、
共働きで家庭内不和(DV不倫)、曽祖母の介護が重なった家庭内では、2人目の娘に気を配る余裕など誰も無かったのである。
ある日、母と姉と3人で本屋に行った。
本好きの母は「2人とも、今日は好きな本を1冊買ってあげるから選びなさい」
本を読みなれた姉は、自分の読める1冊を選び、
私は絵付きの辞典を選んだ。
すると母は「これは難しいから、あなたには読めないわよ。他を選びなさい。」と言い、私の本は却下された。
(最近になって母に聞くと、思ったより高い本を選んだので却下したそう)
仕方なく私は文字の少ない絵の綺麗な絵本を選び買ってもらった。
初めての自分の本。
今でも覚えている。
『小さな池 litle pond』という文字の少ない絵本。
小さな池に風が吹いたり、鳥が来たり、綺麗で不思議な話。
絵が綺麗で、幼い自分でも読める。
毎日のように、何度も何度も、壊れないように大切に…この絵本を読み直した。
そうこうしていると、
「あなたは本が嫌いだから、絵本ばかり読むわね」と。
こうして私に「本嫌い」のレッテルが貼られたのであった。
「本嫌い」のレッテルが貼られていても、普通に文字は読める訳で。
中学生にもなると、実は自分で本を買い読むようになっていた。
よしもとばななさんにハマってほとんど読んでいたし、宮沢賢治は童話から小説まで読み、読むペースが遅いなりに何ヶ月もかけて長編小説も読んでいた。
また、家庭用パソコンが普及し始めた頃で、夜中にパソコン部屋に忍び込んでは自分の考えた小説を書いていた。
書きかけの小説が原稿用紙35枚を過ぎた頃。受験戦争が始まり塾へ通ったりで小説は書けなくなってしまった。
保存したフロッピーディスクは探せばあるかもしれないが、再生するものがない時代。
自分ではよく書けていたと思うだけに、少し勿体ない。
はてさて。
大学生になると、歌(声楽)の世界に猛進する私。
歌は実技ではあるが、身体構造学であったりもする。卒論もある為、大学の図書館にある関連本はほとんど全て読破した。(読んだからといって覚えてはいない)
海外や今は亡き先達から学べる…本はとても優れたツールである。
もちろん師事していた先生方の力が大きいところであるが、大学時代の成長は本からの学びも大きかった。
こうして思い出すと、本を読みなれていないだけで「本嫌い」とは全く思えない。
本が嫌いというよりも、年齢や環境で本が読めなかったり、
子どもは子どもで気を遣って言えなかったところもある。
よく考えると、
私は本ではなく「誰かのもの」が嫌いで、私だけのもの(本や周りとの時間)が欲しかっただけかもしれない。
「本嫌い」の暗示によって、
自身が本嫌いではない、むしろ好きなことに気付くのに、大変に時間がかかってしまった。
当時の父母や周りの苦労も理解できる年齢になったが、
父母や周りが出来なかった分、今、私は好きな本を読み学ぶ。
#コラム #エッセイ #思い出 #毒親 #読書
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
