
個人の信条としての「清貧」は尊いと思うけど、経済政策や政治理念としては「大惨事」を招きかねない:読書録「自由と成長の経済学」
・自由と成長の経済学 「人新世」と「脱成長コミュニズム」の罠
著者:柿埜真吾
出版:PHP新書(Kindle版)
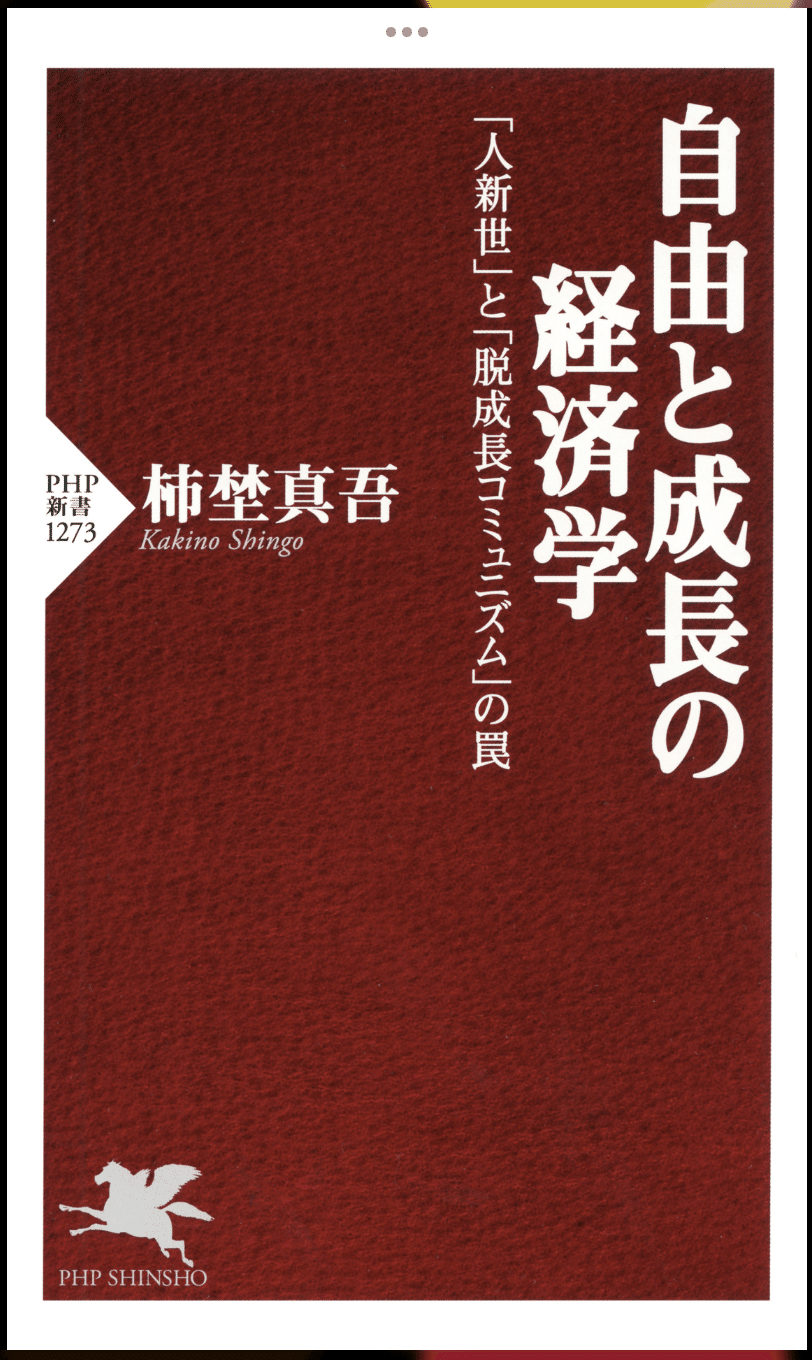
「脱成長」を主張する斎藤幸平氏への反論本。
清々しいまでに「新自由主義」の立場から「脱成長」「新マルクス主義」を否定しています。
ここまでフリードマンやハイエクの主張を肯定的に打ち出してくる作品は久しぶりに読んだな〜って印象です。
元々は井上純一さんの「逆資本論」で、斎藤幸平さんの主張を全否定した本として紹介されてるのを見て読んでみたんですけどね。

(ちなみに「逆資本論」は、中国人の奥さんをもらって、そのホノボノ日常漫画を描かれていた井上さんが、なぜか経済本をシリーズで出されるようになった作品の一つ。
MMTを支持する井上さんが共産主義を全否定しつつw、「現状への異議申し立て」をするという点においてマルクスを評価するという作品です)
まあ、どうですかね〜。
作品としては「脱成長論」に見え隠れする「?」な部分に徹底的に突っ込んでるってとこでしょうか。
端的に言えば、
「いや、それって全体主義・統制経済になりましょうって話じゃないの?」
「二十世紀をかけて<それは上手くいかない>って実例を、惨憺たる被害のもとに積み上げてきたのに、今更そこに回帰しようってぇの?」
って主張。
もちろん「脱成長」サイドにも反論はあるんだろうけど(「ソ連や中国はマルクスのめざした社会主義国家・共産主義国家とは違う」とか)、歴史の現実を突きつけられるとあんまり賛同できない。
半端ない過去の悲劇を前にして、その<理念>に賭ける気にはなれないな…ってのが正直なところです。
もっとも本書の主張にも「どうかな?」と思うとこはあって、その第一は「格差・貧困」への目線。
「長期的にはならされていく」
ってことかもしれませんが、ケインズの言う通り、
「長期的にはみんな死んでいる」。
目の前の<問題>として、「格差・貧困」に<対処>していくことは必要だと僕は思います。
<理念>でドウコウするんじゃなくて、目の前の問題に対処していくという視点で、です。
そういう意味で井上純一さんは「グリーンディール政策」を掲げます。
本書の作者は気候変動対応に対しては懐疑的なスタンスなんですが、井上さんはそういう視点じゃなくて、「目の前にある経済状況への対処」として「グリーンディール」を取り上げているんですよね。(ケインズの言う「穴掘り」…までシニカルじゃないかけど)
僕のスタンスはそっちに近いですかね。
全体主義・独裁国家は勘弁。
でも新自由主義にも振りられても困る。
資本主義・民主主義を顕示しつつ、表出する不具合には対処していく「ほどほど」の新自由主義。
そんなところかしらんw。
「脱成長」とか「清貧」とか「ミニマリズム」とか、<個人>として掲げる分には良いんですよ。
僕もそう言うスタンスには賛同する部分があるし、それを貫徹する人には尊敬の念も描きます。
でもそれを<他人>(自分以外の人間)に押し付けちゃいかん。
ましてや経済政策や統治理念としてそれを国民に押し付けるようになったら…それは<独裁>でしょう。
その気配が「脱成長」にはあるのだ…と言うのが本書が言いたいことじゃないでしょうか・
チョット激しいけどw。
「掲げる理念」は理念として、それを多様な考えを持つ人々がいる中で、どうやって実現させていくか。
現実を変えていくと言う実利の部分を大切にして、どういう妥協点を、どう言うスタンスで求めていくか。
それこそが重要なのだと、「入管法改正」をめぐる立憲内部のガタガタなんかを垣間見て思います。
大きな理念としての「脱成長」ってのは、経済理念としては成立し得ないと思うけど(それは歴史が証明している)、個人の心情や、それを反映したコミュニティの方向性には組み込むことができる<かも>しれない。
そう言うとこじゃないかな…と思ったりします。
「ほどほどの」新自由主義。
結構日本は上手くやって行くんじゃないかと思ったりもするんですけど、甘いかなw。
#読書感想文
#自由と成長の経済学
#柿埜真吾
#PHP研究所
#kindle
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
