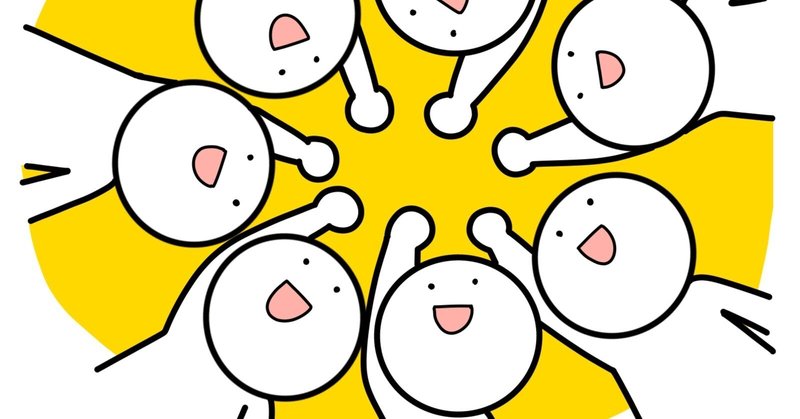
#9 チーム学校はどうなっていく?
平成28年、学校のマネジメント強化策として文科省から発信された「チーム学校」論。
私自身、この30年間、学校改革チームの一員として大小さまざまな高校改革に携わり、生意気にもトップに対して文句や不満を言ってきたが、自分がトップに立った途端、これがなかなか簡単じゃないぞ、という思いに駆られ、改革に伴う「改革の不条理」を味わってきた。
ほんの数年前まで、「意識改革、組織改革しないと、学校の再編統合が起こるぞー!」「来るぞ、来るぞー!」と、職員会議や校内研修会のたびに言ってきた。
あまりにもしつこく言っていたので、先生方は「ああ、あいつまた “オオカミ少年” みたいなこと言っているぞ」と思っていたに違いない。
大切な話は数よりも、根拠あるデータと内容とインパクトが大切なんだと今になって思う愚かさよ。
期せずして、なんと退職した年に再編統合が報道発表され驚いた。
■反作用としてのチーム解体
長きにわたり特殊な組織文化を形成してきた学校教育である。
今後、民間とは異なるマネジメトの概念は根付くのだろうか。
6年前、「チーム学校」が発表されて間もなく、ニュースで文部科学大臣が省内全職員に訓辞する映像が流れた。
学校にチーム概念を浸透させるためには、親である文科省が率先垂範して「チーム文科でいきましょう!」という意気込みだったのだろう。
個人的な感想になるが、あの当時、閣僚や国会議員の不規則発言や不正・不祥事、疑惑が続いていただけに、省庁の「信頼回復」という言葉が世間に空しく響いたような気がするのだ。
高級官僚の皆さんは非常に有能で誠実に仕事をしている方だってたくさんいるはずだ。
各省庁とも政治絡みとはいえ様々なことを忖度しながら、国民に理解されないような偏執的な結束力を発揮し、「チーム省庁」の概念を自ら壊しているような状況が続くと、チーム学校論は“チーム解体”の方向へ向かうのではないかという不安がよぎるのである。
欧米からなだれ込んできた新自由主義的な経済を基盤にした教育モデルによって、「自己責任」や「自立」が過度に強調されてきた。
それもうまくいかないぞということになり、有効な代替案も示されないまま、結局は各学校の自助努力に委ねられてきた公教育である。
そこへもって「働き方改革だ!」「チーム力で乗り越えよ!」だ。
公教育というのは、公費(税金)で運営されており、学校の設置者である育委員会が、いじめ問題や教職員の不祥事でオタオタすると、途端に「社会的な役割を果たしていない」と糾弾される始末だ。
学校自身、何か大胆な改革を断行しようとアイディアを創出しても、お上(文科省や教育委員会)がOKを出してくれないと、カネもヒトも付かない。
国のヒモ付き研究開発事業は、全国のすべての学校にまんべんなく当たるわけではない。
その他大勢の学校は、研究指定校の実践を見倣って「後に続け!」(カネは配当しないけどね!)である。
モデル校に選ばれれば、数百万円から数千万円単位の予算が配当され、それはそれでありがたいのだが、研究期間終了と同時にカネは付かなくなる。
金の切れ目が縁の切れ目ではあるが、そこから先が学校の腕の見せ所だとも言える。
しかし、文科省の力なんぞ借りずに学校を改革している事例は徐々に増えている。
カネがないことを嘆かず、なおかつトップダウン方式の「受け身」にならず、手持ちの人的資源で何ができるかを徹底的に考え、実行に移した組織は強いということを証明してくれている。

ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の理念でもあるESDや SGDs に代表される教育の連続性・持続性、あるいは反復性・集団性等々を網羅した教育活動は、ある種、非効率な活動も織り込みながら、10 年先、20 年先、もっと言えば100年先の成果を期待しながら取り組んでいるのである。
カネを付けてやるから、チーム一丸となって数年以内に目に見える結果を出しないさい!そしてそのノウハウを全国に発表しなさい!!
「カネは出してやったじゃん」というアリバイづくりか。
働き方改革を後ろ盾に「チーム学校」という合い言葉が強迫観念として浸透していくと、チームは解体の方向へ傾き兼ねない。

みんな組織的な教育力の向上を願っているのは間違いない。
肝心の現場が疲弊し、教員志願者が減っているという悲しい不幸な時代が続いている。
依然として学校のマネジメント機能の強化、教育力の向上、教員の資質向上が叫ばれている。
それ自体に異論はない。
資質に優れた個人プレイヤーはたくさんいる。
見方を変えれば、仕事が属人化しているということである。
組織マネジメントが機能して、後続のプレイヤーが次々と養成されていくならいいが、人材育成がされないままスタープレイヤーが他校へ異動すれば、組織は劣化していく。
それが現実だ。

教員定数、教員加配に劇的な改善が見られなければ、チーム学校論は夢のまた夢となってしまう。
法制化された「働き方改革」との連動は本当に実現するのだろうか。
授業料無償化という形で国は生徒・学生のことを慮っていて、もちろんそれそれでいいことなのだが、その分、教員の待遇は後回しになってきた。
2022 年現在、中教審が有能な教員確保の方策として、教育実習と教員採用試験の前倒しを提案している。
それは大学の教員養成課程にもいろんな波が押し寄せることを意味している。
■直近の実態
12月22日、日本教職員組合が、教員の働き方に関する実態調査の結果を公表し、令和元年に教職員給与特別措置法(給特法)が改正された後も長時間労働が改善されていない実態を明らかにした。
1日の平均在校等時間は10時間35分で、全国の公立学校の教職員9702人から得た回答内容によると、正規の労働時間の7時間45分を大きく上回っている。
学校種別では中学校が11時間6分で最も多く、小学校が10時間31分、特別支援学校は9時間52分、高校が9時間44分とのこと。

平均はあくまでも平均である。
統計に隠されている突出した一部のブラック労働(過労死ライン)は、これまで黙殺されてきたが、今回はその一端が示されている。
劣悪な環境に心の病で休職したり自己都合退職した教員の数も多いと聞く。
政府・自民党で給特法の見直しを求める機運が高まる中、日教組は教職調整額の増額ではなく、「長時間労働の是正」を求めている。
1週間当たりの平均時間外労働時間は23時間53分。
月換算すると95時間32分で、厚生労働省が示す「過労死ライン」の80時間を超え、長時間労働が常態化している実態が改めて浮き彫りになった。
仮に時短が進んだとしても、「子どもたちのために」という正義の名の下、時間の長短とは関係なく「感情労働」の負担の大きさが教員の心を蝕んでいく。
個人の資質の問題として処理される悲しさ。
「チーム学校」とは何だろう。
