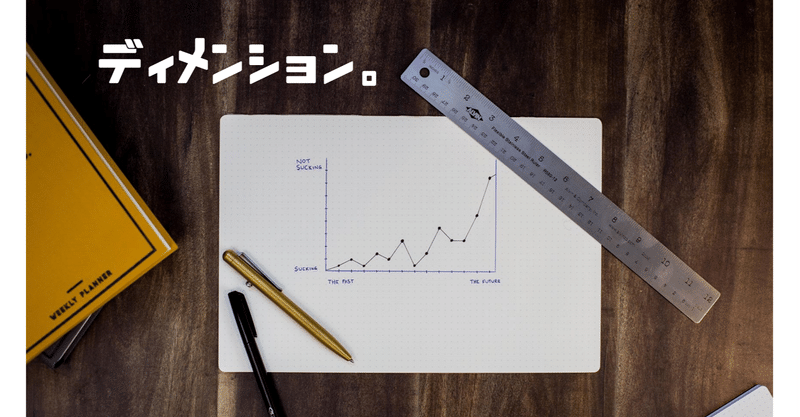
【考察】価値判断の軸を増やすとよさそう
自己肯定感と言うのは個人的にとても大事な概念だなぁと思うのですが、もっとも簡単な高め方というのがこの「価値判断の軸」を増やす行為だと思っています。
■知らず知らずのうちに
自分の生きている世界というのはとても狭いことに気付かされます。
ここでいう”世界の広さ”は行動範囲とうよりは周囲にいる人間の種類を指します。行動範囲と同義とも言えますけどね。
高校生になるときに入試を経験した自分は、この篩(ふるい)を経てかなり人間の種類が減ったな、と(今振り返ると)思います。
高校に行ったら大学受験をして上京しようと目論んでいる人たちが集まってきて、とりあえず体育館の裏で煙草を吸っている人とか、授業中ベランダでゲームをしている人とかはいなくなりました(笑)。
これが本格的に理系、文系に分けられるとより似たような人間が増えてきます。自分のように理系の道を選択して理系の学部に入ればもう悲惨です。
同じような思考回路、同じような趣味嗜好の人間が集合し、理系の場合は特に悲惨なことに急激に異性が減ります。
そのまま技術者としてメーカーに入れば同期も似たような奴らばかり。同じような問題を高校時代に解き、同じような境遇を大学時代に経験し、同じような思考回路で悩み、
社会人になってからは同じ作業着を着て夜遅くまで働き、その足で居酒屋に向かい同じような愚痴を吐き出してビールを煽ります。
この時点であんまり気付いてないんですけどね。
実はかなり似たような奴らに囲まれて生きていたんだな、というのを後になって気付かされるわけです。
■例えば地元の友人
自分のように上京してそのままそこに居座っている人間にとっては幼少時代の友人たちというのはとても大きな存在になります。
あるものは家業を継いでいたりするし、あるものは全く違う土地で全く違く種類の仕事をしているし、あるものはいい歳して働いてなかったり、あるものはもう子供を産んで母親になっていたり。
とにかく会社の同期と違って本当に様々な生き方、文字通り「生き様」を見せてくれます。
自分は絵にかいたようなサラリーマンだったのですが、そんな僕の話をとっても面白そうに聞いてくれて、「すごいね」「さすがだね」とまで言ってくれるのです。
会社の同期と飲んでると愚痴しか出てこないのに(笑)。
これは逆もあります。
自分とは全く違うフィールド、価値判断の軸で戦っている同年代を見ていると、素直に「すごいね」「さすがだね」という感情が出てきます。
相手は謙遜します。「そんなことないって!」と。
それもわかります。なぜなら自分も自分のこと褒められたらそう思うから。
価値判断の軸と言うのは知らず知らずのうちに凝り固まっていくものだと思います。
定期的にそれをぶち壊して新しい角度から自分を見てもらう、または他の人を見てみるということは、当然新しい発見にもなるし、何より自分自身の生き様を肯定する行為になると思うのです。
いわゆるダイバーシティの本質とは少し異なるかもしれませんが、価値判断の軸を増やすという考えで、多様性を受け入れてみるということはとても良いことなのだと思います。
本日も、最後までお読みいただきありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
