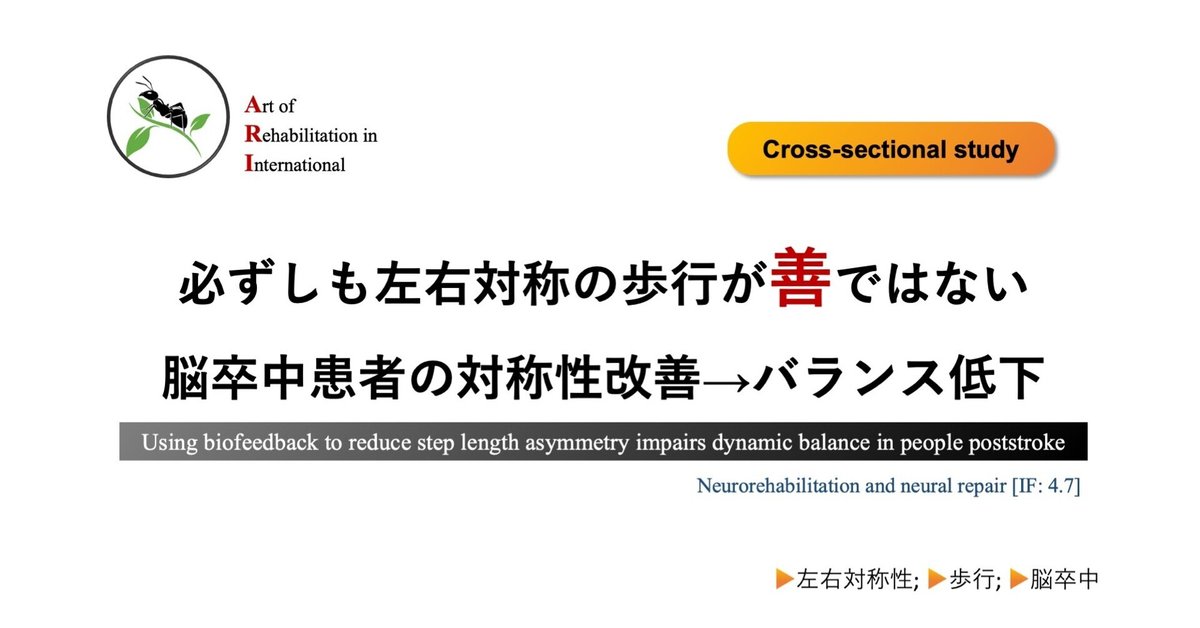
必ずしも左右対称の歩行が善ではない;脳卒中患者の対称性改善→バランス低下
▼ 文献情報 と 抄録和訳
バイオフィードバックを用いて歩幅の非対称性を低減すると、脳卒中後の人の動的バランスが損なわれる
Park, Sungwoo, et al. "Using biofeedback to reduce step length asymmetry impairs dynamic balance in people poststroke." Neurorehabilitation and neural repair (2021): 15459683211019346.
[ハイパーリンク] DOI, PubMed, Google Scholar, PMC_full
[背景] 脳卒中後遺症のある人は、時空間的に非対称な歩行をすることが多い。これは、麻痺した下肢の感覚運動障害が原因の一つである。非対称性を減らすことはリハビリテーションの一般的な目的であるが、対称性を改善することがバランスに及ぼす影響はまだ明らかになっていない。
[目的] バランスの指標としての全身角運動量の同時性を確立し,歩幅の非対称性を減少させることで全身角運動量が減少し,バランスが改善されるかどうかを検討した。
[方法] 36名の慢性脳卒中患者を対象に,臨床的なバランス評価を行い,全身マーカーセットを用いて歩行時の全身角運動量を測定した。次に、バイオフィードバックを用いたアプローチにより、歩幅の非対称性が顕著な15名のサブセットを対象に、歩幅の非対称性を修正し、その結果、全身の角運動量の変化を測定した。
[結果] バイオフィードバックを行わずに歩行した場合、矢状面および前額面の全身角運動量は、Berg Balance ScaleおよびFunctional Gait Assessmentのスコアと負の相関があり、動的バランスの客観的指標としての全身角運動量の有効性が支持された。また,左右対称に歩くと,矢状面での全身角運動量が減少するのではなく増加することが確認された。

矢状面におけるL_Sag^min(全身角運動量)の大きさの変化は、Baselineに対するSLA(歩幅の左右対称性)の大きさの変化と負の相関があり、非対称性の減少が角運動量の増加につながることを示している
[結論] 脳卒中後の人が歩幅の非対称性を自発的に減らすと、動的バランスの測定値が減少した。これは、脳卒中後の人は、歩行中に自然な非対称性から逸脱するとバランスを崩す可能性があるため、それを避けたいという暗黙の選好を持っているのではないかという考えと一致している。
▼ So What?:何が面白いと感じたか?
先生、わたし、前みたいにスタスタ歩けますか?
これは、聞かれる。この質問を受けたことのないPTは、いるだろうか。
本音を書く。
疾病発症後のリハビリテーションとは、『病前に回復する・戻す』という回帰のプロセスではない。
骨形態、中枢神経系、筋力、関節可動域、あらゆるpathologyレベル、impairmentレベルの状況が非可逆的に変わっている。
動作を構成する材料自体が全く変わっているのだ。
当然、その材料を組み合わせ、総合した『歩行』の最適解だって、変わる。
マグロで作れる料理とシラスで作れる料理は、同じではないだろう。
左運動麻痺を生じた脳卒中者にとって、右半身と左半身の最適解は、違ってしまったのだ。
これは悲劇的状況ではない。事実だ。その状況での最適解を探ればいい。
今回の論文結果が、その考えを支持している。
この状況下で、「完全な左右対称が善」論者は、見た目・病前回帰説以外の妥当な回答を、持つだろうか。
厳しく聞こえたかもしれない。
だが、この状況で望まれるマインドセットは、以下のようなものだ。
ないものは考えない あるものをどうするかだ
パラリンピック 2021 ポスター
理学療法士は、冷たい頭で最適解を探り、到達することが求められる。
それは、正確な評価と、確かな知識と、論理的で広範な統合と解釈と、効果的な介入によって。
リハビリテーションとは、だから、戻すものではなく、新しくつくるものだ。
○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥
良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』
こちらから♪
↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○
