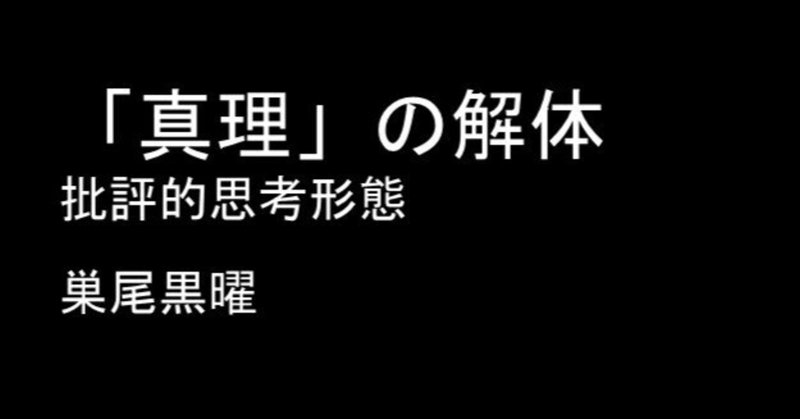
『「真理」の解体 批評的思考形態』試し読み
本稿は「解体」論書 第3巻として発売した『「真理」の解体 批評的思考形態』の試し読みである。
ここに第一章全文を公開する。
本稿は「真理」による分断の解決のために書かれた著作である。
興味のある読者は是非、文章の最後に貼り付けてあるURLから、Kindleにてご一読されたい。
*
1,序言
昨今、筆者の見る限りに於いて、分断に次ぐ分断に、世界は支配されている様に思える。分断、と一口に言えど読者諸賢も想起される様に、様々なる種別のものが存することであろう。例えば政治的観点からでは、右翼対左翼が代表的なものとして挙げられるだろう。彼らは、彼らがフランス革命より名付けられてから、議会を超越して非現実的ですらあるインターネット上の仮想空間(主にSNS)に於いてであっても熾烈(しれつ)な闘争(というより不毛な罵倒の応酬)を繰り広げている。同じ様に時事的な観点で言えば、最近の分断としてはワクチン接種勧奨派対ワクチン接種拒否派が挙げられるだろう。彼らは主にツイッター等といったSNSに於いてこれもまた熾烈な闘争(というよりも不毛な罵倒の応酬)を繰り広げていた。または、これも政治的観点からではあるが、民主党対共和党やトランプ派対反トランプ派、或いは保守対革新も、一つの分断として挙げられると思われる。兎も角、以上、に見ても分かる通り、分断は我々の身近に、それも数多(あまた)夥(おびただ)しく存在し、ある意味では分断は世の常であると言っても過言ではない様である。それ自体は、別段、憂慮すべきことではないと、筆者は思うのだ。良く考えても、考えずとも、そもそも中学校等の学生時代を思い起こせば良いのだ。その場には(大半の人間に於いては)部活動というしち厄介なものが存し、人生の内の貴重な、大切な、極めて至重な、幾らかの時間を余りにも無駄に浪費したことが、恐らく大半の読者諸賢には経験のあられることであろう。その内に於いて何らかの問題が生ずると(或いは生ぜずとも何がしかの派閥という形式に於いて)部内の人間が「分」かれ、「断」たれ、対立した筈である。部活動というのは、通常であれば数人から、多くとも数十人が関わる程度のものであるから、それは小集団での活動であると言って良いだろう。その様な小集団でさえ、以上の様な、分断が発生するのである。どうして分断が我々人間に対して外部的な疎外されたものであると言えようか。むしろ、確かに、分断とは、人の常であるのだ。分断という言葉が少々仰々しいか厳しく思われる読者は、この日常的な分断を「人それぞれ」という言葉に置き換えても良い。
さて、その様な「人それぞれの分断」であるが、それ自体としては先述の通り、特に憂慮すべきでなく、或いは憂懼(ゆうぐ)すべき必要も何ら存在しない。……無論、確かに、そうなのであるが、しかしながらこの此岸、または現実というものには当然ながら、時(これは以前『「予言」の解体 絶対現在的未来予測』に於いて解体した)と場所、そして場合というものどもも付随して存するものであり、分断も当然、現実のものであるから、時、場所、そして場合の制約を受けるのである。分断は、人の常である。勿論、それは一つの事実であるし、我々はそれを真摯に受け止めねばなるまい。だが、この命題から導出される結論というのは、大きく分けて二つ存すると、筆者には考えられる。分断は、人の常である。したがって、それを憂慮すべきではない。これは筆者が上述した一つ目の結論、判断である。では、もう一つは何か。それは、「分断は、人の常である。したがって、憂慮すべきである」だ。つまり、筆者の上述した結論とは正反対のものが、もう一つの結論であると考えて良い。多くの場合は、分断は憂慮すべきではなく、むしろそれは人間の本性上、仕方のないものであるのだ、と、妥協的にその発生を受容されることであろう。けれども、どうしてもそうならない場合というのは、やはり存するのである。
例えば、(筆者は「やらせ」であると考えている)9.11同時多発テロを想起されれば良い。あれはある意味では、キリスト教とイスラーム教という二つの宗教の分断が生んだ悲惨な事件であると言って良いだろう。また……いや、筆者が態々本稿の序言でつらつらと例示せずとも、読者諸賢に何か手頃な政治的問題を手近な情報端末で調べられるだけで、良いのだ。分断が、我々の内憂外患となる例を億恒河沙と、見られる筈である。そして、その「憂慮すべき分断」を認めた上で、我々は気が付くのだ。ああ、やはり分断はいけない、というよりも有害なことであり、目指すべきは調和なのだ、と。恰もヘーゲルの唱えた弁証法が如く、「分断容認」と「分断反対」から「分断の解決」という結論が導き出される訳である。
だが、この様に論を進め、分断の解決を試みようとしても、恐らく上手くは行かないだろうと筆者には思われるのだ。何故か。それは分断の「根源」に目を向けていないが故である。こういった分断解決派の大半は、分断の原因を人間の「外部」に求めようとするだろう。例えば、先程述べた9.11同時多発テロを取り上げてみよう。これはある意味ではキリスト教とイスラーム教の間に存する分断が引き起こしたものであった。そこで分断解決派の人間はこう思惟する筈である。曰く、キリスト教とイスラーム教との宗教的融和こそが、このテロを未然に防ぐことが出来た唯一の手段であり、次にこの様な悲惨な事件を起こさないためにも(実際には多く発生しているが)それを為すべきである、と。確かに、これが成された暁には、キリスト教とイスラーム教との対立は解消され、分断は消失し、晴れて大団円を迎えられるかも知れない。しかし、彼らの視点には一つの事実が欠如している。それはキリスト教対イスラーム教という分断の他にも、分断は無数に存するという、実にさもなく、取るに足りず、見栄えもなく、歯牙にもかからない事実である。つまり、一つの分断を近視眼的に解決したところで、解決にはならない、ということだ。分断は人の常、それから齎される災禍も人の常である。我々は別の方法で分断に対する必要がある。
また、分断というのは、支配層が民衆を支配するための道具ともなり得る。良く見られることであるが、何か支配層にとって不都合なことが起こりそうな場合(または支配層の弄する策によって民衆の悪感情を惹起する可能性が考えられる場合)、民衆の間に争い、即ち分断の種を蒔いてやるのだ。そうすると、人間は云々(うんぬん)対然然(しかじか)という風に自然と組分けされ、相争い、血で血を洗う骨肉の争いに進んで身を投じることとなる。そして支配層の不都合は消え、後には互いの拳で傷ついた肉叢と、互いの口舌で傷ついた精神だけが残る。昨今の政治で良く見られる手法だ。特に新型コロナワクチン接種や改憲に関する事項で、この手法による支配が多発したことが見受けられていた。この支配手法の何が問題であるのかと言えば、(民衆の視点では)解決すべき真の問題を分断という些事によって解決出来なくなる、或いは問題を問題としてすら認識するに能わなくなる、ということである。丁度、増税の告知の日に芸能人が不倫だか何だかをしてマス・コミュニケーションがそれを扇情的に取り上げ、民衆が不倫容認派対不倫極刑派に分かれ、実に真に無駄な闘争に仮想空間上で身を投じる様を、想起されれば良い。この場合、増税の方が、芸能人の不倫などの下らないことよりも重要であり、何より生活に、己の生に直接的に関係する問題である。しかし、大変「上手」に民衆は支配層の手掌の上で、非常に「巧妙」に舞い踊る訳だ。この手法の問題は、これである。分断され、真の問題には手を触れることすら出来ない。また、これの応用として、反対派に真偽入り混じった情報を意図的に流出させ、反対派内部に派閥を作らせ、容易に協力できなくさせた上で、反対派の力を削ぎ落とし、弱体化させる、という手法もある。これも現代政治に於いて良く見られる手法なので、読者諸賢は記憶されると良いだろう。
以上の様に、現代の支配にとって、分断というものが極めて重要な意味を持っている、ということが、読者諸賢には容易に理解されたことであろう。我々が真の問題を解決するには、それに先んじて問題に触れねばならず、そのためにはまず、分断を解決……いや、「解体」しなければならない。では、それを果たすに、一体何を我々は行えば良いのか。これについては無極の意見が存すると思われるが、その一つとして、筆者はこの様に考えた。
分断の根底には、必ず二つや或いはそれ以上の人間の集団が存在し、そしてそれらの一つ一つ、それぞれにそれぞれの「正しいと思うこと」がある。即ち、分断の原因は、この「自分たちが正しいと思っていること」ではないか。
つまり、「自分たちが正しいという思い込み」こそ、分断を生じさせている根源ではないか。
この「自分たちが正しいという思い込み、或いは、正しいと思う事柄」それを纏めて筆者は「真理」と呼ぶ。故に、分断の「解体」。これを成すに、筆者は「真理」の解体を行わねばならない、と、確信したのだ。したがって、筆者はこれから幾らか続くであろう本稿に於いて、「真理」の解体を行う。そのために筆者は先んじて本稿第二章から第九章までを人間の思考に焦点を当て、これを構造化する。これを為すことによって、「真理」の発生の機構が容易に読者諸賢に理解される筈と、筆者が考えるが故である。その上で筆者は本稿第十章および第十一章にて「真理」の解体を行う。なお、第二章から第九章までの議論は、筆者の著作である『「陰謀論」の解体 情報の扱い方』と重複している部分が多いと思われるため、これをお読みになられたありがたい読者は適宜読み飛ばして構わないと思われる。ただし、第八章と第九章は恐らく初出の内容であるから、この二章はお読みになられた方が良いだろう。
以上で、序言で述べられるべきことは全て述べ尽くされた筈である。早速、次章から議論を開始することとしよう。
*
興味のある方は、下記のURLから本編を読まれたい。
宜しければ御支援をよろしくお願い致します。全て資料となる書籍代に使わせていただきます。
