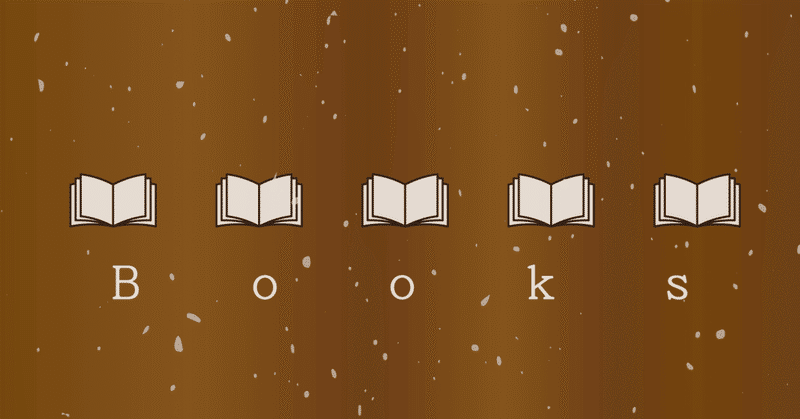
家の書籍の分類について、こうすればいいというものを発見した
こんにちは。
昨日はこんなことを書きました。
本の分類については、図書館のやり方を模倣するのがいいと思いながら、分類が面倒くさいという贅沢な悩みを綴っています。
そんなことを思いながらいろいろと調べていたら、このような記事を発見しました。
図書館の本が3桁の数字で分類されているのは皆さんご存じのことと思うのですが、それとは別に国立国会図書館バージョンがあるそうです。国立国会図書館バージョンの存在を知ったとき「これいい!」と思いました。そう思ったのは以下の点です。
国立国会図書館はわが国の本を網羅している
国立国会図書館法という法律において、すべての出版物は国立国会図書館に納本しなければならないことが定められています。ということは、わたしが所有している本にはだいたい対応できます。対応できないものは、予備校時代のテキストぐらいですが、それはもう増えることないと思うのでいいのです。また、「すべての」というのはわが国レベルでしょうけれども、今のところ和図書(日本の図書)だけで対応できるのでモーマンタイです。そして、図書館は新刊に対応していませんが、それは少し待てばいいので、気にしないことにします。国立国会図書館はひとつしか存在しない
厳密にいえばいくつかありますが、あくまで本館と分館の違いぐらいでしか存在しません。分類記号も、調べたところ、本館と分館では同じものを使っているようですので、同じ書籍に複数の番号がついているということもありません。同じ図書館なら分類記号は同じだろと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、わたしの母校にある図書館は、同じ図書でも図書館によって違う記号を採用していたので、場所が違っても同じ記号かどうかはとても大事です。OPAC が使える
OPAC という検索システムが使えます。探している本がどこに行ったか分からなくなってもこちらで調べれば見当がつくので、検索システムの整備が不要です。これは、インターネットに接続された端末ならば Excel が使えないパソコンでも検索できるので大変便利です。国が運営しているものですから、国や国会が亡ばない限りなくならないです。
ということで、国立国会図書館の記号を参考に分類することにします。先ほど紹介した記事では、普通の図書館の分類法を採用することにしたらしいですが、わたしは、国立国会図書館にします。普通の図書館の分類法に慣れていないので、それなら国立国会図書館のほうがいいかなと思ったのでした。
それでは、いつやるか? 今ではないでしょ。
最後に、今日(5月25日)は納本制度の日だそうです。5月25日から納本の受付を初めたので、今日が記念日として制定されている、とのことです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
