
第3作「男はつらいよ フーテンの寅」1970年松竹
ドラマ版「男はつらいよ」の脚本で、最終回に寅を殺してしまったことでファンのクレームがフジテレビに殺到したのは有名な話。
その罪滅ぼしのために、松竹に掛け合って、映画化したのが、そもそもこのシリーズの1作目「男はつらいよ」でした。
会社側は、当時の常識として、ドラマの映画化を渋ったわけですが、山田監督は、「映画が当たらなかったら、その責任を取って会社を辞める」とまで啖呵を切った末のクランクインだったそうです。
しかし、いざフタを開けてみれば、閑古鳥が泣いていた映画館には、寅さん見たさの観客がドッと押し寄せることになります。
しかも、それまではどちらかといえば女性の観客が多かった松竹の映画館に、まるで寅さんのような威勢のいいねじり鉢巻のお兄さんたちがワンサカ押し寄せたのをみて、会社側は手のひらを返したように山田監督に続編を依頼。
そしてこれもヒットを記録して、松竹としてはまさに山田監督さまさまということになったわけですね。
当然3作目となる本作も監督を打診されるわけですが、この2作で責任を果たしたと思っている山田監督は、今度は会社からの要請を断ります。
この時、山田監督の頭には次回作として、寅さん映画とは全くテイストの違うロードムービー「家族」(これも名作❗️)の構想があったったんですね。
しかし、映画館に観客を呼び戻してくれたヒット・シリーズですから、松竹もそう簡単には諦めません。
結局第3作は、山田監督は、脚本のみ参加で、監督は、山田組の助監督だった森崎東が務めることになります。
そうして作られたのが、この第3作目です。
森崎監督といえば、後の「喜劇女」シリーズや、「生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言」などのエネルギッシュな喜劇で手腕を発揮した監督。
「男はつらいよ」のヒロインは、さくらを演じる賠償千恵子でしたが、森崎作品の代表的ヒロインは、バイタリティ溢れる倍賞美津子。
もちろんこの2人は、同じ松竹歌劇団出身で実の姉妹です。
さあ、その森崎監督が、山田監督の脚本を得て、どんな寅さんを見せてくれるかが本作の見どころということになります。
映画の冒頭、まだ蒸気機関車の走る長野県塩尻市の木曽奈良井宿の旅館で、寅さんは風邪をひいてダウン。
宴会客で大忙しの旅館は寅さんを押し入れ部屋に。
そこに、食事を運んでくる女中が悠木千帆で、思わずニンマリ。
後に樹木希林と改名してからの活躍は、誰もが知るところですが、この時の彼女はすでに27歳。しかしどうみても十代の娘にしか見えなかったなあ。

さて、寅がフラリと柴又に戻ると、とら屋では、タコ社長が持ってきた、寅の見合いの話で盛り上がっています。
ちなみに「このタコっ❗️」というおなじみの呼び方は、本作で初めて登場。
以降シリーズでは、太宰久雄はタコ社長ということになります。
とら屋の面々の前で、理想の女性像をご機嫌に語る寅。
この渥美清による長い一人芝居は、寅がとら屋に戻って来たときには必ず挿入される本シリーズの目玉場面になっていきます。

撮影現場では、このシーンは「寅のアリア」とも呼ばれているそうで、レギュラー陣も、演技を忘れて思わず聞き入ってしまうほどの渥美清の芸の真骨頂。
さて、タコ社長が連れてきた見合いの相手駒子(春川ますみ)というのが、なんと寅さんの昔の知り合いで、しかも彼女は妊娠中であることが判明。
よくよく聞けば駒子には男がいて、その相手は、女と浮気して家出中と判明。

お見合いは一転して、寅が駒子のために奔走するドタバタへと展開していきます。
男を捕まえた寅は駒子と復縁させ、その勢いに乗って2人の結婚式の段取りまでしてしまう暴走ぶり。
調子に乗る寅次郎は、とら屋で二人の披露宴を行い、ハイヤーで2人を新婚旅行に送り出します。
ところが、その費用はもちろん全て、とら屋に回して悪びれもしない寅に、怒り心頭のとら屋の面々。
裏庭では、おいちゃん注視の元、博と寅の取っ組み合いが始まります。
この取っ組み合いは、同じようなシーンが、第一作にもありましたが、これはウケの渥美清の演技が、完全に喜劇的にデフォルメされていて、完全にお笑いのシーンになっていましたが、本作ではかなりマジ。
結局寅は博に、地面に顔を押さえつけられてグーの根も出ない完敗。
山田監督は、自分が演出をしないこの第3作を見て、原作者として違和感を感じたと言っていますが、もしかすると、それはこんなシーンにあったかもしれません。
頭を叩く程度は日常茶飯事な寅さんですが、マジで殴る蹴るの暴力シーンにはならないように、山田監督は結構気を遣った演出をしていましたね。
違和感はまだありました。
それはここまでの柴又でのシークエンスに、なんと妹さくらが一度も登場していないということ。
やはり、すでに全作見ているファンとしては、とら屋の場面に、さくらがいないのは、ちょっと違和感があります。
映画では、この後の寅との別れのシーンで、やっとさくらが登場することになりますが、なんとか、シリーズとしての体裁を整えたという感じでした。

というわけでシリーズを通じて、最も賠償千恵子の出番が少ないのが本作です。
これはおそらく同時期に彼女が主演していた、山田監督作品「家族」での全国ロケーションのために、本作のためのスケジュールがなかなか割けなかったという事情があったのでしょう。
「男はつらいよ」に、さくらが欠かせないことは、当の山田監督が一番よくわかっていること。
ですから「家族」の撮影の空いた時間で、さくらのシーンが撮れるように色々と配慮されたのでしょう。
ちなみに、映画「家族」には、「男はつらいよ」レギュラー陣は、渥美清を含めチョイ役で総出演。エールを送っています。
これはこれで楽しめますので、未見の方は是非ご観賞あれ。
さて、違和感ついでに言うと、本作での寅次郎のファッションも微妙でした。
これは、明らかに前2作とは、ややテイストが違いました。
まずお馴染みの背広は明らかに濃いめで、黒のストライプもハッキリくっきり。
しかも、ハンフリー・ボガートよろしくトレンチコートを羽織り、首周りには粋な黄色のスカーフ。
他の作品ではちょっと記憶にない、シリーズで最もお洒落な寅さんになっていました。
この辺りの演出は、森崎監督による意識的な前2作との「差別化」であり、独自色の出しどころだったのかも知れませんが、すでに寅さんのビジュアル・イメージがしっかりと定着してしまっているファンにとっては違和感になっていたかもしれません。
さて、旅に出た寅の落ち着いた先は、三重県の湯の山温泉。
その温泉旅館のもみじ荘に転がり込んだ寅。
この旅館を切り盛りしているのが、美人の女将お志津。
演じるのは新珠三千代で、彼女が本シリーズ3代目のマドンナとなります。
この人は、僕の世代で記憶に鮮明なのは、なんと言ってもテレビドラマの「細うで繁盛期」の加代さん。
「加代。おみゃあにやる飯はにゃあずら。」という冨士眞奈美の怪演も忘れられませんが、このドラマでも、彼女は旅館の女将を演じていましたね。
とにかく、着物姿で京言葉の印象が強い和服美人です。
ちなみに、ドラマ版の「男はつらいよ」は、全編を通じてマドンナとなるのは、前作でも同じ役を演じた佐藤オリエだけでした。
しかし、作品ごとにマドンナが代わるというフォーマットが、映画版のお楽しみだと、観客が認識し始めたのも、この第3作あたりからということになるでしょう。
新珠三千代は、本作撮影時、39歳ですから、寅とほぼ同世代。
年齢的釣り合いはバッチリです。
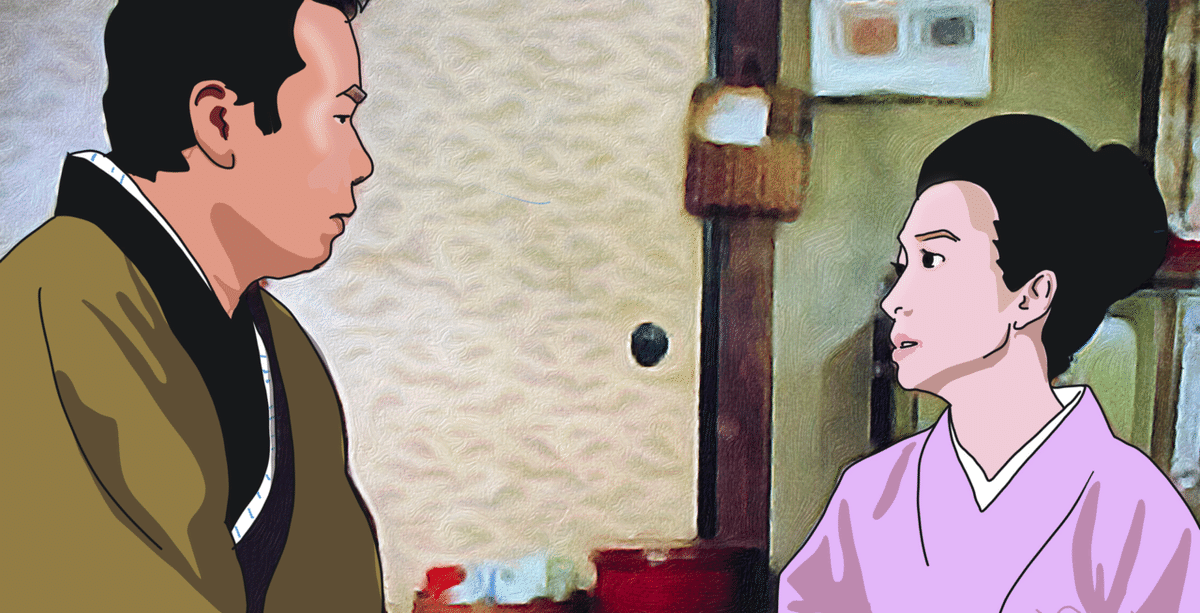
さて、東京の大学に行っているお志津の弟信夫(河原崎健三)と、地元の芸者染奴(香山美子)の駆け落ちに応援するというのが本作のサイド・ストーリー。
信夫と寅は、温泉街の橋上でやりあうことになるのですが、ここでなんと信夫がポケットから取り出すのがナイフ。
これも、ちょっと寅さん映画には、似合わない小道具のような気がしました。
なんだかんだとやり合いながらも、染奴の気持ちを知ると、寅はここでも2人のために大活躍。
地元のテキ屋の親分だった染奴の父親(花沢徳衛)にも話を通します。
スッタモンダの末、信夫は染奴をバイクの後ろに乗せて東京へ。
思えば、この2人は、シリーズ終盤の軸になる甥っ子満男と、そのガールフレンド泉カップルの原型になっていそうですね。
というわけで、本作の寅さんは、若いカップルのためにひと肌もふた肌も脱ぎまくります。

さて、寅とマドンナの恋の行方はの方はどうなったか。
実は、女将さんには、すでに結婚を決めた相手がいます。
しかし、そうとは知らずに、相も変わらず有頂天の寅に、それをなかなか言い出せないお志津。
事情を察した旅館の古株番頭(左卜全)や女中が、あれやこれやの末にやっと寅にそのことを告げます。

かくして、寅のシリーズ3回目の失恋が、ここに悲しくも成立。
寅は、お志津に、置き手紙をして旅へ出ます。
寅が駅への道をとぼとぼ歩いていると、婚約者の運転する外車で、寅次郎とすれ違うお志津。
車を止めてもらい、歩き去るその背中を見送るお志津は、寅に声をかけることは出来ませんでした。
さて、大晦日で大忙しのとら屋では、面々が団欒で年越しそば。
その中には、寅が復縁させた駒子夫婦も、もちろん妹さくらもいます。
テレビでは、「ゆく年くる年」で、鹿児島県の霧島神宮からの中継が始まります。
すると、そこで初詣の客相手にバイをしている寅がテレビ画面に映って、とら屋の面々はビックリ仰天。
1969年は、映画館の大画面に復活した「男はつらいよ」で暮れていくことになりました。
そして、ラストでは、種子島行きの船のデッキで、乗船客たち相手に啖呵売のレクチャーをする寅の元気な声が、錦江湾に響き渡ります。

というわけで、第3作は、マドンナがとら屋を訪れるというシーンがないという珍しい作品になりました。
その代わりに膨らんでいるのが、旅先での寅さんの奮闘ぶり。
信夫との決闘シーン、染奴の父親への挨拶など、とにかく寅さんは本作では仁義切りまくり。
「私、生まれも育ちも関東、葛飾柴又です。姓は車、名は寅次郎、人呼んでフーテンの寅と発します。西に行きましても東に行きましてもとかく土地土地のおあ兄さんおあ姐さんにご厄介をかけがちたる若僧です。以後見苦しき面体お見しりおかれまして、恐惶万端引き立って、よろしく、おたの申します。」
しかし、なんのかんのと言っても映画はヒット。
以後、テレビの台頭で映画という娯楽が斜陽になっていく中、そのテレビから飛び出した、けっしてイケメンではない四角い顔と小さな目のヒーローが、日本の映画界を支えていくことになります。
お盆と正月は、寅さん映画がなければ始まらないと言われるほどの国民的ヒットシリーズへと成長していくことになる本シリーズ。
この時はまだ誰も、ギネスブックにも載るような世界一の長寿映画シリーズになるなどとは思ってもいないことでしょう。
さて、次回第4作目は「新・男はつらいよ」❗️
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
