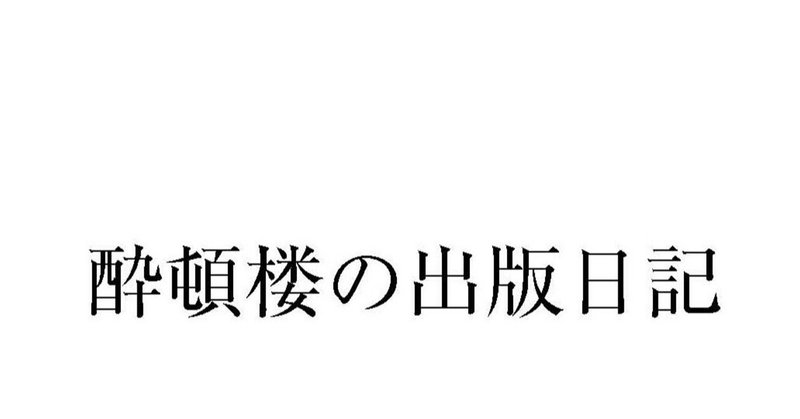
極私的なテーマ

ぼくは中学1年の夏休みに、東京の調布のある中学校から広島の段原中学校に転校してきました。
大学の5年間とプロダクションで1年半ほど編集の仕事をしていた時期の7年足らずをのぞいても、ほぼ半世紀近くを広島で暮らしていて、当然の帰結としてカープファンになってしまいました。
1975年の初優勝のカープをリアルタイムで経験したプロ野球ファンにとって、あのときのカープの魅力というか磁力は強力で、シーズンが進むにつれて虜となっていったファンは少なくないでしょうし、かくいうぼくもそのひとり。
それまでは東京でのご幼少時代に洗脳されて、当たり前のように巨人ファンでしたし、カープに気持ちは傾きつつも巨人にまだ軸足を残していたのが、あのときのカープの快進撃に煽られるように〝宗旨替え〟したのです。
それからは、ウエイトはさておき、カープが人生のテーマのひとつとなっています。
もうひとつのテーマが、いわゆるカタカナの「ヒロシマ」。
そして、このテーマにいま取り組んでいるというわけです。
どこにいっても被爆のモニュメントにぶつかり、何かにつけて被爆問題が取りざたされる広島で、好悪はさておき「ヒロシマ」から自由でいることは難しい。
ぼくの場合、前向きに取り組みたいという意欲だけはあるのは、もともとの出自が広島ではなく、しがらみとか遠慮とかが欠如しているからかもしれません。
したがって「ヒロシマをテーマに書くこと」は、ずっと以前から頭にはあったのですが、一歩踏み込むまでには至らなかったのです。
どこにでも「ヒロシマ」のネタはあるわけで、いまにして思えば意欲の希薄を自戒するしかありませんが、そこから切れ込んでいって成果をものにするための方法論を持ち得ていなかったのも逡巡した理由の人つでしょう。
その方法論をいま手にしたのかというと、心もとないばかりですが、以前から意識していた「ヒロシマ」の隠蔽と捏造という問題から入っていけそうな手応えがあって、昨年から本格的に執筆作業に取り組んできました。
昨日も書きましたが、いまスタイルとして3つを想定しています。
もともとはノンフィクションとして考えていたのですが…、
一、もっと下の年齢層にもアプローチするために企画本にできないか、
一、もっと内容的に突っ込んで書くためにはフィクションだろう
そんな流れで3つの原稿を抱えることになったというわけです。
なのでコンセプトでいえば、その3つともにほぼ共通しています。
今朝もノンフィクション編の原稿の整理をしていたのですが、もうたぶん使うことはないであろうバージョンの「まえがき」にそのコンセプトめいた思いが書かれてあったので、ここに転載しておきます。
❋ ❋ ❋
「まえがき」にかえて
〈ヒロシマ〉というとき…
これは栗原貞子さんの詩「ヒロシマというとき」の冒頭の一節です。
あなたなら、ここにつづけてどんなことをイメージするでしょうか。
ヒロシマというとき…
あなたは「お好み焼き」とか「カキ」とかを思い浮かべるかもしれません。それとも「もみじ饅頭」でしょうか。
いまはコロナ禍で様相は一変しているでしょうが、ついこの前までは広島駅のお好み焼き屋は、広島を訪れる旅行者やビジネスマンで長蛇の列ができていましたし、カキ料理を目的に広島を訪れる観光客もすくなくありませんでした。
もみじ饅頭は、何十年か前に、漫才コンビのB&Bの「もみんじまんじゅ~」のひとことで、すっかり全国区になってしまいましたからね。
でもいまなら圧倒的に「カープ」でしょう。
「広島というとき」
カープの赤を、そしてスタジアムでの熱狂的な応援風景を連想するひとが圧倒的多数でしょう。
ここであえて「ヒロシマ」を「広島」に書き変えたのは、このふたつではその意味あいが大きくちがってくるからです。
「ヒロシマ」という表記から、ストレートにカープは結びつきにくいですからね。
そこまではっきり意識はしていないかたでも、なんとなく感じてはいたのではないでしょうか。栗原さんの詩のようにカタカナで「ヒロシマ」と書く場合は、アメリカが投下した原子爆弾で壊滅した広島やその周辺のこと、あるいはそれを廃絶して恒久平和を希求する思いを語ったり表現するときに使われるのが一般的です。
なので、「ヒロシマ」を意識しているかたなら「被爆」のことを思い浮かべるでしょうし、その象徴としての原爆ドームや、原爆による破壊や被爆者の悲しみに思いをはせるかもしれません。
もしあなたが当事者であれば、憶い出したくもない肉親の悲惨な死とか、地獄としか表現しえなかった街の破壊、怒りや悲しみの記憶がよみがえることでしょう。
前述の栗原さんの詩は、このようにつづきます。
〈ヒロシマ〉というとき\〈ああ ヒロシマ〉と
やさしく答えてくれるだろうか
〈ヒロシマ〉といえば〈パール・ハーバー〉
〈ヒロシマ〉といえば〈南京虐殺〉
〈ヒロシマ〉といえば女や子どもを壕の中にとじこめ
ガソリンをかけて焼いたマニラの火刑
〈ヒロシマ〉といえば/血の炎のこだまが 返ってくるのだ
〈ヒロシマ〉といえば/〈ああヒロシマ〉とやさしく返ってこない
(後略)
この詩が発表されたのは1972年のことでした。戦後27年のことですから、8月6日に広島に原爆が投下されてから同じ年月がたっていました。
それだけのときを経ても、まだヒロシマが理解されない口惜しさや悲しみを、栗原さんは自戒をこめてこの詩に表現しています。
〈ヒロシマ〉といえば、アメリカからは、「日本は卑怯にもパールハーバーを奇襲したではないか」と返され、国の内外から「南京虐殺はどうなんだ」ともちだされる。あるいは「広島だけが被害を受けたわけじゃない」と非難され、「ヒロシマ」というかいわないかのうちに、「いつまでヒロシマ、ヒロシマといってるんだ」と糾弾される。
「ヒロシマ」をヒロシマとしてきちんとした議論すらできない。そんなもどかしさも、栗原さんはこの詩で訴えたかったのでしょう。
栗原貞子さんが、被爆から27年後に訴えたヒロシマの現実。無理解に翻弄されるヒロシマの実情は、被爆から75年経過したいまもほとんど変わってはいないように思えます。
たとえば、原子爆弾の投下時刻と爆破時刻の混同など。
広島への原爆の投下時間は8時15分といわれています。そして、それが爆発したのも8時15分。そこにあった数十秒の時間差が無視、あるいは意図的にスルーされてきたように、これまで語られてきたヒロシマにも誤差や誤認、もっといえば隠蔽や捏造があったことは、いまではよく知られるようになりました。
日本の広島という地方都市が経験した、地獄絵のようにおぞましい出来事でしたが、それを投下した当事者であるアメリカが、戦後すぐに占領軍として日本を統治しはじめプレスコードをしいたために、原爆の非人道性を覆い隠そうという意図のもと、厳しい検閲によって、その被害を蒙った広島ですら「ヒロシマ」を語ることはゆるされず、意図的に誤った情報が流布されたからです。
そのために「ヒロシマ」の真実と、これまで語られてきた「ヒロシマ」との間には、いまだにいくつもの「謎」が横たわっています。その謎から事実とは乖離した「ヒロシマの神話」が誕生しました。それがヒロシマの理解を歪める原因となり、兵器としての原子爆弾にたいする歪んだ信仰を生んで、その結果として栗原さんの嘆きとなったのでしょう。
「核は必要悪だ!」と強弁する前に、あるいは、「核は絶対悪だ!」と訴える前に、あらためてヒロシマの真実を知るために、「ヒロシマの謎」を、これから一緒に解いていこうではありませんか。
以上
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
