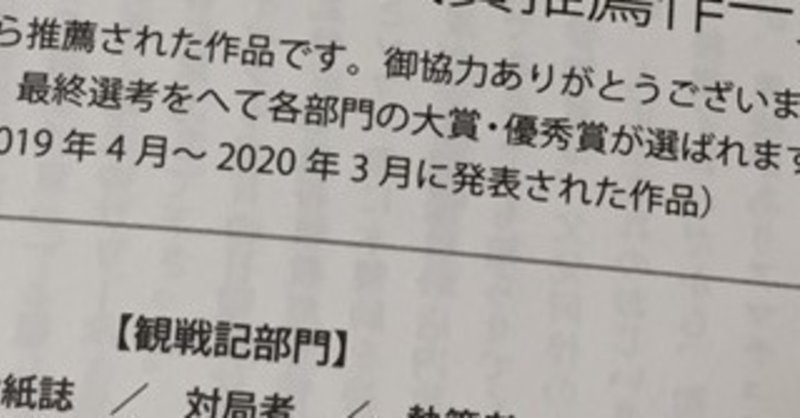
将棋ペンクラブ大賞『観戦記部門』の、観戦記って? その2
その1 の続きです。
観戦記は、それを書ける専門の記者が書く。いわゆる観戦記者、というものだ。観戦記者は一般の記事は書かず、観戦記、あるいは将棋の記事だけを書いている。
観戦記を書くには、まず、プロの将棋を理解できるくらいの将棋の実力がなければならない。だから多くは、将棋好きがうらやましくなるくらいのキャリアを持っている。奨励会(将棋のプロになるための養成機関)に所属していた棋士だったり、学生時代に全国大会で優勝していたり、アマ棋戦で全国大会常連だったり、などだ。一応指し手は、対局後、指した棋士にレクチャーを受ける(この手は自信があったのか、この局面ではどれくらい優勢だと思っていたのか、など)が、観戦記者がある程度理解していないとレクチャーしてもらうポイントが広がりすぎてしまう。勝負所や、均衡が破れたところなどが分からないと、プロと話がかみ合わないで仕事にならないのだ。
そして、指し手だけでなく、『棋界のこと』も知っていなければならない。『棋界のこと』、というのは主に2つ。1つは、将棋界の持つ独自の風習や文化。たとえば、観戦記者というのは対局場に出入りし、終局直後の感想戦に立ち会うのが許されている分、邪魔にならないよう、失礼にあたらないよう、振舞うことができなければならない。感想戦を始めるときに、盤側にドカッと胡坐で座り込んではよろしくない。何時間も感想戦が続いているのであれば途中で足を崩してもいいが、いきなりはダメだ。将棋界にはこういった暗黙のルールが多いが、それらを押さえなければならない。
『棋界のこと』のもう1つは、棋士のこと。だれの弟子か、どういう実績があるか、だれと仲がいいか、どういう性格か、ということを記憶に入れておかなければならない。これは、観戦記に棋士の特徴やエピソードを挿入して文章に肉付けするのに必要だ。指し手だけ書いていては、味気ないものになってしまう。そしてまた感想戦では、対局中に棋士が考えた、頭の中のことを聞き出さないといけない。「ここで実はこう指そうと思ってた」とか、「(相手の)この手で、敗勢を悟った」とか。相手の性格や好みを知って、個人的に仲よくなったり、信用を得られれば、誰も書いていないエピソードや、対局中に思い浮かんだ幻の絶妙手を聞かせてもらえることもある。
観戦記は、その棋戦のすべての対局を載せない、と『その1』で書いたが、それは棋戦の予選のこと。多くの棋戦は決勝リーグや決勝トーナメントがあって、それらはすべて載せられる。そして頂点のタイトル戦番勝負も。棋戦はほとんどすべて、勝ち上がってきた挑戦者と、タイトル保持者が最後に番勝負で戦う。番勝負とは、5番勝負や7番勝負など、複数の対局で勝負を決める方式だ。タイトル戦は将棋界では最も輝かしい舞台なので、地方の老舗旅館やホテルなどで行われる。全国高校野球選手権が甲子園球場を使うのと同じことだ。
多くの新聞では、タイトル戦は日数を多くする。例えば、予選の対局は6日で一局分書くのに、タイトル戦は一局に10日使う、というような。その分、対局場の雰囲気や当日のエピソードなどを多く含められる。だからタイトル戦の観戦記は予選のそれより読み応えあるものになりやすい。実際ペンクラブ大賞で選ばれる賞も、タイトル戦の観戦記に偏っている。
一つの新聞(棋戦)では、大体6人から7人くらいで観戦記をまわしている。だから、一人が受け持つのは年間8局くらいだろうか。観戦記は書き上げるのに時間がかかるので、これくらいが妥当な量でもある。ただ、中には棋戦を掛け持ちしていて、年間20局くらい書く猛者もいる。
大まかに『観戦記』というものを説明すると、こんな感じになる。新聞の記事のひとつだが、ある特定の読者しか対象にしていないので、新聞記事の中で最も専門的な内容になっている。政治に大スキャンダルが起きようが、スポーツで大記録が達成されようが、観戦記欄はなにも変化がない。紙面中のシェルターのようなものなのだ。
『観戦記』というものをさらに知りたい、という人は、将棋観戦記者を主人公にした『盤上のアルファ』を読むともっと深く分かる。この塩田武士さんの小説は、2011年の将棋ペンクラブ大賞の『文芸部門』大賞作品だ。
書き物が好きな人間なので、リアクションはどれも捻ったお礼文ですが、本心は素直にうれしいです。具体的に頂き物がある「サポート」だけは真面目に書こうと思いましたが、すみません、やはり捻ってあります。でも本心は、心から感謝しています。
