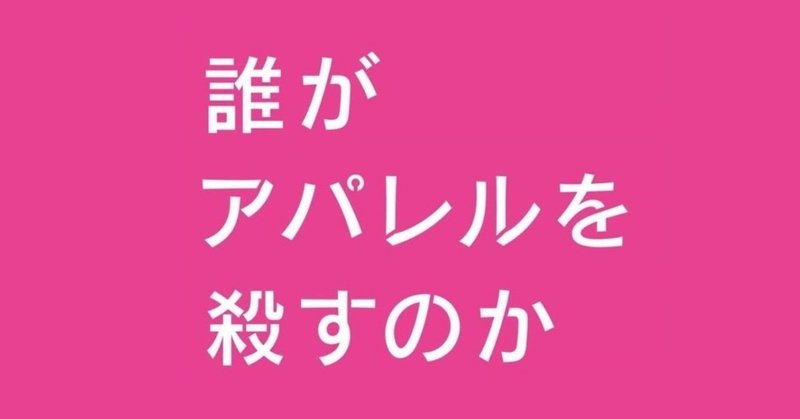
#2 悪い商習慣に疑問を!目先の利益より顧客メリット:誰がアパレルを殺すのか
こんにちは!すがっしゅです。
さて、「ビジネスガッシュ!」第2回です。
今回ご紹介したいのは「誰がアパレルを殺すのか?」という本。
「買いたい服がない…」そう思ったことはありませんか?
セーターなんてブランドものもユニクロも変わりませんよね。笑
どのブランドも同質化し、顧客のニーズを捉えられず、
アパレル業界は大不振。帰路に立たされている状況です。
この本は、今のアパレル業界全体の不振の原因を紐解き、
同時に何がアパレル業界に必要なのか、
現在台頭している新興勢力を例に出しながら、考えていく本です。
*メーカー・SC・売り場…アパレル業界の集団自殺
アパレル企業、ショッピングセンター(SC)や百貨店、売り場を支えるスタッフの雇用環境…。どの側面を見ても、各々が自分のことだけを考え、目先の売上だけを追い続けたことで、アパレル業界全体が集団自殺している現状を、この本はあぶりだしていきます。
アパレル企業の問題
◆大量生産&大量出店というビジネスモデル
ユニクロ等のファストファッション企業は、いわゆるSPA(製造小売り業)と呼ばれる手法を取っています。製造から小売りまでやる訳ですが、ユニクロらは、企画~生産~販売とサプライチェーンを全て把握することで、消費者の変化やトレンドに応じて迅速に売り場や工場に指示を出すことができました。消費者のニーズに柔軟に対応するこのモデルは、バブル崩壊・景気悪化により不振に陥った業界野の中で一躍注目を浴びます。
アパレル各社はユニクロの安さ・速さを真似しようとしますが、真似したのはアジア、特に中国への工場移転。サプライチェーンを把握し、消費者のニーズやトレンドをいち早く商品に反映できる点が本質なのに、見た目だけ真似して、ただただコスト削減を図ったのです。人件費を安く抑え、さらに大量生産によるスケールメリットで、コストを下げていきます。優れた技術や素材を持つ国内の職人や工場は、各社の海外移転により、見放されてしまうことになるのです。
さらに、大量生産された商品を売り切るために、いくつものブランドに枝分かれし、売り場も増える。大量生産&大量出店となります。
大量に売れば、確かに目先の売上を確保することはできます。しかし、需要とは裏腹にひたすら売り場に供給される商品は、やがて不良在庫となり、大量の廃棄商品に。消費者のニーズを無視し、ただ闇雲に商品を供給し続ける「散弾銃商法」を、消費者は見放すようになります。
◆OEM・商社への丸投げ
ユニクロのように、トレンドの商品を「安く」「早く」売ることに固執してしまったアパレル業界は、いつしかコンセプトや商品企画まで、OEMメーカー・商社へ外注してしまうようになります。本末転倒なのですが、本来、トレンドを「作る側」なのにも関わらず、トレンドを「追う側」に立ってしまったのです。
するとどうなるか。自らモノ作りを考えることを止め、トレンドを安く・早く精神で外注し続けることで、その時のトレンド商品ばかりが店頭にならぶことになります。商品の同質化です。どのブランドも、タグだけ違う。どの商品もほとんど同じ。なぜならどの商品も、アパレル企業がOEM・商社に外注し、トレンドを追った商品企画が出来上がり、アジアの工場で安く生産され、大量に店頭にならんでいるものだから。生地も、デザインも、こだわりなんてなにもない。
そうして、消費者は、「セーターなんて、どのお店で買っても同じだ」「買いたい服がない」というように、嘆くようになります…。
ショッピングセンター(SC)・百貨店の問題
◆出店したいなら大量出店が必須というシステム
SCは、売上拡大のために、次々と新たな店舗を展開していきます。すると、埋めなければならないテナントがどんどん増えていきます。この課題を解決するため、SCでは、ブランドが出店を希望した時、1店舗だけでなく他のSCでの出店も含めて複数店舗を必須としている場合が多いよう。アパレル企業としては、大量生産された商品の受け皿として、複数店舗で出店し、大量の商品を一気に売った方が目先の売上を確保できる。SCもテナントを埋められる。WIN-WINという訳で、この形が広がっていきました。
しかし、複数店舗の出店を必須としたせいで、近隣SCとの競争は激化。他のSCとの差別化が必要となり、その結果として、タグしか違わない別のブランドが次々と乱立しました。特徴のないブランドでは当然売れず、不良在庫はどんどん拡大します。さらには、狭いエリアで系列店舗が乱立することにより、同じブランドで顧客の食い合いも起こってしまいます。
アパレルの供給過多を後押ししてしまったのは、SCにも責任があるのです。
◆百貨店の「消化仕入れ」システム百貨店は、SCのように店舗数が増えていった訳ではありませんが、多くのブランドをかき集め、広い売り場にできるだけ多く並べることに力を注ぎました。どんなブランドでも売り場に置けばいい。その考え方の裏には、「消化仕入れ」という独特のシステムがありました。
「消化仕入れ」とは、商品が売れた分だけ「仕入れた」とみなし、仕入れ代金を支払う仕組みのこと。販売員の確保もアパレル企業が負担し、万引きが起きてもアパレル企業が負担する。つまり、百貨店は在庫リスクを全く負わないシステムだったのです。
百貨店の数よりもアパレル企業の数の方が圧倒的に多かったため、アパレル企業は競争を勝ち抜くために、百貨店の方が有利な条件であっても、飲むしかなかったんですね。
リスクなくブランドを店頭に並べられる百貨店は、どんなブランドも次から次へと受け入れます。ですが店頭に並ぶのは同質化で特徴のないブランドだけ。消費者の足は遠のき、百貨店の魅力は大幅に薄れていきました。
販売員の雇用環境の問題
◆販売員の悪すぎる待遇・職種軽視
「洋服が好き」ということでアパレル業界の販売員に就職した人たちはとても多いですが、今ではこんな言葉が囁かれています。
「洋服が好きだからこの業界に入ったけど、こんなに待遇が悪いなら、待遇の良い仕事を探して、稼いだお金で好きな服を買ったほうがいいんじゃないか・・・」
それくらい、販売員の待遇の悪さ・職種軽視は深刻。手取り18万円・実家暮らし、がスタンダード、という状況です。売上ノルマがあったり、そのブランドの服を必ず購入して着なければいけなかったり、ということも。商品企画やバイヤー等の職種にステップアップしようしても、販売員の経験はほとんど評価されないようです。いわゆるブラック業界に成り下がってしまい、販売員のやる気は低下。店舗の質が落ち続けています…。
ECが台頭しているのは事実ですが、今だにアパレルの主な販路はリアル店舗。店舗の現場を支える販売員がいなければ服は売れません。なのに、アパレル企業は販売員を軽視しています。
その裏には、「販売員は派遣会社でなんとかすればいい」というアパレル企業側の常識があります。販売員は長く務めると年齢も重ね、例えば20代向けのブランドであれば、ブランドイメージに合わなくなる。だから派遣会社から常に20代のスタッフを連れてくれば良い。そんな考えが常識になっていて、それが販売員の「使い捨て」意識へとつながっています。
*新興勢力の台頭
アパレル企業、ショッピングセンター(SC)や百貨店、売り場を支えるスタッフの雇用環境…。それぞれの現場のそれぞれの悪い商習慣が絡み合い、「買いたい服がない」状況になってしまったアパレル業界。
しかし、そんな中でも、決して負け組ばかりという訳ではありません。新興勢力がこれまでのアパレル業界の文化・常識を破壊し、新たな勝ち組になりつつあります。
例えば、最近よくニュースでも取り沙汰される、ZOZOTOWN。
今や大手アパレルECへと成長しましたが、その秘密は、服を「買う」から「手放す」まで、消費者の服に対する思いに寄り添ってきた点にあります。
例えば、普段服を買う時、「このブランドのMは、このブランドのSと同じサイズだ…」なんてことありますよね。そんな悩みに答え、ZOZOTOWNでは独自のサイズ規格を採用。どのブランドもZOZOの基準に合わせて、統一したサイズ規格で表示するので、ZOZOユーザーからすればどのブランドを買ってもサイズを間違えることはありません。
「サイズ」でいうと、前に「ZOZOスーツ」が話題になりました。ECが抱える「試着ができずサイズを間違う」という人々の悩みを、ZOZOは真正面から向かい、解決策を提案しています。
他にも、ZOZOUSEDというサービスでは、ZOZOで取り扱った商品だけを消費者から買い取って売る、中古品売買も行っています。
よくできているなと思ったのですが…ZOZOでは扱う商品の購入データを管理しているので、買い取る中古品がいつ買われたのか推定し、経年劣化を想定することができるんですよね。だから、買い取り価格は適正で、買取作業も新たに売る際の値付けも、大幅に簡易化されています。
さらに、このZOZOUSEDでは「買い替え割」というサービスがあり、新品をZOZOで買う時に、過去に買った中古品を下取りに出せば、下取り金額が新品購入金額から割り引かれるようになっているようです。これなら、消費者は「服を買って、使い古したら下取りに出して、そのお金でまた買う」ということがZOZOで全て完結します。消費者の服生活を丸ごと支えてきたことで、ZOZOは成長を遂げました。
他にも、感心したのが「エバーレーン」というアパレル企業の取り組み。
エバーレーンはほとんど店舗を持たず、ECでの購入をメインとしているブランドですが、そのECページでは、なんと商品の生産過程を全て公開。人件費、生地代、関税…それぞれいくらかかっているか・エバーレーンがいくら利益を取っているのか、原価と利益を全て公開しているのです。
大量生産・大量出店を続けてきた従来のアパレル企業は、市場に早く供給しようとするあまり、本来必要のないコストがかかっているケースがよくありました。海外の工場の負担が大きくなると、その工場がまた下請けに仕事を回したり、OEM・商社へ商品の全てを丸投げしたり…、1つの仕事にいくつもの人が関わり、その分商品価格に跳ね返っていました。
エバーレーンは、こうしたアパレル業界に巣食う「不透明性」を問題視。
商品のコスト構造を公開することでとことん「透明性」にこだわり、顧客第一を貫いた結果、信頼を勝ち取って成功を収めています。
他にも、サブスクリプションサービスとしてアパレルのレンタルを展開する企業がでてきたり、国内の職人と手を組んで顧客一人一人にカスタマイズした商品を提供する企業が出てきたり…アパレル業界の悪い風習を打ち破る新興勢力が続々と現れています。
*目先の利益より、顧客のメリット
アパレル業界に古くから染みついている悪い商習慣・文化と、それに疑問を投げかけ真向から反対し、独自の路線を行くことで成功を収める新興勢力。
今 アパレル業界の状況がどうなっているのか、とてもよくわかる本でした。
目先の利益より顧客のメリットを追求すること。
やっぱり、ビジネスはこれに尽きるなぁと思います。
アパレル業界もそうですが、どの業界においても、
「本当は顧客のデメリットになり得るけど、売上が立つから…」
というようなことがあると思うんです。
私は広告業界にいましたが、広告のクオリティを決めるクリエイティブが、あんまり売上にならない、ということがよくあります。
それよりも、媒体費やキャスティングの方が儲かる。
だから、クリエイティブの質よりも、「できるだけ多くTVCM枠を買わせる」とか、「有名な芸能人の出演ありきでクリエイティブを提案する」となりがち。本来、クライアントのメリットを考えれば、クリエイティブに全力を注ぎ、アイデアを買ってもらうのが広告代理店の力量なのに、です(もちろんアイデアで勝負する企業・ビジネスパーソンも多くいますけど!)。
これって、アパレル業界でいう「悪い商習慣」そのものなんですよね。
そんな従来の商習慣を疑って、真に顧客のメリットになることは何か?
その業界・分野で、顧客の悩みとなっていることは何か?
それを捉え、業界の風習を無視してでも1つ1つやり遂げていくこと。
問題意識を持って1つ1つ解決していくこと。
情報社会で企業側の嘘が顧客にバレる今の時代、
そんな真摯な姿勢が、どの業界にも求められるのだと思います。
以上です!
「ビジネスガッシュ!」第2回「誰がアパレルを殺すのか」でした。
アパレル業界の人も、そうでない人も、全てのビジネスパーソンにとって
ビジネスの基本を改めて考えさせられるような本だったのかなぁと思っています。ぜひ読んでみてください。
ではまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
