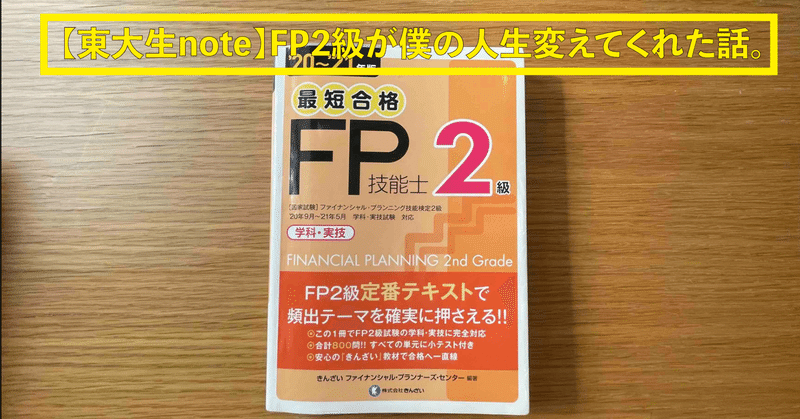
【東大生note】FP2級が僕の人生変えてくれた話。
皆さんこんにちは!東大3年のイケてるスリスリくんです。
土曜日は一週間の中で一番ゆっくりできる日ですよね。(お仕事の方はお疲れ様です!)
僕もレポートが全て終わり、春休みを楽しもうといろいろ計画している最中です笑
さて、今日は僕の人生を変えてくれた「FP」についてご紹介しようと思います!
FPって何?というところから、取得するメリット、FP試験の概要、そして受験して生活がどう変化したかを解説しています。
皆さんに有益な情報をお届けしていきますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。
1.そもそもFPって何?
まず、FPとは何かを簡単にご説明します。
FPとは「ファイナンシャルプランナー」の略で、簡単に言えば「お客様の人生設計を年金・保険・税金といった専門知識をもとにサポートする」専門家のことを言います。
私たちに身近なところでは、
・年金、社会保険制度
・所得税、各種控除など、税制のしくみ
・株式、投資信託など金融資産の特徴、運用方法
・不動産の活用方法
のような分野を学びます。そのほか、住宅ローンや保険、相続などについても勉強します。
これらを身につければ、
・将来もらえる年金額の計算
・所得税の各種控除で、お金がいくら節約でき、いくら自分に戻ってくるのか
・不要な保険の見極め
などが自分でできるようになります。これ、すごく魅力的じゃないですか?!
「人生100年時代」と言われる現代では、私たち一人一人がこのような教養を身につけ、自分の人生を柔軟に切り拓いていく必要があります。
その意味で、FPは私たちが人生設計を行う上で「正しい知識」という最強の武器を提供してくれる資格であるといえます。
2.FP資格・試験について
FPのメリットについてご理解いただけたところで、FP資格・試験についてお話します。
まずお伝えしたいのは、「FPは名称独占資格である」ということです。
例えばFP3級の試験に合格すると、「ファイナンシャル・プランニング技能士3級」と名乗ることができます。
FP試験に合格していない人はこの名称を名乗ることができません。
これが「名称独占」の意味です。
ちなみに、冒頭でお話しした「ファイナンシャルプランナー」というのは誰でも名乗ることができます。
えっ。。と思われるかもしれませんが、FPだけが名乗れるのは
「○級ファイナンシャル・プランニング技能士」 (○は1,2,3のいずれか)
であって、「ファイナンシャルプランナー」は誰でも名乗ることができるのです。
ここは紛らわしいので、注意してくださいね。
また、FPには業務独占がありません。
宅建士であれば重要事項説明、司法書士であれば登記申請書類作成など、有資格者にしか行えない業務がありますが、FPにはそのような業務はありません。
ですので、「就職・転職や社内のスキルアップに使えない」「幅広すぎて専門性に欠ける」といった声も聞かれますが、FP資格の目的は取得することではなく「自分の人生設計に役立てる」ことです。
実際上のメリットはとても大きいので、ぜひ取得され、「実生活で生かす」ことを意識されると良いと思います。
さて、ここまでFP資格についてご説明しました。次はFP試験についてお話します。
まず、FP試験には1,2,3級の3種類があり、それぞれ「学科試験」と「実技試験」があります。
学科試験は
・ライフプランニングと資金計画 (年金・社会保険)
・リスク管理 (保険など)
・金融資産運用 (株式、投資信託など)
・タックスプランニング (所得税、法人税など)
・不動産 (建築基準法など)
・相続・事業承継 (相続税、贈与税など)
の6分野から幅広く出題されます。
実技試験も、実技と言っておきながらペーパーテストです。学科試験より実務的な内容で、年金の額を実際に計算したり、債券の利回りを求めたりします。
FP試験は絶対評価で、「学科試験」と「実技試験」でそれぞれ6割以上正解すると合格となります。
この試験は「日本FP協会」と「きんざい」(金融財政事情研究会)の2つの団体が主催しており、2級と3級はどちらの団体でも受験することができます。
なお、2級を受験するには3級合格者であることなど一定の要件を満たすことが必要で、1級はきんざいでしか受験できませんので注意が必要です。
他にも様々な条件があり、ここでは書き切れませんので、受験される方はぜひ調べてみてください。
一つアドバイスするとすれば、FP協会主催の方が合格率は高めです(私はきんざいで受験しましたが)。
とにかく合格したいという方は、FP協会の方で受験された方が少しはラクかもしれません。
3.FP2級を受験して、人生がどう変わったか
ここからは、FP2級を受験して実際に生活がどう変わったかをお話しします。
「合格」ではなく「受験」と言ったのは、合格発表がまだだからです笑
私は2020年9月試験で3級を取得し、2021年1月試験をきんざい主催で受験しました。
自己採点では学科47点(60点満点)、実技38点(50点満点)だったので、おそらく合格してると思います!
さて、私がFP2級を勉強して変わったことは以下の3つです。
①投資を始めた
これが最も大きい変化でした。今までは「つみたてNISA」や「iDeCo」についてぼんやりとしか理解していなかったのですが、FPの勉強をすることで各制度についてしっかりと理解することができました。
その知識をもとに、先日楽天証券でつみたてNISAを始めました。毎月積み立てられるよう、バイトを頑張りたいと思います笑
②給与所得だけが所得ではない、と気付けた
年収から各種税金を引いたものを所得と呼びますが、皆さんが一般に所得と聞いて思い浮かべるのは「給与所得」ではないでしょうか?
サラリーマンの方が会社からもらう「給料」は給与所得に該当します。しかし、FPの勉強をすると「所得」はなんと10種類もあることに気づきます。
しかも、そのうちのいくつかの所得には給与所得にはない税制上の「優遇」(?)措置が設けられているのです。
気になった方はぜひ調べていただきたいのですが、例えば
・一時所得では、課税の対象となる「総所得金額」に算入する金額は一時所得の金額の2分の1でよい
・不動産所得、事業所得、山林所得による損失(赤字、つまりマイナス)は一定の他の所得と損益通算でき、課税額を減らせる可能性がある
など、「知ってるとおトク」な情報が盛り沢山です。
皆さんも是非、FPを勉強して自らの生活に役立ててください。
③宅建とのダブル学習により、不動産についていっそう理解が深まった
前回の記事:
において、宅建試験が大学生や社会人の方にとって大きなアドバンテージになるという記事を書きました。
宅建ではFPの試験範囲のうち「不動産」について深く勉強しますが、そこで学ぶ知識は完全にFPと重なっています。
つまり、宅建を勉強していれば、FP試験で不動産をほとんど勉強しなくても、不動産分野を得点源にすることができます(不動産にかかる税金については一部FPで勉強する必要があります)。
実際、私はFPを受験する前に宅建を受験していたため、FPの不動産は楽勝でした。
このように、宅建を学べばFPの勉強にもなり、FPを学べば宅建の勉強にもなる。
どちらを学んでも他方に生かせるという意味で、これほど効率よくメリットを享受できる資格は宅建以外にありません。
特にFP2級と宅建をダブルライセンスで持っていれば、特に金融業界や不動産業界志望の就活生にとって非常に大きなアドバンテージとなることでしょう。
まず受験資格のないFP3級と宅建を取得してから、是非FP2級も取得されることを強くオススメします。
本日は日常生活に大いに役立てられ、即効性が高いFP資格についてご紹介しました。
FPは、「得られた知識を活用する」ことでムダな出費を抑えたり、自分の将来に向けて積立投資をするなど、うまく使えば本当に人生を好転させる力を持つ資格だと思います。
皆さんもFPの勉強を通し、今まで何となくしか考えていなかった年金や保険、投資などについてしっかりと理解し、自分で正しい選択ができるようになってほしいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
