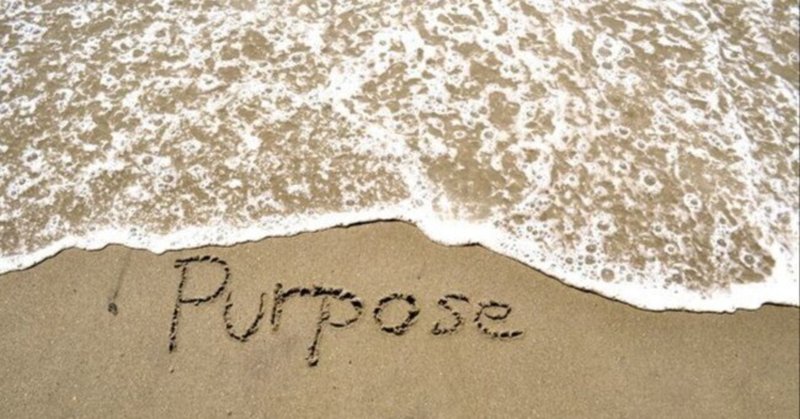
組織として目的を達成する手段
組織として、あるいは企業として何かしらの目的を達成するためには大別して次のような手段があるかと思います。
①学び、自ら身につける
②優秀な人を採用する
③仕組み化する
これらは当然ながらそれぞれの目線でそれぞれのメリット/デメリットがあることは言わずもがなです。
①学び、自ら身につける
これは個人としてメリットが大きい選択肢です。結果、身につけた人材がいれば会社としても願ったり叶ったりですが、それまでにかかる育成コストを考えると企業としてはかなりリスクの高い取り組みと言えるかもしれません。
なぜなら、学んだところで(コストをかけたところで)個人が必ずしも成長するとは限らないからです。特に、本人にその気がない中で企業側が勝手に押し付けたメンバーだったりすると、大抵の場合は「やむなく参加している」だけで何一つ身につかないまま終わる…というのはよくあることです。
しかし、だからこそ他人任せにするのではなく、目的を達成させたい人自身が自ら身に着けてしまうのが一番確実と言えます。しかも、そこで得た知見、その知見を用いて培った経験は、その人自身にとってどこででもやっていける力量として確実に身につくことになります。自信にもつながることでしょう。
しかし反面、同レベルの人が周囲にいないと毎度毎度あなた自身に押し付けようと組織は動くことでしょう。それが如何に難しいことであっても、よほど誠実な企業でない限り人の努力を「労働時間」からしか見ようとしていないでしょうから、報酬や待遇が変わることはありません。真面目に頑張れば頑張るほど貧乏くじを引く…ということにもなってしまいかねないのです。
まぁそんな企業であればさっさと見切りをつけて転職すると言う手を取れるのも「自ら学び取った」人の特権です。そもそもそんな企業に義理立てする必要性などないわけですし、力量が高くなればなるほど引く手数多となることでしょうから早々に移った方が得策です。また、どの企業に移ってもたいして変わらないのであれば独立するという方法もあります。
そうした背景も理解できず、いまだに「採用する側がエライ」と思い込んだまま一定水準以上の実力を身につけた人をいつまでも労働時間でどうこうしようとしたり、無能な上司の下に就けておこうとする企業は優秀な人が居付かなくなるという観点から今後どんどん衰退していくことでしょう。
逆にそうして衰退しそうになった風土を持ってしまったことに気づいたからこそ、昨今優秀な人材であれば新卒でも年収1000支払う企業が出てきているのでしょう。ですが、そこにも一定の落とし穴があるんです。
②優秀な人を採用する
これは採用する側としてメリットが大きい選択肢になります。もちろん個人にとっても自らの強みを活かしやすい環境が整っているかもしれませんので相互に意義のあることなのかもしれません。
企業からの目線で見てみると育成コストがかからない点がメリットでしょうか(採用コストにどれだけかかってるのかはわかりませんが)。また採用直後から効果が期待できるという点もポイントです。それにとにかく楽です。
しかしだからこそ、企業内には理解者が一人もいない…というリスクもあります。仮に裁量を与えても周囲に理解者がいないので孤軍奮闘するしかありません。そう、誰も理解しようとしないで①のように優秀な人にばかりすべてを押し付けることしかしないようになってしまう可能性があるわけです。
この点は個人から見ると相当大きなデメリットになる可能性は覚悟しておいた方がいいかもしれません。優秀であればあるほど、その優秀さに比例して役割と権限を大きくできればいいのですが、そんなことができる真っ当な企業は決して多くありません。
そしてそんな優秀な人にばかりすべてを押し付ける風土を当たり前としてしまった企業もお得な買い物をしたつもりが、逆に大きなリスクを抱えることになります。
そう、離職リスクです。
一人も目的達成に応じた力量を持つ者がいない頃はまだそこまで推進していなかった都合上それほどのダメージも無かったかもしれません。しかし優秀な人を採用し、加速度的に活動や事業等が進んでしまうと、なまじ優秀な人に押し付けっぱなしだった役割や事業というのは一気にリスクを抱えることになってしまいます。
その人が辞めてしまったら、誰も推進できなくなってしまうからです。
採用だけでなんとかしようというのは、実はかなり超属人的な施策で、時代を逆行した非常にリスクの大きな取り組みとなりかねません。
優秀な人材が欲しいのであれば、
・理解のある誠実な上司をつける
・活動にみあった役割と裁量、責任をしっかり与える
ことも常に添えておくことを忘れないようにしましょう。
③仕組み化する
これは企業にとっても個人にとっても非常にメリットの大きい取り組みとなります。
仕組み化すると言うことはギリギリまで「人」に依存しないということです。「人」に依存しないということは、企業としては個人の離職リスクによって活動や事業に支障をきたさなくなるということですし、個人や少人数に一方的に負荷が高まるような危険性が減ります。
また、仕組み化されていれば属人的である業務に比して「ガイドライン」「マニュアル」などの作成も容易になりますし、そうした関わる人の増減があっても引き継ぎやすくなるのでサステナビリティにも大きく貢献します。
さらにIT化可能な事業があれば、IT化することも容易になります。そもそもIT化が可能な条件は「仕組みとして充実している」ことです。既存業務が人に依存したものではなく、仕組みとしてしっかりと確立されていなければIT化することができません。IT化を行う上で重要なビジネスロジック(アルゴリズム)に落とし込むことができなくなるからです。
しかし、この仕組み化にもデメリットが無いわけではありません。
従来のIT投資がそうであるように大事なのは開発だけでなく、適切な保守・運用もしっかり考えておかなくてはあっという間に陳腐化・形骸化するリスクを負うからです。
この辺もITシステムとまったく同じですね。仕組みもシステムも作って終わりではありません。適切な運用と、適切な保守がなくては長期間維持することは不可能です。このことを理解しないままなんとなーく仕組み化に手を出しても上手くはいきません。
まとめ
三者三様ですが、どの選択にもメリット/デメリットやリスクは必ずあります。
そしてそれぞれのリスクにも「影響度」と「発生率(頻度)」があります。

もし企業のなかで、あるいは個人の中でしっかりとリスクを検討したいのであれば「発生率(頻度)」よりも発生した際の「影響度」を中心に考えると言いでしょう。


日本には「万が一」という言葉があるように、どうしても「発生率(頻度)」の方ばかり見ようとしてしまう癖がありますが、発生率がゼロにならない以上、万が一であっても発生してしまった際に致命的なダメージを受けるようではリスク対策として失格です。
真の意味でリスクマネジメントを行うのであれば常に「影響度」を優先しなければなりません。影響度さえ低減させておけば、十に一つだろうが万に一つだろうが致命的な影響を受けることがなくなります。
その点を踏まえたうえで「目先の対策」を図るか「中長期的な安定」を採るかは考えてみるといいでしょう。
いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。
