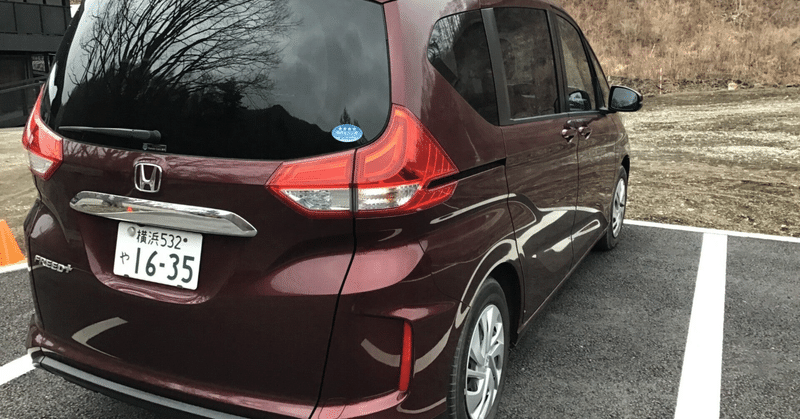
インタビュー調査の分析入門〜読み取りと要素化の実例
ミニバンのインテリア開発を例にとります。
この場合のあるべきインタビューフローとは、下図の左側ではなく右側であるという説明はしました。それがアクティブリスニングインタビューにおける「生活工学的インタビューフロー」の考え方です。商品の評価をしてもらうのではなく、その商品をとりまく体験談をしてもらうのでしたよね。この場合は、「車内での色々な過ごし方・体験」です。

これで実際にインタビューフローを作ると以下のようになります。これは根幹部分のダイジェスト版ではありますが、実際のものもこれと大差はありません。体験のある方はお判りになると思いますが、質問が列記羅列された一般的なものと比較してきわめてシンプルです。「これで大丈夫なの?」と思われれる方も少なからずおられるかと思います。しかし、C/S領域における「ナラティブ」を自発的に引き出す為には、インタビューフローはこのような話題の提示でなければならないわけです。シンプルなのには理由があり、きわめて練り込まれているからこそシンプルになっているのです。シンプルでないと、対象者には意図が伝わらないからです。練り込まれていないものほどグダグダと説明や言い訳の言葉の足し算をしたようなものになってしまいます。そこには練り込まれていないが故の作成者の不安が表れているわけです。「仕事が甘い」のです。
この中には商品についての話題も一応ありますが、最後の部分に付け足し程度に扱われています。多くの場合はそこまでの間に必要な情報は取れてしまうのです。最後であるということは、その前の話題で時間が押せばインタビュアーの判断でカットしてもよいというくらいの扱いであるということです。

なお、このフローの「趣旨説明」の部分には「与えられた話題について、日常の体験や思いを自由に話し合っていただくのが”ルール”!」であると書かれています。これはいずれ司会法のパートで詳しく説明をするつもりですが、このようなことを冒頭に明確に伝えておくことは、自発的なナラティブを引き出す為にはきわめて重要なことなのです。ところが、世の中のインタビューではそのような「基本」が守られていないものが大半です。それが結果として極めて低い満足度につながっていくわけです。
以下はこれを使ったグループインタビューにおいて実際に出てくるであろう話の一部です。この部分からどれだけのことが読み取れるのかが今回の本題です。「商品の話題」ではないところでどれだけの情報が読み取れているのか、ということの検証でもあります。

このわずかな文章から以下のようなニーズとその達成を促進したり阻害したりしている要因(主として商品側のもの)が読み取れます。
ニーズ
・家事で忙しい中、子供を車で幼稚園に送り迎えしたい
・家事育児から解放され運転しながらゆっくりカフェのコーヒーを飲みたい
・家事育児から解放され運転しながらゆっくり好きな音楽を聴きたい
・一人で自由なゆったりとした時間を過ごしたい。
・家族みんなでゆったり遠出・旅行したい。
・家族団らんの時間を増やしたい
ニーズ達成の促進・阻害要因
・家事育児に追われている。
・一人になれる時間がない。
・子供の乗降が楽にできる
・子供が車内でおとなしくしてくれる
・カフェのテイクアウトのコーヒーが運転しながら飲める
・運転しながら好きな音楽が聴ける
・目線が高い=見晴らしが良い
・車内がゆったり広々と感じる=家族みんなが乗っても広さに余裕がある=せせこましく感じない
・渋滞の時にイライラして夫婦喧嘩になる
だいたいこれくらいのことが読み取れると思います。ニーズに関しては、「一人になってゆったり過ごしたい」というニーズと「家族で過ごす時間を大事にしたい」という二系統のニーズに集約されるかと思います。それは一言でまとめて「統合化」すると、「家事育児に追われる中でも豊かな気持ちで過ごしたい」ということになるかと考えられます。
一方、ニーズの促進・阻害要因については「ゆったり感」と「和み=和やか感」が必要であると考えられます。その為には室内の広さや、天井の高さ、見晴らしの良さにつながる視点の高さや、視界の広さ、また、気持ちの豊かさにつながる音楽や飲み物などが楽しめることなどが要素としてあると考えられます。その為には、広々と見える車体と室内のデザイン、グラッシーな窓、性能の良いオーディオ、などが必要でしょう。子供や家族の楽な乗り降りにはミニバンの特徴であるスライドドアは欠かせないでしょう。
つまり、わずかこれだけの会話でも、そこから読み取れることは元の文章の文字数以上の情報量になってくるわけです。「そんなこと言ってない」という議論がナンセンスなことは意識マトリクス理論で説明済みです。無意識のことは言葉には出てこないのです。言葉として発せられた以上のS領域の情報を「脳梁」を使った「間接観察」で読み取るのが「インサイト」です。
先々に詳しく説明するつもりですが、実は、上記の分析ではすでに構造化、統合化も行われています。例えば「家事育児に追われる中でも豊かな気持ちで過ごしたい」というのはニーズを目的-手段関係で構造化(上位化)、統合化した結果です。
さて、この会話の中では「渋滞の時の夫婦喧嘩」という極めて重大な問題が含まれていました。一歩間違うと離婚沙汰です(笑)。しかし、それはマーケターにとっても笑い話では済ましてはならないのです。なぜならばその問題は、そもそもミニバンを購入して利用しているニーズである「家族で過ごす時間を大事にしたい」とは正反対の現象が起きているということだからです。
それは普通は商品開発の課題とは捉えられないことです。商品がどうのこうのできる問題ではないと思われていますし、夫婦喧嘩が商品への不満にもならないからです。まさに「勝手にやってくれ」(笑)なのですが、しかし、それをマジメに解決しようとするのが生活工学的商品開発です。
まず、この状況をCAS分析してみると下図のようになります。ちなみにCASとはニーズとそのニーズ達成の阻害要因を「対立構造」として構造化し、未充足ニーズとして統合化したものだと言えます。

「車内の夫婦喧嘩」という生活行動を生活工学的観点で商品開発の課題としてマジメに捉えるとこういうことになるのです。
それでは、その解決のためにはどんな方法があるでしょうか?
それを見出すのが商品開発の課題設定です。マーケティングリサーチを行う以上、それができない調査にお金を使う意味はないわけです。
一つには、家での夫婦喧嘩の時にそうするように、お互いの距離をとったり、隔離をしたりということがあります。その方向でアイデアを考えると以下のようになります。

できるかできないか、あるいは受容されるかされないかは、後工程で検証されればよいのですが、これらのアイデアのように、「皆が外を向くのも対面するのも自由」とか「背中合わせにもなれる」とか、いっそのこと、「場合に応じて飛行機のファーストクラスのように個室化できる」といったことも考えられるわけです。これらはミニバン、というか自動車においてのシートアレンジの新機軸となるわけです。
その新機軸が実は、あれほどの短い会話の中から発想可能であるというシミュレーションがこの例です。そして、要素化、構造化、統合化を行えばその新機軸をステップバイステップで生み出すことが可能だということなのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
